「説明できない」
初版の表紙

台詞抜粋
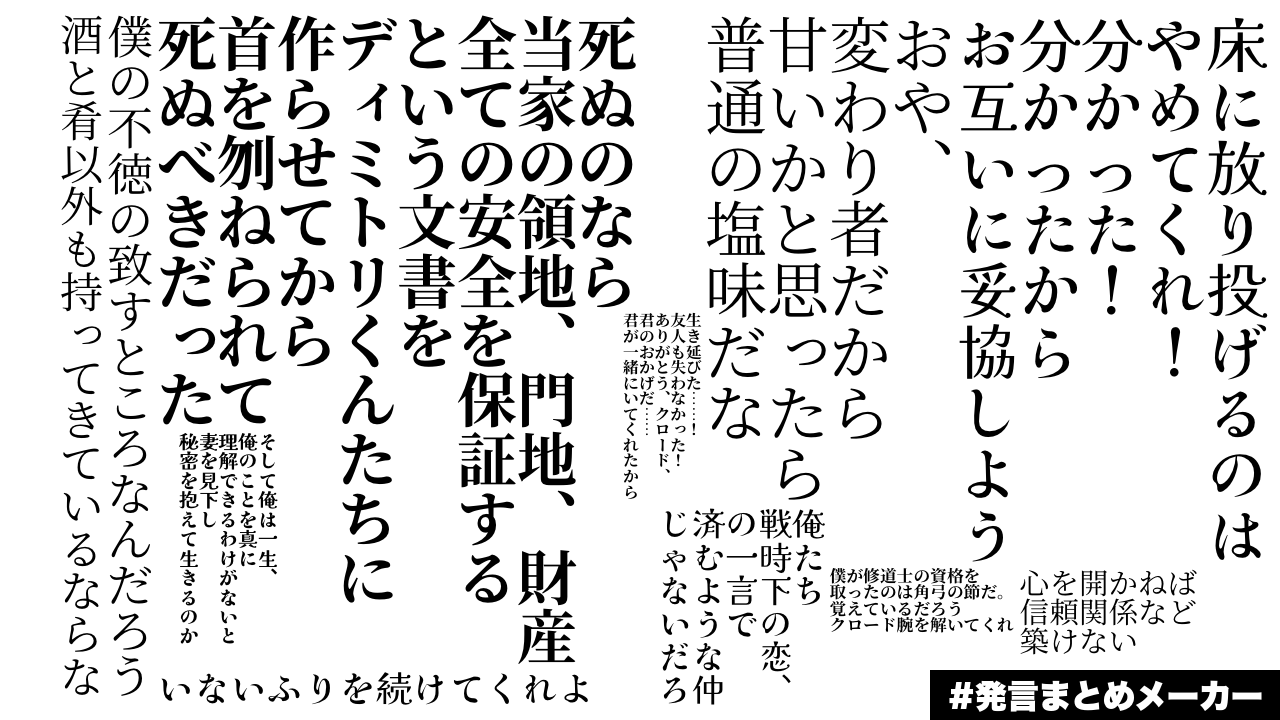
紅花ルートで戦死した記憶のあるクロードと蒼月ルートで戦死した記憶のあるローレンツが翠風ルートで出会ってなんとか2人揃って生き残ることはできないか?と協力していく話です。
1.振り出し
#説明できない #クロロレ #完売本 #表紙 #台詞まとめ
クロードが最後に見たのは天帝の剣を構える元傭兵の女教師だった。五年間行方不明だった彼女が見つかって膠着していた戦況が動き始め───それがクロードにとって望ましいものではなかったのは言うまでもない。
生かしておく限り揉めごとの種になる、と判断されたのは故郷でもフォドラでも同じだった。人生はなんと馬鹿馬鹿しいのだろうか。だが自分の人生の幕が降りる時、目の前にいるのがシャハドやその取り巻きではなくベレス、エーデルガルト、ヒューベルトであることに気づいたクロードは笑った。
もう重たくて二度と上がらない筈の瞼が上がり緑の瞳が現れる。その瞬間は何も捉えていなかったが部屋の窓から差す一条の光に照準が合った瞬間、クロードの動悸は激しく乱れた。戦場で意識を取り戻した際は呼吸が出来るかどうか、視野は失われていないか、音は聞こえるのか、それと体が動くかどうか、を周りの者に悟られぬように確かめねばならない。クロードは目に映ったものを今すぐにでも確認したかったが、行動を観察されている可能性があるので再び目を瞑った。
山鳥の囀りが聞こえ火薬や血の匂いを感じない。手足双方の指も動く。どうやら靴は履いていないらしい。関節も痛みなく動かすことができた。再び一度耳を澄ませたが物が燃える音もクロードの他に人がいる気配も感じない。もう体を動かしてあたりを確かめても良いだろう。そう考えたクロードが身を起こすと寝台に乗せてあった本が大きな音を立てて床に落ちた。
ガルグ=マクで寮生活を送る者は皆、朝日の光に眠りを遮られないように寝る前に雨戸を閉める。しかしクロードの部屋の雨戸は少し合わせが悪く隙間から光が差し込む。その形は忘れようがない。クロードが子供でいられた最後の一年間、毎朝見ていたものなのだ。室内履きなどは履かず裸足のまま窓に近寄り雨戸を開ける。クロードの目の前に広がったのは士官学校の敷地だった。エーデルガルト達が捕虜を捕らえるにしても、クロードにとって庭のようなこの場所に留め置いて何の利があるのだろうか。明るくなった室内を眺めると身嗜みを整える為、壁に掛けておいた鏡が目に入る。鏡の中の自分はまだ頬髭もなく三つ編みが編めるほど前髪が長かった。当たり前だが頬を触ってみても髭の感触はない。椅子には士官学校の制服と級長の証である黄色い外套が掛けられていた。手に取って見てみればまだ子供の頃の細い身体に合わせて仕立ててある。
「嘘だろ……」
クロードは一人虚空に向かって呟いた。
───
ローレンツが最後に見たものは破裂の槍を構えるシルヴァンだった。五年間行方不明だったベレトが姿を表し、ガルグ=マクがファーガスの拠点となってから膠着していた戦況が動き始め───それが帝国にとって望ましいものでなかったのは言うまでもない。
フェルディナントがキッホルの紋章を、ローレンツがグロスタールの紋章を持っているからと言う理由でミルディン大橋の防衛を任された。何も不自然なところはない。だがその命令には恐ろしいほどの悪意が込められていた。それでもシルヴァンがいるなら後を任せられる。最後に感じたのは頬に落ちる彼の涙だった。
遠くで何かが崩れる音がしてローレンツは意識を取り戻した。戦場で意識を取り戻した際はまず呼吸が出来るか確かめるように言われている。肺から喉に逆流した血が溜まっていた筈だが咽せることなく呼吸が出来た。山鳥の囀りが聞こえ頬には冷えた空気を感じる。五感のうち聴覚と触覚は無事であるらしい。付近に人の気配が感じられなかったのでローレンツは思い切って瞼を微かに上げてみた。
部屋の中は薄暗く何がどこにあるのかよく分からない。寝返りを打ってもどこも体に痛みを感じなかった。手足の指は全て揃っており腕も足も動く。身体を起こした時、部屋の外からシルヴァンとフェリクスの話し声が聞こえた。自分は捕虜になったのだろうか。身代金はいくらなのだろう。頭を振って起き上がると伸ばした筈の髪の毛の感触がない。触ってみれば士官学校時代と同じ長さになっていた。
治療の際に切られたのかもしれないと思い、頭を触ってみたが特に怪我もない。大怪我を白魔法で一気に治すと帳尻合わせのように拒否反応が出る。人によってまちまちで、吐く者もいれば体温や気温に関係なく寒気に襲われ毛布が手放せなくなる者もいた。ローレンツの場合は目眩なのだが目が回っている感覚はない。ローレンツは光源にして部屋の様子を伺う為ファイアーの呪文を唱えて魔法陣を出現させた。丸い緑の光がうっすらと室内を照らしていく。見覚えがあるものばかりが目に入りローレンツは絶句した。もう光源など必要ない。起き上がり寝台の脇が定位置の室内履きに足を突っ込んで暗い室内の中、窓に向かって直進する。手を伸ばして雨戸を開け、陽の光の元で振り返ってみればそこには魔道学院にいた頃、買い求めた三段重ねの給茶器があった。
「何が起きたのだ……?」
ローレンツは一人虚空に向かって呟いた。
士官学校の朝は早い。日の出と同時に起きて身支度を整え、訓練をする者たちがいるからだ。金鹿の学級ではラファエル、青獅子の学級ではフェリクス、黒鷲の学級ではカスパルが皆勤賞だろうか。ローレンツも朝食前に身体を動かすようにしているがその三人のように日の出と同時には起きない。
ローレンツは桶に汲んでおいた水で顔を洗い口を濯いだ。早く他の学生たちに紛れて外の様子を見にいかねばならない。前日の自分がきちんと用意していたのであろう制服を身につけ、ローレンツは扉を開けた。私服の外套に身を包んだシルヴァンが訓練服姿のフェリクスに必死で取り繕っている所に出くわす。
「おはよう、フェリクスくん。朝から何を揉めているのだ?」
「煩くしてすまなかった。単にこいつに呆れていただけだ」
そう言うと親指で赤毛の幼馴染を指差しながらフェリクスは舌打ちをした。シルヴァンは朝帰りをディミトリや先生に言わないで欲しいと頼んでいたのだろう。
「情熱的な夜を過ごしたのかね」
呆れたようにローレンツが言うとシルヴァンは照れ臭そうに笑った。
「愚かすぎる。今日は初めての野営訓練だろう」
フェリクスの発言を受けてローレンツは頭の中で暦をめくった。どうやらガルグ=マクに来たばかりの時期らしい。今思えばあの時、行方不明となってその後ずっと姿を表さなかった教師には帝国の息がかかっていたのだろう。本当ならそこに後任としてイエリッツァが潜り込むはずだったのだ。信頼を得て油断したところでディミトリ本人は無理でも、シルヴァンかフェリクスを暗殺できれば五年後の蜂起自体が不可能になる。
「だから山小屋の娘さんとだな……」
「こちらはまだ雪がないんだ。それならどうとでもなるのを知っているくせに白々しいな、お前は」
まだフェルディアで政変は起きていない。辛うじて体裁を保てているファーガスの若者たちは傷ついていたが、五年後を知るローレンツから見ればまだ子犬のような幼気盛りだった。
「初めての合同演習なのだから瑕疵がないようにしたいものだ」
そしてそこでディミトリが彼に選ばれるのだろう。あの時は我が身を引き換えにしてもグロスタール家とグロスタール領しか救えなかった。だがエーデルガルトの悪意を知る今、この時期からやり直せるならば今度こそ、あの戦争が終わるまで自分の足で立っていられるかもしれない。ローレンツは朝食をとり周囲を確かめるため、まだ言い争う二人を置いて食堂へと向かった。
───
クロードは数年ぶりに前髪を編んだ。中途半端に荷解きをしたらしく、混沌としていた部屋は見なかったことにして制服を身につけ扉を開ける。そこにはちょうど世間話が終わったらしいローレンツ、シルヴァン、フェリクスがいた。五年後のローレンツは対帝国の防衛戦に出陣できない。グロスタール伯とクロードの方針が合致したからだ。シルヴァンとフェリクスは即位したディミトリによく従い、王国西部での戦いで武名を上げていた。だが今は三人ともそんな未来が待っているとは知らない。
「おはよう、クロード。今日は合同演習だな」
野盗に襲われ命からがら逃げ出した先で、ジェラルドとベレスに助けられたクロードは五年後ベレスに殺されるのだ。
「そうだな、つつがなく終えたいもんだ」
「僕も尽力しよう」
クロードの記憶によればこの時期のローレンツはもっと食ってかかってきた印象がある。食堂に向かって歩きながら白い横顔を観察したが、まだそこに悪意や苛立ちはない。新しい環境への期待や素直な好奇心がある。母国の王宮に巣食う者たちに比べればフォドラの人々はまだ素朴だ。しかし、望む姿さえ見せればどうとでも操れる、と言う思いあがりのせいでクロードは命を失っている。
ローレンツは言葉通り野営の準備に尽力した。背嚢の数、中身を全て確認してくれたのでクロードは安心して地図を眺めることが出来た。歴史と伝統を誇る士官学校が長年使い続けている経路と野営地だが近年では油断できない、とパルミラの密偵たちはいう。ダスカーの悲劇以降、統治能力を失いつつあるファーガスでは野盗にまで落ちぶれる者も多く治安が悪化していた。三国の国境地帯でもあるガルグ=マクは当然ファーガスとも国境を接している。そこから野盗が入り込むことは当然予想出来た。
事前に密偵からの警告があったのでクロードはあの時も万が一に備えて地図を眺めていた。今回もまた野盗の襲撃があるなら別の村に助けを求めた方が良いのかもしれない。そう考え、改めて地図を眺めてみたが期待外れだった。かなり詳細なはずのこの地図ですら徒歩で行けそうな村があのルミール村しか載っていない。丹念に探せば集落があるのだろうが、その規模の集落に助けを求めたところで自分を信じてくれた同級生は命を落としてしまうだろう。
「クロード、全員準備が整ったぞ」
「ローレンツくんが殆どやってくれたから助かっちゃった!」
そう言ってにこやかに笑うヒルダに真の名すら教えなかったと言うのに、彼女はクロードの命を救うため、デアドラで命を落とした。皆の命を救うために自分に出来ることはなんだろうか。畳む
初版の表紙

台詞抜粋
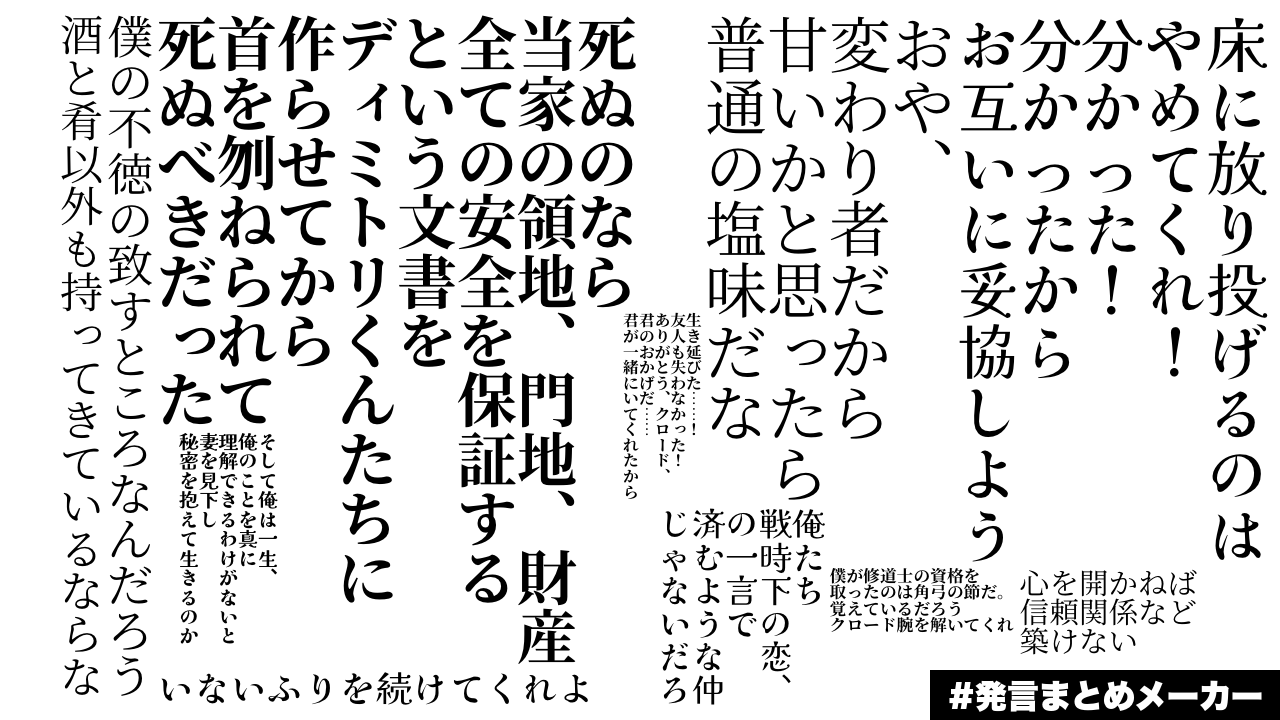
紅花ルートで戦死した記憶のあるクロードと蒼月ルートで戦死した記憶のあるローレンツが翠風ルートで出会ってなんとか2人揃って生き残ることはできないか?と協力していく話です。
1.振り出し
#説明できない #クロロレ #完売本 #表紙 #台詞まとめ
クロードが最後に見たのは天帝の剣を構える元傭兵の女教師だった。五年間行方不明だった彼女が見つかって膠着していた戦況が動き始め───それがクロードにとって望ましいものではなかったのは言うまでもない。
生かしておく限り揉めごとの種になる、と判断されたのは故郷でもフォドラでも同じだった。人生はなんと馬鹿馬鹿しいのだろうか。だが自分の人生の幕が降りる時、目の前にいるのがシャハドやその取り巻きではなくベレス、エーデルガルト、ヒューベルトであることに気づいたクロードは笑った。
もう重たくて二度と上がらない筈の瞼が上がり緑の瞳が現れる。その瞬間は何も捉えていなかったが部屋の窓から差す一条の光に照準が合った瞬間、クロードの動悸は激しく乱れた。戦場で意識を取り戻した際は呼吸が出来るかどうか、視野は失われていないか、音は聞こえるのか、それと体が動くかどうか、を周りの者に悟られぬように確かめねばならない。クロードは目に映ったものを今すぐにでも確認したかったが、行動を観察されている可能性があるので再び目を瞑った。
山鳥の囀りが聞こえ火薬や血の匂いを感じない。手足双方の指も動く。どうやら靴は履いていないらしい。関節も痛みなく動かすことができた。再び一度耳を澄ませたが物が燃える音もクロードの他に人がいる気配も感じない。もう体を動かしてあたりを確かめても良いだろう。そう考えたクロードが身を起こすと寝台に乗せてあった本が大きな音を立てて床に落ちた。
ガルグ=マクで寮生活を送る者は皆、朝日の光に眠りを遮られないように寝る前に雨戸を閉める。しかしクロードの部屋の雨戸は少し合わせが悪く隙間から光が差し込む。その形は忘れようがない。クロードが子供でいられた最後の一年間、毎朝見ていたものなのだ。室内履きなどは履かず裸足のまま窓に近寄り雨戸を開ける。クロードの目の前に広がったのは士官学校の敷地だった。エーデルガルト達が捕虜を捕らえるにしても、クロードにとって庭のようなこの場所に留め置いて何の利があるのだろうか。明るくなった室内を眺めると身嗜みを整える為、壁に掛けておいた鏡が目に入る。鏡の中の自分はまだ頬髭もなく三つ編みが編めるほど前髪が長かった。当たり前だが頬を触ってみても髭の感触はない。椅子には士官学校の制服と級長の証である黄色い外套が掛けられていた。手に取って見てみればまだ子供の頃の細い身体に合わせて仕立ててある。
「嘘だろ……」
クロードは一人虚空に向かって呟いた。
───
ローレンツが最後に見たものは破裂の槍を構えるシルヴァンだった。五年間行方不明だったベレトが姿を表し、ガルグ=マクがファーガスの拠点となってから膠着していた戦況が動き始め───それが帝国にとって望ましいものでなかったのは言うまでもない。
フェルディナントがキッホルの紋章を、ローレンツがグロスタールの紋章を持っているからと言う理由でミルディン大橋の防衛を任された。何も不自然なところはない。だがその命令には恐ろしいほどの悪意が込められていた。それでもシルヴァンがいるなら後を任せられる。最後に感じたのは頬に落ちる彼の涙だった。
遠くで何かが崩れる音がしてローレンツは意識を取り戻した。戦場で意識を取り戻した際はまず呼吸が出来るか確かめるように言われている。肺から喉に逆流した血が溜まっていた筈だが咽せることなく呼吸が出来た。山鳥の囀りが聞こえ頬には冷えた空気を感じる。五感のうち聴覚と触覚は無事であるらしい。付近に人の気配が感じられなかったのでローレンツは思い切って瞼を微かに上げてみた。
部屋の中は薄暗く何がどこにあるのかよく分からない。寝返りを打ってもどこも体に痛みを感じなかった。手足の指は全て揃っており腕も足も動く。身体を起こした時、部屋の外からシルヴァンとフェリクスの話し声が聞こえた。自分は捕虜になったのだろうか。身代金はいくらなのだろう。頭を振って起き上がると伸ばした筈の髪の毛の感触がない。触ってみれば士官学校時代と同じ長さになっていた。
治療の際に切られたのかもしれないと思い、頭を触ってみたが特に怪我もない。大怪我を白魔法で一気に治すと帳尻合わせのように拒否反応が出る。人によってまちまちで、吐く者もいれば体温や気温に関係なく寒気に襲われ毛布が手放せなくなる者もいた。ローレンツの場合は目眩なのだが目が回っている感覚はない。ローレンツは光源にして部屋の様子を伺う為ファイアーの呪文を唱えて魔法陣を出現させた。丸い緑の光がうっすらと室内を照らしていく。見覚えがあるものばかりが目に入りローレンツは絶句した。もう光源など必要ない。起き上がり寝台の脇が定位置の室内履きに足を突っ込んで暗い室内の中、窓に向かって直進する。手を伸ばして雨戸を開け、陽の光の元で振り返ってみればそこには魔道学院にいた頃、買い求めた三段重ねの給茶器があった。
「何が起きたのだ……?」
ローレンツは一人虚空に向かって呟いた。
士官学校の朝は早い。日の出と同時に起きて身支度を整え、訓練をする者たちがいるからだ。金鹿の学級ではラファエル、青獅子の学級ではフェリクス、黒鷲の学級ではカスパルが皆勤賞だろうか。ローレンツも朝食前に身体を動かすようにしているがその三人のように日の出と同時には起きない。
ローレンツは桶に汲んでおいた水で顔を洗い口を濯いだ。早く他の学生たちに紛れて外の様子を見にいかねばならない。前日の自分がきちんと用意していたのであろう制服を身につけ、ローレンツは扉を開けた。私服の外套に身を包んだシルヴァンが訓練服姿のフェリクスに必死で取り繕っている所に出くわす。
「おはよう、フェリクスくん。朝から何を揉めているのだ?」
「煩くしてすまなかった。単にこいつに呆れていただけだ」
そう言うと親指で赤毛の幼馴染を指差しながらフェリクスは舌打ちをした。シルヴァンは朝帰りをディミトリや先生に言わないで欲しいと頼んでいたのだろう。
「情熱的な夜を過ごしたのかね」
呆れたようにローレンツが言うとシルヴァンは照れ臭そうに笑った。
「愚かすぎる。今日は初めての野営訓練だろう」
フェリクスの発言を受けてローレンツは頭の中で暦をめくった。どうやらガルグ=マクに来たばかりの時期らしい。今思えばあの時、行方不明となってその後ずっと姿を表さなかった教師には帝国の息がかかっていたのだろう。本当ならそこに後任としてイエリッツァが潜り込むはずだったのだ。信頼を得て油断したところでディミトリ本人は無理でも、シルヴァンかフェリクスを暗殺できれば五年後の蜂起自体が不可能になる。
「だから山小屋の娘さんとだな……」
「こちらはまだ雪がないんだ。それならどうとでもなるのを知っているくせに白々しいな、お前は」
まだフェルディアで政変は起きていない。辛うじて体裁を保てているファーガスの若者たちは傷ついていたが、五年後を知るローレンツから見ればまだ子犬のような幼気盛りだった。
「初めての合同演習なのだから瑕疵がないようにしたいものだ」
そしてそこでディミトリが彼に選ばれるのだろう。あの時は我が身を引き換えにしてもグロスタール家とグロスタール領しか救えなかった。だがエーデルガルトの悪意を知る今、この時期からやり直せるならば今度こそ、あの戦争が終わるまで自分の足で立っていられるかもしれない。ローレンツは朝食をとり周囲を確かめるため、まだ言い争う二人を置いて食堂へと向かった。
───
クロードは数年ぶりに前髪を編んだ。中途半端に荷解きをしたらしく、混沌としていた部屋は見なかったことにして制服を身につけ扉を開ける。そこにはちょうど世間話が終わったらしいローレンツ、シルヴァン、フェリクスがいた。五年後のローレンツは対帝国の防衛戦に出陣できない。グロスタール伯とクロードの方針が合致したからだ。シルヴァンとフェリクスは即位したディミトリによく従い、王国西部での戦いで武名を上げていた。だが今は三人ともそんな未来が待っているとは知らない。
「おはよう、クロード。今日は合同演習だな」
野盗に襲われ命からがら逃げ出した先で、ジェラルドとベレスに助けられたクロードは五年後ベレスに殺されるのだ。
「そうだな、つつがなく終えたいもんだ」
「僕も尽力しよう」
クロードの記憶によればこの時期のローレンツはもっと食ってかかってきた印象がある。食堂に向かって歩きながら白い横顔を観察したが、まだそこに悪意や苛立ちはない。新しい環境への期待や素直な好奇心がある。母国の王宮に巣食う者たちに比べればフォドラの人々はまだ素朴だ。しかし、望む姿さえ見せればどうとでも操れる、と言う思いあがりのせいでクロードは命を失っている。
ローレンツは言葉通り野営の準備に尽力した。背嚢の数、中身を全て確認してくれたのでクロードは安心して地図を眺めることが出来た。歴史と伝統を誇る士官学校が長年使い続けている経路と野営地だが近年では油断できない、とパルミラの密偵たちはいう。ダスカーの悲劇以降、統治能力を失いつつあるファーガスでは野盗にまで落ちぶれる者も多く治安が悪化していた。三国の国境地帯でもあるガルグ=マクは当然ファーガスとも国境を接している。そこから野盗が入り込むことは当然予想出来た。
事前に密偵からの警告があったのでクロードはあの時も万が一に備えて地図を眺めていた。今回もまた野盗の襲撃があるなら別の村に助けを求めた方が良いのかもしれない。そう考え、改めて地図を眺めてみたが期待外れだった。かなり詳細なはずのこの地図ですら徒歩で行けそうな村があのルミール村しか載っていない。丹念に探せば集落があるのだろうが、その規模の集落に助けを求めたところで自分を信じてくれた同級生は命を落としてしまうだろう。
「クロード、全員準備が整ったぞ」
「ローレンツくんが殆どやってくれたから助かっちゃった!」
そう言ってにこやかに笑うヒルダに真の名すら教えなかったと言うのに、彼女はクロードの命を救うため、デアドラで命を落とした。皆の命を救うために自分に出来ることはなんだろうか。畳む
「説明できない」2.遭遇
#説明できない #クロロレ #完売本
三学級合同の野営訓練が始まった。全ての学生は必ず野営に使う天幕や毛布など資材を運ぶ班、食糧や武器等を運ぶ班、歩兵の班のどれかに入る。まずは一人も脱落することなく全員が目的地まで指定された時間帯に到達することが目標だ。担当する荷の種類によって進軍速度が変わっていくので編成次第では取り残される班が出てくる。
「隊列が前後に伸びすぎないように注意しないといけないのか……」
「レオニーさん、僕たちのこと置いていかないでくださいね」
ラファエルと共に天幕を運ぶイグナーツ、ローレンツと共に武器を運ぶレオニーはクロードの見立てが甘かったせいでミルディンで戦死している。まだ髪を伸ばしていないレオニー、まだ髪が少し長めなイグナーツの幼気な姿を見てクロードの心は勝手に傷んだ。
「もう一度皆に言っておくが一番乗りを競う訓練じゃあないからな」
出発前にクロードは念を押したがやはり持ち運ばねばならない荷の大きさが理由で、記憶通りに進軍速度の違いが生じている。身軽な歩兵がかなり先の地点まで到達し、大荷物を抱える資材班との距離が開き出した。
「ヒルダさん、早すぎる!」
「えー、でも早く着いて休みたくない?」
クロードは伝令のようにそれぞれの班を走って行き来したがそれも限界がある。歩兵の班の最後尾にいたヒルダに武器の班の責任者を務めていたローレンツが駆け寄って行ったのを見た時は正直助かった、と思った。新兵ほど扱いにくいものはない。
前方でローレンツと彼に呼び出された食糧班の責任者であるリシテアが何やら話し込んでいる。その間、歩兵班は待つように言われたらしく引き離されていた資材班がじりじりと追いついてきた。
「クロード、食糧を一食分と訓練用の剣を今ここで全員に配布してはどうだろうか。そうすればこちらの空いた荷車に資材を積める」
「足の遅い資材班を置き去りにせずに済みます」
ローレンツは進軍速度を均一にする為に提案したようだがクロードはこの後、自分たちが盗賊団から襲撃される事を知っている。
「荷が増えた歩兵の足も鈍るかもな。よし、そうしよう」
クロードはローレンツたちの提案を快諾したが理由が違った。この後、盗賊に襲われるのだから手持ちの武器は少しでも多い方がいい。訓練用の剣は刃が潰してあるがそれでも打撃用の武器にはなる。あの時は備えがない状態で襲撃されても皆、生き残っていた。きっと女神のご加護という奴だろう。それでも全力を尽くすのが将来、自分のせいで死ぬ彼らへの手向けだとクロードは思った。
事態はクロードの記憶通りに進み、野営地は星空の下で盗賊に襲われている。槍と剣を使える学生が最前線に立ち、魔法や弓に長けた学生が援護していた。あの時は気づかなかったが、盗賊たちは最初から外套を身に付けたガキはどこだ、と叫んでいる。外套は級長の証だ。エーデルガルトは自分を囮にしてまでクロードやディミトリを殺したかったのだろう。クロードのせいで五年間対同盟の戦端すら開けなかったのは確かだから、気持ちは分からないでもない。あの時は撹乱する為に闇雲に走ったが今のクロードには目指す場所が分かっていた。
帝国領のルミール村まで辿り着けば壊刃、とあだ名されたジェラルドが率いる傭兵団がいる。こっそり抜け出しても気づいたエーデルガルトと二人きりになると殺害されてしまう可能性が高い。だからクロードはディミトリに気付かれるようわざと物音を立てて逃げ出した。一目散に修道院とは全く違う方へ走っていくクロードに気付いたディミトリとエーデルガルトが追いかけてくる。これでエーデルガルトと二人きりになることはない。
盗賊たちは目当ての学生がいないことに気が付き、皆クロードたちの方へ向かってきた。空がぼんやりと白み始め、村の入り口を見張っている傭兵の姿が見えてきたら後はジェラルドが出てくるのを待てばいい。ディミトリとエーデルガルトが必死に窮状を訴えてくれたので、その間にクロードは息を整えることが出来た。
「上手いこと仲間と分断されて多勢に無勢、金どころか命まで盗られるところでしたよ」
「その割には随分とのん気な……。ん? その制服……」
しかし記憶と違う現実を目の当たりにしたクロードの心臓は早鐘のように脈打ち、その場にいる皆の言葉がよく聞こえない。ジェラルドの側に立っているのはベレスではなくベレトと言う名の息子だった。彼もまたエーデルガルトの手を取るならば強く警戒せねばならない。
ジェラルドとベレトは村に攻め入る盗賊たちをあっという間に倒し、その後の展開はクロードの記憶から外れることはなかった。野営地の様子を見に行ってくれた騎兵から残してきた他の学生たちが無事である、との知らせを受けディミトリが微笑む。クロードにとっても初対面であるベレトにディミトリもエーデルガルトも興味津々で、二人はまとわりついて離れない。牽制半分、からかい半分で彼の好みを問うてみるとパルミラ出身のクロードよりも世間知らずなベレトはベレスとは違いレスター諸侯同盟を選んだ。
犠牲者を一人も出すことなく野営訓練を終えて修道院に戻ることが出来た。ほぼ、ローレンツの記憶通りだが異なる点もある。ベレトが金鹿の学級の担任になったのだ。正式に採用された彼は既に士官学校から学生の資料を貰っている。だがグロンダーズで行われる模擬戦を控えたベレトはここ数日、放課後になると学級の皆に話を聞くため修道院の敷地内を走り回っていた。
ローレンツはあの時、模造剣を配ろうとしたのは何故なのかとベレトに問われている。予め野盗たちに襲われているのを知っていたから、とは言えない。言えば狂人扱いされるだろう。
「歩兵の足が早すぎたからだ。補給部隊が本体と分断されたら敵に襲われやすくなる」
食糧がなければ兵たちは戦えない。敵軍を撤退させるため、戦端を開く前に物資の集積所を襲って物資を奪ったり焼き払ってしまうのもよくある話だ。戦わずに済むならそれがいい。ローレンツの言葉を聞いたベレトは首を縦に振った。
「それで足止めして予備の武器を渡したのか。装備をどうするかは本当に難しいんだ。あの場合は結果として合っていたな。良い判断をした」
「ありがとう先生。そう言ってもらえると霧が晴れたような気分になるよ」
戦場の霧という言葉がある。どの将も斥候などを出して可能な限り下調べはするが、それでも敵軍や戦場の正確な現状を正確に知ることはできない。霧に辺りを覆い隠された状態で指揮官は決定を下し、その責任をとる。ローレンツが命を落としたミルディン大橋にもその霧がたちこめていて、霧の中にはベレトがいた。
ベレトは無表情かつとても静かに話す。声を荒げるところを聞いた者はいない。夜の闇のような瞳で彼からじっと見つめられるとローレンツは秘密を見透かされたような気分になる。だが話題は得意とする武器へと切り替わっていった。彼は剣が最も得意だという。
「シルヴァンと同じく槍だ」
口に出した言葉は取り消せない。ローレンツは反射的にベレトが青獅子の学級の担任であるかのように扱ってしまった。例えとして出すにしても唐突すぎる。レオニーと同じく、と言うべきだった。
「シルヴァンとローレンツは槍が得意なのか。覚えておこう。そうか、フェルディアにいたからファーガスの者に詳しいのか」
今日は天気が良くベレトとローレンツ以外にも中庭で、沢山の学生が暖かい日差しと世間話を楽しんでいる。こうした時間を共有することで学級の垣根、すなわち出身地の違いを超えて同じ体験をした者同士が親しくなっていく。後の戦乱を知る身からすれば涙が出そうなほど平和な光景だ。学級の垣根を超えて結んだ友情は五年の時を経て不本意な結果に終わっている。少なくともローレンツとシルヴァンに関してはそうだった。
「そうだな、確かにメルセデスさん、アネットさんとは魔道学院にいた時からの顔見知りだ」
「ありがとう、参考になった」
そういうとベレトはリシテアを探して立ち去った。うまくやり過ごそうと緊張していたのか汗が白い背中を伝っていく。ふとした拍子に過去の記憶が言動に現れてしまわぬよう、今後は更に気をつけねばならない。
「よう、ローレンツ。そんなにファーガスの連中に詳しいなら俺にも聞かせてくれよ」
クロードはいつから話を聞いていたのだろうか。ローレンツはベレトが違和感を感じていないかどうか気にかけるあまり、クロードが耳をそばだてていることが分からなかった。
「君は人より建物の方が好みだろう?」
クロードの言動は今のところローレンツの記憶と大きく異なる点がない。先日も夜中に勝手に出歩いているところに出くわした。あの時は彼の資質を疑ったが後にエーデルガルト相手に五年間ものらりくらりと誤魔化し続けたことを今のローレンツは知っている。あの時、彼が見誤ったのはディミトリの立ち直る力だけだった。
「先生には興味があるぜ。あの人には何か秘密があるはずだ」
目の前に誰にも言えない秘密を抱えた者がいると知らず、クロードは好奇心に目を輝かせている。表面上では彼とローレンツは一歳しか歳は離れていないが、精神的には五歳の開きがある。
「暴くのではなく打ち明けさせてこそ、だろう。信頼を得たかったら闇雲に腹を探ろうとするのはやめることだ」
「そっちこそ闇雲に女子に声かけるのやめろよ。言い寄られるようになってこそ、だろ?」
だが円卓会議で海千山千の大人たちと立派に張り合っていた片鱗はもう見え始めていた。つまり痛いところを正確に突くのだ。
「なっ!僕はシルヴァンとは違う!本気で共に領地を治めてくれる配偶者を探しているのだからな!」
戦争が終わってから配偶者探しを再開しようと考えていたローレンツは結局、独身のまま生涯を終えている。愛する人がいたら降伏や敵前逃亡をしていたかもしれないが、それでも今度は生涯を共に過ごす相手が欲しい。
「資質を磨かなくても良い立場な奴は気軽で良いねえ」
「言っておくがあくまでも勉学のついでだし君に対する監視の目を緩める気はないからな」
そうすればローレンツはクロードのうちに立ちこめる霧が晴れる時を見逃さずに済むのかもしれない。畳む
#説明できない #クロロレ #完売本
三学級合同の野営訓練が始まった。全ての学生は必ず野営に使う天幕や毛布など資材を運ぶ班、食糧や武器等を運ぶ班、歩兵の班のどれかに入る。まずは一人も脱落することなく全員が目的地まで指定された時間帯に到達することが目標だ。担当する荷の種類によって進軍速度が変わっていくので編成次第では取り残される班が出てくる。
「隊列が前後に伸びすぎないように注意しないといけないのか……」
「レオニーさん、僕たちのこと置いていかないでくださいね」
ラファエルと共に天幕を運ぶイグナーツ、ローレンツと共に武器を運ぶレオニーはクロードの見立てが甘かったせいでミルディンで戦死している。まだ髪を伸ばしていないレオニー、まだ髪が少し長めなイグナーツの幼気な姿を見てクロードの心は勝手に傷んだ。
「もう一度皆に言っておくが一番乗りを競う訓練じゃあないからな」
出発前にクロードは念を押したがやはり持ち運ばねばならない荷の大きさが理由で、記憶通りに進軍速度の違いが生じている。身軽な歩兵がかなり先の地点まで到達し、大荷物を抱える資材班との距離が開き出した。
「ヒルダさん、早すぎる!」
「えー、でも早く着いて休みたくない?」
クロードは伝令のようにそれぞれの班を走って行き来したがそれも限界がある。歩兵の班の最後尾にいたヒルダに武器の班の責任者を務めていたローレンツが駆け寄って行ったのを見た時は正直助かった、と思った。新兵ほど扱いにくいものはない。
前方でローレンツと彼に呼び出された食糧班の責任者であるリシテアが何やら話し込んでいる。その間、歩兵班は待つように言われたらしく引き離されていた資材班がじりじりと追いついてきた。
「クロード、食糧を一食分と訓練用の剣を今ここで全員に配布してはどうだろうか。そうすればこちらの空いた荷車に資材を積める」
「足の遅い資材班を置き去りにせずに済みます」
ローレンツは進軍速度を均一にする為に提案したようだがクロードはこの後、自分たちが盗賊団から襲撃される事を知っている。
「荷が増えた歩兵の足も鈍るかもな。よし、そうしよう」
クロードはローレンツたちの提案を快諾したが理由が違った。この後、盗賊に襲われるのだから手持ちの武器は少しでも多い方がいい。訓練用の剣は刃が潰してあるがそれでも打撃用の武器にはなる。あの時は備えがない状態で襲撃されても皆、生き残っていた。きっと女神のご加護という奴だろう。それでも全力を尽くすのが将来、自分のせいで死ぬ彼らへの手向けだとクロードは思った。
事態はクロードの記憶通りに進み、野営地は星空の下で盗賊に襲われている。槍と剣を使える学生が最前線に立ち、魔法や弓に長けた学生が援護していた。あの時は気づかなかったが、盗賊たちは最初から外套を身に付けたガキはどこだ、と叫んでいる。外套は級長の証だ。エーデルガルトは自分を囮にしてまでクロードやディミトリを殺したかったのだろう。クロードのせいで五年間対同盟の戦端すら開けなかったのは確かだから、気持ちは分からないでもない。あの時は撹乱する為に闇雲に走ったが今のクロードには目指す場所が分かっていた。
帝国領のルミール村まで辿り着けば壊刃、とあだ名されたジェラルドが率いる傭兵団がいる。こっそり抜け出しても気づいたエーデルガルトと二人きりになると殺害されてしまう可能性が高い。だからクロードはディミトリに気付かれるようわざと物音を立てて逃げ出した。一目散に修道院とは全く違う方へ走っていくクロードに気付いたディミトリとエーデルガルトが追いかけてくる。これでエーデルガルトと二人きりになることはない。
盗賊たちは目当ての学生がいないことに気が付き、皆クロードたちの方へ向かってきた。空がぼんやりと白み始め、村の入り口を見張っている傭兵の姿が見えてきたら後はジェラルドが出てくるのを待てばいい。ディミトリとエーデルガルトが必死に窮状を訴えてくれたので、その間にクロードは息を整えることが出来た。
「上手いこと仲間と分断されて多勢に無勢、金どころか命まで盗られるところでしたよ」
「その割には随分とのん気な……。ん? その制服……」
しかし記憶と違う現実を目の当たりにしたクロードの心臓は早鐘のように脈打ち、その場にいる皆の言葉がよく聞こえない。ジェラルドの側に立っているのはベレスではなくベレトと言う名の息子だった。彼もまたエーデルガルトの手を取るならば強く警戒せねばならない。
ジェラルドとベレトは村に攻め入る盗賊たちをあっという間に倒し、その後の展開はクロードの記憶から外れることはなかった。野営地の様子を見に行ってくれた騎兵から残してきた他の学生たちが無事である、との知らせを受けディミトリが微笑む。クロードにとっても初対面であるベレトにディミトリもエーデルガルトも興味津々で、二人はまとわりついて離れない。牽制半分、からかい半分で彼の好みを問うてみるとパルミラ出身のクロードよりも世間知らずなベレトはベレスとは違いレスター諸侯同盟を選んだ。
犠牲者を一人も出すことなく野営訓練を終えて修道院に戻ることが出来た。ほぼ、ローレンツの記憶通りだが異なる点もある。ベレトが金鹿の学級の担任になったのだ。正式に採用された彼は既に士官学校から学生の資料を貰っている。だがグロンダーズで行われる模擬戦を控えたベレトはここ数日、放課後になると学級の皆に話を聞くため修道院の敷地内を走り回っていた。
ローレンツはあの時、模造剣を配ろうとしたのは何故なのかとベレトに問われている。予め野盗たちに襲われているのを知っていたから、とは言えない。言えば狂人扱いされるだろう。
「歩兵の足が早すぎたからだ。補給部隊が本体と分断されたら敵に襲われやすくなる」
食糧がなければ兵たちは戦えない。敵軍を撤退させるため、戦端を開く前に物資の集積所を襲って物資を奪ったり焼き払ってしまうのもよくある話だ。戦わずに済むならそれがいい。ローレンツの言葉を聞いたベレトは首を縦に振った。
「それで足止めして予備の武器を渡したのか。装備をどうするかは本当に難しいんだ。あの場合は結果として合っていたな。良い判断をした」
「ありがとう先生。そう言ってもらえると霧が晴れたような気分になるよ」
戦場の霧という言葉がある。どの将も斥候などを出して可能な限り下調べはするが、それでも敵軍や戦場の正確な現状を正確に知ることはできない。霧に辺りを覆い隠された状態で指揮官は決定を下し、その責任をとる。ローレンツが命を落としたミルディン大橋にもその霧がたちこめていて、霧の中にはベレトがいた。
ベレトは無表情かつとても静かに話す。声を荒げるところを聞いた者はいない。夜の闇のような瞳で彼からじっと見つめられるとローレンツは秘密を見透かされたような気分になる。だが話題は得意とする武器へと切り替わっていった。彼は剣が最も得意だという。
「シルヴァンと同じく槍だ」
口に出した言葉は取り消せない。ローレンツは反射的にベレトが青獅子の学級の担任であるかのように扱ってしまった。例えとして出すにしても唐突すぎる。レオニーと同じく、と言うべきだった。
「シルヴァンとローレンツは槍が得意なのか。覚えておこう。そうか、フェルディアにいたからファーガスの者に詳しいのか」
今日は天気が良くベレトとローレンツ以外にも中庭で、沢山の学生が暖かい日差しと世間話を楽しんでいる。こうした時間を共有することで学級の垣根、すなわち出身地の違いを超えて同じ体験をした者同士が親しくなっていく。後の戦乱を知る身からすれば涙が出そうなほど平和な光景だ。学級の垣根を超えて結んだ友情は五年の時を経て不本意な結果に終わっている。少なくともローレンツとシルヴァンに関してはそうだった。
「そうだな、確かにメルセデスさん、アネットさんとは魔道学院にいた時からの顔見知りだ」
「ありがとう、参考になった」
そういうとベレトはリシテアを探して立ち去った。うまくやり過ごそうと緊張していたのか汗が白い背中を伝っていく。ふとした拍子に過去の記憶が言動に現れてしまわぬよう、今後は更に気をつけねばならない。
「よう、ローレンツ。そんなにファーガスの連中に詳しいなら俺にも聞かせてくれよ」
クロードはいつから話を聞いていたのだろうか。ローレンツはベレトが違和感を感じていないかどうか気にかけるあまり、クロードが耳をそばだてていることが分からなかった。
「君は人より建物の方が好みだろう?」
クロードの言動は今のところローレンツの記憶と大きく異なる点がない。先日も夜中に勝手に出歩いているところに出くわした。あの時は彼の資質を疑ったが後にエーデルガルト相手に五年間ものらりくらりと誤魔化し続けたことを今のローレンツは知っている。あの時、彼が見誤ったのはディミトリの立ち直る力だけだった。
「先生には興味があるぜ。あの人には何か秘密があるはずだ」
目の前に誰にも言えない秘密を抱えた者がいると知らず、クロードは好奇心に目を輝かせている。表面上では彼とローレンツは一歳しか歳は離れていないが、精神的には五歳の開きがある。
「暴くのではなく打ち明けさせてこそ、だろう。信頼を得たかったら闇雲に腹を探ろうとするのはやめることだ」
「そっちこそ闇雲に女子に声かけるのやめろよ。言い寄られるようになってこそ、だろ?」
だが円卓会議で海千山千の大人たちと立派に張り合っていた片鱗はもう見え始めていた。つまり痛いところを正確に突くのだ。
「なっ!僕はシルヴァンとは違う!本気で共に領地を治めてくれる配偶者を探しているのだからな!」
戦争が終わってから配偶者探しを再開しようと考えていたローレンツは結局、独身のまま生涯を終えている。愛する人がいたら降伏や敵前逃亡をしていたかもしれないが、それでも今度は生涯を共に過ごす相手が欲しい。
「資質を磨かなくても良い立場な奴は気軽で良いねえ」
「言っておくがあくまでも勉学のついでだし君に対する監視の目を緩める気はないからな」
そうすればローレンツはクロードのうちに立ちこめる霧が晴れる時を見逃さずに済むのかもしれない。畳む
「説明できない」3.初戦
#説明できない #クロロレ #完売本
三学級対抗の模擬戦はクロードたちの勝利に終わった。これもクロードの記憶とは異なっている。容赦がなかったベレスの記憶があるクロードは事前に何か工作するか、ベレトに探りを入れてみたが拒否された。こんな下らないことに全力を尽くすな、という意味なのか気高い倫理観の持ち主なのか、まだクロードには分からない。腹下しの薬は冗談だったが賛同してもらえたら、武器庫に忍び込んで他学級の使う武器の持ち手にひびを入れてしまうつもりだった。
母国やデアドラと比べるとガルグ=マクは肌寒い。気に食わない異母兄たちが王宮で働く女官を寝室に引っ張り込むような寒さだ。それでも来たばかりの頃と比べればかなり暖かくなっている。過酷な太陽の光に慣れたクロードの瞳にも山の緑は眩しく映った。長時間、薄暗い書庫で本を物色していたからだろうか。廊下に差す光に緑の瞳を細めながら歩いていると大司教レアの補佐を務めるセテスに声をかけられた。クロードは規則違反に目を光らせている彼のことがあまり得意ではない。
「ちょうど良かった。クロード、後でベレトと共にこちらに顔を出しなさい」
「分かりました。セテスさんは先生が今どの辺りにいるかご存知ですか?」
ベレトは神出鬼没で授業と食事時以外は何処にいるのか全く見当がつかない。
「忙しくて探していられないから君に頼んだのだ」
セテスにも面倒事を誰かに押し付けるような人間らしさがあったということだ。クロードは記憶力が良い方だと自負している。故にここ一節ほどは記憶と現実の食い違いに驚いていた。最も大きいのは担任教師の性別と模擬戦の勝敗で、細かな違いを挙げればきりがない。その度に過去の自分は何を見ていたのだろうかと思う。
士官学校は修道院の中にあるので、学生寮や校舎以外の施設には修道士やセイロス騎士団の者たちが闊歩している。とりあえず目についた顔見知り全てに片っ端から声をかけていく。食堂にいた、市場にいた、訓練場にいた、と言った具合に皆言うことが異なる。
訓練場に行くとエーデルガルトが斧を、ディミトリが槍を振り回していた。それぞれの従者であるヒューベルト、ドゥドゥが着替えや水を用意して傍に控えている。ディミトリとドゥドゥがこの場に居てくれるお陰で身構えずに済む。クロードは内心でファーガスの大男たちに感謝した。
「クロードも混ざるか?」
「あら珍しい。クロードじゃない」
報告書には明記されていなかったが彼女の振るうアイムールがジュディッド、イグナーツ、レオニーの命を奪ったのかもしれない。
「皆、精が出るな。セテスさんに頼まれてベレト先生を探してるんだが」
「先程までこちらにいらっしゃったのだが、昼食用の魚を釣りたいと言って出ていってしまった」
ダスカー出身であるドゥドゥの話し方はクロードにとって分かりやすい。歴史を誇る古都アンヴァルの名家出身であるヒューベルトの言葉は丁寧すぎて分かりにくいのだ。自領とアンヴァルを行き来して育っているリンハルト、カスパル、フェルディナント、ベルナデッタの言葉は普通なのでそれが彼の個性なのだろう。
「釣果に恵まれなければ長居なさっていることでしょう」
つまりヒューベルトはさっさと行かねばまたすれ違う、と言いたいのだ。いちいち意図を読まねばならないので彼と話していると甘いものが欲しくなる。クロードは四人に礼を言い、走って釣り堀に向かうとベレトがしゃがみ込んで犬の腹をなでていた。動物が好きで釣りが上手いのはベレスと同じらしい。魚籠の中にはそこそこの大物が入っている。
「先生、セテスさんが呼んでいた。俺と一緒に来いと言っている」
ベレトは執務室に行く前に食堂に魚を預けた。確かに魚籠を持ったままでは中の魚が傷んでしまうだろう。
執務室で告げられたのは奉仕活動についてだった。あくまでもセイロス騎士団の補佐だが盗賊討伐に当たれという。
「先生は新兵をたっぷり引き連れて戦場へ行ったことがあるか?」
クロードの質問に普通ならうんざりした表情を浮かべる筈だが、首を横に振るベレトの顔からはなんの表情も読み取れなかった。
「ジェラルドは腕が立つ者以外傭兵団に入れなかった」
傭兵団は訓練機関ではないので当たり前と言えば当たり前の話だった。だが士官学校は違う。そもそも入学前に出来なかったことを出来るようになりにいくのが学校だ。
「そりゃそうだよな、俺たちまずは騎士団の足を引っ張らないようにしないと。ちょっと装備を確かめてくる」
武器庫へ行こうとしたクロードは急にベレトから首根っこを掴まれた。
「食べられるのに食事を抜くのは良くない」
クロードは食への拘りをあまり表に出していない。詳しく語りすぎれば国外で育っていることが明るみに出てしまう。だが食事を抜くのもまた悪目立ちするのも事実だ。さっそくベレトに嗜められているし、ラファエルやローレンツに気付かれればもっと大きな騒ぎになるかもしれない。
クロードはベレトに勧められるがまま彼が釣った魚で作られたパイクの贅沢グリルを平らげた。
クロードから自分たちを襲った盗賊の討伐が今節の課題である、と告げられた皆は初陣だと言って沸き立っていた。金鹿の学級は騎士を目指す平民が目立つ学級で、入学以前に領主の嫡子として盗賊討伐を体験している者はクロードとローレンツしかいないらしい。クロードはローレンツの印象よりはるかに慎重だった。毎日先行したセイロス騎士団がどの方面へ展開していったのか細かく記録をつけて皆に知らせている。セイロス騎士団に追い込んでもらえるとはいえ、どこで戦うのかが気になっていたらしい。
出撃当日、支度を整え大広間で待つ皆の元にベレトがやってきた時にはローレンツたちはどこで戦うのか既に分かっていた。
「騎士団が敵を追い詰めたそうだね。場所はザナド……赤き谷と呼ばれている」
そう言えばクロードはザナドが候補に上がって以来、やたら彼の地についた異名の由来を気にしていた。赤土の土地なのか赤い花でも咲き乱れているのか。土地の異名や古名にはかつてそこで何があったのかが表されていることが多い。土地の環境によっては毒消しが必要になる場合もある。だが先行した騎士団によると特殊な条件は何もない、とのことだった。初陣の者たちにとっては本当にありがたい。
修道院の敷地を出るまでは皆、はしゃいでいたがザナドが近づくにつれて口数が少なくなってきた。静かになったところを見計らったベレトが学生たちの間を縫って声をかけて回っている。一度戦闘が開始されたら終わるまでまともに会話などできない。
「ローレンツ、ラファエルと一緒に前衛を担当してくれ」
「引き受けた」
「だが最初は攻め込まなくていい。二人とも大きくて目立つからな。ぎりぎりまで敵を引き寄せてイグナーツとクロードの一射目を待ってから攻撃するんだ」
ローレンツにはベレトの意図が読めなかった。何故こちらから攻撃しないのだろうか。
「囮になれと?」
「囮というか脅迫の種だな。一射目を当てなければ前衛の二人が攻撃されるのだから当てなくては〝ならない〟」
ベレトは顔の横に両手をあげて人差し指と中指をくいくいと折り曲げている。引用符のつもりらしい。しかし顔は真顔のままなので凄まじい違和感だ。
「そんなことは自明の理ではないか」
「誰かが遠方から射られてそこから戦端が開く。だが自分の手で戦端が開かれることに耐えられる者の方が少ない」
だから一射目は無意識に外してしまう者が多いのだという。しかし前衛を守るためにイグナーツもクロードも必ず敵に当てなくては〝ならない〟。弓での援護を受けながら前進すれば相手は怯む。ローレンツはベレトのあだ名が何故、灰色の悪魔であるのかわかったような気がした。彼なりに新兵の教育と生存率向上を考えた結果なのだろうが、とにかくえげつない。これが危険な現場を渡り歩いてきた者の感覚なのだろう。
「なるほど、だが僕はクロードと親しくないぞ」
だがイグナーツとラファエルは元より友人同士なので有効だ。よく考えられている。
「一緒に戦っていくうちに親しくなる。というか親しくならざるを得ない。小規模な戦闘には参加したことがあるのだろう?ラファエルを頼んだぞ」
そう言うとベレトは剣帯を鳴らしながら駆け足でイグナーツの方へ向かっていった。ローレンツには五年間の記憶があるので素直に受け入れることが出来たが、いきなりこんな事を言われた他の者は何を思うのだろうか。
ザナドに到着してみればまず橋を渡らねばならなかった。ベレトの読みは見事に当たり、猛り狂う盗賊たちは突出したローレンツとラファエルに突進してくる。谷に籠っていては勝ち目のない盗賊たちはほんの少しであろうとセイロス騎士団側の戦力を削れるのではないか、と言う期待に縋っていた。だがまだ堪えねばならない。ローレンツたちの後方から矢羽が風を切る音がして前方からは人が倒れ込む音や呻き声がした。
「前回は不意を突かれちまったが……ま、盗賊なんてこんなもんか」
そう呟いたクロードの放った矢は倒れ込んだ盗賊の口の中に刺さっている。リーガンの紋章の力が成し遂げたのか、仲間への愛着が成し遂げたのかローレンツには分からない。イグナーツは一撃必殺といかなかったようだが、それでもこちらの矢は全て敵に損害を与えている。見事だ、と思いながらローレンツは矢傷に苦しむ盗賊に槍で引導を渡してやった。
「民の暮らしを守るのが貴族の責務……。恨まないでくれたまえよ」
ベレトの指示通り偽りの希望を与えて誘い出し、敵の戦力を削っていくと盗賊の首領コスタスが最後にただ一人取り残された。ここまで上手くいくならこの場ではやり方を変えることはない。叫びながら斧を振り回しているコスタスにクロードが矢を番えた。敵を油断させるために後ろを向いていたのでローレンツは初めて戦場で彼の顔を眺めている。
「貴族には貴族の苦労があるんだよ。俺もつい最近知ったんだがな」
いつも彼の周りに漂い、正体を隠そうとする靄がない。真のクロードの姿がそこにある、ローレンツはそう感じた。畳む
#説明できない #クロロレ #完売本
三学級対抗の模擬戦はクロードたちの勝利に終わった。これもクロードの記憶とは異なっている。容赦がなかったベレスの記憶があるクロードは事前に何か工作するか、ベレトに探りを入れてみたが拒否された。こんな下らないことに全力を尽くすな、という意味なのか気高い倫理観の持ち主なのか、まだクロードには分からない。腹下しの薬は冗談だったが賛同してもらえたら、武器庫に忍び込んで他学級の使う武器の持ち手にひびを入れてしまうつもりだった。
母国やデアドラと比べるとガルグ=マクは肌寒い。気に食わない異母兄たちが王宮で働く女官を寝室に引っ張り込むような寒さだ。それでも来たばかりの頃と比べればかなり暖かくなっている。過酷な太陽の光に慣れたクロードの瞳にも山の緑は眩しく映った。長時間、薄暗い書庫で本を物色していたからだろうか。廊下に差す光に緑の瞳を細めながら歩いていると大司教レアの補佐を務めるセテスに声をかけられた。クロードは規則違反に目を光らせている彼のことがあまり得意ではない。
「ちょうど良かった。クロード、後でベレトと共にこちらに顔を出しなさい」
「分かりました。セテスさんは先生が今どの辺りにいるかご存知ですか?」
ベレトは神出鬼没で授業と食事時以外は何処にいるのか全く見当がつかない。
「忙しくて探していられないから君に頼んだのだ」
セテスにも面倒事を誰かに押し付けるような人間らしさがあったということだ。クロードは記憶力が良い方だと自負している。故にここ一節ほどは記憶と現実の食い違いに驚いていた。最も大きいのは担任教師の性別と模擬戦の勝敗で、細かな違いを挙げればきりがない。その度に過去の自分は何を見ていたのだろうかと思う。
士官学校は修道院の中にあるので、学生寮や校舎以外の施設には修道士やセイロス騎士団の者たちが闊歩している。とりあえず目についた顔見知り全てに片っ端から声をかけていく。食堂にいた、市場にいた、訓練場にいた、と言った具合に皆言うことが異なる。
訓練場に行くとエーデルガルトが斧を、ディミトリが槍を振り回していた。それぞれの従者であるヒューベルト、ドゥドゥが着替えや水を用意して傍に控えている。ディミトリとドゥドゥがこの場に居てくれるお陰で身構えずに済む。クロードは内心でファーガスの大男たちに感謝した。
「クロードも混ざるか?」
「あら珍しい。クロードじゃない」
報告書には明記されていなかったが彼女の振るうアイムールがジュディッド、イグナーツ、レオニーの命を奪ったのかもしれない。
「皆、精が出るな。セテスさんに頼まれてベレト先生を探してるんだが」
「先程までこちらにいらっしゃったのだが、昼食用の魚を釣りたいと言って出ていってしまった」
ダスカー出身であるドゥドゥの話し方はクロードにとって分かりやすい。歴史を誇る古都アンヴァルの名家出身であるヒューベルトの言葉は丁寧すぎて分かりにくいのだ。自領とアンヴァルを行き来して育っているリンハルト、カスパル、フェルディナント、ベルナデッタの言葉は普通なのでそれが彼の個性なのだろう。
「釣果に恵まれなければ長居なさっていることでしょう」
つまりヒューベルトはさっさと行かねばまたすれ違う、と言いたいのだ。いちいち意図を読まねばならないので彼と話していると甘いものが欲しくなる。クロードは四人に礼を言い、走って釣り堀に向かうとベレトがしゃがみ込んで犬の腹をなでていた。動物が好きで釣りが上手いのはベレスと同じらしい。魚籠の中にはそこそこの大物が入っている。
「先生、セテスさんが呼んでいた。俺と一緒に来いと言っている」
ベレトは執務室に行く前に食堂に魚を預けた。確かに魚籠を持ったままでは中の魚が傷んでしまうだろう。
執務室で告げられたのは奉仕活動についてだった。あくまでもセイロス騎士団の補佐だが盗賊討伐に当たれという。
「先生は新兵をたっぷり引き連れて戦場へ行ったことがあるか?」
クロードの質問に普通ならうんざりした表情を浮かべる筈だが、首を横に振るベレトの顔からはなんの表情も読み取れなかった。
「ジェラルドは腕が立つ者以外傭兵団に入れなかった」
傭兵団は訓練機関ではないので当たり前と言えば当たり前の話だった。だが士官学校は違う。そもそも入学前に出来なかったことを出来るようになりにいくのが学校だ。
「そりゃそうだよな、俺たちまずは騎士団の足を引っ張らないようにしないと。ちょっと装備を確かめてくる」
武器庫へ行こうとしたクロードは急にベレトから首根っこを掴まれた。
「食べられるのに食事を抜くのは良くない」
クロードは食への拘りをあまり表に出していない。詳しく語りすぎれば国外で育っていることが明るみに出てしまう。だが食事を抜くのもまた悪目立ちするのも事実だ。さっそくベレトに嗜められているし、ラファエルやローレンツに気付かれればもっと大きな騒ぎになるかもしれない。
クロードはベレトに勧められるがまま彼が釣った魚で作られたパイクの贅沢グリルを平らげた。
クロードから自分たちを襲った盗賊の討伐が今節の課題である、と告げられた皆は初陣だと言って沸き立っていた。金鹿の学級は騎士を目指す平民が目立つ学級で、入学以前に領主の嫡子として盗賊討伐を体験している者はクロードとローレンツしかいないらしい。クロードはローレンツの印象よりはるかに慎重だった。毎日先行したセイロス騎士団がどの方面へ展開していったのか細かく記録をつけて皆に知らせている。セイロス騎士団に追い込んでもらえるとはいえ、どこで戦うのかが気になっていたらしい。
出撃当日、支度を整え大広間で待つ皆の元にベレトがやってきた時にはローレンツたちはどこで戦うのか既に分かっていた。
「騎士団が敵を追い詰めたそうだね。場所はザナド……赤き谷と呼ばれている」
そう言えばクロードはザナドが候補に上がって以来、やたら彼の地についた異名の由来を気にしていた。赤土の土地なのか赤い花でも咲き乱れているのか。土地の異名や古名にはかつてそこで何があったのかが表されていることが多い。土地の環境によっては毒消しが必要になる場合もある。だが先行した騎士団によると特殊な条件は何もない、とのことだった。初陣の者たちにとっては本当にありがたい。
修道院の敷地を出るまでは皆、はしゃいでいたがザナドが近づくにつれて口数が少なくなってきた。静かになったところを見計らったベレトが学生たちの間を縫って声をかけて回っている。一度戦闘が開始されたら終わるまでまともに会話などできない。
「ローレンツ、ラファエルと一緒に前衛を担当してくれ」
「引き受けた」
「だが最初は攻め込まなくていい。二人とも大きくて目立つからな。ぎりぎりまで敵を引き寄せてイグナーツとクロードの一射目を待ってから攻撃するんだ」
ローレンツにはベレトの意図が読めなかった。何故こちらから攻撃しないのだろうか。
「囮になれと?」
「囮というか脅迫の種だな。一射目を当てなければ前衛の二人が攻撃されるのだから当てなくては〝ならない〟」
ベレトは顔の横に両手をあげて人差し指と中指をくいくいと折り曲げている。引用符のつもりらしい。しかし顔は真顔のままなので凄まじい違和感だ。
「そんなことは自明の理ではないか」
「誰かが遠方から射られてそこから戦端が開く。だが自分の手で戦端が開かれることに耐えられる者の方が少ない」
だから一射目は無意識に外してしまう者が多いのだという。しかし前衛を守るためにイグナーツもクロードも必ず敵に当てなくては〝ならない〟。弓での援護を受けながら前進すれば相手は怯む。ローレンツはベレトのあだ名が何故、灰色の悪魔であるのかわかったような気がした。彼なりに新兵の教育と生存率向上を考えた結果なのだろうが、とにかくえげつない。これが危険な現場を渡り歩いてきた者の感覚なのだろう。
「なるほど、だが僕はクロードと親しくないぞ」
だがイグナーツとラファエルは元より友人同士なので有効だ。よく考えられている。
「一緒に戦っていくうちに親しくなる。というか親しくならざるを得ない。小規模な戦闘には参加したことがあるのだろう?ラファエルを頼んだぞ」
そう言うとベレトは剣帯を鳴らしながら駆け足でイグナーツの方へ向かっていった。ローレンツには五年間の記憶があるので素直に受け入れることが出来たが、いきなりこんな事を言われた他の者は何を思うのだろうか。
ザナドに到着してみればまず橋を渡らねばならなかった。ベレトの読みは見事に当たり、猛り狂う盗賊たちは突出したローレンツとラファエルに突進してくる。谷に籠っていては勝ち目のない盗賊たちはほんの少しであろうとセイロス騎士団側の戦力を削れるのではないか、と言う期待に縋っていた。だがまだ堪えねばならない。ローレンツたちの後方から矢羽が風を切る音がして前方からは人が倒れ込む音や呻き声がした。
「前回は不意を突かれちまったが……ま、盗賊なんてこんなもんか」
そう呟いたクロードの放った矢は倒れ込んだ盗賊の口の中に刺さっている。リーガンの紋章の力が成し遂げたのか、仲間への愛着が成し遂げたのかローレンツには分からない。イグナーツは一撃必殺といかなかったようだが、それでもこちらの矢は全て敵に損害を与えている。見事だ、と思いながらローレンツは矢傷に苦しむ盗賊に槍で引導を渡してやった。
「民の暮らしを守るのが貴族の責務……。恨まないでくれたまえよ」
ベレトの指示通り偽りの希望を与えて誘い出し、敵の戦力を削っていくと盗賊の首領コスタスが最後にただ一人取り残された。ここまで上手くいくならこの場ではやり方を変えることはない。叫びながら斧を振り回しているコスタスにクロードが矢を番えた。敵を油断させるために後ろを向いていたのでローレンツは初めて戦場で彼の顔を眺めている。
「貴族には貴族の苦労があるんだよ。俺もつい最近知ったんだがな」
いつも彼の周りに漂い、正体を隠そうとする靄がない。真のクロードの姿がそこにある、ローレンツはそう感じた。畳む
「説明できない」4.背叛
#説明できない #クロロレ #完売本
皆の初陣が終わるとクロードの記憶通りに事態が進み、ロナート卿の叛乱の知らせがガルグ=マクにもたらされた。セイロス教会はロナート卿の養子であるアッシュに何の沙汰も下そうとしていない。軟禁もされないのでアッシュの方が身の潔白を証明するべく自発的に修道院の敷地内に閉じこもっている。鎮圧に英雄の遺産である雷霆まで持ち出す割に対応が一貫していない。前節と同じく金鹿の学級がセイロス騎士団の補佐を任された。クロードの記憶通りならばエーデルガルトたちが鎮圧にあたっていた筈だが展開が違う。彼女はあの時、帝国に対して蜂起したロナート卿を内心では応援していたのだろうか。
アッシュは誰とも話したくない気分の時にドゥドゥが育てた花をよく眺めている。何故クロードがそのことを知っているか、と言うと温室の一角は学生に解放されていて、そこで薬草を育てているからだ。薬草は毒草でもある。他の区画に影響が出ないようクロードなりに気を使っていたが、それでもベレトはクロードが使用している一角をじっと見ていた。
「マヌエラ先生に何か言われたのか? 致死性のものは育ててないぜ」
「その小さな白い花には毒があるのか?」
ベレトが指さした白い花はクロードが根っこ目当てで育てているものだ。花に毒性はないのでそう告げると、花束に入れたいので分けて貰えないかという。そう言えばベレトは変なところで義理堅く、学生全員の誕生日に花束を贈っていた。
「今月はシルヴァンとローレンツとエーデルガルトの誕生日がある。他の二人はともかくローレンツには何か渡すべきだ。前節は世話になったのだから」
クロードは先月ラファエルに干し肉を渡した。士官学校に進学する平民の学生は級長を務める貴族や王族の学生から誕生日を祝われることを名誉としている。レオニーやイグナーツのことは気にかけていたが、ローレンツのことは五年前と変わらず失念していた。しかしベレトが言うことは正しい。
彼は思うところがある、とクロードに対してはっきり宣言した。だが初陣のイグナーツとクロードの実力を信頼し、ラファエルと共に前線で危険な囮役を引き受けている。確かにクロードはローレンツに何か贈るべきだ。
六月十三日当日を迎え七月二十四日までの五週間、クロードはローレンツの二歳年下になった。茶会はベレトに取られてしまったし、手頃な茶葉や茶菓子は他の者と被ってしまう可能性がある。背に腹はかえられぬ、という訳で皆がそろそろ寝ようかという頃、クロードはデアドラのリーガン家から黙って持ち出したそれなりに高い酒を手にローレンツの部屋を訪れた。
扉を開けたローレンツはクロードが持っている酒瓶に目をやると口の端を上げた。どうやら価値がわかっているらしい。
「君から何か貰えるとは嬉しい誤算だ。入りたまえ」
そしてクロードには全く期待していなかったらしい。ベレトに言われるまで不義理を極めていたのはクロード自身が誕生日にあまり思い入れがないからだ。パルミラには月に一度その月に生まれた者をまとめて祝う慣習があり、誕生日を個別に祝わない。
ローレンツの部屋は持ち主の気質がそのまま現れたような雰囲気だったが、神経質さや頑なさは感じられない。ベレト以外からも薔薇の花束をたくさん貰っていて花瓶が足りなかったのか、小物が入っていたはずの籠にまで活けてある。きっとその中には水を張った杯でも仕込んであるのだろう。花は瑞々しさを保っている。
「中々、他の奴と被らない品が思いつかなくてな」
クロードが瓶を渡すとローレンツは慣れた手つきで栓を開けた。下手くそが開けると栓を砕いてしまう。この手のことは従僕にやらせているかと思っていたが、どうやらそうではないらしい。
「いや、これは重畳だ。だがこれは本当にいい酒だから一本丸ごとは気がひける。そうだな、一杯だけいただこう」
そう言うとローレンツは棚から小さめの杯を二つ出した。琥珀色の液体が二つの杯を満たしていく。クロードはローレンツがこんな柔らかな発想をするとは思っていなかった。持参した蒸留酒は甘いものにも合うのでローレンツがリシテアたちから貰った焼き菓子がどんどん減っていく。昔のクロードなら警戒して食べなかっただろう。だが自分の采配が間違っていたせいで戦死したリシテアたちが作ったものを今のクロードは拒否することが出来ない。
「近頃ずっとロナート卿の件で機嫌が悪そうに見えたから気になってたんだ」
ロナート卿叛乱の報せを受けてからローレンツはずっと怒っていた。きっと彼は領民を巻き込んだことが許せないのだろう。そしてアッシュが処断されないことを不思議がっていた。クロードはセイロス教会がダスカーの戦後処理に失敗したせいで叛乱が起きたことを既に知っている。全てがお粗末すぎて怒る気にもなれない。
「皆から祝われたのだ。君までこうして一杯献じてくれたわけだし嬉しくならないわけがなかろう」
白い肌を酒精で染めながら、ローレンツは嬉しそうに今日皆がくれた祝いの品について細々と教えてくれた。彼がこんなに情が深いと五年前から知っていたら、自分は果たして敗戦処理を任せただろうか。五年前の自分は何を見逃したのだろうか。
雷霆を振るうカトリーヌの名を聞いた者に多少なりとも英雄の遺産や紋章の知識があったなら、それがとんだ茶番だと判るだろう。だが無謬であるセイロス教会が彼女をカサンドラではなくカトリーヌ、と呼ぶのならそれに従うしかない。カロン家当主としても令嬢カサンドラに死なれるよりはガルグ=マクで生きていてくれた方が良いのだろう。
ローレンツは霧深い街道をガスパール城に向けて黙々と進んでいた。前方ではクロードとベレトとカトリーヌが何やら話している。ローレンツは五年前に帝国軍が破竹の快進撃を見せた際、正直言ってファーガス神聖王国がほぼ崩壊したと思った。今の彼らの会話を耳にしても、ファーガスが凋落しているという印象が深まっていく。青獅子の学級に所属する学生たちは士官学校に入る前に初陣を済ませている者が多い。それはダスカーの悲劇以降、正常が不安定で小規模な騒乱が後を立たずにいるからだ。
だからあの時ローレンツはフェルディナントと共にミルディン大橋に立った。ファーガスは近々自壊するだろうし、パルミラとの国境を守りながら強大な帝国に抗う力が同盟にはない。ならばせめて領地と領民を守りたいと思った。霧の立ちこめる行路は人生にも似ている。いくら整備されていようと足元が見えなければ転倒してしまう。ローレンツは霧の中で先日激しく転倒し、そのまま人生を終えた筈なのに何故か立ち上がる機会を得た。この機会をどう活かすのか、は全て己の言動にかかっているので慎重に行動せねばならない。
敵襲を告げる声が聞こえ、あたりが俄に騒がしくなる。ローレンツは槍を握り直した。戦場は霧に覆われている。どこに何かあるのか、誰がいるのか全く分からない。だがカトリーヌ率いる教団兵たちは四方から囲まれることを全く恐れず、霧の中へ突っ込んでいく。どうすべきか一瞬躊躇したその時、後方から矢が飛んできてローレンツの目の前にいた敵に刺さった。
「あんなの今の俺たちには無理だから慎重に行こうぜ」
クロードの持つリーガンの紋章は英雄の遺産であるフェイルノートに適合する。現時点で将来フェイルノートを持つに相応しい弓の腕だった。
「ありがとうクロード。そうだな、若輩者にも相応しい振る舞いがある」
せっかく露払いをしてくれると言うのだから任せておくに限る。
「先生が言うにはこの時期、この辺りはここまで濃い霧が発生しないんだそうだ」
ベレトは人の意志で作り上げたものに興味を持たないが地形や天候には興味を持っている。戦闘に関わることだけはとても詳しい。
「ダークメイジか」
盗賊の中にダークメイジがいると厄介だ。霧や毒を発生させる。ローレンツはグロスタール領での盗賊討伐や土地の境界線をめぐる小競り合いの調停に赴いた時に幾度も嫌な思いをしていた。
「先生は副官のヒルダと二人で突っ込んで行ったよ。まあ、あの二人ならすぐに仕留めるだろう」
「ヒルダさんを引っ張っていくのも大変そうだが……さすが先生だな……」
前方からもうやだ! 本気で戦っちゃったじゃない! というヒルダの声が聞こえると同時に霧が晴れた。どこに誰がいるのか明確に分かってしまうので手加減はしてやれない。手槍を構えたローレンツの後ろで弓を引く音がした。クロードは右前方で孤立している教団兵の援護をするのだろう。
視野が回復すれば武器に慣れぬ民草などセイロス騎士団の敵ではない。ローレンツたちは街の人々による脆弱な包囲網を突破し、ロナート卿と対峙するカトリーヌ、ことカサンドラが雷霆を振るうところを見た。怪しい光を放つそれは紋章を持たぬ者が握ればそれだけで命を落とすこともあるのだと言う。クロードたちが弓矢や手槍、それに黒魔法で援護したからだろうか。外敵から民を守るため女神から与えられた英雄の遺産は領民に慕われるロナート卿の命を一撃で奪った。
ロナート卿の今際の際の絶叫はカトリーヌことカサンドラを守る建前を無効にした。実家から逃走する際に英雄の遺産を持ち出した時点で、もう彼女は越えてはならない線を越えている。レア以外の全ての者を自分の人生から切り離してしまったカトリーヌはセイロス騎士団の騎士としては正しい。だがカロン家の令嬢としては死刑になるような大罪を犯す男と親しくなり、家宝を盗み出したろくでなしとなる。
その逸脱や矛盾にローレンツは五年前と同じく恐怖を覚えた。五年前は又聞きでしかなかったが直接見聞きすると迫力が違う。些細な立ち回りの錯誤で彼女は恋人を失い、名誉を失い、家族を失い、名を失った。カトリーヌという新しい名を与えてくれたレア以外、彼女は何も持たない。ローレンツは今も昔も愛する人を持たないのでそこは想像するしかないのだが、他の三つは想像するだけで身を切られるような思いがした。英雄の遺産を受け継ぐ名家の者は失望させてはならない、と言われながら育つ。生まれてすぐに紋章の有無で振り分けられ、誰も彼もが必死で己の立場にしがみつくのだ。
無力感は人を狂わせる。悲惨な現実を目の当たりにして何か出来ないか、と闇雲に奔走した結果が何層にも重なり───ロナート卿の叛乱は世の中を少し乱しただけで終わった。畳む
#説明できない #クロロレ #完売本
皆の初陣が終わるとクロードの記憶通りに事態が進み、ロナート卿の叛乱の知らせがガルグ=マクにもたらされた。セイロス教会はロナート卿の養子であるアッシュに何の沙汰も下そうとしていない。軟禁もされないのでアッシュの方が身の潔白を証明するべく自発的に修道院の敷地内に閉じこもっている。鎮圧に英雄の遺産である雷霆まで持ち出す割に対応が一貫していない。前節と同じく金鹿の学級がセイロス騎士団の補佐を任された。クロードの記憶通りならばエーデルガルトたちが鎮圧にあたっていた筈だが展開が違う。彼女はあの時、帝国に対して蜂起したロナート卿を内心では応援していたのだろうか。
アッシュは誰とも話したくない気分の時にドゥドゥが育てた花をよく眺めている。何故クロードがそのことを知っているか、と言うと温室の一角は学生に解放されていて、そこで薬草を育てているからだ。薬草は毒草でもある。他の区画に影響が出ないようクロードなりに気を使っていたが、それでもベレトはクロードが使用している一角をじっと見ていた。
「マヌエラ先生に何か言われたのか? 致死性のものは育ててないぜ」
「その小さな白い花には毒があるのか?」
ベレトが指さした白い花はクロードが根っこ目当てで育てているものだ。花に毒性はないのでそう告げると、花束に入れたいので分けて貰えないかという。そう言えばベレトは変なところで義理堅く、学生全員の誕生日に花束を贈っていた。
「今月はシルヴァンとローレンツとエーデルガルトの誕生日がある。他の二人はともかくローレンツには何か渡すべきだ。前節は世話になったのだから」
クロードは先月ラファエルに干し肉を渡した。士官学校に進学する平民の学生は級長を務める貴族や王族の学生から誕生日を祝われることを名誉としている。レオニーやイグナーツのことは気にかけていたが、ローレンツのことは五年前と変わらず失念していた。しかしベレトが言うことは正しい。
彼は思うところがある、とクロードに対してはっきり宣言した。だが初陣のイグナーツとクロードの実力を信頼し、ラファエルと共に前線で危険な囮役を引き受けている。確かにクロードはローレンツに何か贈るべきだ。
六月十三日当日を迎え七月二十四日までの五週間、クロードはローレンツの二歳年下になった。茶会はベレトに取られてしまったし、手頃な茶葉や茶菓子は他の者と被ってしまう可能性がある。背に腹はかえられぬ、という訳で皆がそろそろ寝ようかという頃、クロードはデアドラのリーガン家から黙って持ち出したそれなりに高い酒を手にローレンツの部屋を訪れた。
扉を開けたローレンツはクロードが持っている酒瓶に目をやると口の端を上げた。どうやら価値がわかっているらしい。
「君から何か貰えるとは嬉しい誤算だ。入りたまえ」
そしてクロードには全く期待していなかったらしい。ベレトに言われるまで不義理を極めていたのはクロード自身が誕生日にあまり思い入れがないからだ。パルミラには月に一度その月に生まれた者をまとめて祝う慣習があり、誕生日を個別に祝わない。
ローレンツの部屋は持ち主の気質がそのまま現れたような雰囲気だったが、神経質さや頑なさは感じられない。ベレト以外からも薔薇の花束をたくさん貰っていて花瓶が足りなかったのか、小物が入っていたはずの籠にまで活けてある。きっとその中には水を張った杯でも仕込んであるのだろう。花は瑞々しさを保っている。
「中々、他の奴と被らない品が思いつかなくてな」
クロードが瓶を渡すとローレンツは慣れた手つきで栓を開けた。下手くそが開けると栓を砕いてしまう。この手のことは従僕にやらせているかと思っていたが、どうやらそうではないらしい。
「いや、これは重畳だ。だがこれは本当にいい酒だから一本丸ごとは気がひける。そうだな、一杯だけいただこう」
そう言うとローレンツは棚から小さめの杯を二つ出した。琥珀色の液体が二つの杯を満たしていく。クロードはローレンツがこんな柔らかな発想をするとは思っていなかった。持参した蒸留酒は甘いものにも合うのでローレンツがリシテアたちから貰った焼き菓子がどんどん減っていく。昔のクロードなら警戒して食べなかっただろう。だが自分の采配が間違っていたせいで戦死したリシテアたちが作ったものを今のクロードは拒否することが出来ない。
「近頃ずっとロナート卿の件で機嫌が悪そうに見えたから気になってたんだ」
ロナート卿叛乱の報せを受けてからローレンツはずっと怒っていた。きっと彼は領民を巻き込んだことが許せないのだろう。そしてアッシュが処断されないことを不思議がっていた。クロードはセイロス教会がダスカーの戦後処理に失敗したせいで叛乱が起きたことを既に知っている。全てがお粗末すぎて怒る気にもなれない。
「皆から祝われたのだ。君までこうして一杯献じてくれたわけだし嬉しくならないわけがなかろう」
白い肌を酒精で染めながら、ローレンツは嬉しそうに今日皆がくれた祝いの品について細々と教えてくれた。彼がこんなに情が深いと五年前から知っていたら、自分は果たして敗戦処理を任せただろうか。五年前の自分は何を見逃したのだろうか。
雷霆を振るうカトリーヌの名を聞いた者に多少なりとも英雄の遺産や紋章の知識があったなら、それがとんだ茶番だと判るだろう。だが無謬であるセイロス教会が彼女をカサンドラではなくカトリーヌ、と呼ぶのならそれに従うしかない。カロン家当主としても令嬢カサンドラに死なれるよりはガルグ=マクで生きていてくれた方が良いのだろう。
ローレンツは霧深い街道をガスパール城に向けて黙々と進んでいた。前方ではクロードとベレトとカトリーヌが何やら話している。ローレンツは五年前に帝国軍が破竹の快進撃を見せた際、正直言ってファーガス神聖王国がほぼ崩壊したと思った。今の彼らの会話を耳にしても、ファーガスが凋落しているという印象が深まっていく。青獅子の学級に所属する学生たちは士官学校に入る前に初陣を済ませている者が多い。それはダスカーの悲劇以降、正常が不安定で小規模な騒乱が後を立たずにいるからだ。
だからあの時ローレンツはフェルディナントと共にミルディン大橋に立った。ファーガスは近々自壊するだろうし、パルミラとの国境を守りながら強大な帝国に抗う力が同盟にはない。ならばせめて領地と領民を守りたいと思った。霧の立ちこめる行路は人生にも似ている。いくら整備されていようと足元が見えなければ転倒してしまう。ローレンツは霧の中で先日激しく転倒し、そのまま人生を終えた筈なのに何故か立ち上がる機会を得た。この機会をどう活かすのか、は全て己の言動にかかっているので慎重に行動せねばならない。
敵襲を告げる声が聞こえ、あたりが俄に騒がしくなる。ローレンツは槍を握り直した。戦場は霧に覆われている。どこに何かあるのか、誰がいるのか全く分からない。だがカトリーヌ率いる教団兵たちは四方から囲まれることを全く恐れず、霧の中へ突っ込んでいく。どうすべきか一瞬躊躇したその時、後方から矢が飛んできてローレンツの目の前にいた敵に刺さった。
「あんなの今の俺たちには無理だから慎重に行こうぜ」
クロードの持つリーガンの紋章は英雄の遺産であるフェイルノートに適合する。現時点で将来フェイルノートを持つに相応しい弓の腕だった。
「ありがとうクロード。そうだな、若輩者にも相応しい振る舞いがある」
せっかく露払いをしてくれると言うのだから任せておくに限る。
「先生が言うにはこの時期、この辺りはここまで濃い霧が発生しないんだそうだ」
ベレトは人の意志で作り上げたものに興味を持たないが地形や天候には興味を持っている。戦闘に関わることだけはとても詳しい。
「ダークメイジか」
盗賊の中にダークメイジがいると厄介だ。霧や毒を発生させる。ローレンツはグロスタール領での盗賊討伐や土地の境界線をめぐる小競り合いの調停に赴いた時に幾度も嫌な思いをしていた。
「先生は副官のヒルダと二人で突っ込んで行ったよ。まあ、あの二人ならすぐに仕留めるだろう」
「ヒルダさんを引っ張っていくのも大変そうだが……さすが先生だな……」
前方からもうやだ! 本気で戦っちゃったじゃない! というヒルダの声が聞こえると同時に霧が晴れた。どこに誰がいるのか明確に分かってしまうので手加減はしてやれない。手槍を構えたローレンツの後ろで弓を引く音がした。クロードは右前方で孤立している教団兵の援護をするのだろう。
視野が回復すれば武器に慣れぬ民草などセイロス騎士団の敵ではない。ローレンツたちは街の人々による脆弱な包囲網を突破し、ロナート卿と対峙するカトリーヌ、ことカサンドラが雷霆を振るうところを見た。怪しい光を放つそれは紋章を持たぬ者が握ればそれだけで命を落とすこともあるのだと言う。クロードたちが弓矢や手槍、それに黒魔法で援護したからだろうか。外敵から民を守るため女神から与えられた英雄の遺産は領民に慕われるロナート卿の命を一撃で奪った。
ロナート卿の今際の際の絶叫はカトリーヌことカサンドラを守る建前を無効にした。実家から逃走する際に英雄の遺産を持ち出した時点で、もう彼女は越えてはならない線を越えている。レア以外の全ての者を自分の人生から切り離してしまったカトリーヌはセイロス騎士団の騎士としては正しい。だがカロン家の令嬢としては死刑になるような大罪を犯す男と親しくなり、家宝を盗み出したろくでなしとなる。
その逸脱や矛盾にローレンツは五年前と同じく恐怖を覚えた。五年前は又聞きでしかなかったが直接見聞きすると迫力が違う。些細な立ち回りの錯誤で彼女は恋人を失い、名誉を失い、家族を失い、名を失った。カトリーヌという新しい名を与えてくれたレア以外、彼女は何も持たない。ローレンツは今も昔も愛する人を持たないのでそこは想像するしかないのだが、他の三つは想像するだけで身を切られるような思いがした。英雄の遺産を受け継ぐ名家の者は失望させてはならない、と言われながら育つ。生まれてすぐに紋章の有無で振り分けられ、誰も彼もが必死で己の立場にしがみつくのだ。
無力感は人を狂わせる。悲惨な現実を目の当たりにして何か出来ないか、と闇雲に奔走した結果が何層にも重なり───ロナート卿の叛乱は世の中を少し乱しただけで終わった。畳む
「説明できない」5.典儀
#説明できない #クロロレ #完売本
情報には出元と行き先がある。それを見極めずに判断を下すと間違いが起きる。前節、カトリーヌがロナート卿の所持品から見つけた大司教レアの暗殺計画に関する密書は様々な波紋を呼んだ。真偽の程は定かではないが対応せねばならない。
謁見の間に呼び出されたベレトから今節の課題を聞いたクロードは教会があの密書をどう判断したのか悟った。今回も彼の記憶と同じく何者かが教会を混乱させるため、作成した偽物であると判断したのだ。そうでなければ士官学校の学生に警備や見回りを担当させないだろう。だがクロードにとっては丁度良かった。賊の狙いが何処であるのか確かめるため、という大義名分を得て修道院の敷地内を直接、自由に見て回れる。
賊が聖廟の中で何かを探し、奪いに来た。そこでベレスが天帝の剣を手に取り賊を撃退したことをクロードはきちんと覚えている。だが、だからといって日頃入れない聖廟を直接探る機会を逃したくはなかった。それにロナート卿の叛乱の時と同じくまたクロードたちが当事者になっている。詳しく調査しておいて損はないだろう。
ガルグ=マクにはフォドラの外からやってきた住人がクロード以外にも存在する。自然と祖先を崇拝するパルミラからやってきたクロードはセイロス教の信者ではないし決まった信仰を持たない。いずれセイロス教の信者になるため堅信の儀をうけるであろうツィリルよりダグザから来たシャミアやブリギット出身のペトラ、そして後に教会に叛旗を翻すエーデルガルトとヒューベルトの方がクロードと精神的な距離が近い。洋灯を手に聖廟の中を眺めるとそこには無数の棺が置いてあった。盗掘されるような副葬品はない。皆、強欲を戒める宗教の聖職者だから基本は身を宝石で飾ることなく埋葬されている。彼らの生前の生き方が残された遺骨に聖なる力を与える、らしい。賊が宝物殿に宝石を盗みに来るようなそんな単純な者たちであったならば戦争は起きなかっただろう。
探索から戻った埃まみれで白く汚れたクロードから話しかけられた聖廟の衛兵が何度もくしゃみをした。ローレンツなら手巾を何枚も持ち歩いているのだろうが残念ながらクロードには持ち合わせがない。すると心底意外な人物が聖廟の入口の衛兵に手巾を渡した。
「返さなくて結構です。クロード殿、酷いお姿ですな。そのような状態で我が主と同じ建物に入らないでいただきたい」
次期皇帝の侍従に手巾を渡された衛兵は数節後、クロードの記憶通りに帝国軍がガルグ=マクへ侵攻してきたら何を思うのだろう。この時点で帝国、というかエーデルガルトたちの危険性を言いふらして回ることも出来たが白きものを冠に戴き、セイロス教の聖職者に見守られながら即位するアドラステア帝国の皇帝が教会に叛意を持っていると言っても誰も信じないことは明らかだった。
「同感だね。俺も俺と同じ建物に居たくないからさっさと風呂に入るよ」
そういうとクロードは聖廟から足早に立ち去った。おそらくヒューベルトはクロードがどこまで潜ったのか確かめに来たのだろう。埃まみれのまま敷地内を歩いていると訓練を終えて首にかけた布で顔を拭きながら寮の入り口へと歩いてくるローレンツの姿が目に入った。
「十中八九課題絡みだろうが一体どこに顔を突っ込んできたのだ? クロード、埃を払ってやるから外套を貸したまえ。外でやらないと皆の迷惑になる」
手渡された黄色い外套を入り口から少し離れた隅っこでばさばさと振っているローレンツを見てクロードは呆気に取られた。
「ぼんやりしていないで君は上着の埃を払いたまえ。効率が悪いだろう」
クロードはこの手の自分が興味が持てない日常的な作業が苦手だ。食堂で皿を洗えば割ってしまうしディミトリとは違う理由で裁縫も駄目だ。服はうまく畳んで背嚢に入れないと行軍訓練の際に不便なことが身に染みて分かったので、ようやく畳めるようになった。ローレンツの見よう見真似で上着を振っていると手付きがなっていない、とかで取り上げられてしまった。
「これでよし。ああ、ようやく着替えが取りに行ける」
「訓練場に持っていけば二度手間にならないだろう?」
「あそこに持参すると着替えに埃や土がつくから嫌なのだ」
そう言ってさっさと自分の部屋に向かうローレンツの広い背中をぼんやりと見送ったクロードは彼に礼を言うため、慌てて階段を駆け上がった。ローレンツは足が長いし動作もきびきびしているので日常ではすぐに置いていかれてしまう。
「ごめんな、礼を言い忘れてた」
「頼まれたわけではないから礼は結構だ」
ようやく追い付けたのは浴場だった。湯浴み着姿のローレンツが蒸し風呂で長い手足を投げ出して休んでいる。長居するつもりなのか頭と顔に布をかけていたが、白い肌と長い手足でクロードにはすぐに分かった。髪が短く色白で背の高い大男は士官学校に沢山いる。先程くしゃみが止まらなくなった衛兵に手巾をくれてやったヒューベルトもローレンツと仲が良いフェルディナントやシルヴァンも髪が短く手足が長い。
何故クロードはすぐにローレンツが分かったのだろうか。
クロードの誕生日が近い。彼は今節の終わりにようやく十八歳になる。今は服についた埃も上手く払えないような幼さだが、初めての野営訓練で必死になって囮となりザナドでもガスパール領でも実に上手くやっていた。五年前のローレンツは彼の開いた宴に義理で参加してそれだけで済ませている。結局、クロードを監視し分析はしていたが検証や助言はしなかったのだ。やり直しの機会が与えられた現在はきちんと祝いの品を用意するつもりでいる。
士官学校の学生達は実地訓練と言うことで近頃は大体、二週に一度は出撃させられている。皆、体力もつき精神的にも慣れてきたのだがローレンツからすればまだまだだ。冷や冷やさせられることも多く、咄嗟に突き飛ばしてでも敵の攻撃を避けさせる場合も多い。今日もそんな訳でローレンツはキルソードをもった敵が近くにいるにも関わらず回復を怠り、消耗していたクロードを遠ざけるため突き飛ばして彼の利き手の肘に怪我をさせてしまった。その場ですぐにうろ覚えのライブをかけ、戦場でも軽く詫びたが改めて謝罪せねばならない。
ローレンツは夜、後は眠るだけという時間帯に隣室の扉を叩いた。幸いライブがすぐに効いたようで招き入れてくれたクロードの所作に怪我の影響は現れていない。混沌とした部屋の中で何か書き物をしていたようで机の上に灯りがあった。
「怪我の具合はどうだ? 咄嗟のこととはいえ乱暴な扱いをして申し訳なかった」
「いや、おかげで無事だった。こちらこそ昼はきちんと礼も言えなかったから改めて今、礼を言わせてほしい」
クロードはローレンツが座る場所を作るため慌てて椅子の上の本をどかそうとした。崩れ落ちた本の角が柔らかい室内履きしか履いていない足の甲に当たる。あまり知られていないが人間の弱点のひとつだ。さぞ痛いことだろう。
「痛ってぇ!!」
日頃から片付けておかないからだぞ、と叱りたくなったが既にクロードは報いは受けている。ローレンツはクロードに寝台で座って待っているように言い、机の上を片付けてやることにした。そうしなければ床に転がった本のせいで更に怪我をするだろう。
まず開きっぱなしの書字板を手に取った。表紙の木彫が美しくリーガン家の者が持つのに相応しい。きっとローレンツが扉を叩く音を聞いた瞬間に慌てて書字板の蝋を均したのだろう。中身を見るのは貴族らしからぬ行いなので閉じようとした瞬間、文字の消しが甘くうっすらと残った単語がいくつか読めてしまった。
───天帝の剣、死神騎士、エーデルガルト───
動揺が表に現れなければ良いのだが。天帝の剣はこの後ベレトが聖墓で入手するし、死神騎士ともそこで相対する。けしかけていたのはエーデルガルトだ。
「クロード、瓶の蓋はきちんと締めておきたまえ。中身が乾いてしまうし倒して溢れたらどうするのだ。置きっぱなしの本や紙が汚れるだろうに」
ローレンツは机の上に乱雑に置いてある顔や髪につける香油や傷薬、それにインクの瓶を手に取った。倒せば溢れてしまう物だらけのところで、よく書き物が出来るものだと思う。昔はクロードのこういうところがローレンツの癇に障っていた。しかし今はそんな事に構っていられない。クロードも自分と同じくこの先の記憶を持っている可能性が出てきた。
「あれ? 蓋しまってなかったのか? 気がつかなかったよ」
「今後、気をつけることだ。足の甲は平気かね」
ローレンツは物置になっていた背もたれのない腰掛けから本を机の上に移すと、寝台に寝転がって片付け終わるのを待っていたクロードの褐色の足をぐいっと引っ張った。膝の上に腫れた足を載せ机の上で見つけた傷薬を塗ってやる。
「ありがとう。今日はローレンツに助けてもらってばかりだな。ちょっと待っててくれ」
クロードは手当てしてもらったばかりの脚でひょこひょこと床の上のものを避けながら歩き、棚の奥からローレンツにも見覚えがある酒瓶と小ぶりな陶器の杯を出してきた。
「陶器の杯も中々良い物だね」
「この大きさだと飲みすぎないのがいいんだ」
クロードは寝台、ローレンツは椅子に座っているので互いに手元で杯を掲げ琥珀色の液体に口をつける。鼻の奥へ豊かな香りが届いていった。小さな杯が好みだというなら次の休みに市場へ買い出しに行く際に探してみようか、そんなことを考えて先程のクロードの覚え書きから必死で考えを逸らす。クロードが話す時間をとってくれる、と言うなら何を問えば良いのだろうか。酒の味と香りを深く楽しむふりをしてローレンツは白い瞼を下ろした。頭の中を整理したかったからだ。
「なあ、ローレンツ、いつ修道士の資格取ったんだ?」
その隙に背後をとったクロードがローレンツの耳元で囁く。入学当初は槍と馬術に集中し修道士の資格を取ったのは秋なので、本来ならばこの時点のローレンツはライブを使えない。だが幸か不幸か身体が覚えていた。もしあの時、回復してやらなかったら今、こうして背中に感じているクロードの熱が失われていたかもしれない。戦闘中に利き腕が使えなくなったクロードを目にしてライブを使わない、という選択肢はローレンツの中に存在しなかった。瞼を上げずとも喉に、尖らせた串のような物が突きつけられているのが分かる。あとは眠るだけと言う状態なのでいつもと違い立襟が喉を守ってくれない。
クロードは確実にこの先、何が起こるのかを知っている。これはトマシュやモニカの正体がなんであったのか分かっている者の反応だ。彼はローレンツがローレンツではないことを恐れていた。
「確かめたいことがあるなら確かめればいい」
とにかく敵意がないことを伝えるとクロードはローレンツの耳元でサイレスの呪文を唱えた。これでしばらくローレンツは声を上げることができない。何故持っているのか見当もつかないが、クロードは布で出来た紐でローレンツの両腕を縛り上げると寝台の上に転がした。そのままのし掛かられ足の動きも封じられる。褐色の手によって寝間着の前を開かれ、白い肌が夜の冷えた空気にさらされた。クロードの指が左右の鎖骨の下と身体の中央に線を引いていく。獲物を捌き皮を剥ぐ時の刃の動きだ。流石に恐怖を感じたが腕も足も魔法も封じられているので、ローレンツはクロードからされるがままでいるしかない。それに無抵抗でなければ信用されないだろう。
まださほど筋肉のついていないローレンツの白い腹や胸元にクロードの耳が押し当てられた。胃の腑が立てる音や心音を聞いているクロードの顔が熱い。夏といえどもガルグ=マクは高地にあり夜は冷える。意外なことに冷えた白い肌に触れるクロードの熱が心地よかった。今まで感じたことのなかった衝動がローレンツの中から沸き起こり、それを少しでも逃せることを期待して大きく息を吐く。ローレンツの異常を何一つ見逃すまいと大きく見開かれた目がそれを見逃すはずもなかった。
褐色の指がローレンツの薄い唇を割り開く。咥内を探る指を歯で傷つけないようにローレンツは口を大きく開けた。刺激を受けて分泌され始めた唾液がクロードの指を濡らしていく。敵意がないことを示すため、舌で指の腹を舐めるとしばらく口の中を探っていた指が引き抜かれた。口の端が唾液でべたついて気持ち悪い。ローレンツはクロードの様子を伺いながら口の端についた唾液を舌で舐め取った。手で拭えないなら仕方がない。
「お前今、自分がどういう顔してるのか分かってるのかよ……」
クロードの顔が近づいてきた。咥内の様子でも見るのかと思ったがそうではなかった。熱い舌がローレンツの口の中を探っていく。美しい女性の伴侶が欲しいと思っていた筈なのに、上顎の溝をそっとなぞられるとそれだけでかつての理想が頭に浮かばなくなった。口の端から白い顎に向けて垂れた唾液を褐色の指が拭き取る。指が先ほどと同じくローレンツの白い身体に不吉な線を描くのかと思って身構えたが淡く色付く胸の飾りの縁をなぞられた。声は出せないがローレンツの意志とは関係なくクロードから与えられた刺激で身体が痙攣する。どう感じているのか、などクロードには筒抜けだろう。
しかしクロードが何を考えて固くなった自身を押し付けながらローレンツの寝巻を剥いで身体を弄んでいるのか、はさっぱり分からない。だがこの程度ならまだ学生時代の火遊びで済むのだろうか。ローレンツの腹は白濁で汚れていたがクロードの手で高められた結果自身が出したものなのか、クロードがローレンツの腹に擦り付けて出したものなのかよく分からなかった。魔法でかき消された声が荒い息遣いと共に戻ってくる。
「僕が修道士の資格を取ったのは角弓の節だ。覚えているだろう、クロード。腕を解いてくれ」
中途半端なサイレスが中途半端な状態で解けるとローレンツはクロードの耳元で囁いた。ローレンツの頬にぽたぽたとクロードの涙が落ちてくる。ここ数節に渡って彼の感じていた恐ろしいほどの孤独は理解できた。だからローレンツももう孤独ではない。ようやく自由になった腕でローレンツはクロードのことを抱きしめてやった。畳む
#説明できない #クロロレ #完売本
情報には出元と行き先がある。それを見極めずに判断を下すと間違いが起きる。前節、カトリーヌがロナート卿の所持品から見つけた大司教レアの暗殺計画に関する密書は様々な波紋を呼んだ。真偽の程は定かではないが対応せねばならない。
謁見の間に呼び出されたベレトから今節の課題を聞いたクロードは教会があの密書をどう判断したのか悟った。今回も彼の記憶と同じく何者かが教会を混乱させるため、作成した偽物であると判断したのだ。そうでなければ士官学校の学生に警備や見回りを担当させないだろう。だがクロードにとっては丁度良かった。賊の狙いが何処であるのか確かめるため、という大義名分を得て修道院の敷地内を直接、自由に見て回れる。
賊が聖廟の中で何かを探し、奪いに来た。そこでベレスが天帝の剣を手に取り賊を撃退したことをクロードはきちんと覚えている。だが、だからといって日頃入れない聖廟を直接探る機会を逃したくはなかった。それにロナート卿の叛乱の時と同じくまたクロードたちが当事者になっている。詳しく調査しておいて損はないだろう。
ガルグ=マクにはフォドラの外からやってきた住人がクロード以外にも存在する。自然と祖先を崇拝するパルミラからやってきたクロードはセイロス教の信者ではないし決まった信仰を持たない。いずれセイロス教の信者になるため堅信の儀をうけるであろうツィリルよりダグザから来たシャミアやブリギット出身のペトラ、そして後に教会に叛旗を翻すエーデルガルトとヒューベルトの方がクロードと精神的な距離が近い。洋灯を手に聖廟の中を眺めるとそこには無数の棺が置いてあった。盗掘されるような副葬品はない。皆、強欲を戒める宗教の聖職者だから基本は身を宝石で飾ることなく埋葬されている。彼らの生前の生き方が残された遺骨に聖なる力を与える、らしい。賊が宝物殿に宝石を盗みに来るようなそんな単純な者たちであったならば戦争は起きなかっただろう。
探索から戻った埃まみれで白く汚れたクロードから話しかけられた聖廟の衛兵が何度もくしゃみをした。ローレンツなら手巾を何枚も持ち歩いているのだろうが残念ながらクロードには持ち合わせがない。すると心底意外な人物が聖廟の入口の衛兵に手巾を渡した。
「返さなくて結構です。クロード殿、酷いお姿ですな。そのような状態で我が主と同じ建物に入らないでいただきたい」
次期皇帝の侍従に手巾を渡された衛兵は数節後、クロードの記憶通りに帝国軍がガルグ=マクへ侵攻してきたら何を思うのだろう。この時点で帝国、というかエーデルガルトたちの危険性を言いふらして回ることも出来たが白きものを冠に戴き、セイロス教の聖職者に見守られながら即位するアドラステア帝国の皇帝が教会に叛意を持っていると言っても誰も信じないことは明らかだった。
「同感だね。俺も俺と同じ建物に居たくないからさっさと風呂に入るよ」
そういうとクロードは聖廟から足早に立ち去った。おそらくヒューベルトはクロードがどこまで潜ったのか確かめに来たのだろう。埃まみれのまま敷地内を歩いていると訓練を終えて首にかけた布で顔を拭きながら寮の入り口へと歩いてくるローレンツの姿が目に入った。
「十中八九課題絡みだろうが一体どこに顔を突っ込んできたのだ? クロード、埃を払ってやるから外套を貸したまえ。外でやらないと皆の迷惑になる」
手渡された黄色い外套を入り口から少し離れた隅っこでばさばさと振っているローレンツを見てクロードは呆気に取られた。
「ぼんやりしていないで君は上着の埃を払いたまえ。効率が悪いだろう」
クロードはこの手の自分が興味が持てない日常的な作業が苦手だ。食堂で皿を洗えば割ってしまうしディミトリとは違う理由で裁縫も駄目だ。服はうまく畳んで背嚢に入れないと行軍訓練の際に不便なことが身に染みて分かったので、ようやく畳めるようになった。ローレンツの見よう見真似で上着を振っていると手付きがなっていない、とかで取り上げられてしまった。
「これでよし。ああ、ようやく着替えが取りに行ける」
「訓練場に持っていけば二度手間にならないだろう?」
「あそこに持参すると着替えに埃や土がつくから嫌なのだ」
そう言ってさっさと自分の部屋に向かうローレンツの広い背中をぼんやりと見送ったクロードは彼に礼を言うため、慌てて階段を駆け上がった。ローレンツは足が長いし動作もきびきびしているので日常ではすぐに置いていかれてしまう。
「ごめんな、礼を言い忘れてた」
「頼まれたわけではないから礼は結構だ」
ようやく追い付けたのは浴場だった。湯浴み着姿のローレンツが蒸し風呂で長い手足を投げ出して休んでいる。長居するつもりなのか頭と顔に布をかけていたが、白い肌と長い手足でクロードにはすぐに分かった。髪が短く色白で背の高い大男は士官学校に沢山いる。先程くしゃみが止まらなくなった衛兵に手巾をくれてやったヒューベルトもローレンツと仲が良いフェルディナントやシルヴァンも髪が短く手足が長い。
何故クロードはすぐにローレンツが分かったのだろうか。
クロードの誕生日が近い。彼は今節の終わりにようやく十八歳になる。今は服についた埃も上手く払えないような幼さだが、初めての野営訓練で必死になって囮となりザナドでもガスパール領でも実に上手くやっていた。五年前のローレンツは彼の開いた宴に義理で参加してそれだけで済ませている。結局、クロードを監視し分析はしていたが検証や助言はしなかったのだ。やり直しの機会が与えられた現在はきちんと祝いの品を用意するつもりでいる。
士官学校の学生達は実地訓練と言うことで近頃は大体、二週に一度は出撃させられている。皆、体力もつき精神的にも慣れてきたのだがローレンツからすればまだまだだ。冷や冷やさせられることも多く、咄嗟に突き飛ばしてでも敵の攻撃を避けさせる場合も多い。今日もそんな訳でローレンツはキルソードをもった敵が近くにいるにも関わらず回復を怠り、消耗していたクロードを遠ざけるため突き飛ばして彼の利き手の肘に怪我をさせてしまった。その場ですぐにうろ覚えのライブをかけ、戦場でも軽く詫びたが改めて謝罪せねばならない。
ローレンツは夜、後は眠るだけという時間帯に隣室の扉を叩いた。幸いライブがすぐに効いたようで招き入れてくれたクロードの所作に怪我の影響は現れていない。混沌とした部屋の中で何か書き物をしていたようで机の上に灯りがあった。
「怪我の具合はどうだ? 咄嗟のこととはいえ乱暴な扱いをして申し訳なかった」
「いや、おかげで無事だった。こちらこそ昼はきちんと礼も言えなかったから改めて今、礼を言わせてほしい」
クロードはローレンツが座る場所を作るため慌てて椅子の上の本をどかそうとした。崩れ落ちた本の角が柔らかい室内履きしか履いていない足の甲に当たる。あまり知られていないが人間の弱点のひとつだ。さぞ痛いことだろう。
「痛ってぇ!!」
日頃から片付けておかないからだぞ、と叱りたくなったが既にクロードは報いは受けている。ローレンツはクロードに寝台で座って待っているように言い、机の上を片付けてやることにした。そうしなければ床に転がった本のせいで更に怪我をするだろう。
まず開きっぱなしの書字板を手に取った。表紙の木彫が美しくリーガン家の者が持つのに相応しい。きっとローレンツが扉を叩く音を聞いた瞬間に慌てて書字板の蝋を均したのだろう。中身を見るのは貴族らしからぬ行いなので閉じようとした瞬間、文字の消しが甘くうっすらと残った単語がいくつか読めてしまった。
───天帝の剣、死神騎士、エーデルガルト───
動揺が表に現れなければ良いのだが。天帝の剣はこの後ベレトが聖墓で入手するし、死神騎士ともそこで相対する。けしかけていたのはエーデルガルトだ。
「クロード、瓶の蓋はきちんと締めておきたまえ。中身が乾いてしまうし倒して溢れたらどうするのだ。置きっぱなしの本や紙が汚れるだろうに」
ローレンツは机の上に乱雑に置いてある顔や髪につける香油や傷薬、それにインクの瓶を手に取った。倒せば溢れてしまう物だらけのところで、よく書き物が出来るものだと思う。昔はクロードのこういうところがローレンツの癇に障っていた。しかし今はそんな事に構っていられない。クロードも自分と同じくこの先の記憶を持っている可能性が出てきた。
「あれ? 蓋しまってなかったのか? 気がつかなかったよ」
「今後、気をつけることだ。足の甲は平気かね」
ローレンツは物置になっていた背もたれのない腰掛けから本を机の上に移すと、寝台に寝転がって片付け終わるのを待っていたクロードの褐色の足をぐいっと引っ張った。膝の上に腫れた足を載せ机の上で見つけた傷薬を塗ってやる。
「ありがとう。今日はローレンツに助けてもらってばかりだな。ちょっと待っててくれ」
クロードは手当てしてもらったばかりの脚でひょこひょこと床の上のものを避けながら歩き、棚の奥からローレンツにも見覚えがある酒瓶と小ぶりな陶器の杯を出してきた。
「陶器の杯も中々良い物だね」
「この大きさだと飲みすぎないのがいいんだ」
クロードは寝台、ローレンツは椅子に座っているので互いに手元で杯を掲げ琥珀色の液体に口をつける。鼻の奥へ豊かな香りが届いていった。小さな杯が好みだというなら次の休みに市場へ買い出しに行く際に探してみようか、そんなことを考えて先程のクロードの覚え書きから必死で考えを逸らす。クロードが話す時間をとってくれる、と言うなら何を問えば良いのだろうか。酒の味と香りを深く楽しむふりをしてローレンツは白い瞼を下ろした。頭の中を整理したかったからだ。
「なあ、ローレンツ、いつ修道士の資格取ったんだ?」
その隙に背後をとったクロードがローレンツの耳元で囁く。入学当初は槍と馬術に集中し修道士の資格を取ったのは秋なので、本来ならばこの時点のローレンツはライブを使えない。だが幸か不幸か身体が覚えていた。もしあの時、回復してやらなかったら今、こうして背中に感じているクロードの熱が失われていたかもしれない。戦闘中に利き腕が使えなくなったクロードを目にしてライブを使わない、という選択肢はローレンツの中に存在しなかった。瞼を上げずとも喉に、尖らせた串のような物が突きつけられているのが分かる。あとは眠るだけと言う状態なのでいつもと違い立襟が喉を守ってくれない。
クロードは確実にこの先、何が起こるのかを知っている。これはトマシュやモニカの正体がなんであったのか分かっている者の反応だ。彼はローレンツがローレンツではないことを恐れていた。
「確かめたいことがあるなら確かめればいい」
とにかく敵意がないことを伝えるとクロードはローレンツの耳元でサイレスの呪文を唱えた。これでしばらくローレンツは声を上げることができない。何故持っているのか見当もつかないが、クロードは布で出来た紐でローレンツの両腕を縛り上げると寝台の上に転がした。そのままのし掛かられ足の動きも封じられる。褐色の手によって寝間着の前を開かれ、白い肌が夜の冷えた空気にさらされた。クロードの指が左右の鎖骨の下と身体の中央に線を引いていく。獲物を捌き皮を剥ぐ時の刃の動きだ。流石に恐怖を感じたが腕も足も魔法も封じられているので、ローレンツはクロードからされるがままでいるしかない。それに無抵抗でなければ信用されないだろう。
まださほど筋肉のついていないローレンツの白い腹や胸元にクロードの耳が押し当てられた。胃の腑が立てる音や心音を聞いているクロードの顔が熱い。夏といえどもガルグ=マクは高地にあり夜は冷える。意外なことに冷えた白い肌に触れるクロードの熱が心地よかった。今まで感じたことのなかった衝動がローレンツの中から沸き起こり、それを少しでも逃せることを期待して大きく息を吐く。ローレンツの異常を何一つ見逃すまいと大きく見開かれた目がそれを見逃すはずもなかった。
褐色の指がローレンツの薄い唇を割り開く。咥内を探る指を歯で傷つけないようにローレンツは口を大きく開けた。刺激を受けて分泌され始めた唾液がクロードの指を濡らしていく。敵意がないことを示すため、舌で指の腹を舐めるとしばらく口の中を探っていた指が引き抜かれた。口の端が唾液でべたついて気持ち悪い。ローレンツはクロードの様子を伺いながら口の端についた唾液を舌で舐め取った。手で拭えないなら仕方がない。
「お前今、自分がどういう顔してるのか分かってるのかよ……」
クロードの顔が近づいてきた。咥内の様子でも見るのかと思ったがそうではなかった。熱い舌がローレンツの口の中を探っていく。美しい女性の伴侶が欲しいと思っていた筈なのに、上顎の溝をそっとなぞられるとそれだけでかつての理想が頭に浮かばなくなった。口の端から白い顎に向けて垂れた唾液を褐色の指が拭き取る。指が先ほどと同じくローレンツの白い身体に不吉な線を描くのかと思って身構えたが淡く色付く胸の飾りの縁をなぞられた。声は出せないがローレンツの意志とは関係なくクロードから与えられた刺激で身体が痙攣する。どう感じているのか、などクロードには筒抜けだろう。
しかしクロードが何を考えて固くなった自身を押し付けながらローレンツの寝巻を剥いで身体を弄んでいるのか、はさっぱり分からない。だがこの程度ならまだ学生時代の火遊びで済むのだろうか。ローレンツの腹は白濁で汚れていたがクロードの手で高められた結果自身が出したものなのか、クロードがローレンツの腹に擦り付けて出したものなのかよく分からなかった。魔法でかき消された声が荒い息遣いと共に戻ってくる。
「僕が修道士の資格を取ったのは角弓の節だ。覚えているだろう、クロード。腕を解いてくれ」
中途半端なサイレスが中途半端な状態で解けるとローレンツはクロードの耳元で囁いた。ローレンツの頬にぽたぽたとクロードの涙が落ちてくる。ここ数節に渡って彼の感じていた恐ろしいほどの孤独は理解できた。だからローレンツももう孤独ではない。ようやく自由になった腕でローレンツはクロードのことを抱きしめてやった。畳む
#クロロレ #完売本 #また会えようが、会えまいが #現パロ
ローレンツたちは村で一番大きなアンテナを立て、テレビを買った大隊長の自宅に集まってイグナーツとレオニーの勇姿を見守っていた。フォドラ連邦にはプロスポーツというものが存在しない。様々な競技のリーグは存在するがそれらにはその地域の警察・軍・大学が持っているクラブが参加している。激しく厳しい国内予選を勝ち抜き、バイアスロン世界選手権のフォドラ連邦代表に選ばれた二人は今モルフィスに行っている。
イグナーツがライフルで五十メートル先の標的を全て撃ち抜き、レオニーがスキーで他国の選手を追い越す度に室内は歓声で溢れ、酒瓶が空になっていった。彼らは金メダルこそとれなかったが初めてフォドラ連邦に銅メダルをもたらした。珍しく大隊長と休暇が重なったローレンツは大隊長のグラスにウォッカを注いでいる。
「あの二人の闘志あふれる仕草を見たかグロスタール中尉!」
大隊長は彼らの指ハートをひねり潰してやる、と言う意味だと誤解しているが訂正すればもっと面倒くさいことになるのでローレンツは黙って頷いた。二人はアンカリング、と呼ばれる手法にクロードから教わった指ハートのジェスチャーを取り入れている。ローレンツの身にも覚えがあるが、本番の大舞台で緊張しきってしまうと実力が発揮できない。最高のパフォーマンスを発揮出来た状態と指定した動作を脳内で強く関連付けておく。ローレンツの場合は結んでおいた髪を左手で解くことだった。
「あなた、黙って!レオニー同志とイグナーツ同志の会見よ!」
緊張に押し潰されそうになりながらも必死で戦った二人の首には銅メダルが輝いている。これで二人は軍の英雄だ。二人は長々と祖国と軍と両親に感謝を述べ他の選手を讃えている。随行している政治将校も瑕疵が見つけられないだろう。
「おめでとうございます!報奨金は何に使いますか?」
現地テレビ局のレポーターが村の英雄にマイクを差し出している。その言葉はすぐ通訳によってフォドラ語に訳されていく。イグナーツとレオニーはカメラの前でお互いに顔を見合わせてから無言で頷いた。どうやら二人にはずっと前から温めていた考えがあるらしい。酔っ払いたちは皆、口々にテレビが欲しい、いやバイクが良いなどと盛り上がっている。
「それぞれの故郷の村と今住んでいる兵舎村の小学校に楽器を寄付しようと思います」
二人はそう言い切り、通訳がその内容をモルフィス語に訳した。大隊長夫人は二人の言葉に感動して涙ぐんでいる。
何度も部下たちのために乾杯していたローレンツは酔いが回っていたせいか他人事のように良い金の使い方だ、自分がこの村の音楽教師なら何を買うだろうか、とあくまでも他人事として考えていた。この時、大隊長夫人と同じく二人のインタビューに感動した大会ホスト国モルフィスの楽器メーカーが学校用に電子ピアノを提供したことによってローレンツの人生は再び変化を迎えていく。
代表選手の特権は空港の免税店で買い物ができることだ。既に酒と煙草とチョコレートは確保してある。物資不足に悩むフォドラでは紙幣の次に使い勝手が良い。それに加えて年頃の娘らしく化粧品を物色していたレオニーはとんでもない代物を見つけた。手に取った高級スキンケアセットには化粧水などが入ったボトルが数本、入っている。そしてそれぞれのボトルには女性のシンプルなイラストが入っているのだが───これがどう見てもレオニーの知る人々なのだ。疑問と驚きで頭がいっぱいになる。慌てて商品を棚に戻し、イグナーツを探した。話を聞いてもらわないと平静を保てない。
イグナーツも高級時計コーナーのディスプレイを凝視し、呆然としていた。声をかけても全く反応しないので、仕方なく近寄るとイグナーツが見つけたとんでもない物、がレオニーの目にも入った。これなら声が彼の耳に届かないのも納得だった。
ディスプレイの中には高級時計と写真が飾られている。その写真の中では高級そうな背広と腕時計を身につけてクロードが微笑んでいた。どうやらあの後、彼も上手くやっていたらしい。レオニーは声をひそめてイグナーツに話しかけた。政治将校に聞かれたら問題になる。
「あいつ俳優だったのか?」
イグナーツはポケットから取り出したモルフィス語の辞書を捲った。ここはモルフィスなので商品の説明も含め、何もかもがモルフィス語で書いてある。
「いいえ、この時計を作っている会社の社長らしいです」
だからクロードはレオニーたちと初対面の時に腕時計について聞いてきたのだろう。ようやく合点がいった。
「時計を買えばこの写真が付いてくるのかな」
「そもそも高くて手が出せませんが残念なことにそういう仕組みではなさそうです」
ローレンツがこの写真を見たらどれほど喜ぶだろうか。彼はイグナーツとヒルダの失態を隠蔽するためにクロードを八週間も匿ったのだが、彼に情がうつっていることなど皆お見通しだった。
「中尉にあげたかったな。イグナーツ、私も見てもらいたいもんがあるからちょっとこっちに来てくれ!」
今度は化粧品コーナーでレオニーが見つけた高級スキンケアセットのパッケージを手に取ったイグナーツが驚く番だった。人民委員のスカーフの柄まで合っている。どうやらクロードは物覚えがいいらしい。化粧品に入っているロゴとカウンターに置いてあった高級時計のロゴが全く同じなので、きっとこの化粧品を作っている会社もクロードの持ち物なのだろう。
「僕もお金出しますからこれ皆さんの分を買いましょう」
「きっと期待されてるよな」
レオニーはパッケージに刷られているキャッチフレーズを指でなぞった。彼女は国境警備隊の隊員だがそれでも時々は自由な往来を夢見る時がある。───そこにはフォドラ語でたった一言「恋しさ」と書かれていた。
もう少しであれから二年経つ。
カリードは先日買収したモルフィスの某企業への国際電話を掛け終え、一人きりで広々とした台所に立っていた。電話中にちょうど茹で上がった小ぶりのじゃがいもをざるにあける。串はすんなり通り、きちんと奥まで柔らかくなっていた。
カリードはパルミラへの帰国を果たして早々に節税対策だ、と嘯いて慈善団体を設立している。ホームレスの人々に洗濯や入浴の機会を定期的に提供する団体と才能はあるが、環境に恵まれない若者の音楽活動をサポートする団体だ。どちらもまだ活動範囲はパルミラ国内にとどまっている。しかし後者は近いうちにモルフィスかブリギットへ活動の場を広げ拠点をそちらへ移す予定だ。フォドラの子どもたちが安心して参加出来るようにする為にも、徐々にパルミラの色を薄めていく必要がある。
続けてカリードは社員たちから無意味だ、と反対されたがオーナー社長の権限で押し切って化粧品部門を新たに設立した。他にも国内外の他業種の企業をいくつか投資目的だと言い張って買収している。どれかは、何かはフォドラへ、国境沿いのあの村へ届くだろう。化粧品やヘルスケア用品ならフォドラにもパルミラ製の商品が流入することは身をもって知っている。化粧品部門でもっとも評判が良く、白フォドラ人たちの郷愁を誘うようなパッケージデザインの商品は敢えてパルミラ本国では販売させていない。フォドランレディという非公式の通称までついているが、敢えてモルフィスの免税店限定にしていた。若い女性向けの観光ガイドブックにはモルフィスに行った際のマストバイアイテムと書かれている。
カリードは湯気の立つじゃがいもを皿に乗せて塩を振った。こんな風に直接働きかけられれば良いのだが、国同士が敵対しあっているとそう言うわけにもいかない。
「あいつらどんな顔するかな」
茹でたてのじゃがいもは熱過ぎて素手では持てないのでフォークを突き刺して少しずつかじっていく。ほくほくしていて柔らかい。バターを落とすとさらに美味しいのだが胃もたれがするまで食べてしまうので節制している。
もう片方の手には相変わらず行儀悪くスマホを持っていた。敵対している国家で八週間生き延びたことを理由に、未だにカリードを訝しむ者がパルミラの公安関係者にも多数存在する。生きていることこそが魔女の証、と言って罪なき女性を焼き殺した異端審問官と同じ発想をする者が経済的に恵まれた母国に存在するという事実にカリードは衝撃を受けた。
彼らから足元を掬われないように慎重に事を進めていく必要がある。
スポーツニュースでバイアスロンの世界選手権について知った時、カリードは祈るような気持ちで参加選手一覧をチェックした。そこにイグナーツとレオニーの名を見つけた時の喜びは未だに筆舌に尽くし難い。今カリードがスマホで眺めている大会のウェブサイトには参加選手のオフショット写真や競技中の動画が沢山載っている。しかしとにかく扱いの難しいフォドラ連邦の選手である二人の写真は残念なことに出場選手一覧にしか載っていない。証明写真のような小さな写真に写るイグナーツとレオニーは口を真一文字に結んでいた。兵舎村では見たことのない表情だ。しかしカリードはイグナーツが本気で怒った時の顔もレオニーが笑った時の顔も知っている。確かにあの八週間で彼らと親しくなれたのだ。三位に入賞したイグナーツとレオニーは今後、体育競技専門の部隊へ転属となるだろう。ヒルダとマリアンヌはまだローレンツの部下のままなのだろうか。兵舎村の奥方連中もいずれは夫の人事異動で去っていく。こちらの様子を知らせる事ができても首飾りの向こう側で何が起きているのかカリードには知ることができない。
愛おしく思う人々と連絡を取りたいだけなのに国際情勢が自分たちの邪魔をする。空になった皿とフォークをシンクの洗い桶に沈めるとカリードはスマホをテーブルに置き、ソファに横たわって目を閉じた。華やかに遊んでいた頃はこのソファに何人もの客が座っていたが帰国してからはずっとカリード専用だ。内なる心の声に耳を傾ける。子供の頃に聞こえてきた内なる心の声は緑の瞳や血に宿るリーガンの紋章を呪う金切り声で、しかもそれを自分の声だと思い込んでいた。今は違う。
「生活環境が変わって恋人と別れるなんてありふれたことなのに何故僕に執着するのだ?」
その声は淡々としていてこちらを責めることもなくとても優しい。あの八週間でローレンツから与えられた愛と信頼をどう扱うべきだろうか。奪われないように何重にも包み、土を掘って地中の奥深くに隠してしまうべきなのだろうか。だがそれは信頼に応えたことにならないのだ。全てが徒労に終わろうと出来ることはなんでもやっておきたい。内なる心の声への返答はいつも決まっていて揺らぐことがなかった。
「運命に逆らえないなら突っ走りたいんだ」
兵舎村にモルフィスから楽器が届いたので村の小学校で贈呈式を行う事となった。軍の好感度を上げる微笑ましいニュースなので軍の広報紙や地方紙、それに地元の放送局もイグナーツとレオニーに取材を申し込んでいる。二人はいつも身につけている深緑色の戦闘服ではなく茶色の軍服を着用していた。
「あんなに取材に来るなんて!」
「大丈夫よレオニーちゃん!この日に備えてみんなでお手入れしたからカメラ写りはばっちりよ!」
「それだけのことを成し遂げたのだから誇りに思うと良い」
競技用のウェアーやゼッケンを身につけている時ならイグナーツもレオニーも取材陣など歯牙にも掛けないのだろうが、正装しているとどうやら勝手が違うらしい。ローレンツたちは深緑色の戦闘服という気軽ないつもの姿で、小学校のささやかなホールに部下の晴れ姿を見届けに来ただけだ。微笑ましい右往左往を他人事として楽しんでいる。二人はこの贈呈式を最後に体育競技専門部隊への移動が決まっているので良い記念になる。寂しくも嬉しい門出だった。
「ピアノがおまけについてくるとはなあ……」
「でも得をしましたよ!」
いつもなら素直に得をしたことを喜ぶレオニーが若干怯えている。二人が三つの村の子供たちに買ったのは鼓笛隊でも使える打楽器のセットだけで、電子ピアノは大会のホスト国モルフィスの楽器メーカーが寄付してくれたものだ。ローレンツが見たところモルフィスやブリギットであれば習いたての子供に親が気楽に与えるような、ありふれたグレードの電子ピアノなので提供した楽器メーカーもここまで二人が恐縮しているとは夢にも思わないだろう。だが物資不足に悩むフォドラではそのありがたみが違うのだ。
「イグナーツくんの言う通り厚意は素直に受け取るべきだ。ああ、レオニーさん、軍帽の角度が曲がっている。直したまえ」
緊張のあまりいつもなら簡単にこなせること、が全く出来なくなっているのは去年この村に赴任してきた小学校教師も同じらしい。子供たちは既に贈呈された打楽器を手にしており、取材に来た軍の広報紙や放送局のカメラマンから撮影用のポーズ指導が入っている。ここで彼女が伴奏すれば完璧な絵面の写真が撮影できるはずだ。しかしなかなか始まらない。
同梱されていた取扱説明書がモルフィス語で中身が読めないからだろうか。載っている図を見ながらあれこれ弄っても贈呈された電子ピアノが何の反応も示さないので彼女は涙目になっている。だがそれもそのはずだ。そもそもプラグが刺さっていない。緊張ぶりを見ていられなくなったローレンツはついに口を開いた。
「先生、少しよろしいだろうか?」
ローレンツはステージに上り床に膝をついた。腕を伸ばしてプラグを手に持って見せると彼女は礼を言い、その場でへなへなと座り込んでしまった。贈呈品が不良品だったらと思うと怖くて仕方なかったのだろう。皆この後の予定もあるのでローレンツがそのまま動作確認したほうがよさそうだった。腕を伸ばして手近なコンセントにプラグを差し込み電源を入れる。主電源のランプが光ったのでローレンツは椅子を引いて座った。白鍵と黒鍵をその角度から見た瞬間、反射的に左手は髪を解き十指は全て吸い付くように白鍵と黒鍵の上で踊り出す。
三日練習しなければ技術は失われていくと言われている。もう何年もピアノに触れていないローレンツの奏でる音は音大の学友たちからすれば落ちぶれ果てた、聞くに耐えないものだろう。だが指が鍵盤に触れるたびにかつて音楽へ抱いていた愛や喜びが寸分違わず胸の内に蘇る。失ったと思っていたものは今もきちんとローレンツのものだった。
自分が我を忘れグリッサンドを多用した曲を一曲丸ごと弾き終えたことに気付いたローレンツは思わず右手で口を押さえた。鍵盤から指が離れた途端に困惑が意識を支配する。何故視界がフラッシュで白く光り、子供たちも含めて皆が拍手しているのかローレンツには分からなかった。今日たたえられるべきは自分ではない。
「先生、申し訳ない。出過ぎた真似をしました」
「いいえ!そんな中尉!ありがとうございました。一体どちらでピアノを学ばれたのですか?」
「子供の頃に少々……」
正直に応えるべきか迷ったローレンツが誤魔化すとそれまで壁際で皆の様子を見ていたマリアンヌが挙手した。
「中尉、本当のことを言うべきです。私共は我が子のように可愛がっていただいておりますが、私は朝起きてオフィスや詰所で中尉のお姿を見かける度に今日も中尉宛てに召喚除隊の辞令が来なかったのか、と失望しておりました」
「マリアンヌさん、少し落ち着こうか」
「いいえ、私は冷静です……。中尉、中尉が復讐を果たされてからもう二年も経っています」
いつもならとぼけたマリアンヌが揉めごとを起こさないように立ち回る三人が今回に限っては何故か全く彼女を止めようとしない。
「ブリギットの王立音楽アカデミーにいた方は紋章の有無に関わらず国境警備隊ではなく軍楽隊かアンヴァルの交響楽団に所属すべきです。才能を土に埋めて隠しておくなんてこと、あってはならないのです……!」
カリードは自分が作った慈善団体がブリギットでワークショップを兼ねたコンサートを開く時は必ず休暇を取ってブリギットを訪問することにしている。二週間の骨休めだ。彼らの宿舎にもなっているホテルを訪れるとロビーでスタッフたちが歓談していた。
「社長、継続的なご支援本当にありがとうございます。今年もフォドラからの参加者がいますよ」
ブリギット側のスタッフたちはカリードがフォドラ人参加者の有無を気にかけているのは白フォドラ人の血を引くからだ、と思い込んでいる。
「そうか。良いことだ。彼らの才能を貧困に埋もれさせてしまうのは勿体ない」
ブリギットに活動拠点を移動して一年目はフォドラからの参加者はいなかった。三年目になってようやくフォドラから一名参加してくれた。たった一人で参加した若き同胞をアテンドしてあげてほしい、ということでブリギットの王立音楽アカデミーにいるフォドラ人留学生へ実に自然に繋がりが出来た。参加者にとって留学生たちは夢を諦めなかった未来の自分だし留学生にとって参加者たちは可愛い後輩だ。互いにとって良い刺激になる。
「今日はやけに静かだな」
いつもならホテル中どこもかしこも若者たちの話し声や歌声、楽器の音で騒々しい。
「今日はコンサートホールの下見日です。皆大喜びで社長から貰った小遣いを持って行きましたよ。今年のノベルティTシャツの色はネオンブルーです」
「そりゃド派手で分かりやすいな。俺もショッピングモールに行ってみるかな」
ブリギットは自然豊かな国だ。海も山も森もあり、世界中から美しい景観や大自然の中でアクティビティを楽しむ為に観光客が訪れる。まず、その観光客の財布目当てに巨大なショッピングモールが作られた。デパートや遊園地それにコンサートホールも内包しているような巨大なもので、もはやショッピングモール自体が観光名所となっている。参加者たちは下見のついでにショッピングモールで遊ぶのを楽しみにしていた。
そんな巨大なショッピングモールでワークショップ参加者たちを探すのは結構簡単だ。コンサートホールがある関係でこのショッピングモール内にはストリートピアノがいくつか設置されている。カリードが作った慈善団体のワークショップ参加者たちは皆、外国語は達者ではないが、音楽という非言語コミュニケーションには長けていて彼らが設置されているストリートピアノを弾けば拍手喝采だ。
モール内のストリートピアノを巡ってスポンサーロゴ入りのノベルティTシャツを着ている者を探せば良い。今年も派手な色なのできっとすぐに見つかるだろう。カリードはショッピングモールの入り口付近のカフェで買ったドリンクを片手に、モール内をふらふらと歩き始めた。昨年の記憶と微かな音を頼りに大荷物を抱えた買い物客が行き交う広い通路を歩いているといくつかの通路が合流して出来た広場があった。辺りは黒山の人だかりで響き渡る見事な演奏から言ってもワークショップの参加者に違いない。
カリードは微笑みながら人だかりを割って自分の予想が合っているか確かめに行った。カリードの予想は半分正解で半分外れていた。グランドピアノの椅子にはネオンブルーのTシャツを着た少女と白い半袖シャツを身につけた蜘蛛のように手足の長い男性が並んで座っている。二人はフォドラ出身のようで少女は髪が若草色で男性は髪が紫色だった。
兵舎村の棚の下、段ボールの奥深くにしまいこまれていた姿がようやく陽の光を浴びている。この姿だ。誰にも憚られることなく直接、この姿が見たかった。だからこそクロードは気が遠くなるような遠回りをしたし、何年も連続で空振りだったにもかかわらず今年もこうしてブリギットにやって来たのだ。
アテンドしているのであろう参加者との連弾を終え観客に礼を言うため、拍手の中で立ち上がったローレンツは驚きのあまり大きな右手で口元を押さえた。その手には緑色のフェースの腕時計が着けられている。アウトドアスポーツ用の腕時計は演奏の場ではどうにも武骨で仕方なかった。演奏会用の瀟洒な腕時計を見繕ってやるのも良いかもしれない。そんなことを考えながらクロードはローレンツに駆け寄り彼の頬に手を当て唇に長い長いキスをした。
「ローレンツ!いつブリギットに戻ってきたんだよ!こっちに来てるなら知らせてくれれば良かったのに!」
「クロード、長いこと待たせてしまってすまなかった」
くっつけた互いの頬が濡れているが二人とも泣いているのでどちらの涙のせいなのかはよく分からない。
「いや、良いんだ……。こうして来てくれたんだからそんなことは本当にどうでも良いさ……」
先程までは拍手喝采で満たされていた空間が、クロードたちを囃し立てる歓声や指笛で満たされていく。二人の関係は今後も国際情勢に大きく左右されるだろう。今はこうして第三国で会えているが今後、不可能になるかもしれない。だが互いへの思いを土の中に埋めて隠すようなことは絶対にしたくなかった。畳む