「ひとがしら───野暮れ山暮れ」#ひとがしら #クロロレ #R18 #完売本 ↑18?→y/n
「さかしま」1.#クロロレ #さかしま #完売本 #オメガバース #表紙 #台詞まとめ
初版時の表紙

台詞の抜粋
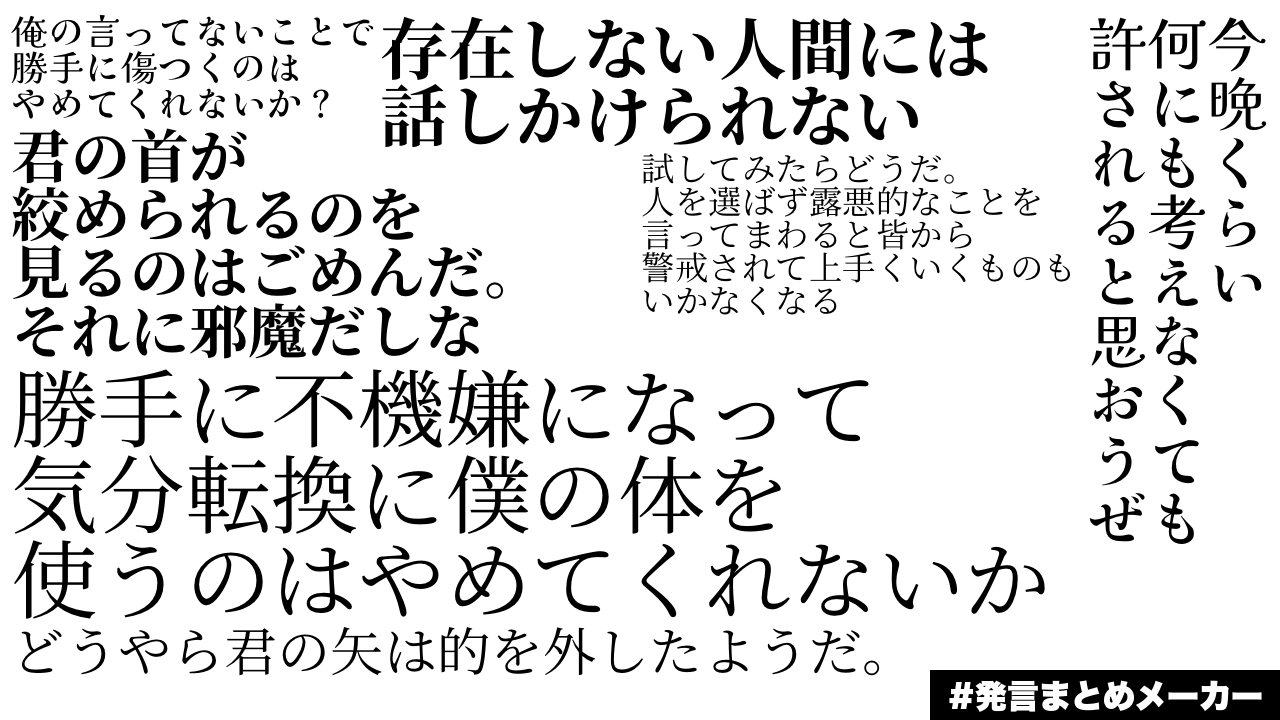
図星を刺された時に人は取り繕うように笑う。笑って口角が上がれば犬歯が見える。犬歯という武器を晒して誠実さを訴えているのか、これで噛みついてやると脅しているのか───その一瞬を切り取っただけでは区別がつかない。流れを把握せねば意図を読むのは不可能だ。クロードが修道院の敷地内で何を探していたのか、その答えをローレンツが知ることはないだろう。
「何かやましいことをしていたに違いない」
寮生活にも慣れ、建物の構造を把握した身であればこそこんな場所から出てくる筈もない、と言うところで二人は遭遇した。
ローレンツは口喧しい。だが出てくる言葉はクロードにとって全て誰かの言葉の丸写しに過ぎない。埃まみれになった外套や表面に貼り付けた笑顔の奥にある物には辿り着けるはずがない。クロードはそう思って彼をあからさまに見くびっていた。だが、今は違う。何故か紫の瞳に心の内を見透かされているような気持ちになっていた。薄暗い廊下に立つ伯爵家の嫡子はいつもクロードの監視を怠らない。
「俺はこの歴史の古い修道院が大好きなんだよ」
クロードはフォドラにしかないものについて調べるため修道院内をうろついている。パルミラには英雄の遺産も紋章も存在しない。だがハンネマンがいることからも分かる通り、ガルグ=マクはそれらの研究の最先端を担っている。
リーガン家の嫡子として正式に認められる前、何度か血を取られた時のことをクロードは今でも偶に思い出す。クロードの血は学者によって他人の血と混ぜられ、凝固した時もあれば凝固しなかった時もあった。一喜一憂する大人たちの気持ちは未だによく分からない。
とにかくクロードはリーガンの紋章を持つアルファである、とセイロス教会そしてレスター諸侯同盟から正式に認められた。
第二の性別とも言われるアルファ・ベータ・オメガはフォドラ社会全体では一・八・一の割合で安定している。だが人口の五パーセントを占める魔法適性がある人々においては二・六・二となり紋章適合者では四・二・四の割合だ。力が強ければ強いほどアルファかオメガに偏っていく。パルミラにいた頃の検査で既に分かっていたことをなぜ改めて検査したのか謎だったが、セイロス教会が独自に魔法適性と紋章と第二性に関して資料を集めているから、らしい。
今年度のガルグ=マク修道院附属士官学校は紋章適合者の当たり年で、クロードが級長を務める金鹿の学級だけでも五人の紋章適合者がいる。今、洋灯が作ったゆらめく影の下でクロードを問い詰めているローレンツもグロスタールの小紋章を持っていた。皆、アルファかオメガどちらかの筈だが公言はしない。極私的な事柄はわざわざ告げて回らなくても宜しい、というのがセイロス教の教えだからだ。この教えは他の事柄にも及んでおりそれを利用してマリアンヌとリシテアも何事かを隠している。クロードも含めて皆秘密ばかりだ。
「君は胡散臭いのだよ。必ず尻尾を掴んでみせる」
そんな中で何の秘密も抱えていなさそうに見える、あくまでも見えるだけだが───ローレンツがクロードを睨んだ。
「俺から目が離せないなんて熱烈だな。発情期か?」
クロードの直接的な物言いにローレンツは虚をつかれたのか、目と口をぽかんと丸く開けたが負けてはいない。呆れたようにふっと笑う姿はもう余裕を取り戻していた。
「馬鹿だな、君は。こんなアルファだらけの学校に来るオメガが抑制剤を飲んでいない筈がないだろう」
もっと踏み込んで言うならばアルファが存在する社会の一員である以上、オメガは抑制剤を服用しないわけにはいかない。それが互いの身の安全を社会的な立場を守る。
クロードはローレンツが下品だ、と言って激昂するかと思っていたのに当てが外れて調子が狂ってしまった。今晩のところは自室へ引き上げる方が良いだろう。隣室のローレンツと共に足音が響かないよう、そっと階段を上りながら小さな声で話を続けた。
「抑制剤の製法を独占するのもセイロス教会だったな」
「だが商人が儲け目当てに参入し、粗悪品を流通させたら人生が壊れる者が沢山出るだろう。やはり世俗とは関係ない教会に任せておくべきだ」
オメガの発情期を抑える薬はセイロス教会がフォドラ全土に流通させているが独占もしている。原材料は公開されておらず、それが分かれば大司教座が何故セイロスが降り立ったという帝都アンヴァルではなく山中のガルグ=マクにあるのか、も分かるのかもしれない。
国外育ちのクロードはリーガン家の嫡子として公表される前、名門貴族の嫡子として相応しい言動ができるように内密に教育を受けていた。その中にはフォドラの一般的な人々の考えも含まれる。殆どの人々がセイロス教会の至上権を認めていた。信仰、道徳をはじめありとあらゆる事象に関してセイロス教会は無謬であると信じている。
そんな考えだからアルファの抗フェロモン剤がいつまで経っても開発されないのだ、と当時のクロードは呆れた。産む側であり三ヶ月に一度十日ほど発情期のあるオメガはアルファ、ベータと比べて立場が弱いとされている。社会の規範はどうしても多数派であるベータからの視線に準じていく。
ベータはオメガがアルファを惹きつけるために分泌するフェロモンの感受性に乏しく、ほとんど感知出来ない。アルファが本能を理由に一切我慢をせず、オメガを襲う様子を見ればオメガの立場は弱く見えるのだろう。襲われないように自衛する必要があり、仮に不誠実なアルファと番になった場合は人生が破滅してしまう。男性女性を問わずオメガの社会的役割はベータ女性と同じく出産することなので、どの階層の女性からも共感は得やすい。
だがクロードに言わせればアルファもベータと比べればオメガと同じく立場が弱いのだ。アルファがどんなに優秀だとしても、抑制剤を飲んでいない発情期を迎えたオメガを目の前に出されたら理性は飛び、獣になってしまう。いくらアルファが本能に抗えないから、と主張しても第三者から見れば理不尽な暴力以外の何者でもない。見た目ではいっさい第二性の区別が付かないためアルファにとっては更に事態が悪化する。本当に襲われていたのはオメガなのか?実はベータだったのでは?そんな風に社会の大多数を占めるベータたちから疑われてもおかしくはない。
クロードもそんな本能に任せた行動はしたくなかった。例え自分の両親がフォドラの首飾りを超えるような、運命の出会いを果たした夫妻だったとしても、だ。
ローレンツの考えは一風、変わっている。幻想を抱く社会の一員のくせに妙に現実的なのだ。
「確かにな。大陸全土に遍く存在するオメガたちに抑制剤を配って回るなんて、儲けを考えたらやっていられない。慈善事業かな?」
「君のその、何にでも利益や理由を求めたがる姿勢は危ういぞ」
まあ、君という存在自体が抱える問題と比べれば些細なことだがね───と付け加え、ローレンツは隣室に消えていった。確かに自分は危うい。洋灯を机に置き気合を入れるため、鏡で自分の顔を見た。
《しっかりしろ、〝クロード=フォン=リーガン〟こんな時期にこんな所で尻尾を出すわけにはいかないのだから》
睫毛で出来た影の下で緑の瞳が煌めいている。故郷パルミラで忌み嫌われた瞳に動揺は現れていない。だが内心は違っていた。理由を必要としない人々が理解出来ない、というフォドラにおけるクロードの弱点をローレンツから見透かされたような気がする。畳む
初版時の表紙

台詞の抜粋
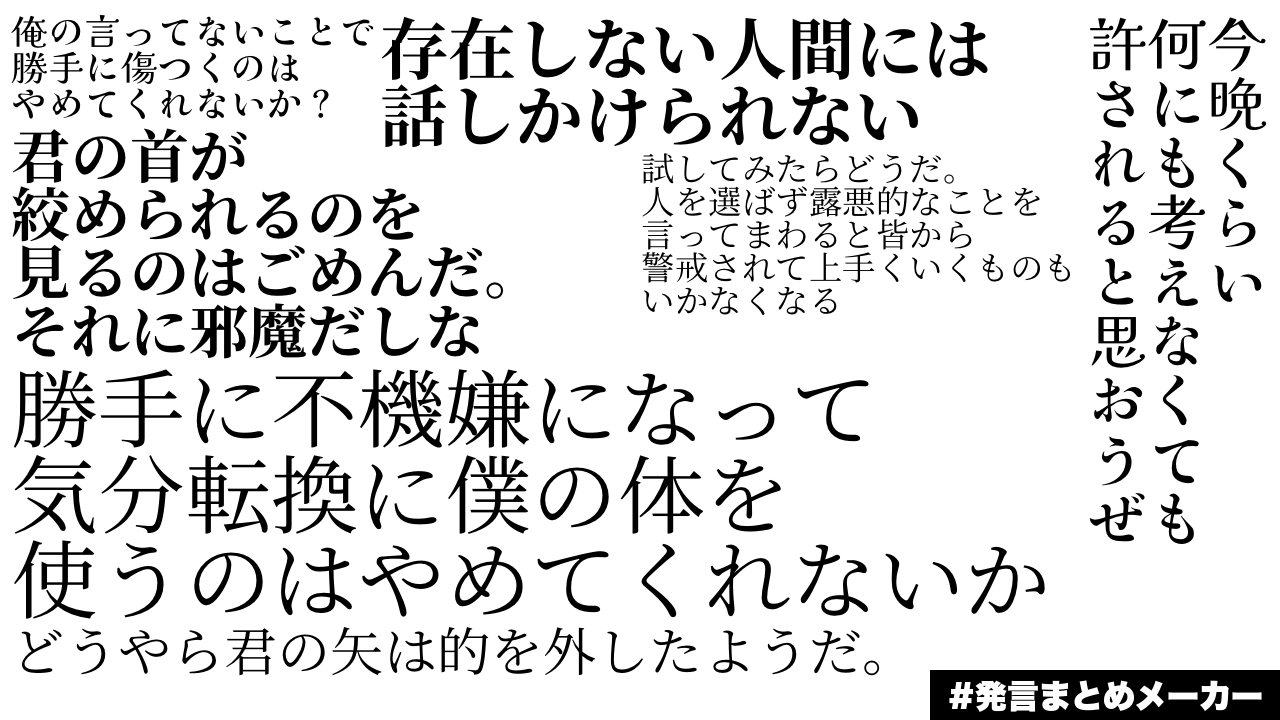
図星を刺された時に人は取り繕うように笑う。笑って口角が上がれば犬歯が見える。犬歯という武器を晒して誠実さを訴えているのか、これで噛みついてやると脅しているのか───その一瞬を切り取っただけでは区別がつかない。流れを把握せねば意図を読むのは不可能だ。クロードが修道院の敷地内で何を探していたのか、その答えをローレンツが知ることはないだろう。
「何かやましいことをしていたに違いない」
寮生活にも慣れ、建物の構造を把握した身であればこそこんな場所から出てくる筈もない、と言うところで二人は遭遇した。
ローレンツは口喧しい。だが出てくる言葉はクロードにとって全て誰かの言葉の丸写しに過ぎない。埃まみれになった外套や表面に貼り付けた笑顔の奥にある物には辿り着けるはずがない。クロードはそう思って彼をあからさまに見くびっていた。だが、今は違う。何故か紫の瞳に心の内を見透かされているような気持ちになっていた。薄暗い廊下に立つ伯爵家の嫡子はいつもクロードの監視を怠らない。
「俺はこの歴史の古い修道院が大好きなんだよ」
クロードはフォドラにしかないものについて調べるため修道院内をうろついている。パルミラには英雄の遺産も紋章も存在しない。だがハンネマンがいることからも分かる通り、ガルグ=マクはそれらの研究の最先端を担っている。
リーガン家の嫡子として正式に認められる前、何度か血を取られた時のことをクロードは今でも偶に思い出す。クロードの血は学者によって他人の血と混ぜられ、凝固した時もあれば凝固しなかった時もあった。一喜一憂する大人たちの気持ちは未だによく分からない。
とにかくクロードはリーガンの紋章を持つアルファである、とセイロス教会そしてレスター諸侯同盟から正式に認められた。
第二の性別とも言われるアルファ・ベータ・オメガはフォドラ社会全体では一・八・一の割合で安定している。だが人口の五パーセントを占める魔法適性がある人々においては二・六・二となり紋章適合者では四・二・四の割合だ。力が強ければ強いほどアルファかオメガに偏っていく。パルミラにいた頃の検査で既に分かっていたことをなぜ改めて検査したのか謎だったが、セイロス教会が独自に魔法適性と紋章と第二性に関して資料を集めているから、らしい。
今年度のガルグ=マク修道院附属士官学校は紋章適合者の当たり年で、クロードが級長を務める金鹿の学級だけでも五人の紋章適合者がいる。今、洋灯が作ったゆらめく影の下でクロードを問い詰めているローレンツもグロスタールの小紋章を持っていた。皆、アルファかオメガどちらかの筈だが公言はしない。極私的な事柄はわざわざ告げて回らなくても宜しい、というのがセイロス教の教えだからだ。この教えは他の事柄にも及んでおりそれを利用してマリアンヌとリシテアも何事かを隠している。クロードも含めて皆秘密ばかりだ。
「君は胡散臭いのだよ。必ず尻尾を掴んでみせる」
そんな中で何の秘密も抱えていなさそうに見える、あくまでも見えるだけだが───ローレンツがクロードを睨んだ。
「俺から目が離せないなんて熱烈だな。発情期か?」
クロードの直接的な物言いにローレンツは虚をつかれたのか、目と口をぽかんと丸く開けたが負けてはいない。呆れたようにふっと笑う姿はもう余裕を取り戻していた。
「馬鹿だな、君は。こんなアルファだらけの学校に来るオメガが抑制剤を飲んでいない筈がないだろう」
もっと踏み込んで言うならばアルファが存在する社会の一員である以上、オメガは抑制剤を服用しないわけにはいかない。それが互いの身の安全を社会的な立場を守る。
クロードはローレンツが下品だ、と言って激昂するかと思っていたのに当てが外れて調子が狂ってしまった。今晩のところは自室へ引き上げる方が良いだろう。隣室のローレンツと共に足音が響かないよう、そっと階段を上りながら小さな声で話を続けた。
「抑制剤の製法を独占するのもセイロス教会だったな」
「だが商人が儲け目当てに参入し、粗悪品を流通させたら人生が壊れる者が沢山出るだろう。やはり世俗とは関係ない教会に任せておくべきだ」
オメガの発情期を抑える薬はセイロス教会がフォドラ全土に流通させているが独占もしている。原材料は公開されておらず、それが分かれば大司教座が何故セイロスが降り立ったという帝都アンヴァルではなく山中のガルグ=マクにあるのか、も分かるのかもしれない。
国外育ちのクロードはリーガン家の嫡子として公表される前、名門貴族の嫡子として相応しい言動ができるように内密に教育を受けていた。その中にはフォドラの一般的な人々の考えも含まれる。殆どの人々がセイロス教会の至上権を認めていた。信仰、道徳をはじめありとあらゆる事象に関してセイロス教会は無謬であると信じている。
そんな考えだからアルファの抗フェロモン剤がいつまで経っても開発されないのだ、と当時のクロードは呆れた。産む側であり三ヶ月に一度十日ほど発情期のあるオメガはアルファ、ベータと比べて立場が弱いとされている。社会の規範はどうしても多数派であるベータからの視線に準じていく。
ベータはオメガがアルファを惹きつけるために分泌するフェロモンの感受性に乏しく、ほとんど感知出来ない。アルファが本能を理由に一切我慢をせず、オメガを襲う様子を見ればオメガの立場は弱く見えるのだろう。襲われないように自衛する必要があり、仮に不誠実なアルファと番になった場合は人生が破滅してしまう。男性女性を問わずオメガの社会的役割はベータ女性と同じく出産することなので、どの階層の女性からも共感は得やすい。
だがクロードに言わせればアルファもベータと比べればオメガと同じく立場が弱いのだ。アルファがどんなに優秀だとしても、抑制剤を飲んでいない発情期を迎えたオメガを目の前に出されたら理性は飛び、獣になってしまう。いくらアルファが本能に抗えないから、と主張しても第三者から見れば理不尽な暴力以外の何者でもない。見た目ではいっさい第二性の区別が付かないためアルファにとっては更に事態が悪化する。本当に襲われていたのはオメガなのか?実はベータだったのでは?そんな風に社会の大多数を占めるベータたちから疑われてもおかしくはない。
クロードもそんな本能に任せた行動はしたくなかった。例え自分の両親がフォドラの首飾りを超えるような、運命の出会いを果たした夫妻だったとしても、だ。
ローレンツの考えは一風、変わっている。幻想を抱く社会の一員のくせに妙に現実的なのだ。
「確かにな。大陸全土に遍く存在するオメガたちに抑制剤を配って回るなんて、儲けを考えたらやっていられない。慈善事業かな?」
「君のその、何にでも利益や理由を求めたがる姿勢は危ういぞ」
まあ、君という存在自体が抱える問題と比べれば些細なことだがね───と付け加え、ローレンツは隣室に消えていった。確かに自分は危うい。洋灯を机に置き気合を入れるため、鏡で自分の顔を見た。
《しっかりしろ、〝クロード=フォン=リーガン〟こんな時期にこんな所で尻尾を出すわけにはいかないのだから》
睫毛で出来た影の下で緑の瞳が煌めいている。故郷パルミラで忌み嫌われた瞳に動揺は現れていない。だが内心は違っていた。理由を必要としない人々が理解出来ない、というフォドラにおけるクロードの弱点をローレンツから見透かされたような気がする。畳む
「さかしま」2.#クロロレ #さかしま #完売本 #オメガバース
第二性の検査は血液検査で行われる。ベータの血と混ぜられた時に凝固しなければ検査はそれで終了だ。ローレンツの血はベータの血と混ぜた際に凝固し、オメガの血とは混ざり合い、アルファの血と混ぜた時に凝固した。彼がグロスタールの紋章を継がないただのオメガであったならば絶望したかもしれない。
しかしローレンツはその身にグロスタールの小紋章を宿しており将来、彼の伴侶となる者には元より様々な条件を課されていた。当事者であるローレンツからしてみればそこにアルファであるべし、という条件がひとつ加わるだけにすぎない。恋を知らない身の上だからそんなに冷静でいられるのだ、という意見もある。だが物心ついた頃から領民のため家のために生きよ、と言い聞かせられて育てば当たり前の話だった。
幸い、まだ実家で暮らしていた十四才の頃に自宅で初めての発情期、いわゆる熱発作を迎えたのでローレンツは知らない誰かを加害者にせず済んでいる。嫡子がオメガだと診断されると両親はすぐに教育係をつけた。教育係はどう振る舞えばローレンツが生き物として破滅しないのかを教えてくれた。セイロス教会が開発した抑制剤のおかげで第二性は個人の能力に影響しないが、立ち振る舞いには指導が必要となる。
親元から離れる前に必ず毎日抑制剤を服用すればアルファを刺激せずに済むことや運命の番とその美しい誤謬について学ぶことができた。不運なオメガは単にその場にいただけのアルファを誘惑してしまうし、そのアルファを運命の番だと誤解してしまう。実際はその場にいる最も強い独り者のアルファを無意識下で本能的に狙っているに過ぎないが、気の持ちようで物事の捉え方は変わるものだ。自分で自分を騙した方が結果を許容して幸せに生きていけるのだろう。
暴走した脳の熱が全身に伝わっていくような熱さと今まで味わったことのない快楽があと少しで味わえる筈なのに、という焦ったさと悔しさはローレンツにとってさっさと過去のものにしたい感覚だ。しかし忌々しいことにこれが中々過ぎ去ってくれない。
全て、未だに生々しく刻みつけられている。あの時は全身からどっと汗が噴き出し、雨に打たれたかのように身につけていた服が内側からびしょ濡れになった。アルファはその大量にかいた汗に混ざって出てくるフェロモンを甘く感じるらしい。つまり嗅覚だけでなく味覚まで侵食されてしまうのだ。決して他言はできないが、匂いに惹きつけられ行動が制御できないアルファをある意味では哀れな存在だ、とローレンツは思う。
学生の身の安全を確保し正しく指導せねばならない教師や士官学校の職員たちは学生たちの第二性を正確に把握しているが、それを決して学生には明かさない。そしてガルグ=マクの士官学校で寮生活を送る学生たちは誰も第二性について互いに問うような真似はしない。知ったところで生まれつきのものは変更出来ないからだ。
好いた女性が女性しか愛せない人だった、好いた男性が男性しか愛せない人だったという事態は第二性に関係なく起こり得る。そのように考えておけばアルファだからオメガだから、と過剰に悲劇に浸らずとも生きていける。
故にローレンツが父であるグロスタール伯から監視せよ、と言われていたクロードの第二性がなんであろうとローレンツには全く関係ない筈だった。しかしあの物言いで彼が発情期のオメガたちから切望される側なのであろう、アルファなのであろう、と予想ができてしまった。正直言って察したくなかった。これでは彼を冷静な目で見られない。
今晩もクロードは自室を抜け出し何かを探って回っていたようだ。消灯後だったのでローレンツは軽装だったが、クロードはきちんと私服の上着を着込んでいた。一体どこまで足を伸ばしたのだろうか。
セイロス教の中央教会が平民たちにあかせない秘密を抱えているのはクロードに指摘されるまでもない。そんなことは火を見るより明らかだ。だがその秘密が暴露され、平民たちが不安に駆られた時に領主が無能であれば暴動に発展するだろう。領主が平民たちと信頼で結ばれていれば彼らが不安を感じることはない。
───それが理想の在り方だが理想と現実は違う。
教会が沈黙を守っているとしたら、それは領主の側に至らぬ点があるからだ。故に教会の秘密を不要不急であるにも関わらず、好奇心に任せて暴くのはとても下品な振る舞いだとローレンツは考えている。自分の欲望は完全に制御するのが望ましい。
ガルグ=マクの士官学校で学ぶ将来の領主たちは皆、領主として知っておくべきことは然るべき時に教会から知らされるだろう、と信じている。クロードも将来、レスター諸侯同盟の盟主になれば中央教会の秘密に触れる機会もあるだろうに彼は待てないらしい。どんな育ち方をしたのだろうか?第二性に関する言質を取られるような物言いを鑑みるに、ローレンツの父エルヴィンがクロードを訝しむのも当然だった。監視していく中で彼が隠しておきたいと思っているものが何なのか、おいおい分かっていくのだろう。
ローレンツは自室に置いてある水差しから杯に水を注いだ。初めての熱発作のことを思い出すだけで喉が渇いてしまう。誰も見ていない自室なので不作法だが喉を鳴らして杯の水を一気に飲んだ。自分の喉あるいは頸に噛み付き、身体の奥深くを開くアルファは一体、誰なのだろうか。熱発作の前は自分の喉や頸など意識しなかったがあの日以来、そのことを考えない日はない。
横になったローレンツは薄い寝巻きの上から臍の下を白い手でさすった。おそらく子宮がある辺りが疼いているような気がする。伴侶となるのが女性のアルファであれ男性のアルファであれ、命がけで出産するのはローレンツだ。医師が切開しその場で修道士から回復魔法をかけてもらうのだが、腹が切り開かれている最中の痛みもさることながら回復魔法をかけてもらった後も暫くはとても痛むものだ、と出産経験のある男性オメガの教育係から聞いている。生物としての本能を満たした快楽の果てに、命を落としかねない苦痛が待っているのはオメガの人生における理不尽のうち最大のものと言えるだろう。
前節、ローレンツたちは盗賊が相手とはいえ、初めて人を手にかけた。噎せ返るような血の匂いのせいで感覚が鈍るかと思ったのに、かえって五感が研ぎ澄まされた。自分の振るった槍が肉体にめり込んでいく感触も顔の脇を掠めていった矢羽の立てる音も全て、この身に刻まれている。そうでなければクロードをもう少し平然とした態度で見られた筈だ。
先ほどクロードはローレンツに発情期なのかと問うた。冗談とはいえあまりに明け透けな物言いについ、素で返答してしまった。素は危うい。素を隠さなければ発情期ではないから困っているのだよ───とクロードに告げてしまう。確かにクロードは父の言う通り胡散臭く監視対象だが、ローレンツは彼を困惑させたい訳ではない。
初めての熱発作から数年を経て、抑制剤の服用は完全に習慣としてローレンツに身についている。発情期を薬で抑制しながら送る集団生活、寮生活も魔道学院で経験済みだ。それなのに。
発情期でもないのにクロードを目にするとあの日を思い出し、感情が昂るのを抑えられないからローレンツは困っている。畳む
第二性の検査は血液検査で行われる。ベータの血と混ぜられた時に凝固しなければ検査はそれで終了だ。ローレンツの血はベータの血と混ぜた際に凝固し、オメガの血とは混ざり合い、アルファの血と混ぜた時に凝固した。彼がグロスタールの紋章を継がないただのオメガであったならば絶望したかもしれない。
しかしローレンツはその身にグロスタールの小紋章を宿しており将来、彼の伴侶となる者には元より様々な条件を課されていた。当事者であるローレンツからしてみればそこにアルファであるべし、という条件がひとつ加わるだけにすぎない。恋を知らない身の上だからそんなに冷静でいられるのだ、という意見もある。だが物心ついた頃から領民のため家のために生きよ、と言い聞かせられて育てば当たり前の話だった。
幸い、まだ実家で暮らしていた十四才の頃に自宅で初めての発情期、いわゆる熱発作を迎えたのでローレンツは知らない誰かを加害者にせず済んでいる。嫡子がオメガだと診断されると両親はすぐに教育係をつけた。教育係はどう振る舞えばローレンツが生き物として破滅しないのかを教えてくれた。セイロス教会が開発した抑制剤のおかげで第二性は個人の能力に影響しないが、立ち振る舞いには指導が必要となる。
親元から離れる前に必ず毎日抑制剤を服用すればアルファを刺激せずに済むことや運命の番とその美しい誤謬について学ぶことができた。不運なオメガは単にその場にいただけのアルファを誘惑してしまうし、そのアルファを運命の番だと誤解してしまう。実際はその場にいる最も強い独り者のアルファを無意識下で本能的に狙っているに過ぎないが、気の持ちようで物事の捉え方は変わるものだ。自分で自分を騙した方が結果を許容して幸せに生きていけるのだろう。
暴走した脳の熱が全身に伝わっていくような熱さと今まで味わったことのない快楽があと少しで味わえる筈なのに、という焦ったさと悔しさはローレンツにとってさっさと過去のものにしたい感覚だ。しかし忌々しいことにこれが中々過ぎ去ってくれない。
全て、未だに生々しく刻みつけられている。あの時は全身からどっと汗が噴き出し、雨に打たれたかのように身につけていた服が内側からびしょ濡れになった。アルファはその大量にかいた汗に混ざって出てくるフェロモンを甘く感じるらしい。つまり嗅覚だけでなく味覚まで侵食されてしまうのだ。決して他言はできないが、匂いに惹きつけられ行動が制御できないアルファをある意味では哀れな存在だ、とローレンツは思う。
学生の身の安全を確保し正しく指導せねばならない教師や士官学校の職員たちは学生たちの第二性を正確に把握しているが、それを決して学生には明かさない。そしてガルグ=マクの士官学校で寮生活を送る学生たちは誰も第二性について互いに問うような真似はしない。知ったところで生まれつきのものは変更出来ないからだ。
好いた女性が女性しか愛せない人だった、好いた男性が男性しか愛せない人だったという事態は第二性に関係なく起こり得る。そのように考えておけばアルファだからオメガだから、と過剰に悲劇に浸らずとも生きていける。
故にローレンツが父であるグロスタール伯から監視せよ、と言われていたクロードの第二性がなんであろうとローレンツには全く関係ない筈だった。しかしあの物言いで彼が発情期のオメガたちから切望される側なのであろう、アルファなのであろう、と予想ができてしまった。正直言って察したくなかった。これでは彼を冷静な目で見られない。
今晩もクロードは自室を抜け出し何かを探って回っていたようだ。消灯後だったのでローレンツは軽装だったが、クロードはきちんと私服の上着を着込んでいた。一体どこまで足を伸ばしたのだろうか。
セイロス教の中央教会が平民たちにあかせない秘密を抱えているのはクロードに指摘されるまでもない。そんなことは火を見るより明らかだ。だがその秘密が暴露され、平民たちが不安に駆られた時に領主が無能であれば暴動に発展するだろう。領主が平民たちと信頼で結ばれていれば彼らが不安を感じることはない。
───それが理想の在り方だが理想と現実は違う。
教会が沈黙を守っているとしたら、それは領主の側に至らぬ点があるからだ。故に教会の秘密を不要不急であるにも関わらず、好奇心に任せて暴くのはとても下品な振る舞いだとローレンツは考えている。自分の欲望は完全に制御するのが望ましい。
ガルグ=マクの士官学校で学ぶ将来の領主たちは皆、領主として知っておくべきことは然るべき時に教会から知らされるだろう、と信じている。クロードも将来、レスター諸侯同盟の盟主になれば中央教会の秘密に触れる機会もあるだろうに彼は待てないらしい。どんな育ち方をしたのだろうか?第二性に関する言質を取られるような物言いを鑑みるに、ローレンツの父エルヴィンがクロードを訝しむのも当然だった。監視していく中で彼が隠しておきたいと思っているものが何なのか、おいおい分かっていくのだろう。
ローレンツは自室に置いてある水差しから杯に水を注いだ。初めての熱発作のことを思い出すだけで喉が渇いてしまう。誰も見ていない自室なので不作法だが喉を鳴らして杯の水を一気に飲んだ。自分の喉あるいは頸に噛み付き、身体の奥深くを開くアルファは一体、誰なのだろうか。熱発作の前は自分の喉や頸など意識しなかったがあの日以来、そのことを考えない日はない。
横になったローレンツは薄い寝巻きの上から臍の下を白い手でさすった。おそらく子宮がある辺りが疼いているような気がする。伴侶となるのが女性のアルファであれ男性のアルファであれ、命がけで出産するのはローレンツだ。医師が切開しその場で修道士から回復魔法をかけてもらうのだが、腹が切り開かれている最中の痛みもさることながら回復魔法をかけてもらった後も暫くはとても痛むものだ、と出産経験のある男性オメガの教育係から聞いている。生物としての本能を満たした快楽の果てに、命を落としかねない苦痛が待っているのはオメガの人生における理不尽のうち最大のものと言えるだろう。
前節、ローレンツたちは盗賊が相手とはいえ、初めて人を手にかけた。噎せ返るような血の匂いのせいで感覚が鈍るかと思ったのに、かえって五感が研ぎ澄まされた。自分の振るった槍が肉体にめり込んでいく感触も顔の脇を掠めていった矢羽の立てる音も全て、この身に刻まれている。そうでなければクロードをもう少し平然とした態度で見られた筈だ。
先ほどクロードはローレンツに発情期なのかと問うた。冗談とはいえあまりに明け透けな物言いについ、素で返答してしまった。素は危うい。素を隠さなければ発情期ではないから困っているのだよ───とクロードに告げてしまう。確かにクロードは父の言う通り胡散臭く監視対象だが、ローレンツは彼を困惑させたい訳ではない。
初めての熱発作から数年を経て、抑制剤の服用は完全に習慣としてローレンツに身についている。発情期を薬で抑制しながら送る集団生活、寮生活も魔道学院で経験済みだ。それなのに。
発情期でもないのにクロードを目にするとあの日を思い出し、感情が昂るのを抑えられないからローレンツは困っている。畳む
「さかしま」3.#クロロレ #さかしま #完売本 #オメガバース
ロナート卿の叛乱について一報が入って以来、士官学校は悪い意味で落ち着かない。気の毒なアッシュは必死で様々なものを堪えていた。義理の兄クリストフに続き、養父ロナート卿を失うかもしれない恐怖に脅える彼にはどんな言葉も慰めにはならない。今節、金鹿の学級が修道院から課された奉仕活動はそのロナート卿の叛乱を鎮圧するセイロス騎士団の補佐だ。流石に当事者の養子が所属する青獅子の学級には任せられない、と教会が考えたのだろう。
叛乱のあらましと今節の課題が発表されて以来、ローレンツはずっと機嫌が悪い。彼の考える立派な領主像とロナート卿の振る舞いがかけ離れているからだ。槍を鍛錬する際も苛立ちをぶつけるかのような態度が目立ち、訓練用の槍を壊してしまうことが多い。
そんな彼は柄だけになった槍を構え、槍と戦う時の間合いを知りたいというラファエルの訓練に付き合っている。大柄なラファエルが本気で籠手を振るって来るのに先ほどからずっと基本の動作である直突きを繰り返していた。本能的に巻き技を使いたくなる筈だが、ローレンツは意志の力でその欲求をねじ伏せて同じ動作を繰り返している。しかしどうやらラファエルの叫び声がうるさいらしい。ローレンツの眉間に微かに皺が寄っているのをクロードは見逃さなかった。
クロードの兵種はアーチャーで今はスナイパーを目指している。資格試験のことを考えれば他人の訓練を見物している暇はない。だがクロードは、ベレトからアッシュが心を落ち着けて訓練できるように的場を彼に譲ってくれ、と言われていた。
稽古場の片隅に置いてある長椅子に腰掛けたクロードは同じ兵種であるレオニーと並んで、近接戦闘の訓練を眺めながら弓の手入れをしていた。二人とも最初は真面目に調整していたのだが、どうしても同じ空間にいる他の者の訓練に目がいってしまうため手は動いていない。
「うわ、ラファエルもローレンツもすごいな!なあクロード、私は槍が使えるけどあんたは身ひとつでグラップラーと渡り合う羽目になったらどうする?」
「すっ飛んで逃げるね!」
レスター諸侯同盟の盟主であるリーガン家嫡子のあまりに明け透けな答えを聞いたレオニーはひどすぎる!と言って弓を置き、手を叩いて笑った。回避に自信がある兵種同士でその場に留まって、攻撃を避け続けていても体力が尽きれば負けてしまう。クロードの考えも間違ってはいない。
そこにラファエルとの訓練を終えたローレンツが首にかけた布で汗を拭きながらやってきた。クロードは彼から盟主としての資質を問われている。そう宣言された時にクロードは正直いって、面白い気持ちではなかった。探られることよりもっと嫌なことがある。
資質と言う単語が嫌だった。生まれついての才のことを資質と言う。生まれついての才と努力して身につけた才の区別は付くのか、逆にローレンツへ質問する機会が来ないだろうかと狙っている。
「レオニーさんの心がけは素晴らしい。クロード、それに比べてなんだ君は。将来の盟主としての自覚がないのか?弓矢以外に武器を扱えるようになっておくべきだ。近接戦闘をする時もあるだろう」
「ローレンツ先生もご存知の通りそんな事態に陥らないようにするのが俺の本分だよ」
「小賢しいことばかり言うのは無様だぞ」
そう言うとローレンツは水筒が乱立している机から自分の物を手に取った。訓練中はヒルダやマリアンヌですら筒に直接口を当てて飲むのだが、いつも彼は上品に蓋へ水を注いでから飲んでいる。こいつが所作を乱す様なことってあるのかね、とクロードが思った瞬間やはり手が疲れていたのかローレンツは蓋を取り落としそうになった。口の端から水が溢れ、水滴が白い喉元に落ちていく。もし彼がオメガならば、喉仏の下や頸にアルファを誘引するフェロモンの分泌腺があるはずだ。
「レオニーさん、女性の前で無作法なことをしてしまって申し訳ない」
「気にすんなってローレンツ。お行儀がいいのは知ってるからさ」
その光景を見て何故か言葉を失ってしまったクロードは調整中の弓を傍に置いて、もぞもぞと足を動かし組み直した。級長としての務めを果たすために学級全体を注意深く見ているに過ぎないのに何故こんなに落ち着かない気持ちになるのか。
ヒトは複雑な進化を遂げた結果、発情期を隠すようになった生物だ。アルファの女性もベータの女性も排卵しているかどうかは自分にも分からない。卵が先か鶏が先かは人によって意見が異なるが、排卵しているかどうかが不明であるからこそ人間の男性は配偶者と通年で性交する。そんな中で唯一、原始の名残を留めるのがオメガの男女たちだ。彼らは排卵していると周囲に知らしめてしまう体質に振り回され、抑制剤が開発されるまではアルファやベータから下に見られていた。今はセイロス教会附属の施療院が開発した抑制剤のおかげで服薬さえしていれば、オメガの男女はアルファやベータの女性と同じように暮らしていける。
しかしそれ以前の時代に産むだけの役立たず、と見做されたオメガの男女が淘汰されなかったのは何故か。強者が生き残り弱者が滅びることが淘汰と思われがちだが実際は適者生存が正しい。いくら無能と看做されようとも絶対に血を分けた後継者を必要とする身分が高いアルファにとって、確実に妊娠し出産してくれるオメガはお家存続のためになくてはならない存在だった。オメガの男女は蔑まれようとそんな風にして社会に適応し、生存してきた。フォドラに限定すれば紋章を受け継ぐ子供を高確率で産んでくれると言う事情もある。
士官学校で生涯の伴侶を見つける者は多い。表現は酷いがある程度の品質が保証されているからだ。現に黒鷲の学級にいるドロテアは婚活目的の進学だ、と公言している。しかし紋章を継ぐアルファにとって情報が足りないままの恋愛は危険すぎる。第二性を知らぬまま恋に落ちた相手がオメガであれば、アルファであるクロードは本能に逆らえない。リーガン家の嫡子としても、パルミラ王家に連なる者としても結婚相手や子供を産ませる相手は慎重に選ばねばならないというのに───
必死で冷静になろうとする級長の姿を見て、図星を指されてしょげているとでも思ったのだろうか。助言に対して反論せずとりあえず考えようとするのは素晴らしい変化だ、と告げてローレンツは汗を流すために去っていった。その広い背中を眺めてもクロードには彼の第二性がなんなのかさっぱり分からない。顔が小さく手足が長く、体躯がしっかりしたローレンツが小柄なリシテアの面倒を見ている姿は我が子を慈しむ親のようにも見えるし、歳が離れた美しい恋人同士のようにも見える。
「なあレオニー。俺に槍を教えてくれないか?」
「鍛錬で忙しい合間を縫って教えてもすっ飛んで逃げるんじゃ教え甲斐がないよ」
「そんなこと言わずに頼むよ」
「うーん、それにクロードまで槍を選んだらうちの学級は武器が偏る。剣か斧だな。つまり先生かヒルダだ」
弦の張り具合を確かめ終えたレオニーからの返答は芳しくないものだった。だが、どうすべきかの助言は与えてもらえたのでそれで良い。担任のベレトは教えるのが上手いが、その訓練内容が夜の修道院探索に出かけられないほど苛烈なのは分かっている。選択肢はひとつだった。畳む
ロナート卿の叛乱について一報が入って以来、士官学校は悪い意味で落ち着かない。気の毒なアッシュは必死で様々なものを堪えていた。義理の兄クリストフに続き、養父ロナート卿を失うかもしれない恐怖に脅える彼にはどんな言葉も慰めにはならない。今節、金鹿の学級が修道院から課された奉仕活動はそのロナート卿の叛乱を鎮圧するセイロス騎士団の補佐だ。流石に当事者の養子が所属する青獅子の学級には任せられない、と教会が考えたのだろう。
叛乱のあらましと今節の課題が発表されて以来、ローレンツはずっと機嫌が悪い。彼の考える立派な領主像とロナート卿の振る舞いがかけ離れているからだ。槍を鍛錬する際も苛立ちをぶつけるかのような態度が目立ち、訓練用の槍を壊してしまうことが多い。
そんな彼は柄だけになった槍を構え、槍と戦う時の間合いを知りたいというラファエルの訓練に付き合っている。大柄なラファエルが本気で籠手を振るって来るのに先ほどからずっと基本の動作である直突きを繰り返していた。本能的に巻き技を使いたくなる筈だが、ローレンツは意志の力でその欲求をねじ伏せて同じ動作を繰り返している。しかしどうやらラファエルの叫び声がうるさいらしい。ローレンツの眉間に微かに皺が寄っているのをクロードは見逃さなかった。
クロードの兵種はアーチャーで今はスナイパーを目指している。資格試験のことを考えれば他人の訓練を見物している暇はない。だがクロードは、ベレトからアッシュが心を落ち着けて訓練できるように的場を彼に譲ってくれ、と言われていた。
稽古場の片隅に置いてある長椅子に腰掛けたクロードは同じ兵種であるレオニーと並んで、近接戦闘の訓練を眺めながら弓の手入れをしていた。二人とも最初は真面目に調整していたのだが、どうしても同じ空間にいる他の者の訓練に目がいってしまうため手は動いていない。
「うわ、ラファエルもローレンツもすごいな!なあクロード、私は槍が使えるけどあんたは身ひとつでグラップラーと渡り合う羽目になったらどうする?」
「すっ飛んで逃げるね!」
レスター諸侯同盟の盟主であるリーガン家嫡子のあまりに明け透けな答えを聞いたレオニーはひどすぎる!と言って弓を置き、手を叩いて笑った。回避に自信がある兵種同士でその場に留まって、攻撃を避け続けていても体力が尽きれば負けてしまう。クロードの考えも間違ってはいない。
そこにラファエルとの訓練を終えたローレンツが首にかけた布で汗を拭きながらやってきた。クロードは彼から盟主としての資質を問われている。そう宣言された時にクロードは正直いって、面白い気持ちではなかった。探られることよりもっと嫌なことがある。
資質と言う単語が嫌だった。生まれついての才のことを資質と言う。生まれついての才と努力して身につけた才の区別は付くのか、逆にローレンツへ質問する機会が来ないだろうかと狙っている。
「レオニーさんの心がけは素晴らしい。クロード、それに比べてなんだ君は。将来の盟主としての自覚がないのか?弓矢以外に武器を扱えるようになっておくべきだ。近接戦闘をする時もあるだろう」
「ローレンツ先生もご存知の通りそんな事態に陥らないようにするのが俺の本分だよ」
「小賢しいことばかり言うのは無様だぞ」
そう言うとローレンツは水筒が乱立している机から自分の物を手に取った。訓練中はヒルダやマリアンヌですら筒に直接口を当てて飲むのだが、いつも彼は上品に蓋へ水を注いでから飲んでいる。こいつが所作を乱す様なことってあるのかね、とクロードが思った瞬間やはり手が疲れていたのかローレンツは蓋を取り落としそうになった。口の端から水が溢れ、水滴が白い喉元に落ちていく。もし彼がオメガならば、喉仏の下や頸にアルファを誘引するフェロモンの分泌腺があるはずだ。
「レオニーさん、女性の前で無作法なことをしてしまって申し訳ない」
「気にすんなってローレンツ。お行儀がいいのは知ってるからさ」
その光景を見て何故か言葉を失ってしまったクロードは調整中の弓を傍に置いて、もぞもぞと足を動かし組み直した。級長としての務めを果たすために学級全体を注意深く見ているに過ぎないのに何故こんなに落ち着かない気持ちになるのか。
ヒトは複雑な進化を遂げた結果、発情期を隠すようになった生物だ。アルファの女性もベータの女性も排卵しているかどうかは自分にも分からない。卵が先か鶏が先かは人によって意見が異なるが、排卵しているかどうかが不明であるからこそ人間の男性は配偶者と通年で性交する。そんな中で唯一、原始の名残を留めるのがオメガの男女たちだ。彼らは排卵していると周囲に知らしめてしまう体質に振り回され、抑制剤が開発されるまではアルファやベータから下に見られていた。今はセイロス教会附属の施療院が開発した抑制剤のおかげで服薬さえしていれば、オメガの男女はアルファやベータの女性と同じように暮らしていける。
しかしそれ以前の時代に産むだけの役立たず、と見做されたオメガの男女が淘汰されなかったのは何故か。強者が生き残り弱者が滅びることが淘汰と思われがちだが実際は適者生存が正しい。いくら無能と看做されようとも絶対に血を分けた後継者を必要とする身分が高いアルファにとって、確実に妊娠し出産してくれるオメガはお家存続のためになくてはならない存在だった。オメガの男女は蔑まれようとそんな風にして社会に適応し、生存してきた。フォドラに限定すれば紋章を受け継ぐ子供を高確率で産んでくれると言う事情もある。
士官学校で生涯の伴侶を見つける者は多い。表現は酷いがある程度の品質が保証されているからだ。現に黒鷲の学級にいるドロテアは婚活目的の進学だ、と公言している。しかし紋章を継ぐアルファにとって情報が足りないままの恋愛は危険すぎる。第二性を知らぬまま恋に落ちた相手がオメガであれば、アルファであるクロードは本能に逆らえない。リーガン家の嫡子としても、パルミラ王家に連なる者としても結婚相手や子供を産ませる相手は慎重に選ばねばならないというのに───
必死で冷静になろうとする級長の姿を見て、図星を指されてしょげているとでも思ったのだろうか。助言に対して反論せずとりあえず考えようとするのは素晴らしい変化だ、と告げてローレンツは汗を流すために去っていった。その広い背中を眺めてもクロードには彼の第二性がなんなのかさっぱり分からない。顔が小さく手足が長く、体躯がしっかりしたローレンツが小柄なリシテアの面倒を見ている姿は我が子を慈しむ親のようにも見えるし、歳が離れた美しい恋人同士のようにも見える。
「なあレオニー。俺に槍を教えてくれないか?」
「鍛錬で忙しい合間を縫って教えてもすっ飛んで逃げるんじゃ教え甲斐がないよ」
「そんなこと言わずに頼むよ」
「うーん、それにクロードまで槍を選んだらうちの学級は武器が偏る。剣か斧だな。つまり先生かヒルダだ」
弦の張り具合を確かめ終えたレオニーからの返答は芳しくないものだった。だが、どうすべきかの助言は与えてもらえたのでそれで良い。担任のベレトは教えるのが上手いが、その訓練内容が夜の修道院探索に出かけられないほど苛烈なのは分かっている。選択肢はひとつだった。畳む
「さかしま」4.#クロロレ #さかしま #完売本 #オメガバース
ローレンツは父エルヴィンに命じられてクロードを監視するうちに、自分にはない美徳を彼に見出した。彼はすぐに頭を下げて頼みごとが出来るのだ。もちろん盟主となった後ならば相応しい振る舞いではない。だがまだ彼はその位についておらず、公的にはリーガン家の嫡子と言えども十代の学生に過ぎない。
「直接、現地の者に聞けば良いではないか。両隣の教室に沢山いるだろう」
「俺は同盟の人間がどう思うのか知りたいんだ。当事者は案外当てにならないものなんだよ。フリュムの乱も七貴族の変もダスカーの悲劇も皆、自分にとって都合のいい話しか言わないだろう?」
当初ローレンツは渋っていたが勉強になる、と言われてはクロードに協力せざるを得なかった。日中は互いに忙しい身であるので週に何度か、寝る前に時間を取っている。クロードの部屋は落ち着いて話ができる環境ではないので場所はローレンツの部屋だ。喋り通しで喉が渇くのでいつも紅茶を淹れて出している。暗黙の了解で、クロードが二杯飲みおえたら話がどんなに盛り上がろうと中途半端に終わろうとその晩は終了だ。
今日の主題はダスカーの悲劇がファーガス社会に及ぼした影響について、だ。先日修道院から出された課題と関係がある。それに口に出すのは憚られるがローレンツの人生にも影響があった。ダスカーの悲劇がなければローレンツは今年度、士官学校に入っていない。
「ローレンツはフェルディアにいたことがあるんだよな?」
クロードの視線が棚に鎮座するファーガス式の給茶器とローレンツを行き来した。親帝国派の筆頭であるグロスタール家の嫡子がファーガス神聖王国の首都フェルディアにある魔道学院へ通っていたのが不思議なのだろう。
「そうだ。だから多少はファーガスに土地勘があるし昼に中庭でする正式な茶会では出さないが、ファーガス式の濃く煮出した茶も飲み慣れている。自室で手軽に飲むにはちょうど良いのだ」
「こういうのはフェルディナントにも出すのか?」
クロードにそう尋ねられてローレンツは苦笑すると小さく首を横に振った。
「こんな手軽なもの出せるわけがなかろう。彼を招くなら全力を出さねばならない」
「そうかい。これでも充分美味いのにもったいないな」
「そうは言ってもひと工夫はしている」
ローレンツが卓に飾っておいた松ぼっくりを手に取ると、玉虫色に輝く小さな甲虫が慌てて翅を広げて飛んでいった。今日は少々暑く、日中ずっと窓を開けていたせいか見事に開いていた傘の中に紛れ込んだらしい。角度によって金色にも緑色にも見える甲虫は再び山の中に戻っていった。
「どうやら寛いでいたらしい。無事退出したようだし網戸だけでなく窓も閉めるか」
「俺が閉めるよ」
クロードが席を立ち、窓を閉めた。これからの会話はファーガス出身の学生たちに聞かれたくない。いずれは窓を閉める必要があったが、そのきっかけが甲虫だっただけだ。
「話を戻すとこれはグロスタール領から持参したものだ。給茶器の中で炭と一緒に焼くと松の香りがほんの少し紅茶に移る」
「松脂か……なるほどな」
クロードはかすかな香りを確認するため、目を閉じ紅茶を口に含んだ。
「そうだ。今見せたこれが最後のひとつだよ。秋になったらこちらでも拾おうと思っている」
松ぼっくりは脂を多く含んでいるため燃料に向いていて、野営の際にも焚き付けなどに使われる。来年の今頃はグロスタール領に戻って、ローレンツは父エルヴィンの補佐をしているはずだ。夜になったら自分が子供でいられた最後の年を偲んで、ガルグ=マクの香りがする紅茶を一人きりの自室で飲むのだろう。賑やかな集団生活も、こんな風に自室へクロードを招くのも今年で終わりか、と思うと何故か寂しさで胸の奥が痛む。爵位を継いだら他人と寝巻姿で語り合う機会などなくなるはずだ。
「いいね。土が違うから松脂の香りも変わるのか」
松脂は弓の接着剤としても咳止めの薬としても利用するので、元からクロードも興味を持っていたのだろう。
「いや、そもそもガルグ=マクとグロスタール領とでは松の種類が異なるのだ。流石に種類が同じであったら人間の嗅覚では違いは分からないだろう」
「だが根差す土が違えば、種類が同じでも匂いが変わるかもしれない。……興味深くはあるが本題に入ろうか。ロナート卿は誰に何を吹き込まれたんだろうな」
ダスカーの悲劇以来、ファーガスはありとあらゆる面で余裕を失った。些細なことが人々を破滅へと導いていく。それほど人心が荒廃し制度が疲弊しているのだ。藁にも縋りたい状態でロナート卿は誰から、どんな偽りの希望を与えられたのだろうか。
「誰、はともかく処刑された嫡子が実は無実であった、むしろガルグ=マクの中央教会が〝ダスカーの悲劇〟の首謀者だった、と信じ込まされたのではないだろうか。僕にはそれくらいしか思いつかない」
そうでなければ領民全てを巻き込むと分かった上で叛旗を翻すことなど出来ないだろう。叛乱は不満の表明と原因解決を迫る手段だ。時には蜂起した不満分子が自ら原因を解決しようとする。
「誰がそんな出鱈目を吹き込んだんだろうな」
「ファーガスが弱体化して喜ぶ者たちだろう。どこの誰かは知らないが」
入学した当初であればがさつでアルファであると見透かされてしまうような人物を、クロードを自室に入れるなどあり得ない、と言って一笑に付しただろう。だが今となっては彼が一杯目を飲み終えてしまいそうなことがこんなにも惜しい。
「なあローレンツ。俺が思うにダスカーの件、ファーガスの連中はまだ下手人なんかどうでもいいんだ」
緑色の瞳を穏やかな琥珀色の水面に映しながらクロードはとんでもない発言をした。
「クロード!あれほどの大事件に対して下手人がどうでもいいなどあり得ない」
「国王弑逆だぞ。そんな大それた事件、地方の少数民族だけで起こせるもんか。皆、無意識のうちに当時からわかっていた筈だ。人間、安心するためならどんな荒唐無稽な話でも信じるもんさ。そして連中が冷静になるまで真相は解明されない」
ローレンツにも分かっていた。ただ、言語化しなかっただけだ。後始末を担当したセイロス騎士団も分かっていたが、当事者ではないからファーガス神聖王国の主張を受け入れた。さっさと幕を引きたかったからだろう。ダスカー人はその時、そこに居たからという理由で虐殺されている。
ロナート卿の反乱鎮圧後、大司教の暗殺を企む密書について知らされた瞬間に馬鹿らしい、そんな素直なやり方で暗殺などできるわけがない、と切って捨てたクロードらしい意見だった。過激な意見を述べた本人二杯目の紅茶で呑気に喉を潤している。一方でローレンツは落ち着きを取り戻すために紅茶に口をつけた。今晩はこれで終いだ。
「ではロナート卿に嘘を吹き込んだ者がダスカーの首謀者、もしくは首謀者に連なる者だろうな。今回の件でファーガスは更に弱体化した。その連中が満を持して修道院へ直接手を出してくるのか」
「そうだ。それに連中はいずれ同盟にも似たようなことを仕掛けてくる可能性が高い。俺もお前もお互い弱点につけ込んだ、甘い毒みたいな嘘に惑わされない様に気をつけようぜ」
クロードはそう言うとローレンツの部屋から出ていった。クロードにとっての甘い毒のような嘘はなんだろうか。ローレンツにとっての甘い毒は……。畳む
ローレンツは父エルヴィンに命じられてクロードを監視するうちに、自分にはない美徳を彼に見出した。彼はすぐに頭を下げて頼みごとが出来るのだ。もちろん盟主となった後ならば相応しい振る舞いではない。だがまだ彼はその位についておらず、公的にはリーガン家の嫡子と言えども十代の学生に過ぎない。
「直接、現地の者に聞けば良いではないか。両隣の教室に沢山いるだろう」
「俺は同盟の人間がどう思うのか知りたいんだ。当事者は案外当てにならないものなんだよ。フリュムの乱も七貴族の変もダスカーの悲劇も皆、自分にとって都合のいい話しか言わないだろう?」
当初ローレンツは渋っていたが勉強になる、と言われてはクロードに協力せざるを得なかった。日中は互いに忙しい身であるので週に何度か、寝る前に時間を取っている。クロードの部屋は落ち着いて話ができる環境ではないので場所はローレンツの部屋だ。喋り通しで喉が渇くのでいつも紅茶を淹れて出している。暗黙の了解で、クロードが二杯飲みおえたら話がどんなに盛り上がろうと中途半端に終わろうとその晩は終了だ。
今日の主題はダスカーの悲劇がファーガス社会に及ぼした影響について、だ。先日修道院から出された課題と関係がある。それに口に出すのは憚られるがローレンツの人生にも影響があった。ダスカーの悲劇がなければローレンツは今年度、士官学校に入っていない。
「ローレンツはフェルディアにいたことがあるんだよな?」
クロードの視線が棚に鎮座するファーガス式の給茶器とローレンツを行き来した。親帝国派の筆頭であるグロスタール家の嫡子がファーガス神聖王国の首都フェルディアにある魔道学院へ通っていたのが不思議なのだろう。
「そうだ。だから多少はファーガスに土地勘があるし昼に中庭でする正式な茶会では出さないが、ファーガス式の濃く煮出した茶も飲み慣れている。自室で手軽に飲むにはちょうど良いのだ」
「こういうのはフェルディナントにも出すのか?」
クロードにそう尋ねられてローレンツは苦笑すると小さく首を横に振った。
「こんな手軽なもの出せるわけがなかろう。彼を招くなら全力を出さねばならない」
「そうかい。これでも充分美味いのにもったいないな」
「そうは言ってもひと工夫はしている」
ローレンツが卓に飾っておいた松ぼっくりを手に取ると、玉虫色に輝く小さな甲虫が慌てて翅を広げて飛んでいった。今日は少々暑く、日中ずっと窓を開けていたせいか見事に開いていた傘の中に紛れ込んだらしい。角度によって金色にも緑色にも見える甲虫は再び山の中に戻っていった。
「どうやら寛いでいたらしい。無事退出したようだし網戸だけでなく窓も閉めるか」
「俺が閉めるよ」
クロードが席を立ち、窓を閉めた。これからの会話はファーガス出身の学生たちに聞かれたくない。いずれは窓を閉める必要があったが、そのきっかけが甲虫だっただけだ。
「話を戻すとこれはグロスタール領から持参したものだ。給茶器の中で炭と一緒に焼くと松の香りがほんの少し紅茶に移る」
「松脂か……なるほどな」
クロードはかすかな香りを確認するため、目を閉じ紅茶を口に含んだ。
「そうだ。今見せたこれが最後のひとつだよ。秋になったらこちらでも拾おうと思っている」
松ぼっくりは脂を多く含んでいるため燃料に向いていて、野営の際にも焚き付けなどに使われる。来年の今頃はグロスタール領に戻って、ローレンツは父エルヴィンの補佐をしているはずだ。夜になったら自分が子供でいられた最後の年を偲んで、ガルグ=マクの香りがする紅茶を一人きりの自室で飲むのだろう。賑やかな集団生活も、こんな風に自室へクロードを招くのも今年で終わりか、と思うと何故か寂しさで胸の奥が痛む。爵位を継いだら他人と寝巻姿で語り合う機会などなくなるはずだ。
「いいね。土が違うから松脂の香りも変わるのか」
松脂は弓の接着剤としても咳止めの薬としても利用するので、元からクロードも興味を持っていたのだろう。
「いや、そもそもガルグ=マクとグロスタール領とでは松の種類が異なるのだ。流石に種類が同じであったら人間の嗅覚では違いは分からないだろう」
「だが根差す土が違えば、種類が同じでも匂いが変わるかもしれない。……興味深くはあるが本題に入ろうか。ロナート卿は誰に何を吹き込まれたんだろうな」
ダスカーの悲劇以来、ファーガスはありとあらゆる面で余裕を失った。些細なことが人々を破滅へと導いていく。それほど人心が荒廃し制度が疲弊しているのだ。藁にも縋りたい状態でロナート卿は誰から、どんな偽りの希望を与えられたのだろうか。
「誰、はともかく処刑された嫡子が実は無実であった、むしろガルグ=マクの中央教会が〝ダスカーの悲劇〟の首謀者だった、と信じ込まされたのではないだろうか。僕にはそれくらいしか思いつかない」
そうでなければ領民全てを巻き込むと分かった上で叛旗を翻すことなど出来ないだろう。叛乱は不満の表明と原因解決を迫る手段だ。時には蜂起した不満分子が自ら原因を解決しようとする。
「誰がそんな出鱈目を吹き込んだんだろうな」
「ファーガスが弱体化して喜ぶ者たちだろう。どこの誰かは知らないが」
入学した当初であればがさつでアルファであると見透かされてしまうような人物を、クロードを自室に入れるなどあり得ない、と言って一笑に付しただろう。だが今となっては彼が一杯目を飲み終えてしまいそうなことがこんなにも惜しい。
「なあローレンツ。俺が思うにダスカーの件、ファーガスの連中はまだ下手人なんかどうでもいいんだ」
緑色の瞳を穏やかな琥珀色の水面に映しながらクロードはとんでもない発言をした。
「クロード!あれほどの大事件に対して下手人がどうでもいいなどあり得ない」
「国王弑逆だぞ。そんな大それた事件、地方の少数民族だけで起こせるもんか。皆、無意識のうちに当時からわかっていた筈だ。人間、安心するためならどんな荒唐無稽な話でも信じるもんさ。そして連中が冷静になるまで真相は解明されない」
ローレンツにも分かっていた。ただ、言語化しなかっただけだ。後始末を担当したセイロス騎士団も分かっていたが、当事者ではないからファーガス神聖王国の主張を受け入れた。さっさと幕を引きたかったからだろう。ダスカー人はその時、そこに居たからという理由で虐殺されている。
ロナート卿の反乱鎮圧後、大司教の暗殺を企む密書について知らされた瞬間に馬鹿らしい、そんな素直なやり方で暗殺などできるわけがない、と切って捨てたクロードらしい意見だった。過激な意見を述べた本人二杯目の紅茶で呑気に喉を潤している。一方でローレンツは落ち着きを取り戻すために紅茶に口をつけた。今晩はこれで終いだ。
「ではロナート卿に嘘を吹き込んだ者がダスカーの首謀者、もしくは首謀者に連なる者だろうな。今回の件でファーガスは更に弱体化した。その連中が満を持して修道院へ直接手を出してくるのか」
「そうだ。それに連中はいずれ同盟にも似たようなことを仕掛けてくる可能性が高い。俺もお前もお互い弱点につけ込んだ、甘い毒みたいな嘘に惑わされない様に気をつけようぜ」
クロードはそう言うとローレンツの部屋から出ていった。クロードにとっての甘い毒のような嘘はなんだろうか。ローレンツにとっての甘い毒は……。畳む
「さかしま」5.#クロロレ #さかしま #完売本 #オメガバース
クロードは薬学に興味がある。自分の命を守るために身につけざるを得なかった。しかしそのおかげで自然の中で目に入るありとあらゆるものが、クロードにとっては利用できる可能性を秘めた素材となった。クロードにとって雑草という名の草はない。修道院の中も同じだ。全てが謎を解くための鍵に見える。
一方でローレンツは「美術品ならともかく、壁を眺めて何が楽しいのか分からない」と言っていた。彼には少しでも自分が有利になるよう、目につくもの全てを利用してやろうと考えた経験がない。周囲を飢えた目で見る必要がなかったのだ。それはローレンツの育ちの良さの表れだ。
修道院を狙う賊の目的を探るためクロードは担任であるベレト、それにセイロス騎士団の許可を得て堂々と敷地内を探って回った。あまり良い顔はされなかったがそこは気にしていない。日頃入れない聖廟に実際に換金出来る宝物があるかどうか、はクロードにとって関係なかった。情報という宝が詰まった宝物庫も同然の立入禁止区域に堂々と入れることが素晴らしい。
換気されていない埃だらけの空間で探索をするのでクロードは久しぶりに髪や顔に布を巻いていた。顔を隠していると故郷にいた頃、こっそり街中に行った時のような気持ちになる。あの時より背は伸び、口は回るようになったが。
葬られている人々の棺や墓石の文字は書体が違いすぎて、崩し字の字典がなければクロードには読めない。だが意匠を丹念に見ていくと故人がどのような功績を立てたのかがわかってくる。書記の棺には文房具や書物が彫られていたし、天秤が彫られているものはおそらく法学で功績があったのだろう。そんな中、とある棺がクロードの興味を引いた。場違いなまでに様々な草花や果物それに蟹や蜥蜴、甲虫の姿が彫られている。セイロス教の施設で自然を称えるような物が見つかるのは珍しい。この棺は彩色が微かに残っていて、先日ローレンツの部屋で見かけた美しい甲虫らしきものが色付きで描かれていた。可能ならば木炭と大きな紙を使って原寸大で写し取りたいところだが、そんな都合が良い物を持っているわけもなく時間も限られている。仕方ないのでクロードは手持ちの書字板にわかったことを急いで記した。興味は尽きないがこの棺ばかりに関わってはいられない。階段の上から俯瞰で聖廟を眺め異質な、目を引く物がないか確かめた。
この聖廟はセイロス教に尽くした故人を偲び讃えるために作られている。その証拠にほとんどの棺には様々な意匠が凝らされていた。だがただひとつ、誰にも何も伝えようとしない棺がある。ひた隠しにせねばならない何かがあの棺にはあるらしい。賊の狙いが聖廟であるならばあの棺が目当てだとクロードは思った。無銘の棺に近寄り触ろうとするとぐにゃりと空間が歪む。結界を張ってまで見せたくない何かがあるのだろう。
聖廟から出るとクロードは埃から守ってくれた布を頭から取り去った。埃を叩いて畳んでしまえば単なる一枚布に戻り、持っていても怪しまれはしない。自室に置いてある植物図鑑で、棺に彫られていた植物がなんであったか調べようと扉に手をかけた時にくしゃみの音がクロードの鼓膜を刺激した。反射的に音がした方を見ると訓練着姿のローレンツが手巾を顔にあてていた。隣室の住人のくしゃみは体格の割に音が高く、こう言っては何だが可愛らしい。
「クロード、君はいったい何処でそんな埃まみれになったのだ?」
「先生の手伝いだ」
ローレンツは着替えと身体を拭く布や香油、それに櫛を手に持って自室から出てきたところだった。直接訓練場に一式を持っていく者もいるが、土埃で汚れてしまうことを気にする者は自室まで取りに戻る。ローレンツは後者だった。汗だくだから早く身体を清めたいだろうにわざわざ取りに戻るその姿を見て、クロードの身体の手綱を握っていた知的好奇心が鞍から降りてしまう。植物図鑑は後で読むことにした。
「そうか。僕は見ての通りだよ。君も早く入浴した方がいいな。ではお先に」
クロードが手早く支度を終えて自室の扉を開けると当然だがローレンツの姿は見る影もなかった。彼は足が長いので歩くのが早い。先ほどのくしゃみはクロードにまとわりついていた埃のせいかもしれないが、汗をかいた体が冷えれば同じように可愛らしい音を立ててくしゃみをするのだろう。
───可愛らしい?何故そんなことを考えた?
最近ローレンツとは互いに歩み寄っているとは言え、彼はどう小さく見積もっても自分より握り拳二つ分は背が高く、うなじの毛を刈り上げているような男性だ。だがもし仮に彼の第二性がオメガであってくれたなら。
独身のオメガは男性であれ女性であれ親しくならない限り、アルファやベータ相手には絶対に第二性を隠してしまう。過去の歴史がそうさせるし質の良い抑制剤があるここフォドラではそれが可能なのだ。そして社会の多数派を占めるベータたちは第二性を表明する必要がない。そんな社会に属するアルファは発情期のせいで社会との関わりに障害を持ち、蔑まれていたオメガとは対称的な理由で自身がアルファであると表明できない。都合よく、加害者にさせられてしまう危険がある。
ローレンツと仲が良いと言えばフェルディナントやシルヴァンだ。彼らはローレンツから第二性を告げられているのだろうか。クロードが自分はアルファである、とローレンツにきちんと告げる日は来るのだろうか。そんな益体もないことを考えていると何故か寂寥感に心を支配された。
脱衣所の籠は空のままになっているものが多く、浴室内はあまり人がいないらしい。クロードは前髪の三つ編みを解き、脱衣所で湯浴み着に着替えた。これもフォドラ独特の風習で、なんと裸ではないという理由で浴室が男女別になっていない───流石に洗い場は男女別だが。
浴室への通り道である洗い場には何人か学生がいた。適当に挨拶をして浴室内に備え付けられている大きな鉢のお湯を何杯か身体にかける。浴室に入るとやはり中は空いていて、ローレンツが独り充満する蒸気の中、目を閉じたまま白く長い手足を台の上に投げ出して寛いでいた。汗で湯浴み着が貼り付き鍛練でついた筋肉の線が透けて見える。ローレンツは汗を含んだ紫の髪の毛を白い手でかきあげた際に反対側に座ったクロードに気づいて目線だけ寄越してきた。温まって血行がよくなったせいか頬が赤い。彼は元の顔色が磁器のように白いので赤みが目立つ。日頃はよく回る舌が動いてくれず、なんと声をかけるべきかクロードが迷っていると向こうから話しかけてきた。
「さっきから黙ってこちらを見ているが僕の顔に何かついているのか?」
「何もついていないから黙って見てたのさ」
「今晩はどうする」
「そうだな、課題について先生に報告する前に少し話したい」
ローレンツは頷いてお先に、と言うと洗い場へ向かった。汗で湯浴み着が貼り付いているせいで背中や腰の線がクロードからよく見えた。後を追う気にもなれず、空いているのを良いことにクロードも手足を台の上に投げ出す。聖廟から出てきた時は早く植物図鑑で自分が見たものの裏を取りたいと思っていたのに何故のんびりと入浴しているのだろうか。
今、クロードの身体の手綱を握っているものの正体は何なのだろうか。畳む
クロードは薬学に興味がある。自分の命を守るために身につけざるを得なかった。しかしそのおかげで自然の中で目に入るありとあらゆるものが、クロードにとっては利用できる可能性を秘めた素材となった。クロードにとって雑草という名の草はない。修道院の中も同じだ。全てが謎を解くための鍵に見える。
一方でローレンツは「美術品ならともかく、壁を眺めて何が楽しいのか分からない」と言っていた。彼には少しでも自分が有利になるよう、目につくもの全てを利用してやろうと考えた経験がない。周囲を飢えた目で見る必要がなかったのだ。それはローレンツの育ちの良さの表れだ。
修道院を狙う賊の目的を探るためクロードは担任であるベレト、それにセイロス騎士団の許可を得て堂々と敷地内を探って回った。あまり良い顔はされなかったがそこは気にしていない。日頃入れない聖廟に実際に換金出来る宝物があるかどうか、はクロードにとって関係なかった。情報という宝が詰まった宝物庫も同然の立入禁止区域に堂々と入れることが素晴らしい。
換気されていない埃だらけの空間で探索をするのでクロードは久しぶりに髪や顔に布を巻いていた。顔を隠していると故郷にいた頃、こっそり街中に行った時のような気持ちになる。あの時より背は伸び、口は回るようになったが。
葬られている人々の棺や墓石の文字は書体が違いすぎて、崩し字の字典がなければクロードには読めない。だが意匠を丹念に見ていくと故人がどのような功績を立てたのかがわかってくる。書記の棺には文房具や書物が彫られていたし、天秤が彫られているものはおそらく法学で功績があったのだろう。そんな中、とある棺がクロードの興味を引いた。場違いなまでに様々な草花や果物それに蟹や蜥蜴、甲虫の姿が彫られている。セイロス教の施設で自然を称えるような物が見つかるのは珍しい。この棺は彩色が微かに残っていて、先日ローレンツの部屋で見かけた美しい甲虫らしきものが色付きで描かれていた。可能ならば木炭と大きな紙を使って原寸大で写し取りたいところだが、そんな都合が良い物を持っているわけもなく時間も限られている。仕方ないのでクロードは手持ちの書字板にわかったことを急いで記した。興味は尽きないがこの棺ばかりに関わってはいられない。階段の上から俯瞰で聖廟を眺め異質な、目を引く物がないか確かめた。
この聖廟はセイロス教に尽くした故人を偲び讃えるために作られている。その証拠にほとんどの棺には様々な意匠が凝らされていた。だがただひとつ、誰にも何も伝えようとしない棺がある。ひた隠しにせねばならない何かがあの棺にはあるらしい。賊の狙いが聖廟であるならばあの棺が目当てだとクロードは思った。無銘の棺に近寄り触ろうとするとぐにゃりと空間が歪む。結界を張ってまで見せたくない何かがあるのだろう。
聖廟から出るとクロードは埃から守ってくれた布を頭から取り去った。埃を叩いて畳んでしまえば単なる一枚布に戻り、持っていても怪しまれはしない。自室に置いてある植物図鑑で、棺に彫られていた植物がなんであったか調べようと扉に手をかけた時にくしゃみの音がクロードの鼓膜を刺激した。反射的に音がした方を見ると訓練着姿のローレンツが手巾を顔にあてていた。隣室の住人のくしゃみは体格の割に音が高く、こう言っては何だが可愛らしい。
「クロード、君はいったい何処でそんな埃まみれになったのだ?」
「先生の手伝いだ」
ローレンツは着替えと身体を拭く布や香油、それに櫛を手に持って自室から出てきたところだった。直接訓練場に一式を持っていく者もいるが、土埃で汚れてしまうことを気にする者は自室まで取りに戻る。ローレンツは後者だった。汗だくだから早く身体を清めたいだろうにわざわざ取りに戻るその姿を見て、クロードの身体の手綱を握っていた知的好奇心が鞍から降りてしまう。植物図鑑は後で読むことにした。
「そうか。僕は見ての通りだよ。君も早く入浴した方がいいな。ではお先に」
クロードが手早く支度を終えて自室の扉を開けると当然だがローレンツの姿は見る影もなかった。彼は足が長いので歩くのが早い。先ほどのくしゃみはクロードにまとわりついていた埃のせいかもしれないが、汗をかいた体が冷えれば同じように可愛らしい音を立ててくしゃみをするのだろう。
───可愛らしい?何故そんなことを考えた?
最近ローレンツとは互いに歩み寄っているとは言え、彼はどう小さく見積もっても自分より握り拳二つ分は背が高く、うなじの毛を刈り上げているような男性だ。だがもし仮に彼の第二性がオメガであってくれたなら。
独身のオメガは男性であれ女性であれ親しくならない限り、アルファやベータ相手には絶対に第二性を隠してしまう。過去の歴史がそうさせるし質の良い抑制剤があるここフォドラではそれが可能なのだ。そして社会の多数派を占めるベータたちは第二性を表明する必要がない。そんな社会に属するアルファは発情期のせいで社会との関わりに障害を持ち、蔑まれていたオメガとは対称的な理由で自身がアルファであると表明できない。都合よく、加害者にさせられてしまう危険がある。
ローレンツと仲が良いと言えばフェルディナントやシルヴァンだ。彼らはローレンツから第二性を告げられているのだろうか。クロードが自分はアルファである、とローレンツにきちんと告げる日は来るのだろうか。そんな益体もないことを考えていると何故か寂寥感に心を支配された。
脱衣所の籠は空のままになっているものが多く、浴室内はあまり人がいないらしい。クロードは前髪の三つ編みを解き、脱衣所で湯浴み着に着替えた。これもフォドラ独特の風習で、なんと裸ではないという理由で浴室が男女別になっていない───流石に洗い場は男女別だが。
浴室への通り道である洗い場には何人か学生がいた。適当に挨拶をして浴室内に備え付けられている大きな鉢のお湯を何杯か身体にかける。浴室に入るとやはり中は空いていて、ローレンツが独り充満する蒸気の中、目を閉じたまま白く長い手足を台の上に投げ出して寛いでいた。汗で湯浴み着が貼り付き鍛練でついた筋肉の線が透けて見える。ローレンツは汗を含んだ紫の髪の毛を白い手でかきあげた際に反対側に座ったクロードに気づいて目線だけ寄越してきた。温まって血行がよくなったせいか頬が赤い。彼は元の顔色が磁器のように白いので赤みが目立つ。日頃はよく回る舌が動いてくれず、なんと声をかけるべきかクロードが迷っていると向こうから話しかけてきた。
「さっきから黙ってこちらを見ているが僕の顔に何かついているのか?」
「何もついていないから黙って見てたのさ」
「今晩はどうする」
「そうだな、課題について先生に報告する前に少し話したい」
ローレンツは頷いてお先に、と言うと洗い場へ向かった。汗で湯浴み着が貼り付いているせいで背中や腰の線がクロードからよく見えた。後を追う気にもなれず、空いているのを良いことにクロードも手足を台の上に投げ出す。聖廟から出てきた時は早く植物図鑑で自分が見たものの裏を取りたいと思っていたのに何故のんびりと入浴しているのだろうか。
今、クロードの身体の手綱を握っているものの正体は何なのだろうか。畳む
「さかしま」6.#クロロレ #さかしま #完売本 #オメガバース
今節のクロードとヒルダはずっと疲労困憊だ。口を開けば疲れた、しか言わない。休みの日には担任であるベレトに呼び出されエーデルガルト、リンハルト、ディミトリ、アッシュと共に守秘義務のある課題に取り組んでいる。当然だが彼らは同級生たちにも何に取り組んでいるのか秘密にしていた。マリアンヌもヒルダから何も知らされていないが、ローレンツによるとヒューベルトやドゥドゥですら主君がベレトとどこで何をしているのか知らされていないらしい。
「ではヒルダさんから嫌われているわけではないのですね」
「良かった。マリアンヌさんがようやく明るい顔を見せてくれて安心したよ」
ヒルダがいないと極端に内向き思考なマリアンヌが誰かを苛立たせたり動揺させてしまうことが多い。そんなマリアンヌを庇うため、ローレンツは彼女と共に行動する機会が自然と増えた。今日もローレンツが掴んでいることだけでも伝えよう、と思って茶会に招いている。
マリアンヌが男性であるローレンツと安心して共に行動できるのはオメガ同士だからだ。オメガはベータやアルファに対して自分の第二性を明かさないが、オメガだけの場であれば事情は異なる。学生たちの健康管理を担う医師のマヌエラが秘密裏に主催したオメガ達の会合で、互いの姿を初めて見た時には驚いたものだが今は茶会に招き合う仲だ。
「エドマンド家の力があれば第二性に振り回されるのも最小限になるだろう、と実の両親が……」
「僕もグロスタール家に生まれていなければどうなっていたか分からない。僕の場合は天佑だが、マリアンヌさんは辺境伯のお眼鏡にかなったのだ。もっと自信を持っていい」
何度目かの会合でそんな会話を交わして以降、二人は親友になった。オメガの男女同士は結婚しても子供を授かることはない。だが悩みや恐れを共有し、生涯を通じた大切な友人になることは出来る。発情なのか恋愛なのか、お相手からの愛は肉欲なのか愛情なのか、区別をつけたいお年頃のオメガたちにとって同じ立場の者に話を聞いてもらう時間は精神の安定に必要不可欠なものだ。
マリアンヌは在学中にとにかくまずは有力者の友人を作れ、と養父であるエドマンド辺境伯から言われているらしい。だがヒルダとローレンツがいるのでこれで充分、とばかりに彼女は金鹿の学級に篭っていた。良港を抱えるエドマンド領の後継者としてファーガスやアドラステアに知己を作れ、ということなのだろうが第二性に加えて他にも何やら秘密があるマリアンヌにはまだ難しい。
一方で人見知りを全くしないローレンツは将来の伴侶を探すため、アルファであろうと思われる貴族の女性たちに声をかけている。しかし彼女たちからの評判はすごぶる悪い。いくつか理由はあるのだが、中庭で語らうローレンツとマリアンヌの二人が事情を知らぬものたちから見ればお似合いに見えるのもそのうちのひとつだ。既にマリアンヌがいるのに更に声をかけるなんて、と思われている。
「失礼、肩に虫が」
そう言うとローレンツは手巾を手に取り、マリアンヌの肩に止まっていた緑色に輝く甲虫をそっとつまんだ。季節が進み、山の中といえども気温が上がり虫も含めて動物たちの行動が活発になっている。
「ありがとうございます。ローレンツさん」
「いや、礼にはおよばない」
「鳥たちも何故かこの虫は食べないのです。不思議ですね」
ローレンツが白い手巾を軽く払うと甲虫は角度によっては金色に見える翅を広げて、木々の向こうへ飛んでいった。クロードと話している時にも紛れ込んで場を和ませた小さな来訪者はオグマ山脈の固有種なのだろうか。
「あーっ!マリアンヌちゃんたちいいなー!」
戦闘後なのか眉間に皺を寄せ、ぼろぼろの格好をしたベレトとヒルダとクロードの三人が中庭にやってきた。疲れているのか目を何度か瞬かせてクロードがため息をつく。ペラペラとよく口が回る、口から先に生まれてきたのか、となじられるクロードだが疲れのせいか言葉も出てこないらしい。
「他言無用だ」
ベレトがヒルダとクロードがローレンツとマリアンヌに秘密を話さないよう釘を刺した。彼らは一体、どこで何をやっているのだろう。二人の動きがベレトの言葉に拘束され、ヒルダとクロードが息を呑んだ。ただならぬ三人の雰囲気にローレンツとマリアンヌも黙っているしかない。気まずくなったその刹那、テーブルの上にまだ残っていた胡瓜のサンドイッチにベレトの手が伸び、あっという間に口の中に消えた。尊重されて育った長男と一人っ子という組み合わせでは遠慮の塊がよく発生する。茶会用に口を大きく開けずとも食べられるよう小さく切り分けてあったせいか、元傭兵のベレトはまさに一口で食べてしまった。
クロードが相手ならばローレンツはくどくどと行儀作法について注意しただろう。だが相手は傭兵団の中で育ったベレトだ。礼儀作法をどこからどう説けば良いのか全く分からない。いつも伏し目がちなマリアンヌも驚いて目を見開いている。
「だから他言無用と言っただろう。しかし美味いな、これは」
真顔で答える担任教師を見てヒルダとクロードが堪えきれないと言った調子で笑い出した。
「あっはっは!いや、先生それは!確かに他言無用だ!セテスさんに知られたら怒られるな!」
「腹が減ったな。食堂に何かないか聞きに行こう」
ベレトは表情が乏しく、いつも真顔で突拍子もないことをしでかすのでいつもローレンツもマリアンヌも呆然としてしまう。だが剣呑な雰囲気は完全に失せた。
守秘義務のある課題に誘われず、内心では失望していたローレンツはベレトの奇行のおかげでクロードたちを問い詰めるという不躾な行為に及ばず済んでいる。そこを見越しあえて不躾な行為に及んで自ら泥を被っているのだとしたらローレンツは一生、ベレトに敵わない。
「マリアンヌさん、先生に皿を空にされてしまったしそろそろお開きにしようか」
「ええ、ローレンツさん、ありがとうございました。近頃気が塞いでいたのでよい気分転換になりました」
オメガである二人は常に抑制剤を服用し発情期が来ないように調整しているため、ごく軽い生理が来るだけだ。血の匂いだけならば香水などでアルファを誤魔化せる。
だが嗅覚が鋭い他の生物は誤魔化せない。犬なども訓練すれば判別に使えるだろう。ただフォドラの社会がその必要を感じないからやっていないだけだ。そしてある種の匂いに反応する昆虫は多い。汗であれば蚊、腐肉であれば蝿、そしてこのガルグ=マクに生息する甲虫はオメガの分泌するフェロモンに反応する。前者二つは微量であっても激しい反応を見せるが、玉虫色の甲虫は個体によって反応の激しさに違いがある。
かつてそこに気付いたセイロス教の修道士がいた。名を忘れられた修道士は特性ごとに甲虫を選り分けて繁殖し、観察した。フォドラには虫を愛でる文化はない。その修道士はクロードのように、どこか別の土地からやってきたものだったから気付いたのかもしれない。その修道士個人の資料も先の大火の際に宝杯の儀にまつわる資料と共に焼失してしまった。男性なのか女性なのか第二性はなんであったのか。今も昔もフォドラ中のオメガたちが女神の次に感謝の祈りを捧げる名無しの誰かは列聖されていない。畳む
今節のクロードとヒルダはずっと疲労困憊だ。口を開けば疲れた、しか言わない。休みの日には担任であるベレトに呼び出されエーデルガルト、リンハルト、ディミトリ、アッシュと共に守秘義務のある課題に取り組んでいる。当然だが彼らは同級生たちにも何に取り組んでいるのか秘密にしていた。マリアンヌもヒルダから何も知らされていないが、ローレンツによるとヒューベルトやドゥドゥですら主君がベレトとどこで何をしているのか知らされていないらしい。
「ではヒルダさんから嫌われているわけではないのですね」
「良かった。マリアンヌさんがようやく明るい顔を見せてくれて安心したよ」
ヒルダがいないと極端に内向き思考なマリアンヌが誰かを苛立たせたり動揺させてしまうことが多い。そんなマリアンヌを庇うため、ローレンツは彼女と共に行動する機会が自然と増えた。今日もローレンツが掴んでいることだけでも伝えよう、と思って茶会に招いている。
マリアンヌが男性であるローレンツと安心して共に行動できるのはオメガ同士だからだ。オメガはベータやアルファに対して自分の第二性を明かさないが、オメガだけの場であれば事情は異なる。学生たちの健康管理を担う医師のマヌエラが秘密裏に主催したオメガ達の会合で、互いの姿を初めて見た時には驚いたものだが今は茶会に招き合う仲だ。
「エドマンド家の力があれば第二性に振り回されるのも最小限になるだろう、と実の両親が……」
「僕もグロスタール家に生まれていなければどうなっていたか分からない。僕の場合は天佑だが、マリアンヌさんは辺境伯のお眼鏡にかなったのだ。もっと自信を持っていい」
何度目かの会合でそんな会話を交わして以降、二人は親友になった。オメガの男女同士は結婚しても子供を授かることはない。だが悩みや恐れを共有し、生涯を通じた大切な友人になることは出来る。発情なのか恋愛なのか、お相手からの愛は肉欲なのか愛情なのか、区別をつけたいお年頃のオメガたちにとって同じ立場の者に話を聞いてもらう時間は精神の安定に必要不可欠なものだ。
マリアンヌは在学中にとにかくまずは有力者の友人を作れ、と養父であるエドマンド辺境伯から言われているらしい。だがヒルダとローレンツがいるのでこれで充分、とばかりに彼女は金鹿の学級に篭っていた。良港を抱えるエドマンド領の後継者としてファーガスやアドラステアに知己を作れ、ということなのだろうが第二性に加えて他にも何やら秘密があるマリアンヌにはまだ難しい。
一方で人見知りを全くしないローレンツは将来の伴侶を探すため、アルファであろうと思われる貴族の女性たちに声をかけている。しかし彼女たちからの評判はすごぶる悪い。いくつか理由はあるのだが、中庭で語らうローレンツとマリアンヌの二人が事情を知らぬものたちから見ればお似合いに見えるのもそのうちのひとつだ。既にマリアンヌがいるのに更に声をかけるなんて、と思われている。
「失礼、肩に虫が」
そう言うとローレンツは手巾を手に取り、マリアンヌの肩に止まっていた緑色に輝く甲虫をそっとつまんだ。季節が進み、山の中といえども気温が上がり虫も含めて動物たちの行動が活発になっている。
「ありがとうございます。ローレンツさん」
「いや、礼にはおよばない」
「鳥たちも何故かこの虫は食べないのです。不思議ですね」
ローレンツが白い手巾を軽く払うと甲虫は角度によっては金色に見える翅を広げて、木々の向こうへ飛んでいった。クロードと話している時にも紛れ込んで場を和ませた小さな来訪者はオグマ山脈の固有種なのだろうか。
「あーっ!マリアンヌちゃんたちいいなー!」
戦闘後なのか眉間に皺を寄せ、ぼろぼろの格好をしたベレトとヒルダとクロードの三人が中庭にやってきた。疲れているのか目を何度か瞬かせてクロードがため息をつく。ペラペラとよく口が回る、口から先に生まれてきたのか、となじられるクロードだが疲れのせいか言葉も出てこないらしい。
「他言無用だ」
ベレトがヒルダとクロードがローレンツとマリアンヌに秘密を話さないよう釘を刺した。彼らは一体、どこで何をやっているのだろう。二人の動きがベレトの言葉に拘束され、ヒルダとクロードが息を呑んだ。ただならぬ三人の雰囲気にローレンツとマリアンヌも黙っているしかない。気まずくなったその刹那、テーブルの上にまだ残っていた胡瓜のサンドイッチにベレトの手が伸び、あっという間に口の中に消えた。尊重されて育った長男と一人っ子という組み合わせでは遠慮の塊がよく発生する。茶会用に口を大きく開けずとも食べられるよう小さく切り分けてあったせいか、元傭兵のベレトはまさに一口で食べてしまった。
クロードが相手ならばローレンツはくどくどと行儀作法について注意しただろう。だが相手は傭兵団の中で育ったベレトだ。礼儀作法をどこからどう説けば良いのか全く分からない。いつも伏し目がちなマリアンヌも驚いて目を見開いている。
「だから他言無用と言っただろう。しかし美味いな、これは」
真顔で答える担任教師を見てヒルダとクロードが堪えきれないと言った調子で笑い出した。
「あっはっは!いや、先生それは!確かに他言無用だ!セテスさんに知られたら怒られるな!」
「腹が減ったな。食堂に何かないか聞きに行こう」
ベレトは表情が乏しく、いつも真顔で突拍子もないことをしでかすのでいつもローレンツもマリアンヌも呆然としてしまう。だが剣呑な雰囲気は完全に失せた。
守秘義務のある課題に誘われず、内心では失望していたローレンツはベレトの奇行のおかげでクロードたちを問い詰めるという不躾な行為に及ばず済んでいる。そこを見越しあえて不躾な行為に及んで自ら泥を被っているのだとしたらローレンツは一生、ベレトに敵わない。
「マリアンヌさん、先生に皿を空にされてしまったしそろそろお開きにしようか」
「ええ、ローレンツさん、ありがとうございました。近頃気が塞いでいたのでよい気分転換になりました」
オメガである二人は常に抑制剤を服用し発情期が来ないように調整しているため、ごく軽い生理が来るだけだ。血の匂いだけならば香水などでアルファを誤魔化せる。
だが嗅覚が鋭い他の生物は誤魔化せない。犬なども訓練すれば判別に使えるだろう。ただフォドラの社会がその必要を感じないからやっていないだけだ。そしてある種の匂いに反応する昆虫は多い。汗であれば蚊、腐肉であれば蝿、そしてこのガルグ=マクに生息する甲虫はオメガの分泌するフェロモンに反応する。前者二つは微量であっても激しい反応を見せるが、玉虫色の甲虫は個体によって反応の激しさに違いがある。
かつてそこに気付いたセイロス教の修道士がいた。名を忘れられた修道士は特性ごとに甲虫を選り分けて繁殖し、観察した。フォドラには虫を愛でる文化はない。その修道士はクロードのように、どこか別の土地からやってきたものだったから気付いたのかもしれない。その修道士個人の資料も先の大火の際に宝杯の儀にまつわる資料と共に焼失してしまった。男性なのか女性なのか第二性はなんであったのか。今も昔もフォドラ中のオメガたちが女神の次に感謝の祈りを捧げる名無しの誰かは列聖されていない。畳む