「flow」第1部 最終話「クロード」
#flow #完売本 #現パロ
───
教会は伽藍堂である。真善美はその壁に刻まれているだけに過ぎない。
だがそれ故に聖なるものを、真善美を求める人々の全てを受け入れ、人々の悪しき部分を赦し、人々に良き行いを促すことができる。
教会は伽藍堂である。だが教会は伽藍堂でなければならない。
───
ベレトはこのままヒトが発展するところを眺めつつ、穏やかに長い生を閉じられると思っていた。科学の恩恵を受け、これだけ豊かに自由に暮らせるようになったのに何故ヒトは他人の行動を縛ろうとする動きを支持できるのだろうか。宗教警察は異端審問官という古い葡萄酒を入れた新しい皮袋にすぎない。
十七世紀にイングリットやユーリスに手伝ってもらったようなことも監視カメラがあると難しく、どうすべきか分からなかった。ソティスに叱られるのもまた良し、という気持ちでヒルダたちの安全が確保されたのを見届けたベレトはデアドラを去り、再びクパーラで眠ることにした。
以前と変わらず野生の飛竜もまだ健在で群をなして飛ぶ姿が見られるし、羽音を聞きながら眠ることができる。もしかしたら夢の中では自分も白きものになって空を飛んだり炎を吐きたり出来るかもしれない、と思って眠りについたがそれは叶わなかった。
今回、クパーラでベレトが見た夢にソティスや白きものは登場せず、ヒトとして過ごした最後の一年間、士官学校で教師をしていたあの一年間の夢しか見なかった。
フォドラ統一戦争の夢すら見なかった。
教師に戻るのが自分の運命なのかもしれない。そう考えたベレトは勝手知ったるフェルディア総合大学で高校教師の資格を取った。ガルグ=マクも庭のようなものだったが、石油化学産業で食べている土地なだけあって宗教警察から学生を守ってくれる、シルヴァン=ジョゼ=ゴーティエ記念奨学金で学費の支払いが出来る、という点でフェルディアに軍配があがった。二十世紀になってもまだ入学時にフェルディアブルーのローブを渡す伝統は続いている。
石油産業で豊かになったファーガスは十二世紀末の貧しい姿が嘘のようだった。レアはセイロス教の禁忌に石油の利用を入れていたが、古代にしても十二世紀末にしても当時は精製する技術がなかった。わざわざ禁忌にせずとも魔法を推奨するだけで充分だったろう。
フレスベルグ製作所の蒸気機関なくしてファーガスの発展は見込めなかった。結局、全ては絡み合っている。こんな風に技術が進歩していくことを直接知っているせいか、ベレトの授業は臨場感があって分かりやすいと評判が良かった。
社会科全ての資格があり、剣術と魔道も指導できる教師としてベレトはフォドラ中の高校で教えて回った。ガルグ=マクにこだわるつもりはなかったので場所は何処でも構わなかったが、オグマ山脈が見える土地にいる時にはベレト先生は気がつくと山を見ている、と生徒や同僚皆から言われた。
当時はまだ全てが紙の書類で管理されていたし、コンタクトレンズで瞳の色が変えられるようになったので各地で沢山名義を作り、別人を装って教師をするのは簡単だった。アンヴァルの教え子はフレスベルグ製作所に就職が決まったと言って喜び、ヌーヴェルの教え子は地元の大学へ進学した後ブリギットでフォドラ語を教える教師になった。ガラテアやゴーティエの高校はブレーダッドオイルから全生徒へ教科書の提供があり、フェルディアの教え子たちはやはり地元フェルディア総合大学へ進学したがった。エドマンドの教え子は地元の農学校で酪農を学び、デアドラの教え子は外航船の船員になった。
サウィン村にある分校の教師をしていた時の校長がガルグ=マクへ移動し、彼女から国立ガルグ=マク大学附属高校で教師をやらないか、と打診されたベレトは二つ返事で引き受けた。少し怖かったが例え士官学校ではないとしても何者かに呼ばれたのだろう。
国立ガルグ=マク大学附属高校は全寮制のためフォドラ中から優秀な学生が集まり、交換留学生も多数受け入れている。交換留学生はパルミラとブリギット出身の学生が多い。ベレトはレンズ研磨の修行をした際にパルミラ語を覚えたことを今の職場では明かしていなかった。
しかしうっかり同僚の前で生徒のパルミラ土産の説明文をすらすらと読んだことが災いし、新年度から地理と倫理と剣術クラブの顧問の他に留学生の受け入れ担当もするはめになってしまった。基本的にはフォドラ語でやりとりをするとはいえ、いざという時のためにパルミラ語のおさらいもしなくてはならない。
剣術クラブの指導後、誰も残っていない職員室でようやくベレトは来年度受け入れる予定の留学生たちに関する資料を開いた。とあるページで資料を捲る手が止まる。彼と再会するのは五世紀ぶりだった。二年早かったら金鹿の学級の名物コンビが再結成されていただろう。だが、ローレンツは二年前に卒業していた。彼はこのご時世には珍しい紋章持ちで、大学の紋章研究科から身体を調べられたりしてそれなりに面倒な高校生活を送っていたが、数世紀前に再会できた時のように守ってやれたと思う。
───親族同士で揉めている様子を多感な年頃の息子に見せたくない、という両親の意向でクロードは母親の故郷であるフォドラへ一年間留学することになった。特に興味もないのだが、母に言わせるとパルミラ訛りだという自分のフォドラ語が矯正できればそれで充分だと思っている。国立ガルグ=マク大学附属高校への留学生受け入れ試験に合格し、地元でお別れパーティをやったと思ったらもうフォドラの学校に到着していた、そんな状態だった。
どうやらクロードの到着は早過ぎたらしく構内は人影がまばらだ。事前に送られていた名札を胸元につけ大きなトランクを引っ張りながら歩いていく。乾燥したパルミラとは全く違う、春先の山の湿った空気を吸い込むと何故か肺の中まで冷えるような気がする。
クロードから見て広場の向こうに〝留学生はこちら〟という表示が見えた。その真下には黒髪に黒い瞳をしたスーツ姿の男性教師が立っている。学生の顔と名前でも確認しているのか書類を懸命に見ていたが、クロードに気がつくと近寄って手を差し出してきた。
『初めまして、クロード。留学生受け入れ担当のベレト=アイスナーです。君の学年に教える科目は倫理。フォドラでの一年間を有意義に楽しく過ごして下さい』
クロードは一瞬だけ何故名乗る前に名前を知られているのかと不思議に思ったが、胸元の名札に思い当たった。何度か瞬きをして、ベレトから差し出された手を握り返す。
『驚いた、ガルグ=マクにパルミラ語が話せる教師がいるなんて知らなかった!』
『少し話せるのがバレたせいで君ら留学生担当になった。ちなみに明日からはジャージしか着ないしフォドラ語しか話さないよ』
軽口を叩いてにこやかに笑うベレトを見ているとパルミラ出国前には母親から、フォドラ入国後にはガルグ=マクのパルミラ大使館から、きつく注意された宗教警察がらみのことが疑わしくなってくる。クロードはガルグ=マクでは誰がセイロス教宗教警察の協力者か分からないから言動に注意せよ、セイロス教の禁忌に触れるな、と言う助言を受けていた。
『じゃあベレト先生、俺も明日からフォドラ語しか話さないことにします。訛ってるけど』
ベレトは無言でクロードに向かって親指を立てた。ベレトの最初の教え子はベレトの最後の教え子でもあった。畳む
#flow #完売本 #現パロ
───
教会は伽藍堂である。真善美はその壁に刻まれているだけに過ぎない。
だがそれ故に聖なるものを、真善美を求める人々の全てを受け入れ、人々の悪しき部分を赦し、人々に良き行いを促すことができる。
教会は伽藍堂である。だが教会は伽藍堂でなければならない。
───
ベレトはこのままヒトが発展するところを眺めつつ、穏やかに長い生を閉じられると思っていた。科学の恩恵を受け、これだけ豊かに自由に暮らせるようになったのに何故ヒトは他人の行動を縛ろうとする動きを支持できるのだろうか。宗教警察は異端審問官という古い葡萄酒を入れた新しい皮袋にすぎない。
十七世紀にイングリットやユーリスに手伝ってもらったようなことも監視カメラがあると難しく、どうすべきか分からなかった。ソティスに叱られるのもまた良し、という気持ちでヒルダたちの安全が確保されたのを見届けたベレトはデアドラを去り、再びクパーラで眠ることにした。
以前と変わらず野生の飛竜もまだ健在で群をなして飛ぶ姿が見られるし、羽音を聞きながら眠ることができる。もしかしたら夢の中では自分も白きものになって空を飛んだり炎を吐きたり出来るかもしれない、と思って眠りについたがそれは叶わなかった。
今回、クパーラでベレトが見た夢にソティスや白きものは登場せず、ヒトとして過ごした最後の一年間、士官学校で教師をしていたあの一年間の夢しか見なかった。
フォドラ統一戦争の夢すら見なかった。
教師に戻るのが自分の運命なのかもしれない。そう考えたベレトは勝手知ったるフェルディア総合大学で高校教師の資格を取った。ガルグ=マクも庭のようなものだったが、石油化学産業で食べている土地なだけあって宗教警察から学生を守ってくれる、シルヴァン=ジョゼ=ゴーティエ記念奨学金で学費の支払いが出来る、という点でフェルディアに軍配があがった。二十世紀になってもまだ入学時にフェルディアブルーのローブを渡す伝統は続いている。
石油産業で豊かになったファーガスは十二世紀末の貧しい姿が嘘のようだった。レアはセイロス教の禁忌に石油の利用を入れていたが、古代にしても十二世紀末にしても当時は精製する技術がなかった。わざわざ禁忌にせずとも魔法を推奨するだけで充分だったろう。
フレスベルグ製作所の蒸気機関なくしてファーガスの発展は見込めなかった。結局、全ては絡み合っている。こんな風に技術が進歩していくことを直接知っているせいか、ベレトの授業は臨場感があって分かりやすいと評判が良かった。
社会科全ての資格があり、剣術と魔道も指導できる教師としてベレトはフォドラ中の高校で教えて回った。ガルグ=マクにこだわるつもりはなかったので場所は何処でも構わなかったが、オグマ山脈が見える土地にいる時にはベレト先生は気がつくと山を見ている、と生徒や同僚皆から言われた。
当時はまだ全てが紙の書類で管理されていたし、コンタクトレンズで瞳の色が変えられるようになったので各地で沢山名義を作り、別人を装って教師をするのは簡単だった。アンヴァルの教え子はフレスベルグ製作所に就職が決まったと言って喜び、ヌーヴェルの教え子は地元の大学へ進学した後ブリギットでフォドラ語を教える教師になった。ガラテアやゴーティエの高校はブレーダッドオイルから全生徒へ教科書の提供があり、フェルディアの教え子たちはやはり地元フェルディア総合大学へ進学したがった。エドマンドの教え子は地元の農学校で酪農を学び、デアドラの教え子は外航船の船員になった。
サウィン村にある分校の教師をしていた時の校長がガルグ=マクへ移動し、彼女から国立ガルグ=マク大学附属高校で教師をやらないか、と打診されたベレトは二つ返事で引き受けた。少し怖かったが例え士官学校ではないとしても何者かに呼ばれたのだろう。
国立ガルグ=マク大学附属高校は全寮制のためフォドラ中から優秀な学生が集まり、交換留学生も多数受け入れている。交換留学生はパルミラとブリギット出身の学生が多い。ベレトはレンズ研磨の修行をした際にパルミラ語を覚えたことを今の職場では明かしていなかった。
しかしうっかり同僚の前で生徒のパルミラ土産の説明文をすらすらと読んだことが災いし、新年度から地理と倫理と剣術クラブの顧問の他に留学生の受け入れ担当もするはめになってしまった。基本的にはフォドラ語でやりとりをするとはいえ、いざという時のためにパルミラ語のおさらいもしなくてはならない。
剣術クラブの指導後、誰も残っていない職員室でようやくベレトは来年度受け入れる予定の留学生たちに関する資料を開いた。とあるページで資料を捲る手が止まる。彼と再会するのは五世紀ぶりだった。二年早かったら金鹿の学級の名物コンビが再結成されていただろう。だが、ローレンツは二年前に卒業していた。彼はこのご時世には珍しい紋章持ちで、大学の紋章研究科から身体を調べられたりしてそれなりに面倒な高校生活を送っていたが、数世紀前に再会できた時のように守ってやれたと思う。
───親族同士で揉めている様子を多感な年頃の息子に見せたくない、という両親の意向でクロードは母親の故郷であるフォドラへ一年間留学することになった。特に興味もないのだが、母に言わせるとパルミラ訛りだという自分のフォドラ語が矯正できればそれで充分だと思っている。国立ガルグ=マク大学附属高校への留学生受け入れ試験に合格し、地元でお別れパーティをやったと思ったらもうフォドラの学校に到着していた、そんな状態だった。
どうやらクロードの到着は早過ぎたらしく構内は人影がまばらだ。事前に送られていた名札を胸元につけ大きなトランクを引っ張りながら歩いていく。乾燥したパルミラとは全く違う、春先の山の湿った空気を吸い込むと何故か肺の中まで冷えるような気がする。
クロードから見て広場の向こうに〝留学生はこちら〟という表示が見えた。その真下には黒髪に黒い瞳をしたスーツ姿の男性教師が立っている。学生の顔と名前でも確認しているのか書類を懸命に見ていたが、クロードに気がつくと近寄って手を差し出してきた。
『初めまして、クロード。留学生受け入れ担当のベレト=アイスナーです。君の学年に教える科目は倫理。フォドラでの一年間を有意義に楽しく過ごして下さい』
クロードは一瞬だけ何故名乗る前に名前を知られているのかと不思議に思ったが、胸元の名札に思い当たった。何度か瞬きをして、ベレトから差し出された手を握り返す。
『驚いた、ガルグ=マクにパルミラ語が話せる教師がいるなんて知らなかった!』
『少し話せるのがバレたせいで君ら留学生担当になった。ちなみに明日からはジャージしか着ないしフォドラ語しか話さないよ』
軽口を叩いてにこやかに笑うベレトを見ているとパルミラ出国前には母親から、フォドラ入国後にはガルグ=マクのパルミラ大使館から、きつく注意された宗教警察がらみのことが疑わしくなってくる。クロードはガルグ=マクでは誰がセイロス教宗教警察の協力者か分からないから言動に注意せよ、セイロス教の禁忌に触れるな、と言う助言を受けていた。
『じゃあベレト先生、俺も明日からフォドラ語しか話さないことにします。訛ってるけど』
ベレトは無言でクロードに向かって親指を立てた。ベレトの最初の教え子はベレトの最後の教え子でもあった。畳む
「flow」番外編"Bargain.2"
#完売本 #クロロレ #年齢操作 #flow #イグナーツ #リシテア
※イグナーツとリシテアが結婚しています
リシテアとイグナーツがデアドラからコーデリア領に戻る途中、グロスタールの屋敷で一泊するのは留守居をしているストームに会うためだった。だが傷心旅行を早めに切り上げたのか父親であるローレンツも戻っているという。ストームは嵐の日に生まれたローレンツの一人息子のあだ名で、彼の本名はエドガー=ローレンツ=グロスタールだ。
ストームの母は家同士の付き合いでグロスタール家に嫁いでいる。だがリシテアの婿としてコーデリア家に入った騎士上がりのイグナーツにも丁寧に接してくれる人だった。五歳年下のローレンツとはどこへ行くのも一緒な仲睦まじい夫婦でその頃の思い出話はたえることがない。彼女の死は皆に衝撃を与え、ローレンツは一年間祝事には一切参加しなかったし、その後もどこへ行くにも喪服しか着なかった。
それまでは伊達男と名高く、しょっちゅう服を仕立てていたというのに。長い間本当に酷い有りさまだったので気分を変えさせるため、彼の両親はローレンツに無理やり平服を着せた。
これまで縁のなかったパルミラへ一人で旅行へ行かせた、とローレンツの父エルヴィンから聞いた時にリシテアもイグナーツも良い機会だと思った。それなのに三ヶ月の予定を一ヶ月で切り上げて帰ってきている。執事からそう告げられたリシテアもイグナーツも不安しか感じなかった。旅行も続けられなかったのだろうか。
不安は募ったが、再会したローレンツは喪服ではなく旅先で気に入って買い求めた青い光沢のある生地で仕立てさせた上着を着ていた。しかも家中の人々を心配させた、本人に全く自覚がないのに涙を流す現象もどうやら治ったらしい。
見事な腕前で淹れてくれた紅茶はパルミラ風でいつもより少し味が濃かったが、向こうで買ってきたと言う変わった食感の茶菓子によく合っている。
「二人にも随分と心配をかけたね」
「いえ、気にしないでください。少なくとも私はこの珍しいお菓子で許してさしあげます」
「気に入ったので現物も料理本もたくさん買い込んでしまってね」
リシテアとの会話から察するにローレンツは物欲が戻ったらしい。日々の暮らしを楽しんでいた彼が生きている己を罰するかのように、内側にに篭る姿は見る者全ての涙を誘ったし、イグナーツも胸が締め付けられるように辛かった。人生は本当にままならない。
だが、もうすぐ一歳半になるよちよち歩きのストームを連れて、薔薇園を散歩する彼の姿は隣に亡くなった奥方がいないのが不思議なくらい元のローレンツそのものだった。
皆、ひとまずは安心した。そうなると次は詮索が身をもたげてくる。一体旅先のパルミラで何があったのか。久しぶりになんの憂いもなく、グロスタールの屋敷で過ごしたリシテアは幼い頃から何度も泊まっている馴染みの客室で夫のイグナーツに推理を披露していた。
「イグナーツ。私が思うにローレンツ兄様には新しく好い人が出来たのかもしれません」
「朗らかになってましたよね、確かに。ストームのためにも本当に良かった」
豊かな黒髪をブラシで梳かしていたリシテアが目元を押さえた。
「あら……いやだ、今度は私が泣いてしまうなんて。でも胸元に薔薇も付けていたし元のローレンツ兄様に戻ってくれたみたいで嬉しくて」
「紹介してもらえたら、僕たちからもその方にお礼を言いましょう」
イグナーツから濡れた手巾を渡されたリシテアは、それが絞って冷やしたものであることに気付いた。気を利かせてブリザーで冷やしてくれたのだろう。目が腫れないよう、目元にあててしまったのでイグナーツの顔は見えない。寝室で夜眠る前に話を聞いてくれる相手が失われてしまったら、と考えるだけで恐ろしい。楽しそうに相槌を打ってくれるイグナーツを失ってしまったら、リシテアだってどうなってしまうのかわからないのだ。
一方でカリードはフォドラに関する本を読み漁るため、図書館へ通い詰める日々を送っていた。カリードの住む港町はフォドラと近いこともあり、パルミラ語で書かれた本だけでなくフォドラ語の本もおいてある。どちらも読んだ。
カリードはフォドラの言葉は話せるが読み書きは得意ではない。口に出して音を聞かねば上手く意味が理解出来ず、フォドラ語の本を読むのにはかなり手間取った。その上、手当たり次第に読んだせいで調べ物としての効率も悪かった。しかしそのおかげでカリードのフォドラの文化への理解は深まっている。
彼は数週間かけついに知るべきだったこと、に自力で辿り着いた。カリードは彼をグロスタールのローレンツ=ヘルマンだと思っていたが違うらしい。ようやく何が書いてあるのか理解できるようになった貴族名鑑によると、彼はグロスタール伯爵家の一員だった。グロスタール家は十傑の遺産テュルソスの杖を受け継ぐ名門で、グロスタール領という土地の名前が彼の家名に因んで付けられている。彼は貴族の中の貴族だった。
カリードはフォドラの貴族というのはもっと冷酷で情がないものだと思っていた。だが実際に出会った彼は妻を亡くしたことが悲しくて悲しくて仕方ない人だったし、カリードが汚した服を洗ってくれて母譲りの緑色の瞳をきれいだと褒めてくれて───それ以上のこともあったし、別れ際の涙はもう不随意ではなかった、と思う。あんなに情の深い人をカリードは他に知らない。もう一度ローレンツに会いたい。ただ、彼から再会するにあたって条件を出されていた。それは別れ際の態度から察するに、ローレンツ自身の誓いでもあったのだ。
十六世紀のパルミラはダグザと海の覇権を争っており、海軍の主力はほぼダグザ方面へ割いていた。海軍の名においてフォドラの通商航路の妨害をする余裕はない。そこでパルミラ国王は民間船に対し、私掠免許を発行した。私掠免許を持つ船は敵国及び中立国の船を攻撃し、船や積荷を奪う許可を得たことになる。略奪や拿捕で得た利益は一割が国王個人、一割が船長、二割が出資者、残りの六割が乗組員達に分配された。乗組員達は受け取った六割を更に人数で割って分かち合う。その際に操舵手と船医は少しだけ取り分を多くしてもらえるのが常だった。
大型船は拿捕や略奪に備えて武装している。海賊行為は命がけだが一攫千金を狙うものたちからも投資家たちからも人気があった。私掠船は利益率の良い投資先で、それに絡んだ詐欺行為や私掠免許の強奪や偽造も横行している。
特に私掠免許の強奪や偽造は発覚すれば許可のない海賊行為を行った罪で海事裁判所に訴えられ、死刑になる。だがそれでもなお利益目当てに手を染める者が跡を絶たない。
命がけと言えば私掠船に入り込み、パルミラ国王が発行した私掠免許の真贋や正確な名義を確かめる密偵たちもそうだ。密偵は私掠船の数を正確に把握し統制したいパルミラの王府が雇うこともあれば、敵対国や中立国の政府や民間人が雇うこともある。旧レスター諸侯同盟の名家たちも海事に限らずパルミラに多数の密偵を放っていた。
少しでもフォドラと縁があり、大金を稼げる仕事がしたかったカリードは旧レスター諸侯同盟の名家ゴネリル家の密偵となった。彼を現地採用した密偵がグロスタール領出身だったこともかなり大きい。実際、上司の故郷の話を聞くだけで心が躍った。特に若様がまだ再婚なさらない、という話を聞けた晩は興奮して寝付けなかったほどだ。
カリードは様々な船に乗り込み、パルミラ人の外見と流暢なフォドラ語を利用しありとあらゆるものを煙に巻いて船長たちの秘密を暴いた。秘密を暴かれた私掠船の船長たちはそのまま海事裁判所に訴えられ、裁かれるものと脅迫されフォドラに協力させられるものに分かれる。
その判断を下すのが密偵頭の〝クロード〟だった。レスターからパルミラへ送り込まれた密偵たちはそれぞれ協力するように言われている。彼らの頭の名はそれがどこの誰であろうといつも〝クロード〟だ。〝クロード〟になれたら出自がなんであろうと、名家の人々からは一目置かれるようになる。船上で野蛮な行為のあった晩、カリードはいつもローレンツのことを思い出して正気を保った。
「本当に明日フォドラに帰っちゃうのか?」
「帰るよ。君のおかげで落ち込んでいる自分のことも許せたし、幼い息子には父親が必要だから」
フォドラへ連れて行って欲しいとせがむか格好をつけて自分もすぐに行くから待っていて欲しい、と言うべきか。迷ったカリードは眉尻を下げ、黙ってローレンツの顔を見つめた。頼まれごとが嬉しくて頑張ってしまったが、乗れる船なんか見つけてやらなければよかった気がする。でもローレンツから無能だと見做されるのはもっと嫌だった。
「僕のように心を病んだ男が何を言っても説得力はないかもしれないが、君は善良で頭が良いのだから優れた何か、になるべきだ」
カリードが黙って身体を強張らせているとローレンツが手を握ってきた。長くて白い指と褐色の指が組み合わさり白い顔が上から近づいてくる。
「それに君の未来が僕の性欲で定まるのはいやだな」
ローレンツは冗談めかしていたが、カリードは自分の耳元で囁かれたその言葉に雷に打たれたような衝撃を受けた。その時は分かっていなかったがグロスタール家の力があれば、あの時点の野良犬のようなカリードをフォドラへ連れて帰ってしまうのは簡単だった。だがローレンツは本当に誠実な人物で、それが搾取であると考えた。カリードには自力で優れた人間になる可能性があり、自力で自分と対等な人間になれると信じてくれた。
愛する人に信頼されたからには全力で応えるしかない。こうして優れた何か、になろうとしてもがき苦しむカリードの姿が女神の御心を動かしたのかもしれない。もしくさたった半月しか共に過ごさなかったのにカリードの可能性を信じて、突き放したローレンツの真面目さが女神の御心を動かしたのかもしれない。
正確なところは分からないがとにかく事態は動いた。近々デアドラ港の港長が代替わりする、という噂はカリードの耳にも入っている。それにまつわる人事異動の噂で持ちきりだ。港長が代替わりするなら今の〝クロード〟も引退する可能性がある。聞くところによると二人とも隠居してもおかしくない老人だ。次の〝クロード〟になったカリードがデアドラで暮らすようになれば、ローレンツは再び連絡を取ってくれるかもしれない。グロスタール領からローレンツが会いに来てくれるかもしれない。
そのためには今までと同じく、今回の航海でもしくじることは出来かった。甲板では船員たちが食糧不足を解消するために釣った鮫が大暴れしている。その様子をマストの上から眺めながらカリードは不敵に笑った。畳む
#完売本 #クロロレ #年齢操作 #flow #イグナーツ #リシテア
※イグナーツとリシテアが結婚しています
リシテアとイグナーツがデアドラからコーデリア領に戻る途中、グロスタールの屋敷で一泊するのは留守居をしているストームに会うためだった。だが傷心旅行を早めに切り上げたのか父親であるローレンツも戻っているという。ストームは嵐の日に生まれたローレンツの一人息子のあだ名で、彼の本名はエドガー=ローレンツ=グロスタールだ。
ストームの母は家同士の付き合いでグロスタール家に嫁いでいる。だがリシテアの婿としてコーデリア家に入った騎士上がりのイグナーツにも丁寧に接してくれる人だった。五歳年下のローレンツとはどこへ行くのも一緒な仲睦まじい夫婦でその頃の思い出話はたえることがない。彼女の死は皆に衝撃を与え、ローレンツは一年間祝事には一切参加しなかったし、その後もどこへ行くにも喪服しか着なかった。
それまでは伊達男と名高く、しょっちゅう服を仕立てていたというのに。長い間本当に酷い有りさまだったので気分を変えさせるため、彼の両親はローレンツに無理やり平服を着せた。
これまで縁のなかったパルミラへ一人で旅行へ行かせた、とローレンツの父エルヴィンから聞いた時にリシテアもイグナーツも良い機会だと思った。それなのに三ヶ月の予定を一ヶ月で切り上げて帰ってきている。執事からそう告げられたリシテアもイグナーツも不安しか感じなかった。旅行も続けられなかったのだろうか。
不安は募ったが、再会したローレンツは喪服ではなく旅先で気に入って買い求めた青い光沢のある生地で仕立てさせた上着を着ていた。しかも家中の人々を心配させた、本人に全く自覚がないのに涙を流す現象もどうやら治ったらしい。
見事な腕前で淹れてくれた紅茶はパルミラ風でいつもより少し味が濃かったが、向こうで買ってきたと言う変わった食感の茶菓子によく合っている。
「二人にも随分と心配をかけたね」
「いえ、気にしないでください。少なくとも私はこの珍しいお菓子で許してさしあげます」
「気に入ったので現物も料理本もたくさん買い込んでしまってね」
リシテアとの会話から察するにローレンツは物欲が戻ったらしい。日々の暮らしを楽しんでいた彼が生きている己を罰するかのように、内側にに篭る姿は見る者全ての涙を誘ったし、イグナーツも胸が締め付けられるように辛かった。人生は本当にままならない。
だが、もうすぐ一歳半になるよちよち歩きのストームを連れて、薔薇園を散歩する彼の姿は隣に亡くなった奥方がいないのが不思議なくらい元のローレンツそのものだった。
皆、ひとまずは安心した。そうなると次は詮索が身をもたげてくる。一体旅先のパルミラで何があったのか。久しぶりになんの憂いもなく、グロスタールの屋敷で過ごしたリシテアは幼い頃から何度も泊まっている馴染みの客室で夫のイグナーツに推理を披露していた。
「イグナーツ。私が思うにローレンツ兄様には新しく好い人が出来たのかもしれません」
「朗らかになってましたよね、確かに。ストームのためにも本当に良かった」
豊かな黒髪をブラシで梳かしていたリシテアが目元を押さえた。
「あら……いやだ、今度は私が泣いてしまうなんて。でも胸元に薔薇も付けていたし元のローレンツ兄様に戻ってくれたみたいで嬉しくて」
「紹介してもらえたら、僕たちからもその方にお礼を言いましょう」
イグナーツから濡れた手巾を渡されたリシテアは、それが絞って冷やしたものであることに気付いた。気を利かせてブリザーで冷やしてくれたのだろう。目が腫れないよう、目元にあててしまったのでイグナーツの顔は見えない。寝室で夜眠る前に話を聞いてくれる相手が失われてしまったら、と考えるだけで恐ろしい。楽しそうに相槌を打ってくれるイグナーツを失ってしまったら、リシテアだってどうなってしまうのかわからないのだ。
一方でカリードはフォドラに関する本を読み漁るため、図書館へ通い詰める日々を送っていた。カリードの住む港町はフォドラと近いこともあり、パルミラ語で書かれた本だけでなくフォドラ語の本もおいてある。どちらも読んだ。
カリードはフォドラの言葉は話せるが読み書きは得意ではない。口に出して音を聞かねば上手く意味が理解出来ず、フォドラ語の本を読むのにはかなり手間取った。その上、手当たり次第に読んだせいで調べ物としての効率も悪かった。しかしそのおかげでカリードのフォドラの文化への理解は深まっている。
彼は数週間かけついに知るべきだったこと、に自力で辿り着いた。カリードは彼をグロスタールのローレンツ=ヘルマンだと思っていたが違うらしい。ようやく何が書いてあるのか理解できるようになった貴族名鑑によると、彼はグロスタール伯爵家の一員だった。グロスタール家は十傑の遺産テュルソスの杖を受け継ぐ名門で、グロスタール領という土地の名前が彼の家名に因んで付けられている。彼は貴族の中の貴族だった。
カリードはフォドラの貴族というのはもっと冷酷で情がないものだと思っていた。だが実際に出会った彼は妻を亡くしたことが悲しくて悲しくて仕方ない人だったし、カリードが汚した服を洗ってくれて母譲りの緑色の瞳をきれいだと褒めてくれて───それ以上のこともあったし、別れ際の涙はもう不随意ではなかった、と思う。あんなに情の深い人をカリードは他に知らない。もう一度ローレンツに会いたい。ただ、彼から再会するにあたって条件を出されていた。それは別れ際の態度から察するに、ローレンツ自身の誓いでもあったのだ。
十六世紀のパルミラはダグザと海の覇権を争っており、海軍の主力はほぼダグザ方面へ割いていた。海軍の名においてフォドラの通商航路の妨害をする余裕はない。そこでパルミラ国王は民間船に対し、私掠免許を発行した。私掠免許を持つ船は敵国及び中立国の船を攻撃し、船や積荷を奪う許可を得たことになる。略奪や拿捕で得た利益は一割が国王個人、一割が船長、二割が出資者、残りの六割が乗組員達に分配された。乗組員達は受け取った六割を更に人数で割って分かち合う。その際に操舵手と船医は少しだけ取り分を多くしてもらえるのが常だった。
大型船は拿捕や略奪に備えて武装している。海賊行為は命がけだが一攫千金を狙うものたちからも投資家たちからも人気があった。私掠船は利益率の良い投資先で、それに絡んだ詐欺行為や私掠免許の強奪や偽造も横行している。
特に私掠免許の強奪や偽造は発覚すれば許可のない海賊行為を行った罪で海事裁判所に訴えられ、死刑になる。だがそれでもなお利益目当てに手を染める者が跡を絶たない。
命がけと言えば私掠船に入り込み、パルミラ国王が発行した私掠免許の真贋や正確な名義を確かめる密偵たちもそうだ。密偵は私掠船の数を正確に把握し統制したいパルミラの王府が雇うこともあれば、敵対国や中立国の政府や民間人が雇うこともある。旧レスター諸侯同盟の名家たちも海事に限らずパルミラに多数の密偵を放っていた。
少しでもフォドラと縁があり、大金を稼げる仕事がしたかったカリードは旧レスター諸侯同盟の名家ゴネリル家の密偵となった。彼を現地採用した密偵がグロスタール領出身だったこともかなり大きい。実際、上司の故郷の話を聞くだけで心が躍った。特に若様がまだ再婚なさらない、という話を聞けた晩は興奮して寝付けなかったほどだ。
カリードは様々な船に乗り込み、パルミラ人の外見と流暢なフォドラ語を利用しありとあらゆるものを煙に巻いて船長たちの秘密を暴いた。秘密を暴かれた私掠船の船長たちはそのまま海事裁判所に訴えられ、裁かれるものと脅迫されフォドラに協力させられるものに分かれる。
その判断を下すのが密偵頭の〝クロード〟だった。レスターからパルミラへ送り込まれた密偵たちはそれぞれ協力するように言われている。彼らの頭の名はそれがどこの誰であろうといつも〝クロード〟だ。〝クロード〟になれたら出自がなんであろうと、名家の人々からは一目置かれるようになる。船上で野蛮な行為のあった晩、カリードはいつもローレンツのことを思い出して正気を保った。
「本当に明日フォドラに帰っちゃうのか?」
「帰るよ。君のおかげで落ち込んでいる自分のことも許せたし、幼い息子には父親が必要だから」
フォドラへ連れて行って欲しいとせがむか格好をつけて自分もすぐに行くから待っていて欲しい、と言うべきか。迷ったカリードは眉尻を下げ、黙ってローレンツの顔を見つめた。頼まれごとが嬉しくて頑張ってしまったが、乗れる船なんか見つけてやらなければよかった気がする。でもローレンツから無能だと見做されるのはもっと嫌だった。
「僕のように心を病んだ男が何を言っても説得力はないかもしれないが、君は善良で頭が良いのだから優れた何か、になるべきだ」
カリードが黙って身体を強張らせているとローレンツが手を握ってきた。長くて白い指と褐色の指が組み合わさり白い顔が上から近づいてくる。
「それに君の未来が僕の性欲で定まるのはいやだな」
ローレンツは冗談めかしていたが、カリードは自分の耳元で囁かれたその言葉に雷に打たれたような衝撃を受けた。その時は分かっていなかったがグロスタール家の力があれば、あの時点の野良犬のようなカリードをフォドラへ連れて帰ってしまうのは簡単だった。だがローレンツは本当に誠実な人物で、それが搾取であると考えた。カリードには自力で優れた人間になる可能性があり、自力で自分と対等な人間になれると信じてくれた。
愛する人に信頼されたからには全力で応えるしかない。こうして優れた何か、になろうとしてもがき苦しむカリードの姿が女神の御心を動かしたのかもしれない。もしくさたった半月しか共に過ごさなかったのにカリードの可能性を信じて、突き放したローレンツの真面目さが女神の御心を動かしたのかもしれない。
正確なところは分からないがとにかく事態は動いた。近々デアドラ港の港長が代替わりする、という噂はカリードの耳にも入っている。それにまつわる人事異動の噂で持ちきりだ。港長が代替わりするなら今の〝クロード〟も引退する可能性がある。聞くところによると二人とも隠居してもおかしくない老人だ。次の〝クロード〟になったカリードがデアドラで暮らすようになれば、ローレンツは再び連絡を取ってくれるかもしれない。グロスタール領からローレンツが会いに来てくれるかもしれない。
そのためには今までと同じく、今回の航海でもしくじることは出来かった。甲板では船員たちが食糧不足を解消するために釣った鮫が大暴れしている。その様子をマストの上から眺めながらカリードは不敵に笑った。畳む
「flow」番外編"Bargain.3"
#完売本 #クロロレ #flow #年齢操作 #ヒルダ
ベレトは巡警の詰所で捕縛用の縄を一本ずつ手に取り強化魔法をかけていた。引きちぎるものは滅多にいないが念には念を入れている。檻の中に入っている大柄な沖仲仕(おきなかし)がベレトに声をかけてきた。
「センセイ、もう大人しくするからこれ外してくれよ」
昨晩、待機中に酒に酔って大暴れした男の手首足首には縄が巻かれている。指を鳴らせば勝手に結び目が解けてくれるような世の中ならば楽なのだが、そんなことはない。ベレトは腰から下げた鍵で扉を開け、中に入ると男の手首足首の結び目に触った。重ねがけした強化魔法を解除してから縄を解いてやる。
「手枷の方が楽なんじゃねえか?」
「牡蠣が美味い時期に手首足首を冷やすのは良くない。沖仲仕は身体が資本だ」
ベレトから若草色の瞳でじっと見つめられた沖仲仕は決まり悪そうに目を逸らした。筋骨隆々な身体つきも鮮やかな刺青も彼は恐れない。
「何があったのか話してくれ。言葉で伝えてもらわなくては何も分からない。このまま嫌なことがあるたびに酒を飲んで暴れるのか?」
彼は変わった巡警で沖仲仕たちに読み書きを教えたり、暴れん坊の手首足首が冷えないように気にかけたりする。酒が抜けて落ち着いたらベレトは改めて何故暴れたのか、について供述をとるつもりだった。同僚からは酒に酔って暴れた、で充分だと言われるが性分は変えられない。
「それで嫁がな……俺のいない時にもしかしたら……」
「確かめるのが怖くて飲んだのか。怖いよな、でも留置所に手首足首縛られた状態で一晩ぶち込まれて、仕事に穴を開けるのと奥さんと話し合うのはどちらがマシだと思う?」
筋骨隆々の男たちは怖いものなど何一つないような顔をしている。だが、単に自分が何を恐れているのか自覚していないだけだ。それに加えて怒りと恐れと悲しみの区別がついていないものが多い。ベレトは彼らにその区別をつけてほしいと考え、いつも可能な限り詳しく供述を取っていた。怒りと恐れと悲しみの区別に無自覚な状態を放置するとひどい、としか表現しようのないことが起きてしまう。それはかつて、ダスカーでも起きたことだ。
「ベレト、港長がお呼びだ。なんだ、また供述を取り直してるのか?」
昨日の彼はムカついたから酒を飲んで目についた弱虫を殴ってやった、としか言わなかった。どんなものにも語るべき何かがある。
「そうだ。また似たようなことがあった時は絶対に、酒に逃避させない」
「効き目があるのかねえ。まあ続きは引き受けた」
「また魔獣の目撃情報でもあったのか?」
「さてね。とにかく来い、とさ」
デアドラ港の全てを取り仕切る港長のヒルダは老いてなお、十傑の遺産であるフライクーゲルを振り回す。通商航路の安全を脅かす魔獣を一刀両断するが、得物を持っていなければ小柄な愛らしい老婦人だ。
ベレトが執務室の扉を叩くと中から入りなさい、と言う声がした。机の上には所狭しと書類が広げられており、珍しく書類から顔もあげない。この時期になると彼女は体が冷えるから、と言って暖炉の火を絶やさないようにしている。
だが火が消えていることに気づかないほど集中して書類を読んでいたらしい。ベレトは黙って火かき棒で暖炉の灰を探り、まだ使えそうな薪の欠片を見つけるとファイアーの呪文を唱えて火をつけた。
「何の用だろうか?」
「次の〝クロード〟を誰にしようかしら」
そういうと机に広げてある身上書を指さした。
「読んでいいのだろうか?」
「一緒に考えて貰いたくて呼んだのだから当然よ。次の港長は私のお気に入りの子がやるからいい"クロード"を選んであげたいの」
ヒルダが引退する、と言う噂はどうやら本当だったらしい。
「グロスタール家のローレンツ=ヘルマン=グロスタール。グロスタールの小紋章を受け継いでいるから、テュルソスの杖も使える。嫡子もいるから丁度いいわね」
不満げな顔をしてベレトが自分を見つめていることに気がついたヒルダは口を思いっきり曲げた。ベレトは何故か、十傑の遺産の使用者がすり減らされることを極端に嫌う。独身のうちに壊れてしまうと後継者が作れない。もう嫡子がいるなら遺産の使いすぎで本人が壊れても別に構わない、という意図を含んだ物言いが引っ掛かったのだろう。だがヒルダも同じような状態で任に就いた。
「他に知るべきことは?」
「身上書はローレンツの物もあるから読んでちょうだい。彼のために良い〝クロード〟を選ぶんだから彼のことも知らなくてはね」
ヒルダから渡されたローレンツの身上書を読んだベレトの顔がみるみるうちに曇っていった。転地療養を経て父親の補佐に復帰、と書いてある。彼の脳裏にフェルディアで読んだローレンツの資料の内容が浮かんだ。気を付けてやらねばテュルソスの杖に侵食されてしまう可能性がある。
「少し精神的に危ういようだが本当に良いのか」
「地上ならともかく海上で魔獣の相手をするのに遺産や紋章の力なしでは厳しいわ」
ヒルダがいうことはもっともだった。紋章も遺産も持たないものだけで対処しようとすると、魔獣を気絶させた時に攻撃の当たらない海底まで沈んでしまう。すると追撃が出来ない。確実に仕留めるためには陸に近い水深が浅いところで戦闘せねばならないが、敗北して上陸を許せば大惨事が起きる。名家に生まれ強い力を持ったものが責務を果たさねば、助かるはずの人々が大勢死ぬ。選択の余地はなかった。
「では決定なんだな」
「そうよ。ローレンツに多少の瑕疵はあっても変わらない。だからセンセイお願いよ。どうかローレンツを助けてやって」
「微力を尽くすよ。まずはこの人選が最初のお手伝いだな」
ベレトはヒルダに軽口を返すと今度は〝クロード〟候補たちの身上書を読み始めた。密偵たちは皆それぞれに優秀だった。その中に一人若さが際立つものがいる。
「せめて一度でも直接、会ったことがあればねえ。皆、任務や依頼があるから迂闊に呼び出すわけにも行かないのよ。書類だけで選ぶのは本当に難しいわ。皆実績が素晴らしいから決め手に欠ける」
「俺なら彼にする」
ベレトから差し出された身上書に目を通したヒルダは首を傾げた。パルミラ出身で二十歳に満たない。ヒルダが真っ先にない、と判断した候補者だった。
「理由は?」
「目が緑だから」
「意味が分からないわ」
確かに身体的特徴欄には焦茶の髪、緑の瞳、褐色の肌、中肉中背、と書いてある。だからなんだというのだろうか。ヒルダは目線で続きを促した。
「パルミラ人は瞳の色が黒いんだ。髪はいくらでも染められるし、海の仕事をすれば皆日焼けはするものだから、肌もまあ……港から街に出なければなんとなく互いに都合が良い誤解をして貰える。だが瞳の色だけは変えられない。どんなにパルミラを自分の故郷と思っていても瞳の色のせいで否定される。だから自分の中のフォドラの血に賭けたんだ」
密偵たちの中には他にもパルミラの血を引く者がいるが、皆フォドラ育ちだった。育った土地に対して芽生える自然な愛着心と利用できる己の見た目故にヒルダたちに雇われている。
ベレトの選んだ彼だけがどこに在ろうとも異物だった。
「彼だけがずっと背水の陣で戦っていた」
「なるほどね。参考になったわ。助言通りにするかどうかは分からないけれど」
「 ヒルダ、引き継ぎが終わったらフォドラ中に散らばった孫の顔を見て回るのはどうだろうか。きっとおもしろいぞ」
「そうね、それに孫にフライクーゲルの使い方を教えてやらなくちゃね」
ゴネリルの紋章を持つ孫が次のフライクーゲルの持ち主だ。自分はフライクーゲルとうまく距離を保つことが出来たが、孫はどうだろうか。ベレトが先ほどローレンツのことを心配していたが、同じようにヒルダの孫も細心の注意を払って慎重に導かなばならない。
ヒルダには考えるべきことがいくらでもあり、どんな案件だろうといつまでも囚われている訳にいかなかった。しばらく未定の振りをするがこの人事のせいで問題が生じたらベレトに解決させれば良い。そのために彼を呼んだのだから。
いつもと違って真の意味で、乗客としてデアドラ行きの客船に乗ったカリードは客室の小さな寝台に寝転がった。船員用の部屋と比べれば小さな窓までついているここは天国だと思う。窓から微かに入る月の光でデアドラ港湾公社から来た文書を読み返した。何度読んでもデアドラヘ出頭せよ、と書いてあるので顔が綻んでしまう。国境を越えてデアドラに呼ばれる程度には有能と見做されたのだ。
仮に〝クロード〟絡みでなかったとしても、デアドラ港での用事が終わって休みが取れたらグロスタール領に行ってみようと思っていた。一度行ってみれば今後、自分がどうすべきか考えも浮かぶだろう。
船の帆は風を受けて陸地沿いに目的地へ進み、カリードが瞼を開けた頃にはエドマンドを通過していた。このまま何もなければもうすぐデアドラに着く。
船内では水を無駄に出来ないので蒸留酒と香料を混ぜたものが身体の手入れによく使われる。甘い香りの混ぜ物を手に取って手や顔を拭いていると甲板から大砲用意!というかけ声が聞こえてきた。
フォドラ沿岸に出る魔獣は鎖国状態の頃は守り神として讃えられたらしい。だが今は単なる厄介者でどの地点で出没したのか報告する義務がある。どうやらカリードの乗る船は出現に備えて警戒すべき海域に入ったらしい。もし魔獣に遭遇してしまったら───こんな小さな船の場合、やれることはひとつだけだ。砲撃して怯んだ隙にさっさと逃げてしまうしかない。
どうか海が穏やかなまま航海が終わりますように、と船上にいる全ての人が女神やご先祖に祈りを捧げている。誰かの願いが天まで届いたのか、何事もないまま警戒海域を抜けることが出来た。
フォドラの行政区分は統一前の三国に準拠している。ファーガス、アドラステア、そしてレスターだ。デアドラは依然としてレスター地方で一番の大都会で人も物も集まる。遅れて始まった乗客たちの朝食は水より日持ちするビールに虫が沸かないよう何度も焼いて固くした麺麭を浸してふやかしたもの、壊血病予防で食べることが推奨されているキャベツの酢漬け、という質素極まりない物だ。しかしデアドラが近いとなればもう文句も出ない。皆の頭に浮かぶのは今、実際口にしている物ではなく、近いうちにデアドラで食べられるはずの豪華な料理だ。カリードもデアドラに着いたら宿で身支度を整え、この時期のデアドラ名物である牡蠣を食べるつもりでいる。
朝食を終え乗客のほとんどが下船の準備をしに客室へ戻っていた。だがカリードは大した荷物を持っていない。余らせた時間を潰すため甲板に出て、沿岸の風景を眺めていた。パルミラとは全く違う様式の、カリードからすれば見慣れない建物は母にとっては見慣れたものだったのだろうか。
船がデアドラ港の沖合に停泊すると艀(はしけ)がわらわらと寄ってきた。港に直接接岸できない大きさの船に乗った場合、または接岸する順番が待てない場合に乗客は艀に乗り換えて上陸する。カリードは荷物を背負って梯子を降りていたが途中で面倒臭くなり、手を離して艀に向かって飛び降りた。水飛沫が上着にかかったのが何故か面白くて笑ってしまう。危険行為だ、転覆したらどうしてくれる、と艀の漕ぎ手に怒られたので降りる時に多めに心付けを払った。
デアドラ港の船着き場には既に屋台があるのだが、そこには寄らず税関へ向かう。入国審査の順番を待つ行列が既にできていたが、並んでいるのはフォドラ人ばかりだった。外国人用の列は空いている。カリードがパルミラの王府が発行した旅券を見せると職員は無言で旅券に港湾公社からの命令書を挟んでから上陸許可印を押した。申し送りがあったのかもしれないが、それでも一瞥もしないのは保安上、問題があるのではないだろうか。
デアドラ港を出ればもうデアドラ市街だ。デアドラはフォドラで唯一無二の水の都で、港の前には巨大な広場がありその脇にはもう水路が広がっている。狭い歩道しか存在しないこの街では馬車ではなく、船が人と荷物を乗せて水路を行き交う。カリードは橋を渡って渡し船の乗り場へ向かった。
パルミラの港町ならば巨大な馬車の乗降場があるはずの場所に宿屋の客引きたちが大勢いる。彼らは皆、宿の名と場所、それに一泊いくらなのかを書いた看板を掲げていた。口々に今なら宿までのゴンドラ代を半分持つとか食事にワインを一杯つける等自分たちの宿がいかに優れているか口上を述べている。
その中にうちの宿には風呂がついている、というものがいた。公衆浴場へ行く場合は新しい外出着を持参して、汚れた服を持ち帰らねばならない。敷地内に風呂があるならば軽装で風呂場へ行って入浴し、そのまま部屋に戻って休める。
だが看板を見てみるとかなり遠い。手漕ぎの渡し船では一時間近くかかるだろう。命令書に書いてあった出頭時間に間に合わせるためには当日、ゴンドラを自分のためだけに一艘、呼ばねばならない。金はなくはないが贅沢すぎる気もする。カリードが黙って看板の内容と遠さを天秤にかけて考え込んでいると視線に気づいた客引きから声をかけられた。
「悩んでるみたいだな。泊まってくれたら服を洗ってやるよ。宿持ちでな。デアドラで服を仕立てるのに薄汚れた格好で行ったら仕立て屋に舐められるぜ?」
確かに下船する時にはしゃいだせいでカリードの上着は海水で濡れている。洗わねば匂うだろう。だが長旅で疲れている身で上着のような大物を洗うのは面倒くさい。
「今からそんな辺鄙なところに行って昼飯はどこで食えばいいんだ?」
「食堂もあるぜ。うちの島は牡蠣が取れるから今の時期はそればっかりだけどな」
「朝早くに出なきゃならないんだが」
「それなら仕入れの船の帰りに乗ればいいさ。帰りが空にならずに済んだって漕ぎ手も喜ぶぜ」
こうして説得されたカリードは一時間手漕ぎのゴンドラに揺られることにした。益体のない話でもしていればあっという間に過ぎるだろう。デアドラの中心部には港とセイロス教会と商工会がある。基本、宿屋の値段はこれらにどれだけ近いかで決まっていくのだが、カリードの選んだ宿屋は距離だけで見れば強気な値段設定をしていた。利便性ではなく設備と宿泊客への気配りで勝負に出ているらしい。
「静かでいい宿だぜ。騒々しいのが嫌いなお偉いさんの別荘も同じ島にあるから見えたら案内してやるよ」
「上屋敷を構えるには遠すぎないか?」
「貴族や豪商ってのはさ、デアドラで使う船も持ってる。滞在中は俺みたいな漕ぎ手を雇って、ずっと別荘で寝泊まりさせるから本人たちは早起きだけすればいいんだよ。すげえ身分だよな」
客引きとの会話に船の漕ぎ手も加わり、ああだこうだと話しているうちに客引きが瀟洒な屋敷を指差した。
「あのグロスタール屋敷の裏側がうちの宿の船着き場だよ。背中合わせになってるんだ」
カリードはその後のことをよく覚えていない。だが、滞在中ずっと客引きと漕ぎ手が異常に愛想良くしてきたので、無意識のうちに桁違いに高額な心付けを二人に払っていたらしい。畳む
#完売本 #クロロレ #flow #年齢操作 #ヒルダ
ベレトは巡警の詰所で捕縛用の縄を一本ずつ手に取り強化魔法をかけていた。引きちぎるものは滅多にいないが念には念を入れている。檻の中に入っている大柄な沖仲仕(おきなかし)がベレトに声をかけてきた。
「センセイ、もう大人しくするからこれ外してくれよ」
昨晩、待機中に酒に酔って大暴れした男の手首足首には縄が巻かれている。指を鳴らせば勝手に結び目が解けてくれるような世の中ならば楽なのだが、そんなことはない。ベレトは腰から下げた鍵で扉を開け、中に入ると男の手首足首の結び目に触った。重ねがけした強化魔法を解除してから縄を解いてやる。
「手枷の方が楽なんじゃねえか?」
「牡蠣が美味い時期に手首足首を冷やすのは良くない。沖仲仕は身体が資本だ」
ベレトから若草色の瞳でじっと見つめられた沖仲仕は決まり悪そうに目を逸らした。筋骨隆々な身体つきも鮮やかな刺青も彼は恐れない。
「何があったのか話してくれ。言葉で伝えてもらわなくては何も分からない。このまま嫌なことがあるたびに酒を飲んで暴れるのか?」
彼は変わった巡警で沖仲仕たちに読み書きを教えたり、暴れん坊の手首足首が冷えないように気にかけたりする。酒が抜けて落ち着いたらベレトは改めて何故暴れたのか、について供述をとるつもりだった。同僚からは酒に酔って暴れた、で充分だと言われるが性分は変えられない。
「それで嫁がな……俺のいない時にもしかしたら……」
「確かめるのが怖くて飲んだのか。怖いよな、でも留置所に手首足首縛られた状態で一晩ぶち込まれて、仕事に穴を開けるのと奥さんと話し合うのはどちらがマシだと思う?」
筋骨隆々の男たちは怖いものなど何一つないような顔をしている。だが、単に自分が何を恐れているのか自覚していないだけだ。それに加えて怒りと恐れと悲しみの区別がついていないものが多い。ベレトは彼らにその区別をつけてほしいと考え、いつも可能な限り詳しく供述を取っていた。怒りと恐れと悲しみの区別に無自覚な状態を放置するとひどい、としか表現しようのないことが起きてしまう。それはかつて、ダスカーでも起きたことだ。
「ベレト、港長がお呼びだ。なんだ、また供述を取り直してるのか?」
昨日の彼はムカついたから酒を飲んで目についた弱虫を殴ってやった、としか言わなかった。どんなものにも語るべき何かがある。
「そうだ。また似たようなことがあった時は絶対に、酒に逃避させない」
「効き目があるのかねえ。まあ続きは引き受けた」
「また魔獣の目撃情報でもあったのか?」
「さてね。とにかく来い、とさ」
デアドラ港の全てを取り仕切る港長のヒルダは老いてなお、十傑の遺産であるフライクーゲルを振り回す。通商航路の安全を脅かす魔獣を一刀両断するが、得物を持っていなければ小柄な愛らしい老婦人だ。
ベレトが執務室の扉を叩くと中から入りなさい、と言う声がした。机の上には所狭しと書類が広げられており、珍しく書類から顔もあげない。この時期になると彼女は体が冷えるから、と言って暖炉の火を絶やさないようにしている。
だが火が消えていることに気づかないほど集中して書類を読んでいたらしい。ベレトは黙って火かき棒で暖炉の灰を探り、まだ使えそうな薪の欠片を見つけるとファイアーの呪文を唱えて火をつけた。
「何の用だろうか?」
「次の〝クロード〟を誰にしようかしら」
そういうと机に広げてある身上書を指さした。
「読んでいいのだろうか?」
「一緒に考えて貰いたくて呼んだのだから当然よ。次の港長は私のお気に入りの子がやるからいい"クロード"を選んであげたいの」
ヒルダが引退する、と言う噂はどうやら本当だったらしい。
「グロスタール家のローレンツ=ヘルマン=グロスタール。グロスタールの小紋章を受け継いでいるから、テュルソスの杖も使える。嫡子もいるから丁度いいわね」
不満げな顔をしてベレトが自分を見つめていることに気がついたヒルダは口を思いっきり曲げた。ベレトは何故か、十傑の遺産の使用者がすり減らされることを極端に嫌う。独身のうちに壊れてしまうと後継者が作れない。もう嫡子がいるなら遺産の使いすぎで本人が壊れても別に構わない、という意図を含んだ物言いが引っ掛かったのだろう。だがヒルダも同じような状態で任に就いた。
「他に知るべきことは?」
「身上書はローレンツの物もあるから読んでちょうだい。彼のために良い〝クロード〟を選ぶんだから彼のことも知らなくてはね」
ヒルダから渡されたローレンツの身上書を読んだベレトの顔がみるみるうちに曇っていった。転地療養を経て父親の補佐に復帰、と書いてある。彼の脳裏にフェルディアで読んだローレンツの資料の内容が浮かんだ。気を付けてやらねばテュルソスの杖に侵食されてしまう可能性がある。
「少し精神的に危ういようだが本当に良いのか」
「地上ならともかく海上で魔獣の相手をするのに遺産や紋章の力なしでは厳しいわ」
ヒルダがいうことはもっともだった。紋章も遺産も持たないものだけで対処しようとすると、魔獣を気絶させた時に攻撃の当たらない海底まで沈んでしまう。すると追撃が出来ない。確実に仕留めるためには陸に近い水深が浅いところで戦闘せねばならないが、敗北して上陸を許せば大惨事が起きる。名家に生まれ強い力を持ったものが責務を果たさねば、助かるはずの人々が大勢死ぬ。選択の余地はなかった。
「では決定なんだな」
「そうよ。ローレンツに多少の瑕疵はあっても変わらない。だからセンセイお願いよ。どうかローレンツを助けてやって」
「微力を尽くすよ。まずはこの人選が最初のお手伝いだな」
ベレトはヒルダに軽口を返すと今度は〝クロード〟候補たちの身上書を読み始めた。密偵たちは皆それぞれに優秀だった。その中に一人若さが際立つものがいる。
「せめて一度でも直接、会ったことがあればねえ。皆、任務や依頼があるから迂闊に呼び出すわけにも行かないのよ。書類だけで選ぶのは本当に難しいわ。皆実績が素晴らしいから決め手に欠ける」
「俺なら彼にする」
ベレトから差し出された身上書に目を通したヒルダは首を傾げた。パルミラ出身で二十歳に満たない。ヒルダが真っ先にない、と判断した候補者だった。
「理由は?」
「目が緑だから」
「意味が分からないわ」
確かに身体的特徴欄には焦茶の髪、緑の瞳、褐色の肌、中肉中背、と書いてある。だからなんだというのだろうか。ヒルダは目線で続きを促した。
「パルミラ人は瞳の色が黒いんだ。髪はいくらでも染められるし、海の仕事をすれば皆日焼けはするものだから、肌もまあ……港から街に出なければなんとなく互いに都合が良い誤解をして貰える。だが瞳の色だけは変えられない。どんなにパルミラを自分の故郷と思っていても瞳の色のせいで否定される。だから自分の中のフォドラの血に賭けたんだ」
密偵たちの中には他にもパルミラの血を引く者がいるが、皆フォドラ育ちだった。育った土地に対して芽生える自然な愛着心と利用できる己の見た目故にヒルダたちに雇われている。
ベレトの選んだ彼だけがどこに在ろうとも異物だった。
「彼だけがずっと背水の陣で戦っていた」
「なるほどね。参考になったわ。助言通りにするかどうかは分からないけれど」
「 ヒルダ、引き継ぎが終わったらフォドラ中に散らばった孫の顔を見て回るのはどうだろうか。きっとおもしろいぞ」
「そうね、それに孫にフライクーゲルの使い方を教えてやらなくちゃね」
ゴネリルの紋章を持つ孫が次のフライクーゲルの持ち主だ。自分はフライクーゲルとうまく距離を保つことが出来たが、孫はどうだろうか。ベレトが先ほどローレンツのことを心配していたが、同じようにヒルダの孫も細心の注意を払って慎重に導かなばならない。
ヒルダには考えるべきことがいくらでもあり、どんな案件だろうといつまでも囚われている訳にいかなかった。しばらく未定の振りをするがこの人事のせいで問題が生じたらベレトに解決させれば良い。そのために彼を呼んだのだから。
いつもと違って真の意味で、乗客としてデアドラ行きの客船に乗ったカリードは客室の小さな寝台に寝転がった。船員用の部屋と比べれば小さな窓までついているここは天国だと思う。窓から微かに入る月の光でデアドラ港湾公社から来た文書を読み返した。何度読んでもデアドラヘ出頭せよ、と書いてあるので顔が綻んでしまう。国境を越えてデアドラに呼ばれる程度には有能と見做されたのだ。
仮に〝クロード〟絡みでなかったとしても、デアドラ港での用事が終わって休みが取れたらグロスタール領に行ってみようと思っていた。一度行ってみれば今後、自分がどうすべきか考えも浮かぶだろう。
船の帆は風を受けて陸地沿いに目的地へ進み、カリードが瞼を開けた頃にはエドマンドを通過していた。このまま何もなければもうすぐデアドラに着く。
船内では水を無駄に出来ないので蒸留酒と香料を混ぜたものが身体の手入れによく使われる。甘い香りの混ぜ物を手に取って手や顔を拭いていると甲板から大砲用意!というかけ声が聞こえてきた。
フォドラ沿岸に出る魔獣は鎖国状態の頃は守り神として讃えられたらしい。だが今は単なる厄介者でどの地点で出没したのか報告する義務がある。どうやらカリードの乗る船は出現に備えて警戒すべき海域に入ったらしい。もし魔獣に遭遇してしまったら───こんな小さな船の場合、やれることはひとつだけだ。砲撃して怯んだ隙にさっさと逃げてしまうしかない。
どうか海が穏やかなまま航海が終わりますように、と船上にいる全ての人が女神やご先祖に祈りを捧げている。誰かの願いが天まで届いたのか、何事もないまま警戒海域を抜けることが出来た。
フォドラの行政区分は統一前の三国に準拠している。ファーガス、アドラステア、そしてレスターだ。デアドラは依然としてレスター地方で一番の大都会で人も物も集まる。遅れて始まった乗客たちの朝食は水より日持ちするビールに虫が沸かないよう何度も焼いて固くした麺麭を浸してふやかしたもの、壊血病予防で食べることが推奨されているキャベツの酢漬け、という質素極まりない物だ。しかしデアドラが近いとなればもう文句も出ない。皆の頭に浮かぶのは今、実際口にしている物ではなく、近いうちにデアドラで食べられるはずの豪華な料理だ。カリードもデアドラに着いたら宿で身支度を整え、この時期のデアドラ名物である牡蠣を食べるつもりでいる。
朝食を終え乗客のほとんどが下船の準備をしに客室へ戻っていた。だがカリードは大した荷物を持っていない。余らせた時間を潰すため甲板に出て、沿岸の風景を眺めていた。パルミラとは全く違う様式の、カリードからすれば見慣れない建物は母にとっては見慣れたものだったのだろうか。
船がデアドラ港の沖合に停泊すると艀(はしけ)がわらわらと寄ってきた。港に直接接岸できない大きさの船に乗った場合、または接岸する順番が待てない場合に乗客は艀に乗り換えて上陸する。カリードは荷物を背負って梯子を降りていたが途中で面倒臭くなり、手を離して艀に向かって飛び降りた。水飛沫が上着にかかったのが何故か面白くて笑ってしまう。危険行為だ、転覆したらどうしてくれる、と艀の漕ぎ手に怒られたので降りる時に多めに心付けを払った。
デアドラ港の船着き場には既に屋台があるのだが、そこには寄らず税関へ向かう。入国審査の順番を待つ行列が既にできていたが、並んでいるのはフォドラ人ばかりだった。外国人用の列は空いている。カリードがパルミラの王府が発行した旅券を見せると職員は無言で旅券に港湾公社からの命令書を挟んでから上陸許可印を押した。申し送りがあったのかもしれないが、それでも一瞥もしないのは保安上、問題があるのではないだろうか。
デアドラ港を出ればもうデアドラ市街だ。デアドラはフォドラで唯一無二の水の都で、港の前には巨大な広場がありその脇にはもう水路が広がっている。狭い歩道しか存在しないこの街では馬車ではなく、船が人と荷物を乗せて水路を行き交う。カリードは橋を渡って渡し船の乗り場へ向かった。
パルミラの港町ならば巨大な馬車の乗降場があるはずの場所に宿屋の客引きたちが大勢いる。彼らは皆、宿の名と場所、それに一泊いくらなのかを書いた看板を掲げていた。口々に今なら宿までのゴンドラ代を半分持つとか食事にワインを一杯つける等自分たちの宿がいかに優れているか口上を述べている。
その中にうちの宿には風呂がついている、というものがいた。公衆浴場へ行く場合は新しい外出着を持参して、汚れた服を持ち帰らねばならない。敷地内に風呂があるならば軽装で風呂場へ行って入浴し、そのまま部屋に戻って休める。
だが看板を見てみるとかなり遠い。手漕ぎの渡し船では一時間近くかかるだろう。命令書に書いてあった出頭時間に間に合わせるためには当日、ゴンドラを自分のためだけに一艘、呼ばねばならない。金はなくはないが贅沢すぎる気もする。カリードが黙って看板の内容と遠さを天秤にかけて考え込んでいると視線に気づいた客引きから声をかけられた。
「悩んでるみたいだな。泊まってくれたら服を洗ってやるよ。宿持ちでな。デアドラで服を仕立てるのに薄汚れた格好で行ったら仕立て屋に舐められるぜ?」
確かに下船する時にはしゃいだせいでカリードの上着は海水で濡れている。洗わねば匂うだろう。だが長旅で疲れている身で上着のような大物を洗うのは面倒くさい。
「今からそんな辺鄙なところに行って昼飯はどこで食えばいいんだ?」
「食堂もあるぜ。うちの島は牡蠣が取れるから今の時期はそればっかりだけどな」
「朝早くに出なきゃならないんだが」
「それなら仕入れの船の帰りに乗ればいいさ。帰りが空にならずに済んだって漕ぎ手も喜ぶぜ」
こうして説得されたカリードは一時間手漕ぎのゴンドラに揺られることにした。益体のない話でもしていればあっという間に過ぎるだろう。デアドラの中心部には港とセイロス教会と商工会がある。基本、宿屋の値段はこれらにどれだけ近いかで決まっていくのだが、カリードの選んだ宿屋は距離だけで見れば強気な値段設定をしていた。利便性ではなく設備と宿泊客への気配りで勝負に出ているらしい。
「静かでいい宿だぜ。騒々しいのが嫌いなお偉いさんの別荘も同じ島にあるから見えたら案内してやるよ」
「上屋敷を構えるには遠すぎないか?」
「貴族や豪商ってのはさ、デアドラで使う船も持ってる。滞在中は俺みたいな漕ぎ手を雇って、ずっと別荘で寝泊まりさせるから本人たちは早起きだけすればいいんだよ。すげえ身分だよな」
客引きとの会話に船の漕ぎ手も加わり、ああだこうだと話しているうちに客引きが瀟洒な屋敷を指差した。
「あのグロスタール屋敷の裏側がうちの宿の船着き場だよ。背中合わせになってるんだ」
カリードはその後のことをよく覚えていない。だが、滞在中ずっと客引きと漕ぎ手が異常に愛想良くしてきたので、無意識のうちに桁違いに高額な心付けを二人に払っていたらしい。畳む
「flow」番外編"Bargain.5"
#完売本 #クロロレ #flow #年齢操作
翌日、デアドラのグロスタール屋敷の使用人たちの間で嵐が発生していた。発生源である若様は幸せそうに黙って頬を染めているだけで埒が開かない。嵐はあの、いつも完璧であろうとする若様が朝食の時間になっても降りてこない、という事態から始まった。
グロスタール家の使用人のうち半数はグロスタール領の本家、ガルグ=マクそれとデアドラの上屋敷の間を定期的に移動している。どの屋敷でも支障なく働けるようにするためだ。だからデアドラの上屋敷で働いている者のうち、半数は妻を亡くし完全に病んでいたローレンツの姿を覚えている。あの痛ましい姿はなかなか忘れられるものではない。
その時の記憶が新しい召使が、朝食の時間になっても食堂に現れない若様を心配してローレンツを起こしにいった。扉を数度叩いて入室しても、まだすうすうと寝息をたてて眠っている。寝坊はしているがあの時期の眠れず起き上がれず、と言った不健康さは影を潜めていた。幸せそうな寝顔であることにまずは安心したが、それでも起こさねばならない。
「おはようございます。ローレンツ様、朝食の支度が整いました」
直接の声かけには流石に反応し、ローレンツの白く薄い瞼が上がった。菫青石のような若様の瞳が現れる。数度の瞬きの後、使用人の姿を認めたローレンツは寝坊に対しての照れ隠しなのか眉尻を下げ少し微笑んだ。
「ああ、おはよう。そうか、僕は寝坊してしまったのだな。急な予定変更ですまないが今朝はここで朝食を取りたい」
かすれた声でローレンツがそう命じると使用人は直ちに用意させていただきます、と言って部屋から下がった。一人きりになった部屋で重い身体をなんとか動かす。寝巻きの上からバスローブを羽織るのも一苦労だった。きちんと前を合わせないと鎖骨周りの鬱血痕が見えてしまう。クロードが宿に戻ったのは夜が明ける前だった。ほんの数時間前まで数年ぶりの、人には言えない行為に二人で没頭していたせいでひどく腰が痛む。ヒルダの元へ出向くまでに少しでも体力を回復させねばならない。
厨房では朝食は自室で、との変更を聞いた料理人が寝台用の小さな皿を出しながら、直接ローレンツと話した使用人を尋問していた。暗い雰囲気ではなかったが頬が赤く声が少しかすれていたと言う。皿を手にした彼女はグロスタール家に仕える古株で、かつてはローレンツの離乳食も作っていた。
「確か今回もどこかの偉い方々とお会いになるんだろう?喉に良いものをお出ししなくては」
「せっかくのお美しいお声があれでは……」
「胃と喉に優しいものにしないとね。牛乳で煮た粥に蜂蜜で甘味をつけてお出ししようか。この時期は干した檸檬しかないのが残念だよ。檸檬の蜂蜜煮を作って差し上げたかった」
「では次善の策としてジンジャーティーをおつけしよう」
結論が出た二人は顔を見合わせると大麦と生姜を探しに食糧貯蔵庫へと走った。
寝室で体調に配慮された朝食を終えたローレンツは軋む腰を庇いながら身支度を整えた。立襟の襯衣を着て念のために喉に襟巻きを巻く。喉はまだ引き攣れたような感覚が残っていた。これからは少し控えめにせねばならない。
カリードはローレンツより十才近く若いので歯止めが効かないのは当たり前だ。しかし昨日は久しぶりだったから、という言い訳があったせいで自分の箍も外れてしまった。
ローレンツの憔悴ぶりを心配した両親は息子のために様々なことを試している。全ての屋敷からローレンツの亡き妻が使っていた鏡台や寝台を運び出し、屋敷の構造を独身男性が住むものに作り替えた。他にも後添えを探そうとしたり彼らに思いついたこと、出来ることは全てやった。それでも好転しなかったため、苦し紛れに提案したのがパルミラへの旅行だった。かなり遠回りしたが結果は成功で、もうローレンツの目から勝手に涙がこぼれることもない。
当時のローレンツにとって後添え探しは言語道断だったし、模様替えも無害だが無意味と感じていた。両親の心遣いを昨日、カリードと再会するまでは本当に余計なお世話だと思っていた。しかし両親が模様替えをしていなければ、ローレンツはカリードを屋敷に呼ばなかっただろう。使う寝室も使うベッドも妻が生きていた頃とは全く異なっている。
約束の時間ぎりぎりまで横になっていたらなんとか、革の長靴で歩ける程度には腰や股関節の痛みが和らいだ。一安心したローレンツだが船着き場にもうひとつ大きな山があふ。水上で揺れる船の縁に足を踏み出すのが怖い。転倒してしまうかもしれない。
見送りに来てくれた使用人に手を貸してもらい、なんとか乗り込んだ。しかし踏みしめた一歩目で痛めている所に衝撃が走り、呻き声が出てしまう。なんとかやり過ごし席に着いたが、気が利く使用人は心配そうにローレンツを見つめている。
お気をつけて、と手を振って見送る使用人に応えてローレンツは小さく手を振った。漕ぎ手たちはそんな二人のやりとりに気をかけない。ようやく仕事だ、とばかりに力強く櫂を動かしはじめたので、見る見るうちにグロスタール屋敷は小さくなっていった。
パルミラで共に過ごした時と比べて、ローレンツの身体の負担が大きいのはカリードの背が伸びたからだ。その事に気づき、かっと熱くなった頬に潮風が心地よい。あの頃はつむじの位置も分かるほど彼は小さかった。そんな子供に依存するわけにいかない、と分かっていても離れるのが惜しくて半月も一緒に過ごしてしまった。
思いもよらぬ土地で再会出来たが、立派な青年になった彼と自分は今後どんな関係を築いていけば良いのだろう。本来ならヒルダからなぜデアドラに呼び出されたのかについて考えねばならない。だがローレンツの脳裏には全く関係ない私生活のことばかりが浮かんでいる。
その頃、グロスタール屋敷ではローレンツを見送った使用人が慌てて倉庫の中を漁っていた。旦那様が使う杖が一本くらい残されているか、と思ったが見つからない。同僚たちは湯沸かし釜の修理がらみで色々と忙しくしているので、昼食の際に皆に聞くしかなさそうだった。
昼食の時間は屋敷の使用人たちにとって、休憩時間であると同時に報告と打ち合わせの時間でもある。使用人たちは一切に今日の若様は様子がおかしい、という話を口々にし始めた。昨日まではおかしな所など何もなかった。お体の具合も良さそうだったし一体、何があったのだろう。
使用人たちがそれぞれ自分が何をみたのか語り合う中、洗濯係が遅れてやってきた。彼女が顔を真っ赤にして自分がどんな状態の敷布を洗ったのか、を告げるとデアドラのグロスタール屋敷に吹き荒れる嵐はその勢力を増した。昨晩の人払いはそういうことだったらしい。
夕食後に訪れた客の姿を見た唯一の使用人は周囲から詰問された。男だった、と告げると皆は息を呑んだ。肌が褐色で前髪を編んでいたのでパルミラ人のように見えたが、言葉が流暢で瞳が緑だったから本当にどこの者か全くわからないのだという。港町は日焼けしたものが多いし、パルミラ暮らしが長いだけかもしれない。小間使いたちは新たな恋の予感にはしゃぐものと若様が再び誰かの物になってしまう寂しさに気が塞ぐものの真っ二つに分かれた。
デアドラ港に到着しローレンツは漕ぎ手の手を借りながら下船した。港湾公社へと向かうにはいくつか橋を渡らねばならない。決死の覚悟で橋の階段を上った。橋の上からは港湾公社の建物全体を見ることができる。レスター地方はとにかく奢侈で軽薄と言われがちだが、ヒルダの執務室は最上階にあった。上に立つものは頑健であるべしという理想が間取りで体現されている。手摺りのありがたみを実感しているローレンツが今、そこまで上るのはかなり時間がかかるだろう。
約束の刻限を守るために己の身体を奮い立たせて階段の手摺りを掴んだローレンツはどうにか橋を降り始めた。元より道ゆく人とぶつかったりしないよう、視線を前の方にやりながら歩いていたからかもしれない。港湾公社から出てくるカリードの姿がローレンツの目に入った。彼もすぐにローレンツに気づいたらしく駆け寄ってくる。
「奇遇だな」
「昨日と比べれば必然にしか思わないけどな!」
確かに信じられないことに彼とローレンツは同じ街にいる。直立しているのが辛くて、階段の踊り場で手すりに腰を預けているローレンツには難なく階段を駆け上がってきたカリードの若さが眩しい。
「君の用事は終わったのか?」
「まあね。数年間の頑張りが報われたよ。あれ?具合悪いのか?」
褐色の手がローレンツの額に伸びてくる。美しく整えられた紫の髪の毛をかき分け温かい手が額に触れた。下の段にいるせいかカリードは爪先立ちになっていてローレンツからだとつむじが見える。まるで初めて会った頃のような身長差になった。
「風邪ではない。もし風邪を引いていたら翌日仕事だという君とその……ああいったことはしなかった。うつしてしまうだろう?そうではなくて腰が痛いのだ」
頬を染めてローレンツは白状した。思い当たる節しかないカリードは顔も真っ赤にして両手で顔を覆って何かを呟いている。
「………る」
「聞こえないぞ」
「責任取る。部屋まで送っていくから」
「部屋?何を言っている?」
「まだ守秘義務があるから言えないんだよ!」
カリードはローレンツの左側に寄り添って左脇に右腕を差し込み、左手で彼の左手を手に取った。共に前を向き階段を一歩ずつ下りていく。楽に移動が出来るようになったが段差に気を付けろ、だのなんだのといちいちカリードからの掛け声が入るのが少し恥ずかしい。だがこうなると予想できたのに我慢できなかった昨晩の自分がもっと恥ずかしい。結局カリードの言葉に甘えた状態で、ローレンツはヒルダの執務室がある最上階まで階段を上りきった。
「降りる時も手伝うからここで待ってる」
「時間がかかるかもしれないぞ」
執務室の扉のすぐ前に謎の男が立っているのは邪魔にならないのだろうか。ローレンツは執務室の扉を叩いた。内側から扉を開けてくれたのはレオニーではなくローレンツよりも背が高い男の秘書だった。今日ヒルダの執務室を訪れる男共はがっかりするだろう。
「久しぶりね、さあ座って」
本当に幸いなことに椅子を勧められ、業務とは一切関わりのなさそうな筋肉を蓄えた黒髪の秘書が淹れてくれた紅茶にありがたく口をつける。茶器から漂う薔薇の香りが昂っていた神経を落ち着かせてくれた
「調子はどうなの?」
ローレンツの紅茶の好みも調子を崩していた頃の様子も知るヒルダの飾り気がない言葉には重みがあった。ローレンツは周りを心配させた、という事実と付き合う日々をまだ過ごさねばならない。
「調子は良いつもりです」
「そう、それならその状態を保ってちょうだい。私は近々ゴネリル領に帰るから色々と根回しが必要なのよ」
何故ヒルダが自分に教えてくれるのかは分からないが、長くデアドラ港の港長を務めたヒルダの後任は大変だろう、と他人事ながらローレンツは同情した。
「次はあなただから。だってあなたテュルソスの杖が使えるでしょう?」
ローレンツの茶器が派手に音を立てた。動揺したせいで、立ち振る舞いに影響が出るなどあってはならないことなのに。
「僕ですか?!しかし僕はその……よろしいのでしょうか?」
ひどく調子を崩していた頃の自分を知るヒルダが、後継者として自分を選ぶと考えていなかったローレンツは口籠った。
「もう貴方のための〝クロード〟も用意したわ。それにエドマンド伯やコーデリア伯に改めてお伝えする場で、私が最も信頼する部下を紹介する」
「なんだか……ありがたくはあるのですが外堀を埋められたような……」
名誉ある職に就くことになった、と扉の前で待つカリードやグロスタール領で待っている家族たちに伝えたらきっと喜んでくれるだろう。そう考えるだけでローレンツの顔は綻んだ。
「良い知らせは先に伝えたわ。悪い知らせは後ほどエドマンド伯やコーデリア伯と一緒に聞いてちょうだい。それとこの話はまだお父上以外にはしないで。良いわね?」
頃合いを見計らって茶器を下げにきた秘書がヒルダに耳打ちをした。
「あらバルタザール、もうそんな時間なの?予定が詰まっているのでとりあえずこの話はこれでおしまい。しばらくデアドラで楽しんでからグロスタール領に戻ると良いわ。ご両親とストームへのお土産を忘れず買いなさい」
ローレンツが退出しようとすると何も言わずに大柄なバルタザールが、椅子から立ち上がるのに手を貸してくれた。嫌な予感がする。
「この部屋の窓からは橋の上がよく見えるのよ。〝クロード〟とは節度をもって仲良くなさい。お大事にね」畳む
#完売本 #クロロレ #flow #年齢操作
翌日、デアドラのグロスタール屋敷の使用人たちの間で嵐が発生していた。発生源である若様は幸せそうに黙って頬を染めているだけで埒が開かない。嵐はあの、いつも完璧であろうとする若様が朝食の時間になっても降りてこない、という事態から始まった。
グロスタール家の使用人のうち半数はグロスタール領の本家、ガルグ=マクそれとデアドラの上屋敷の間を定期的に移動している。どの屋敷でも支障なく働けるようにするためだ。だからデアドラの上屋敷で働いている者のうち、半数は妻を亡くし完全に病んでいたローレンツの姿を覚えている。あの痛ましい姿はなかなか忘れられるものではない。
その時の記憶が新しい召使が、朝食の時間になっても食堂に現れない若様を心配してローレンツを起こしにいった。扉を数度叩いて入室しても、まだすうすうと寝息をたてて眠っている。寝坊はしているがあの時期の眠れず起き上がれず、と言った不健康さは影を潜めていた。幸せそうな寝顔であることにまずは安心したが、それでも起こさねばならない。
「おはようございます。ローレンツ様、朝食の支度が整いました」
直接の声かけには流石に反応し、ローレンツの白く薄い瞼が上がった。菫青石のような若様の瞳が現れる。数度の瞬きの後、使用人の姿を認めたローレンツは寝坊に対しての照れ隠しなのか眉尻を下げ少し微笑んだ。
「ああ、おはよう。そうか、僕は寝坊してしまったのだな。急な予定変更ですまないが今朝はここで朝食を取りたい」
かすれた声でローレンツがそう命じると使用人は直ちに用意させていただきます、と言って部屋から下がった。一人きりになった部屋で重い身体をなんとか動かす。寝巻きの上からバスローブを羽織るのも一苦労だった。きちんと前を合わせないと鎖骨周りの鬱血痕が見えてしまう。クロードが宿に戻ったのは夜が明ける前だった。ほんの数時間前まで数年ぶりの、人には言えない行為に二人で没頭していたせいでひどく腰が痛む。ヒルダの元へ出向くまでに少しでも体力を回復させねばならない。
厨房では朝食は自室で、との変更を聞いた料理人が寝台用の小さな皿を出しながら、直接ローレンツと話した使用人を尋問していた。暗い雰囲気ではなかったが頬が赤く声が少しかすれていたと言う。皿を手にした彼女はグロスタール家に仕える古株で、かつてはローレンツの離乳食も作っていた。
「確か今回もどこかの偉い方々とお会いになるんだろう?喉に良いものをお出ししなくては」
「せっかくのお美しいお声があれでは……」
「胃と喉に優しいものにしないとね。牛乳で煮た粥に蜂蜜で甘味をつけてお出ししようか。この時期は干した檸檬しかないのが残念だよ。檸檬の蜂蜜煮を作って差し上げたかった」
「では次善の策としてジンジャーティーをおつけしよう」
結論が出た二人は顔を見合わせると大麦と生姜を探しに食糧貯蔵庫へと走った。
寝室で体調に配慮された朝食を終えたローレンツは軋む腰を庇いながら身支度を整えた。立襟の襯衣を着て念のために喉に襟巻きを巻く。喉はまだ引き攣れたような感覚が残っていた。これからは少し控えめにせねばならない。
カリードはローレンツより十才近く若いので歯止めが効かないのは当たり前だ。しかし昨日は久しぶりだったから、という言い訳があったせいで自分の箍も外れてしまった。
ローレンツの憔悴ぶりを心配した両親は息子のために様々なことを試している。全ての屋敷からローレンツの亡き妻が使っていた鏡台や寝台を運び出し、屋敷の構造を独身男性が住むものに作り替えた。他にも後添えを探そうとしたり彼らに思いついたこと、出来ることは全てやった。それでも好転しなかったため、苦し紛れに提案したのがパルミラへの旅行だった。かなり遠回りしたが結果は成功で、もうローレンツの目から勝手に涙がこぼれることもない。
当時のローレンツにとって後添え探しは言語道断だったし、模様替えも無害だが無意味と感じていた。両親の心遣いを昨日、カリードと再会するまでは本当に余計なお世話だと思っていた。しかし両親が模様替えをしていなければ、ローレンツはカリードを屋敷に呼ばなかっただろう。使う寝室も使うベッドも妻が生きていた頃とは全く異なっている。
約束の時間ぎりぎりまで横になっていたらなんとか、革の長靴で歩ける程度には腰や股関節の痛みが和らいだ。一安心したローレンツだが船着き場にもうひとつ大きな山があふ。水上で揺れる船の縁に足を踏み出すのが怖い。転倒してしまうかもしれない。
見送りに来てくれた使用人に手を貸してもらい、なんとか乗り込んだ。しかし踏みしめた一歩目で痛めている所に衝撃が走り、呻き声が出てしまう。なんとかやり過ごし席に着いたが、気が利く使用人は心配そうにローレンツを見つめている。
お気をつけて、と手を振って見送る使用人に応えてローレンツは小さく手を振った。漕ぎ手たちはそんな二人のやりとりに気をかけない。ようやく仕事だ、とばかりに力強く櫂を動かしはじめたので、見る見るうちにグロスタール屋敷は小さくなっていった。
パルミラで共に過ごした時と比べて、ローレンツの身体の負担が大きいのはカリードの背が伸びたからだ。その事に気づき、かっと熱くなった頬に潮風が心地よい。あの頃はつむじの位置も分かるほど彼は小さかった。そんな子供に依存するわけにいかない、と分かっていても離れるのが惜しくて半月も一緒に過ごしてしまった。
思いもよらぬ土地で再会出来たが、立派な青年になった彼と自分は今後どんな関係を築いていけば良いのだろう。本来ならヒルダからなぜデアドラに呼び出されたのかについて考えねばならない。だがローレンツの脳裏には全く関係ない私生活のことばかりが浮かんでいる。
その頃、グロスタール屋敷ではローレンツを見送った使用人が慌てて倉庫の中を漁っていた。旦那様が使う杖が一本くらい残されているか、と思ったが見つからない。同僚たちは湯沸かし釜の修理がらみで色々と忙しくしているので、昼食の際に皆に聞くしかなさそうだった。
昼食の時間は屋敷の使用人たちにとって、休憩時間であると同時に報告と打ち合わせの時間でもある。使用人たちは一切に今日の若様は様子がおかしい、という話を口々にし始めた。昨日まではおかしな所など何もなかった。お体の具合も良さそうだったし一体、何があったのだろう。
使用人たちがそれぞれ自分が何をみたのか語り合う中、洗濯係が遅れてやってきた。彼女が顔を真っ赤にして自分がどんな状態の敷布を洗ったのか、を告げるとデアドラのグロスタール屋敷に吹き荒れる嵐はその勢力を増した。昨晩の人払いはそういうことだったらしい。
夕食後に訪れた客の姿を見た唯一の使用人は周囲から詰問された。男だった、と告げると皆は息を呑んだ。肌が褐色で前髪を編んでいたのでパルミラ人のように見えたが、言葉が流暢で瞳が緑だったから本当にどこの者か全くわからないのだという。港町は日焼けしたものが多いし、パルミラ暮らしが長いだけかもしれない。小間使いたちは新たな恋の予感にはしゃぐものと若様が再び誰かの物になってしまう寂しさに気が塞ぐものの真っ二つに分かれた。
デアドラ港に到着しローレンツは漕ぎ手の手を借りながら下船した。港湾公社へと向かうにはいくつか橋を渡らねばならない。決死の覚悟で橋の階段を上った。橋の上からは港湾公社の建物全体を見ることができる。レスター地方はとにかく奢侈で軽薄と言われがちだが、ヒルダの執務室は最上階にあった。上に立つものは頑健であるべしという理想が間取りで体現されている。手摺りのありがたみを実感しているローレンツが今、そこまで上るのはかなり時間がかかるだろう。
約束の刻限を守るために己の身体を奮い立たせて階段の手摺りを掴んだローレンツはどうにか橋を降り始めた。元より道ゆく人とぶつかったりしないよう、視線を前の方にやりながら歩いていたからかもしれない。港湾公社から出てくるカリードの姿がローレンツの目に入った。彼もすぐにローレンツに気づいたらしく駆け寄ってくる。
「奇遇だな」
「昨日と比べれば必然にしか思わないけどな!」
確かに信じられないことに彼とローレンツは同じ街にいる。直立しているのが辛くて、階段の踊り場で手すりに腰を預けているローレンツには難なく階段を駆け上がってきたカリードの若さが眩しい。
「君の用事は終わったのか?」
「まあね。数年間の頑張りが報われたよ。あれ?具合悪いのか?」
褐色の手がローレンツの額に伸びてくる。美しく整えられた紫の髪の毛をかき分け温かい手が額に触れた。下の段にいるせいかカリードは爪先立ちになっていてローレンツからだとつむじが見える。まるで初めて会った頃のような身長差になった。
「風邪ではない。もし風邪を引いていたら翌日仕事だという君とその……ああいったことはしなかった。うつしてしまうだろう?そうではなくて腰が痛いのだ」
頬を染めてローレンツは白状した。思い当たる節しかないカリードは顔も真っ赤にして両手で顔を覆って何かを呟いている。
「………る」
「聞こえないぞ」
「責任取る。部屋まで送っていくから」
「部屋?何を言っている?」
「まだ守秘義務があるから言えないんだよ!」
カリードはローレンツの左側に寄り添って左脇に右腕を差し込み、左手で彼の左手を手に取った。共に前を向き階段を一歩ずつ下りていく。楽に移動が出来るようになったが段差に気を付けろ、だのなんだのといちいちカリードからの掛け声が入るのが少し恥ずかしい。だがこうなると予想できたのに我慢できなかった昨晩の自分がもっと恥ずかしい。結局カリードの言葉に甘えた状態で、ローレンツはヒルダの執務室がある最上階まで階段を上りきった。
「降りる時も手伝うからここで待ってる」
「時間がかかるかもしれないぞ」
執務室の扉のすぐ前に謎の男が立っているのは邪魔にならないのだろうか。ローレンツは執務室の扉を叩いた。内側から扉を開けてくれたのはレオニーではなくローレンツよりも背が高い男の秘書だった。今日ヒルダの執務室を訪れる男共はがっかりするだろう。
「久しぶりね、さあ座って」
本当に幸いなことに椅子を勧められ、業務とは一切関わりのなさそうな筋肉を蓄えた黒髪の秘書が淹れてくれた紅茶にありがたく口をつける。茶器から漂う薔薇の香りが昂っていた神経を落ち着かせてくれた
「調子はどうなの?」
ローレンツの紅茶の好みも調子を崩していた頃の様子も知るヒルダの飾り気がない言葉には重みがあった。ローレンツは周りを心配させた、という事実と付き合う日々をまだ過ごさねばならない。
「調子は良いつもりです」
「そう、それならその状態を保ってちょうだい。私は近々ゴネリル領に帰るから色々と根回しが必要なのよ」
何故ヒルダが自分に教えてくれるのかは分からないが、長くデアドラ港の港長を務めたヒルダの後任は大変だろう、と他人事ながらローレンツは同情した。
「次はあなただから。だってあなたテュルソスの杖が使えるでしょう?」
ローレンツの茶器が派手に音を立てた。動揺したせいで、立ち振る舞いに影響が出るなどあってはならないことなのに。
「僕ですか?!しかし僕はその……よろしいのでしょうか?」
ひどく調子を崩していた頃の自分を知るヒルダが、後継者として自分を選ぶと考えていなかったローレンツは口籠った。
「もう貴方のための〝クロード〟も用意したわ。それにエドマンド伯やコーデリア伯に改めてお伝えする場で、私が最も信頼する部下を紹介する」
「なんだか……ありがたくはあるのですが外堀を埋められたような……」
名誉ある職に就くことになった、と扉の前で待つカリードやグロスタール領で待っている家族たちに伝えたらきっと喜んでくれるだろう。そう考えるだけでローレンツの顔は綻んだ。
「良い知らせは先に伝えたわ。悪い知らせは後ほどエドマンド伯やコーデリア伯と一緒に聞いてちょうだい。それとこの話はまだお父上以外にはしないで。良いわね?」
頃合いを見計らって茶器を下げにきた秘書がヒルダに耳打ちをした。
「あらバルタザール、もうそんな時間なの?予定が詰まっているのでとりあえずこの話はこれでおしまい。しばらくデアドラで楽しんでからグロスタール領に戻ると良いわ。ご両親とストームへのお土産を忘れず買いなさい」
ローレンツが退出しようとすると何も言わずに大柄なバルタザールが、椅子から立ち上がるのに手を貸してくれた。嫌な予感がする。
「この部屋の窓からは橋の上がよく見えるのよ。〝クロード〟とは節度をもって仲良くなさい。お大事にね」畳む
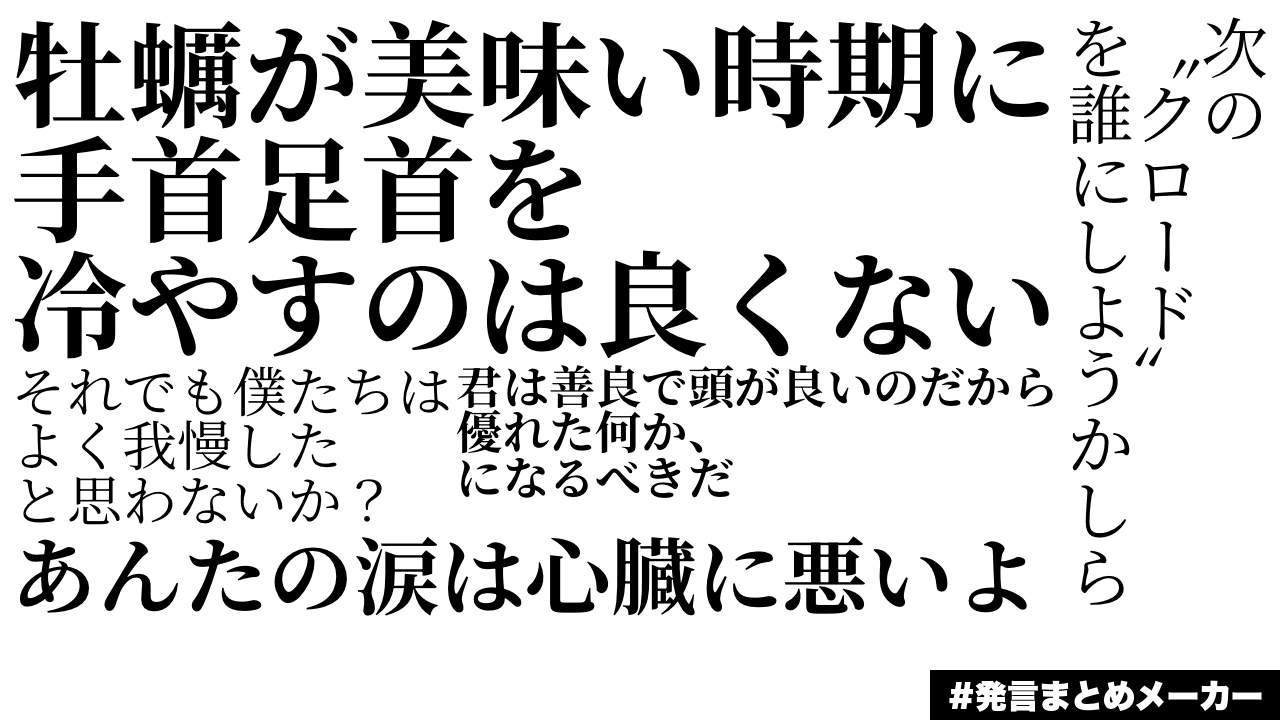
#完売本 #ヒルマリ #flow #レオニー #ラファエル
13.
───
一九二五年
そのように考えた最初の人々は神祖と聖人たちの至らなさを理由として欲のままに地上で生き、冥界へと追放された。
彼らは欲のままに真善美のすべてに反したので満たされぬ欲に苦しむ生と冥界以外の世界を持たない。
───
フォドラにおける無線通信の歴史はデアドラ港から始まっている。パルミラの電気技術者による無線音声送受信実験成功を受けてデアドラ港と船舶が連絡を取るための船舶無線が導入された。安全情報などの業務用でこの時点ではまだ電波を利用した航行用レーダーは開発されていない。音質が悪かったので通話には使えず船舶無線用の信号、次に電報のコードが決められ電報局が開局しフォドラの人々は新たな双方向通信手段を手に入れた。
数年後、首都であるガルグ=マク新市街に放送塔が建てられ試験放送が開始されると各地で開局申請が出された。しかしガルグ=マクの逓信省が許可を出したのは首都のガルグ=マク、アンヴァル、フェルディア、デアドラの四局だけだった。
ラジオデアドラは他局と違い日曜夜以外は二十四時間放送をし続けている。深夜帯のラジオパーソナリティとして雇用されたレオニーは元々は百貨店のエレベーターガールとして働いていたのだが買い物に訪れたラジオ局の構成作家が彼女の声の美しさと客の話し声に埋没しないその通りの良さに目を、いや耳を付けてスカウトしたのだった。
深夜帯一時から五時のうち三時から五時が彼女の担当で番組を終える時はおはようございます、という。早寝早起き派だったレオニーの生活は一変してしまった。
百貨店のエレベーターガールは街の小さな女の子なら誰もが憧れる花形職業だ。それだけで済んだらまだレオニーは動きやすく華やかな黄色と黒のチェック柄のジャケットに黒のスカートに身を包みエレベーターガールを続けていただろう。そんな素敵な制服に身を包みにこやかに客と接する姿が誘蛾灯の様におかしな男性を惹きつけることがある。
それは休日にレオニーが客として職場に買い物に来たときのことだった。あの時あのエレベーターにマリアンヌが乗っていなかったらレオニーは今でも百貨店で働いていたかもしれない。縁や運は本当に不思議なものだ。
その日、レオニーとマリアンヌが乗り合わせたエレベーターの中でレオニーは同僚が男性客から触られている事に気づいた。前からたちの悪い客がいるという話がエレベーターガール達の間で共有されていた。
モスグリーンのスカートが捲れ上がりストッキング用のガーターベルト着けた太ももが露わになる事もストッキングが傷む事もいとわずレオニーは不埒な振る舞いに及んだ男性客の腰に膝蹴りをくらわせ怯んだところで腕を捻じ上げて確保した。体が咄嗟に動いたのだという。レオニーは自分が男を確保している隙に早く非常ボタンを押す様に言ったのだが恐怖で竦んでいる同僚は手が震えて何も出来ずその場にいたマリアンヌが隙間から腕を伸ばして非常ボタンを押した。通信回線が開き何事か問う声に対して痴漢が出た、エレベーター内で既に確保したから警備員を呼んで欲しい、とレオニーが報告した。
「今日はもう仕事って気分じゃないだろうから許可が出たら私が代わってやるよ」
警察での手続きの都合上結局代わりに入る事は出来なかったようですが被害にあわれた方にそう提案したレオニーさんには後光がさして見えました、とマリアンヌは警察で証言している。
緊急停止したエレベーターの前には買い物客に犯人を見せない為か被害者が誰なのかを隠す為か警備員によって従業員用の出入り口まで衝立が並べられていた。人目につかぬよう搬入口に警察車両も到着していたがそれが地味な紺色だったのはどうやら百貨店側が配慮を、と警察に頼んだかららしい。
警察の事情聴取まで受けたマリアンヌは警察署前にある二十四時間営業のダイナーでレオニーに温かいココアを奢ってもらっていた。そこそこ消耗していたのでありがたくいただく。マリアンヌにとって久しぶりのココアだった。朝の情報番組担当のリシテアが死にたくなった時には大体脳に甘味が足りていないからまずココアを飲め、としつこく言っていたせいで一時期店頭からココアは姿を消していたが再び街中で見かけるようになった。リシテアは迂闊に自分の好きなものを番組内で挙げるせいで好物をなかなか食べられなくなる飲めなくなると言う事を繰り返している。
「マリアンヌだっけ?さっきはありがとな!」
ハキハキと喋るレオニーはエレベーターガールという機械的なイメージのある職についているせいか私服も女性の曲線美を目立たせる保守的ものではなく直線的なシルエットをつくるツーピースの体が動かしやすそうな服を身に付けていた。
「警察は第三者の証言があると動きやすいそうです」
「慣れてるんで驚いた!私なんか時間がかかりすぎてびっくりしたのに。予定とか合ったんじゃないか?大丈夫?」
レオニーは改めて物好きにも警察で証言してくれたマリアンヌを見つめた。流行りの釣鐘型をした帽子に収まっている水色の髪は短くしているようにも見えたがどうやら編み上げているらしい。書き物をする仕事なのか所作に問題があるのかその両方なのか短めにまくった上着から見えたブラウスの袖にインクの染みがついていた。
「私はラジオデアドラの構成作家で取材の手伝いもします。警察の方からお話を伺ったこともあります。だから慣れていると言ってもいい、のかもしれません」
遅れましたがと言ってマリアンヌが差し出した名刺には確かにラジオデアドラの物で表面に名前と部署とラジオ局の住所、裏には彼女が担当する番組名と放送時間が書いてある。レオニーが聞いたことのない深夜から早朝にかけて放送される番組ばかりだった。
「うちには受信機がないから職場の社員食堂で聞いてる。昼のドラマにみんな夢中だよ!作家って事はあれの脚本書いたりしてるのか?」
マリアンヌは構成作家なので台本は書くが脚本は書かない。口で説明するのは面倒なのでこの誤解についてはいつも言葉を濁してしまう。書き言葉ならばどんな面倒なことでもすらすらと説明が出来るのに話すとなると途端に口が動かなくなる。
「部署が違うので…」
「そっか。警察沙汰をきっかけにして営業をかけるのも変な話だけどさ、良かったらまた買い物に来てくれよな!私はエレベーターに乗りっぱなしだから値引きはできないけどさ」
「買い物もですがラジオデアドラの社員として百貨店に取材に伺う事もあるかもしれません。その時にもよろしくお願いします」
「分かった。上司にもそれとなく話しておくさ。とりあえず疲れたから今日は素直に帰るよ」
そう言うとレオニーは残りのココアを飲み干し伝票を手に取った。彼女がきびきびと動くので幅広の帽子についた大ぶりな羽飾りが楽しげに揺れる。躍動感と自信に満ち溢れる都会の働く女性そのものだった。
レオニーが去った後マリアンヌはココアのおかわりを頼み鞄から手帳を取り出した。忘れないうちに警察で逆に何を聞き出せたのか必死で書き留める。レオニーの溌剌さはこれで伝わるだろう。そう思ってメモを満足気に読み返していたマリアンヌだったがこの時、彼女はレオニーの個人的な連絡先を聞き忘れていた。その為思ったより早くラジオデアドラの社員として百貨店へ訪れることになる。
───
神祖に、聖人に、教会に至らぬ所があったとしても教会は聖なるものを、真善美を求めて生きる人々の為にそれらを示し続け理想と人々を繋ぐ架け橋でなくてはならない。
示された聖なるものを見た人々が自らの悪しき行いを恥じ良き行いをする様に心がけるからだ。
───
レオニーがガラス越しに出されたディレクターであるヒルダの合図に合わせてマイクロホンのスイッチを切った。目の前には構成作家のマリアンヌが座っていて清々しい日の出の光が放送を終えたばかりのレオニーたちを照らす。
「今日もなんてひどい台本なんだ!」
「ええ〜そうかなあ〜?マリアンヌちゃんの台本すっごく良かったと思うけど!」
「なんなんだよ!この焦げた私物プレゼントって!」
「レオニーさんなら絶対に面白く出来ると思いまして」
先週新市街にあるマリアンヌの住むアパートが火事で半焼した。半分残っている、とだけ聞くと暮らせそうな気もするが実際の現場は酷いものでとても生活など出来ない。幸いな事にその時、彼女は不在で焼けずに残った物もあった。余談だがその話を聞いたラジオデアドラの関係者たちは皆、一瞬はマリアンヌの不注意を疑ったという。
彼女は顔見知りからいきなり静謐の美を称えられるほど美しい女性なのだが構成作家として書く台本はレオニーに言わせればネジが飛んだ物ばかりだ。レオニーとマリアンヌの間にある机には番組で使った焦げた帽子それに焦げた辞書や焦げた詩集が数冊積み上げられている。
「使い物にならない上に番組パーソナリティの私物ですらないと言う事実とレオニーさんの真っ当さが正面からぶつかった時に笑いが生まれる、と思いまして」
「私マリアンヌちゃんの嫌なことがあってもタダで起きないところ大好き〜!」
「ありがとうございます。私も親切なヒルダさんがとても……好きです」
今はディレクターのヒルダが焼け出されたマリアンヌを「うちは部屋が余ってるから」という理由で自宅に住まわせてやっている。今日マリアンヌが着ている洋服も彼女の借り物だ。きっと一人暮らしをしていた数日前よりまともな生活を送っている筈だ。ヒルダはマリアンヌと違って化粧品を腐らせない。
「レオニーちゃんも一緒に朝ご飯食べよ!」
レオニーはこの二人に言い返してやろう、と番組放送中はいつも思っているのだが終わる頃には疲れと空腹で言い返す気力が残っていない。三人がやって来たラジオ局の目の前にあるダイナーは関係者御用達で二十四時間営業をしている。当然、この店の店内放送はラジオデアドラだ。早朝のニュース番組でアナウンサーが読み上げるニュースを聞きながら番組スタッフ達と朝食をとっているとまた火事が起きたようだった。火事のニュースを耳にしたマリアンヌが焼けたアパートのことを思い出して伏し目がちになる。
「なんか最近火事が多くない?取材に行ったら怒られるかなあ?」
目玉焼きの黄身を潰しながら何か思い付いたらしいヒルダがメモをし始めた。レオニーが担当している2時間はこんな時間はどうせ誰も聞いていない、と言う理由でやりたい放題の枠だ。こんな時間帯でも聞いているのは荷揚げや荷下ろしの為に待機しているデアドラ港の沖仲仕達が多く彼らに向けてボートレースや競馬中継の予告が入る。しかし朝5時を過ぎて嘘のように内容が真面目になった。今は解説員が最近の天候不順について語っている。
「焼け出された直後は忙しいので…」
マリアンヌがスクランブルエッグをケチャップとかき混ぜながら応じた。この口ぶりだと先方の都合がつきそうな頃に取材に行っても不思議ではない。相手を怒らせても泣かせても放送ではレオニーならなんとかしてくれるだろうと思っているので2人ともやりたい放題だ。
「そっかあ、それもそうだよね!あ、レオニーちゃんにまた手紙が来てるよ。食べ終わったら読んであげて」
ヒルダから渡される手紙の束はいつも開封済みだ。あんな時間に聞いていてわざわざレオニー宛の手紙を出すような聴取者は基本、好意があって好かれようとして手紙を出すが中にはきっと見るに耐えないようなものもあるだろう。しかし ヒルダはそういった類の手紙がレオニーの目に触れないようにしてくれている。
「あんた達がパーソナリティに見せられなかった手紙特集を出来ないんだからきっとすごいのをみてるんだろうな」
レオニーは塩で味付けしてある豆の煮物をトーストに乗せふたつ折りにして頬張った。朝食についての葉書やお便りを募集した際に書いてあった食べ方で試してみたら美味しかったのでよく真似している。豆が溢れないように器用に食べるとレオニーは手についたパン屑を払って手紙の束を手に取った。
「さあ、路面電車も動き始めたしレオニーちゃんは帰って一眠りして!」
「ヒルダ達は水上バスの始発待ちか。歴史地区は素敵だけど住むには少し不便だな」
ヒルダの自宅がある一帯は十五年前に歴史地区に指定されてから手押しの台車と乳母車と車椅子以外の車輪は使用が禁止されている。移動には足と船しか使えない。デアドラの新市街にあるマリーナに自家用船を係留するには莫大な費用がかかり空きがなかなか出ない為どうしても水上バスと水上タクシーを利用する様になる。
ヒルダはレスター地方屈指の名家であるゴネリル家の娘だ。ゴネリル家のルーツはパルミラの首飾り建設時までは確実に遡ることが可能で、それ以前になるとお伽話や神話の領域になる。ヒルダ言うところの由緒正しいご先祖サマ、がまだデアドラがレスター諸侯同盟の首都だった頃に建てた上屋敷は現在の新市街にあったのでまだその上屋敷を所有していればヒルダもレオニーの様に路面電車で帰宅できただろう。しかし彼女の曽祖父がその上屋敷をデアドラ市に売却し改めて網の様に水路が張り巡らされている旧市街へ家を建て直した。船着場がある立派な屋敷で ヒルダの曽祖父は毎朝、自宅からボートで釣りに出てその日に食べる魚を釣っていたらしい。ヒルダは釣りに興味がないが同居している父や兄は釣りが好きなので活用している。
「それじゃ遠慮なくお先に失礼するよ、二人ともおやすみ!」
レオニーが去るとヒルダはハンドバッグから彼女に渡さなかった開封済みの封筒を取り出した。マリアンヌに中身を確認させる。
「分かりにくいですがファイアーの術式です。レオニーさんに魔法適性があった場合、読み上げさせたらスタジオが火事になります」
マリアンヌは意外性の宝庫だ。口下手なのに文章を書かせれば誰よりも奇抜なものを書くし、引っ込み思案で人付き合いが苦手なのに全寮制の士官学校で理学魔法の訓練を受けていたのでメイジとプリースト双方の資格を持っている。寮でのあだ名はその無口さからサイレスだったらしい。
「あーあ、女だけで番組を作ってるからかしら?また警察に行かないと。その前に上に相談か」
「そうですね、誰かに読み上げられる前に加筆して術式を無効にしますから証言してください」
マリアンヌが万年筆で悪意の塊の様な便箋に記号や文字列を書き込むとそれらは一瞬だけ青く光り、すぐに輝きを失っていった。もしかしたら彼女のアパートの住人にもこんな手紙が来て知らずに読み上げた結果、火事になったのかもしれない。ヒルダもマリアンヌと同じことを考えたのか無言で頷いた。
───
隕石の衝突エネルギーで高温となった地表はどろどろに溶けて鉄などの重いものが沈み高い圧力の下で固まっていく。固形の内核と液状の外核が生まれ自転により液状の外核は回転し電気が発生した。その電気により生じた地磁気は惑星全体を覆い宇宙線や太陽風を遮る防御壁となる。
磁気微生物の中にあるマグネトソームは地磁気によって守られた惑星に引き寄せられていった。
───
ヒルダとマリアンヌから報告を受けた上司が悪意のある攻撃をされたと判断し局の法務部にこの案件は委ねられた。ラジオデアドラは警備体制の強化が必要と判断し警備員を新たに二名雇い入れた。大柄な金髪で、玄関に立っているだけで抑止力になるであろうラファエルと魔法を使った嫌がらせに対処出来るベレトだ。
ラファエルは休憩中、筋肉をいじめると称して背中に誰かを座らせながら腕立て伏せをしている姿が評判を呼び、たまにギャラなしで番組に出演させられている。もう1人のベレトは誰かの過去を思い起こさせる静かさなので番組でパーソナリティがたまに話題に出すものの出演した事はない。ただ、マリアンヌとは通じ合うものがあったのかすぐに打ち解けた為その姿を見た局内の男性陣は衝撃を受けた。今日もまた2人で立ち話をしている。
「ヒルダさん、一瞬だけ便箋に環が見えたんだそうです」
「魔法適性検査は」
「本家筋の方々は十傑の遺産絡みで受けていると聞いたことはありますが、ヒルダさん本人はどうなのか分かりません」
「今時はそんなものか……。自分のことだと捉えないと皆、ますます魔法とは縁遠くなるな」
ファイアーの術式が仕込んである新たな手紙をマリアンヌに見せられた際ベレトは線をたった一本書き足すだけで無効にした。マリアンヌはガルグ=マクの士官学校で正式な訓練を受けた身なので、目の前のベレトの腕が本物であることがそれだけで分かる。彼なら警察や軍の魔法部門で上級職にだってつける筈だが、地方で警備員をやっていると言うことはきっと訳ありなのだろう。
「でも私がプリーストの資格を持っていると知ると皆さんレストやライブをかけてもらいたがるんです。訳のわからない医薬品より自然で良い、と」
ふふ、と静かに笑うマリアンヌが内心で何を考えているのかベレトには手に取るようにわかる。レストやライブの術式だって訳がわからない癖に、と思っているのだ。今のマリアンヌはそこで笑えるから構成作家が出来る。ベレトが最初に出会ったマリアンヌなら無理だった筈だ。改めて良い時代になったと思う。豊かさで紋章も魔法も存在意義を薄められ、最初のマリアンヌが背負っていた重荷は今やないに等しい。
「人間は身勝手なものだ。だがそれも今や飯の種だね?今後は番組宛の手紙の開封は警備部がするべきだ。それと局員全ての魔法適性検査が必要だ」
「このおかしな嫌がらせがデアドラで横行しているなら皆自分の状態を知るべきですね、確かに」
ベレトはマリアンヌの言葉を首肯しながら大欠伸をした。もう交代要員も来たので帰る前に男性用仮眠室で寝るのだという。ラジオデアドラの男性用仮眠室はいつシーツを交換したのか誰も知らない。殆どの局員はここで寝るなら廊下の床に、という代物だ。一体どんな生き方をしてきたのだろう。マリアンヌだって紆余曲折あったがベレトのそれはなんだか途方もないような気がした。
一方その頃、ヒルダは損害保険代理店で一連の火事に火災保険の詐欺の可能性があるかどうか意見を聞き終え、市立図書館で新聞の縮刷版を読んでいた。不審な火事が起きたのはどこの誰の家なのかを調べている。まるで科学から魔法に立ち返れ、と言わんばかりに先端技術に関わる人の家ばかりが火事を起こしていた。放送局が狙われてもおかしくない。それに確かマリアンヌの隣人はレスター光学の研究所勤務だった。
続けてヒルダは警察白書にも手を伸ばした。犯罪被害者の分析が載っている筈だ。だが警察白書には年齢・性別・年収・居住地別の被害者分析は載っていても職業での分析はなかった。では加害者はどうだろうか。単独犯なのか組織なのか。脅迫の為に放火するのは犯罪組織の手口だと書いてあるが技術者を脅迫する犯罪組織とは一体どんな組織なのだろう。ヒルダには見当がつかなかった。一人で考え込んでいてもこれ以上いい考えは浮かびそうにない。今日のところはこれで時間切れのようだった。
ラジオ局に戻るとちょうど休憩室で放送終了後のリシテアが1人でココアを飲んでいた。ヒルダも自動販売機でソーダを買って向かいに座る。
「マリアンヌなら打ち合わせで会議室に行きましたよ」
「あーいいのいいの。リシテアちゃんにも考えてもらいたいんだけど、これ見てくれる?」
ヒルダのメモを見たリシテアが口に手を当ててうーん、と唸りながら考え込んでいる。年上のヒルダに頼られたからには気の利いた事を言いたいと思っていた。
「えっ、これはマリアンヌのアパートも関係あるんですか……?」
「それにレオニーちゃん宛にも変な手紙が来たの。おかしいって気がついてマリアンヌちゃんが無効にしてくれた」
「レオニーにもですか……。私にも来るかもしれませんね。その変な手紙」
リシテアはカップの底に残っていたココアを飲み干すと彼女なりの答えを出した。
「宗教関係とか?」
「えーっ!うちの局、司祭様の人生相談番組もあるのに?」
デアドラのセイロス教会聖職者は番組を持っているだけでなく、大規模な記念礼拝を行う際にラジオデアドラに広告も出すしラジオで説法もする。ラジオという新しい場と積極的に関わっていた。
「いや、デアドラのセイロス教会がどうのって話ではないです。今って二十世紀ですよ?ラジオもガス灯もある今、そんな主張をするならよっぽど強い後ろ盾がある、と確信していないと無理です。言えません。だから女神様が自分達の味方だと信じ込んでいる人達、それで宗教関係と言いました」
リシテアの説明はヒルダの腑に落ちたので大げさに礼を言った。彼女は手短に宗教関係、とは言ったが町中の小さな聖堂を守り、託児所を開いている修道女や神父の様な地に足がついた人々ではなく暗黒時代の異端審問官のような集団を指している。己の身に宿る魔力を蔑ろにしていた技術者たちを彼ら自身が持つ魔力で罰する、という残酷な発想はなかなか出てくるものではない。
リシテアが気がついたようなことを警察や保険会社の保険調査員が見逃すとも思えないが、警備部には伝えておくべきだろう。ヒルダが自分の机でベレト宛にメモを書きおえた時に近所の教会の鐘が鳴った。ヒルダにとっては放送準備の時間を知らせる鐘の音なのでスタジオにいかねばならない。放送終了後にベレトにすぐ渡せるようわかりやすい場所にメモを置いた。
放送中、誰もいなくなった部屋に緑の髪をした社員がそっと入り込みヒルダがベレトに渡す筈だったメモはその社員の手の中で燃やされた。最新の火災報知器も感知できないくらい小さな魔法の炎だった。
翌日、デイリーレスターの一面を宗教警察設立が検討されているという記事が飾った。写真は白黒なので読者は全く気がつかなかったがガルグ=マクでその準備にあたる人々は皆全て緑の髪に緑の目をしていた。
※細かい顛末が気になる場合はこちらもお読みください
https://horreum.sub.jp/teg/?tag=%e3%83%a...
畳む