2024年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
「flow」第1部10〜11「代替品」#完売本 #flow #ヒューベルト #ペトラ #コンスタンツェ #ハピ #エーデルガルト #フェルディナント #カスパル
10.
───
一七一〇年
僧侶の皮、王族の皮は誠に使い勝手が良く聖人たちをうまくごまかすことができた。
目の霞んだ人々は中身が入れ替わっていることに気づかない。そのまま僧侶の皮を被って聖人たちに近づいてみると彼らの数が減っていることに気付いた。聖人たちさえ居なくなってしまえば目の霞んだ人々など敵ではない。
───
パルミラやブリギットを始めとする周辺国と比べ、フォドラで医学が発展しなかった理由はいくつもある。信仰魔法への傾倒の他に大麻や阿片などが宗教上の禁忌に触れるため栽培すら出来ず、医療に利用出来なかったことも理由のひとつだ。
部位の切断など不可逆で激しい痛みを伴う外科的処置を行う際だけは利用出来なくもなかったが、その際も禁忌に触れない強い酒を使う例が殆どだった。気休めでしかない。
一世紀ほど前、病禍の時代にフォドラの社会は激しい変化を遂げた。それまでは大量の医薬品や設備を必要とし、完治させるまで時間がかかる医師より魔道書だけですぐに人を癒す修道士の方が必要経費が掛からず優れている、とされていた。
しかし信仰魔法は使い手が同じ空間に居続けなければ発動しない。だが薬は予め渡しておけば患者が辛くなったその時に服用できる。手術も終えてしまえば後は別のものに看護させれば良い。圧倒的な人手不足に直面し、フォドラでようやく医療行為が見直され───その一環で大麻や阿片の医学利用と栽培が解禁された。
麻酔に向く芥子は産地であるブリギットの中でも標高が高い乾燥した寒冷地で栽培され、温暖なアドラステア地方やレスター地方では中々根付かない。気候の条件から言えばファーガス地方では栽培可能だ。しかし信心深い人々が多いファーガスの農家は栽培したがらない。
安定供給を目指すならブリギットやダグザから輸入するしかなかった。フォドラ統一戦争の後にブリギットの女王ペトラ一世とベレト王の間で交わされた通商条約により、少ないながらも鎮痛剤そして麻酔薬の原料となる阿片の供給は安定している。しかしいずれは自力で芥子栽培をすることが望ましいとされていた。
調査の結果、フォドラの衛生局はオグマ山脈に連なる某高原ならば栽培可能ではないかと考え、ブリギットの農業勧業局から技術官を招き試験栽培を始めている。うまく運用できれば将来的には麻酔薬を全て国産品に切り替えられるだろう。
禁止薬物の原材料を育てているので霧が試験農場の詳細を隠してくれるのはありがたい。しかし目の前に伸ばした自分の手も見えないような霧は問題だ。作物に影響が出るし、コンスタンツェがヌーヴェル家の持つ魔道の知識を注ぎ込んで作った防御結界に触れても、魔獣と遭遇しても命がなくなるだろう。
早朝の吐く息も白く濁り己も消えてなくなりそうな天候の中、ヒューベルトはブリギットから派遣された技術官であるペトラを見つめた。正確に言えば彼女が持つランプの灯りを見つめている。
「果実、大きさ、ありません」
霧の向こうから片言で話す彼女はいつも誠実で、教えを乞う側を下に見ることがない。そこが彼女の持つ確かな知識と同じくらい素晴らしい点だ、とヒューベルトは評価している。そんな彼女の声は落胆していた。
つい先日まで目の前には赤い花が咲き乱れていた。芥子は花が枯れた後で結実し、その実を傷つけると白い乳液が滲み出す。その乳液はしばらく経つと粘性を示し色は黒く変化する。この黒くなった乳液を集めて乾かしたものが麻酔の原料となる生阿片だ。ひとつまみの生阿片を精製するのに花は百本近く必要になる。ブリギットでは一面の赤い芥子の花が季節の風物詩だ。世界中の痛みに苦しむ人々が赤い花にいくらでも金を払う。
「いいえ、結実しただけでも大したものです。ここは貴殿のお国の名産地と違って湿度が高い」
「ありがとう。しかし、種子、取れます。とても小さい、とても沢山、注意、必要です」
ダグザでは小さな物を表す時に〝芥子粒のような〟という言い回しを使うのだ、とヒューベルトの上司であるコンスタンツェが言っていた。種子を採取する時には取りこぼしがないよう、細心の注意を払う必要がある。芥子も大麻も国家が完全管理して栽培する予定なので間違いは許されない。そういった細かいことならば、と言って上司であり六大貴族に連なる名家出身のコンスタンツェがヒューベルトをこの計画の責任者に推薦した。
コンスタンツェに言わせれば医学と魔術は偉大なるヌーヴェル家の者によって融合を果たす筈だが、それには他人に任せねばならないことも多いらしい。
「ご安心ください。絶対にならずものたちの財源にはさせません」
ヒューベルトの家系は代々医療に携わる、と運命づけられている。ベレト王からベストラ家再興の許可が出た日に運命は決まった。現在はともかく当時は殆ど受け継ぐ地位も領地もなく、あるのは貴族の称号と王と対立した過去だけと言う虚しい状態だった家名に何故、先祖がこだわったのかがヒューベルトには理解できない。だが王はとても喜び、自分が喜んだことを記録に記せと命じたと聞く。
都合の良い逸話かと思いきや物好きな一族のものがガルグ=マク旧市街にある公文書館で確認したところ本当に事実として記されていた。王の心は広いにも程があるのではないだろうか。
「過去を気に病む必要はないが、どうしても気になるのならその分、他の誰かの命を救えば良い」
ベレト王はもっと広い意味を込めて先祖を激励した筈だが、とにかくベストラ家においてはそう言うことになったのだ。だが血筋のせいなのか黒魔法は使えても信仰魔法の才能が全くない。当時の世の中では分が悪かったが、信仰魔法を専門とする修道士ではなく医師や薬師になるしかなかった。
ベストラ家の人々は一族郎党で医学を志していくうちに、やがて医学研究における禁忌が少ない他国へ留学するようになった。他国で出版された医学書をフォドラ語に翻訳し、人体解剖実験に参加する。ヒューベルトも薬草について学ぶためにブリギットへ行ったことがあった。ベストラ家の人々は翻訳するだけでなく一族の者が他国で参加した様々な実験、特に解剖実験について本も書いた。
これらの医学書は統一王と呼ばれたベレトが印刷と出版を自由化しなければ、セイロス教の禁忌に触れていたため発禁となっていただろう。人体解剖を忌避する感覚は未だにフォドラでは色濃く残っている。
統一王に逆らった家系、というより現在では人の体を切り刻む家系という理由でヒューベルトの一族を嫌うものたちは多い。それでも彼の一族は効率良く人を救うことをまだ目指している。
「ならずもの、意味、何ですか?」
『ならずもの、です』
ヒューベルトがブリギット語で話すとペトラがため息をついた。言葉遣いに気をつけねばならない。彼がブリギット語を多少は理解できることが計画の責任者になれた理由のひとつだった。
「ヒューベルトと私、ブリギットではブリギット話す、フォドラではフォドラ語話す、約束です」
「申し訳ない。フォドラ語で単語の説明をすべきでした」
素直に謝るとヒューベルトも芥子の果実を検分し始めた。ペトラの指摘通り実が小さい。傷をつけてヘラを使い乳液を採取する方法では必要とする量を確保するために作付面積を倍にするか、新たな抽出方法を考える必要があった。頼りたくはないのだが、遠い祖先の残した恐ろしい記録に何か手掛かりがあるかもしれない。
───
目の霞んだ人々のうち殆どのものが最初の人々が作った武器を持つことが出来ない。無理に持つと獣に成り果ててしまうからだ。
獣に成り果てたものは討ち取られた。そうしなくてはその土地を滅ぼしてしまう。
たまに人の姿を保ったまま武器を持てるものが現れるとその人々を尊い、と言って崇めた。
───
今時は魔法職で募集をかける時に勤務先が地方では中々人が集まらない。石でも投げた方がまだ効き目のありそうな理学魔法しか使えない癖に自分が選ばれし二パーセントだと分かっているので皆、成功するために都会へ行ってしまう。
ガルグ=マク新市街にある衛生局はフォドラの医療全てを統括している。信仰魔法との縦割り行政が長年の問題だったが、目標が治癒であるならば方法論の違いで管轄を分けるべきではない。
医療行為は世俗のものだ、という主張にセイロス教会がついにおれて信仰魔法も衛生局の管轄となった。衛生局側がアドラステア帝国の頃より続き、一度はお取り潰しの目にあったものの不屈の闘志で再興を果たして六大貴族にその名を連ねる名家、ヌーヴェル家のものを局長にした時点でセイロス教会が譲歩するのは決まっていたのかもしれない。医学と魔道は互いに欠けたところを補いあって更に便利になるべきだ、と言うのが衛生局の局長コンスタンツェの主張だった。
そういった高尚な議論はさておき、人口あたりの医療従事者数が足りていないと言う現状を解決するにはレストを使える修道士か鎮痛剤や麻酔を使える医師がいればいい。
全人口のうち二パーセントしかいない魔法が使えるののうち、何割が修道士になってくれるのかを考えると医師の方がまだ人数を読みやすかった。修道士は軍に入ることも多いが医師は医師になるしかない。修道士による治療と比べた時に経費の高さは問題だが、それを解決するため衛生局は鎮痛剤と麻酔薬の国産化を目指している。
勤務先がオグマ山脈の魔獣が出没する山奥、と言うこともあって試験農場の警備責任者は中々見つからなかった。コンスタンツェが張った防御結界を現地で保守点検をするものを早急に見つけねばならない。試験農場で栽培するのは依存性が極めて高い麻薬の原料でもある。関わるのは最少人数にしたいが衛生局としてもヒューベルトにそこまでさせるわけにいかなかった。試験農場の内側だけでも大変なのだから。
今日もどうせ見つからないのだろう。結界に綻びが出てヒューベルトたちを困らせる前にフェルディア総合大学まで直接探しにいかねば、と思いながらコンスタンツェは最上階の窓から実技審査の様子を眺めた。局の中庭で黒手袋をして古びたフェルディア総合大学のマントを着た男が結界を張っている。男性の場合、髪を伸ばしておいた方が多少は魔力の足しになるのだが、鬱陶しさに負けて若草色の髪を短く切っている時点で見込みはないように思えた。
しかし彼は杭も紙も使わず反閇だけで空間を閉じている。結界に向けて試験官がバケツの水をぶちまけても水が通過していくだけで何も起きなかったが、試験官が投げ込んだ木材は粉々になった。網状に結界を貼ることによって雨は通し、魔獣や人は通過させない仕組みになっているらしい。
コンスタンツェは慌てて机に戻って採用通知を書くと窓を開けて改良したウインドの呪文を唱え、採用通知を試験官の胸元に送った。
書類が風に乗って不自然な最短距離で試験官の胸元に飛び込んでくる。その様子を見たベレトは思わず口笛を吹いた。開いた窓の奥に金髪の巻き毛に囲まれた懐かしい顔を見つけ、思わず笑顔になってしまう。血筋もあるだろうが本人の努力が素晴らしい。
身なりを整えたら局長室へ向かうよう試験官から言われたベレトがチラチラと横目で局内を窺うとどうやら手狭なようで、書類が溢れ出しそうになっている。レンズ研磨も良い仕事だったが久しぶりに田舎で体を動かしたい気分なのに書類仕事は嫌だった。
ノッカーで扉を叩くと奥から入るように、と懐かしい声がベレトに話しかけてきた。久しぶりに出会うコンスタンツェは心もふたつに割れておらず安定している。一族郎党が捨て石にされ、領地も爵位も取り上げられた状態から這い上がった前のコンスタンツェが何の不安もなく育ったらこんな感じになるのだろう。第一印象だけでいえば愛されて育ったコンスタンツェの孫娘に雰囲気が似ていた。
「今時はまともに魔法が使えるものが中々いませんが貴方は違いました。安心して私の防御結界を任せられますわ!詳細は今から口頭で説明するのでこの場で覚えて帰って頂戴。何ひとつ書き残してはなりません」
オグマ山脈の某高原にある試験農場で何を栽培し誰がいるのか。どのような防御結界を張っているのか。秘匿部署とはそうしたものなので、ベレトは淀みなくコンスタンツェの説明を全て復唱した。
「ではすぐに出発します」
「路銀なしには辛い距離よ。ある程度の経費は先に下で受け取っておきなさい。それと身辺調査はもう部下がしているでしょうから事細かには聞きません」
そう言うとコンスタンツェは一度口を閉じてベレトの顔をじっと見つめた。白い肌に若草色の髪と瞳、ヌーヴェル領にある本宅に飾ってある王と六大貴族達の姿を描いた絵にどことなく雰囲気が似ているような気がする。
「貴方ガルグ=マクは初めてかしら?」
ガルグ=マクで一世紀以上を過ごし新市街を作ったのは自分だが、こう言う時は真顔でごく一部だけを伝えるに限る。
「何度か来たことはあります」
コンスタンツェは新しい部下の言葉を聞き、素直に引き下がった。彼が身につけていたフェルディア総合大学のマントは古すぎる。古着屋で買い物をしたと言われればそれ以上返す言葉はない。だが彼の姿を見るうちにコンスタンツェはヌーヴェル家に伝わる御伽噺を思い出してしまった。この御伽噺はノアの紋章を隠していた時と同じく、世間に対して隠された状態で伝えられている。
───フォドラ最後の王はまだ生きてフォドラ中を彷徨っている。正体を隠し、剣が使えることを隠して民の中に紛れ込んで様々な仕事に就いて生活を楽しんでいる。だからもし王と出くわしたとしても深く追求してはならない───
ヌーヴェル家は昔から魔道学院、つまり現在のフェルディア総合大学と縁が深く、禁退出扱いの資料も読むことが出来る。コンスタンツェの祖母が言うには3世紀ほど前に魔道学院で働いていたアンヴァル出身のベレト=アイスナーと名乗る人物と二世紀前にデアドラ港で働いていたフェルディア出身のベレト=アイスナーと名乗る人物は限りなく王である可能性が高いらしい。では先ほどまで目の前にいた人物はどうだろうか?
コンスタンツェは手を叩いて秘書を呼び、お茶の用意をするように言った。秘書が選んで淹れたベルガモットティーに口を付け、満足げに微笑むとコンスタンツェは窓の外を眺めた。
「あれっ?今日のコニーなんだかとっても嬉しそうじゃん」
「そうね、ハピ。あなたの秘書としては本当に酷い言葉遣いも全く気にならないほど機嫌が良いわ。試験農場の警備責任者も決まったし、久しぶりに大好きなお祖母様のことを思い出したからかしら」
「ふーんそうなんだ。思い出してあげるのも供養だって言うよ。じゃあこれはコニーのおばあちゃんにね」
そう言うとハピはカップをもうひとつ出して紅茶を淹れた。
11.
───
一七九〇年
武器を持っただけで獣に成り果てるならば目が霞んだ人々は獣も同然だ。
獣たちは聖人たちという牧者に飼い慣らされる羊の様だった。自分たちは違う、最初の人々はその様に考えた。
───
石炭は十七世紀初頭の病禍で魔法を産業に活かせなくなるまで、鍛冶屋の補助燃料や一般家庭の暖炉くらいにしか使い道がなかった。だが今や石炭は黒魔法の代替品となった。石炭はアドラステア地方、特にヘヴリング領の根幹をなす資源となっている。
眷族たちは自然への影響を気にかけて化石燃料ではなく、魔法を社会が消費するエネルギーの根本に据えていたが、フォドラから魔法の力が失われてしまったためこの流れはもう止まらない。
炭鉱には様々な技術が集約される。坑道から排出された地下水を汲み上げるため釣瓶や水上輪が利用され、軌道で石炭が運び出された。軌道は最初トロッコや馬車鉄道が走っていたが、のちに蒸気機関車が走るようになる。石炭を乾留したコークスを使った製鉄法が開発されると一気に安価で良質な鉄が提供されるようになった。黒いダイアモンドの力を借りたフォドラは工業化の時代を迎えている。
フレスベルグ家はアドラステア帝国の帝位継承権と免税特権を放棄することと引き換えに伯爵家として再興をベレト統一王から許された。その代わりに納税の義務を負い、苦し紛れに様々なことを模索している。そのうちのひとつがフレスベルグ製作所だ。鉱山機械の修理点検製作を生業としている。
継承権を返上し再興が許されたのはファーガス神聖王国の王位継承権を持っていたブレーダッド家も同じだ。だがブレーダッド家は民に親しまれていたので再興も民から望まれたものだろう。
しかしフレスベルグ家はそうではない。何代か前の祖先は苦労した、とエーデルガルトは幼い頃から何度も聞かされている。それはそうだろう。そもそも何故再興を目指したのか全く分からない、と彼女は思っている。
今では単に爵位を持っているだけで、やっていることは商家とほとんど変わらない。エーデルガルトは絵を描くのが好きだったのでせめて製図を引け、と言われた。その結果、流れ流れて親族が経営するフレスベルグ製作所で技術者として働いている。
接待用に絵面を綺麗にしたいから、という訳で呼び出されたエーデルガルトは豊かな茶色の髪を結い上げ、作業着ではなくドレスを身につけている。ドレスと言っても補正下着を着る必要がない簡素なものだ。羽織る上着も腰までしかない。まるで男物のような丈が短いデザインだったが動きやすいので気に入っている。
エーデルガルトはフェルディナントの作った〝火力で揚水する機械〟の実演が上手くいくかどうか、唇を真一文字にして紺色の瞳で見つめていた。執政官の案内役をしているので目線を機械だけに向けるのはよくないと分かっていたが、どうしてもそらすことが出来ない。
フェルディナントはアミッド大河で行われた櫂を外側に付けた船の実演で失敗している。彼は錨用の水平回転巻き上げ装置を使って櫂が動くように改造した。装置は理論通りに動いたのだが、巻き上げ装置のバーを押して回る人々の姿が古代の船のようだと酷評されてしまったのだ。
彼が考案した装置を帆船に導入すれば無風状態の際、船内に人手さえあれば風が受けられる地点まで到達出来る。満帆にしている帆船より速度も出た。実用性を疑われてしまったため導入する造船会社は今も存在しない。
とにかく今度は失敗するわけにいかない。〝火力で揚水する機械〟試作機の不具合を修正するため、フェルディナントは髪を切る暇も髭を剃る暇もなかった。しかしガルグ=マクからやってくる執政官とその部下たちの前で身嗜みを整えないのは問題がある。周りからそう言われた彼は慌てて髭を剃り、真新しい白い襯衣を身につけた。伸びた橙色の髪は後ろで束ねて誤魔化している。
執政官の視察先にフレスベルグ製作所が選ばれたのはフェルディナントが六大貴族エーギル家の出身だからだ。執政官から久しぶりに顔が見たい、と言われたら誰も断ることはできない。
現在の執政官は久しぶりに六大貴族から選出された。ベルグリーズ家の出身で、偉大な先祖に肖るべくカスパルと名付けられた青年は紋章も魔法適性も持たないので科学技術に嫌悪感がない。彼が身びいきする人間ではないことは知れ渡っているので、彼が褒めればフェルディナントが特許を取得する予定の〝火力で揚水する機械〟を導入する鉱山が増えるだろう。フェルディナントはフレスベルグ製作所の期待を背負っていた。
懐かしく思うもの同士、視線だけで挨拶すると補助ボイラーと主ボイラーの水量を確かめたフェルディナントはいささか緊張した面持ちで火を入れて視察団に向かって機械の説明を始めた。
「容器の中の水を蒸気で押し出し、蒸気の凝縮を利用して生まれた真空を利用してここの地下水を汲みあげます」
「フェルディナント、念のために凝縮について説明しておかないと」
先に作った資料を執政官府へ提出できるような余裕があれば良かったが、それも無理だったのでぶっつけ本番だ。技術者同士では説明する必要のない単語でも、こういう場では置いていかれるものを出さないために噛み砕いておくべきだろう。そう考えたエーデルガルトはフェルディナントに助け舟を出した。
「ありがとう、エーデルガルト。その通りだ。凝縮とはこの場合、気体が液体になることを言います」
理解したかどうかフェルディナントが目線で問うと少なくとも執政官は肯いた。興味津々と言った目つきで実演を見ている。賑やかな音を立て機械が地下水を吸い上げ始めた。
「そうか!体積が減るから真空になるんだな!」
「その通りだカスパ……いや、執政官。この機会は原理も操作も単純です。吐出し弁が音を立て、吐出し管が熱くなれば蒸気の凝縮によって真空が作り出せたと分かります。あとはレバーで切り替えるだけで地下水を汲み上げられるようになります」
良いものを見せてもらった、勉強になったと喜ぶ執政官たちを見て失敗はなかったと確信し、関係者一同の頬が緩む。
「燃料は炭鉱ならその場で採れる訳だし効率がいいな。実際に運用するとまた不具合が出てくるのかもしれないがこれはすごい。なあ、フェルディナントこれは試作品なんだろ?」
「ああそうだ。君の前での動作確認に成功したから直ちに特許は申請するが、まだまだ改良の余地はたくさんあるのだ。さらに改良を加えてフォドラ中の鉱山にこの機械を売ってみせる」
フェルディナントは拳を握りしめ高らかにカスパルの前で誓った。
「はは!その意気だぜ。法改正して安全のために設置を義務付ける日も近いな」
そんな会話も交わされたが結論から言うといざ、使おうとするとフェルディナントが発明した装置は高い圧力が必要となった。そのままでは危険すぎて鉱山で使用することは出来ない。この機会はエーデルガルトによって跡形もないほど改良され、ようやく実用化された。しかし根本となった〝火力で揚水する〟というフェルディナントの発想がなければ、世界初の商業用蒸気機関は生まれなかっただろう。
のちにエネルギー革命が起き、燃料の主役が石炭から石油に転換された。アドラステア地方の炭鉱は時の流れに逆らえず次々と閉鎖された。しかしその時すでにフォドラ有数の総合電機メーカーとして成長していたフレスベルグ製作所が閉鎖された炭鉱を離職した人々の新たな職場となり、彼らは慣れ親しんだアドラステア地方から離散することなく生活が出来た。
こうしてフレスベルグ家は産業史にも名を残した。
───
一八一〇年
微生物が宇宙空間を移動する際にどのように移動したのかについてはいくつかの説がある。
恒星からの放射圧、すなわち光圧で宇宙空間を移動した、とする光パンスペルミア説では微生物が隕石などに付着せず微生物それ自体が宇宙空間を移動したと主張している。
───
レスター地方の山岳地帯、通称フォドラの喉元に山の民と呼ばれるクパーラという少数民族が住んでいる。独自の文化とセイロス教とは異なる信仰を持ち、フォドラが統一されるまでは幻と言われるほど排他的だった。しかし信教の自由が保証された今は違う。
工業化が一気に進んだフォドラだが、彼らの居留地だけは時が止まったかのような光景を見られる。そして彼らは流れ着いた異物であるベレトが一日につき二時間くらいしか起きていられない生活を何年か続けていても全く気にしない。親切なことに毎日誰かが食べ物と飲み物と着替えを用意してくれるので、無言のまま夢遊病患者の様に食べて身綺麗にしてまた眠る。
クパーラの人々だけが魔法適性者の割合を五パーセントのまま保持しているし、フォドラの西側では珍しくなった大紋章を継ぐものもいた。野生の飛竜もクパーラの固有種だけは個体数が減少していない。
ベレトはここで眠るとごく稀にだが、ソティスの夢を見ることが出来た。数世紀分の答え合わせをゆったりと夢の中でしている。ふわふわと宙を漂う緑色の髪の少女は眉間にしわを寄せて頬を膨らませた。
「おぬし!長いことわしを思い出しもせず薄情ではないか!」
「怒られるのが怖くて」
「怒らぬ!!」
ソティスは声を思い切り荒げていたが気が付いていない。
「俺はレアを困惑させるようなことしかしなかった。今もそうだが言われないことを察するのは無理だったから」
「娘も知らないことだらけで、言えることの方が少なかったのであろう」
これはソティスのいう通りで、確かにレアは母の若き日の姿を知らなかった。久しぶりに目にするソティスの姿は髪の色を除けばフレンよりも眷族としては幼く見える。当時、ベレトにまとわりついていたソティスの姿を正確に伝えてもレアが自分の母親だと分からなかったのは当たり前かもしれない。
「そうだな。俺もレアが大司教をしていたのと同じくらい長く王をやっていたら、わからないことだらけで言えないことばかりになっただろう」
夢の中は自由な筈なのにベレトとソティスは懐かしい寮の自室にいた。自由だからどんな場所でも選べた筈なのに。
「ガルグ=マクにいた小童どもとその子孫はよくやっておる」
「きちんと俺の代わりのものも魔法の代わりになるものも見つけた」
レアは長命である己自身を社会を安定させる礎にした。しかしベレトの教え子たちは家系や血筋ではなく執政官という役職を社会を安定させる礎にした。役職に就く者が存在すれば良いだけなので、代替わりしようと先代の執政官と血縁がなかろうと揺らがないのだ。魔法を失った時も白魔法の代わりに医学を発展させ、黒魔法の代わりに科学を発展させた。
「おぬしが人間どもを全く疑わず信じて手放せたからじゃ。わしらはどこか少しは疑っておったし手放せなかった。子離れができなかった」
「俺は人間だったからなあ。ところでソティス。俺はあと何年生きていられる?」
フレンですらどんなに短く見積もっても千年以上は生きていた。レアやセテスは何千年も生きていた筈だ。だがベレトは心臓に嵌められた紋章石とそこに宿ったソティスの意識によって生かされているだけだ。
「数千年生きるのが本来の寿命だが、おぬしは千年もつかどうか分からない。わしらからすれば哀れなことに髪が若草色のまま童のうちに死ぬのじゃ」
どうやら残り時間は二世紀くらいのようだった。その間、八時間睡眠で過ごせるなら充分な時間があると言える。
「そのうち何年を眠って過ごす?」
しかし今のように二時間しか起きていられないならば、ベレトは死ぬまでこの居住区で微睡んでいるしかない。
「起きていたければ夢も含めて紋章の力を使わぬように心掛けよ。わしはおぬしと最後まで共にあろうぞ」
寂しそうなソティスの言葉には心当たりがあった。クパーラの人々が暮らす居留地には魔獣が出る。その魔獣を駆除しようとして返り討ちにあっていたバルタザールを助けるため、ベレトは久しぶりに炎の紋章の力を使った。そして起きていられなくなった。
「おい、アンタ起きたいのか?」
夢の中では目を開けていたのに現実では瞼が重く、バルタザールのたてた物音や声に反応して微かに動くだけだ。横たわったまま強張っている手を顔に乗せて指で眉間を揉む。
「起きたい」
「わっ!久しぶりに声を聞いたぞ。忘れかけてたぜ」
バルタザールはクパーラの人々が暮らす居留地にあるカジノで警備員をしている。大した産業のないクパーラではカジノが大きな収入源で、少数民族の生活や文化を守る資金もそこから捻出されている。博打うちの財布がクパーラを守っていた。そしてバルタザール本人も博打うちなので、彼のささやかな薄い財布も居留地を守ることに貢献している。
「金がかかったろうにすまなかった」
「いや、長老たちからアンタの面倒を見てやれば借金の返済日を伸ばしてやると言われたんでな。それでどんな夢を見た」
クパーラの人々は夢を重要視していた。彼らの考えでは夢だけが時と場所を超え、分からなくなってしまった真実に直接触れることができる。
現に彼らの創世神話は今も書き加えられている。夢を見るたびに分からなくなってしまった真実に触れ、分からなかったことが明らかになるからだ。神話の謎に触れるような夢は強い夢、と呼ばれる。ガルグ=マクから来た学者たちは定期的にクパーラの神話を記録に残していた。
バルタザールが起きていられなくなったベレトを今時珍しく治癒魔法が使える呪い師のところに担ぎ込んでいる。身体を信仰魔法で癒してもらった後も起きていられないベレトを見た呪い師は夢を見なければならない、と告げた。余っている部屋をベレトが夢を見るために使っても構わない、と言う。
クパーラでは昔から、人生を問うような強い夢は呪い師の管理下で見る。呪い師に夢を勧められた、ということで居留地の人々は異常な眠り方をするベレトを自然に受け入れていた。
「夢の中で会いたかった人に長生きしたければもう夢を見るなと言われた」
ため息をついたベレトの若草色の瞳から涙が一粒こぼれ落ち、頬を滑り下りていく。
ソティスの夢はおそらく炎の紋章とベレトの心臓にはまっている紋章石が揃わなければ見られない夢だ。現在、ベレトの心臓はソティスの依代でもある紋章石によって動いている。
ソティスの亡骸から作られた紋章石はまずアガルタの民から武器の動力源として利用され、次にレアが作り上げた何体もの〝お母さまの容れ物〟を生かすことにも使われた。力尽きつつある紋章石に炎の紋章の力は強すぎるのだろう。
「命を削るくらい強い夢なんだろう。たまにそういう話を聞くぜ」
「いつ頃死ぬのかも教えてもらえた」
「不思議でもなんでもないさ。夢だけが時と場所を超えられるんだから」
クパーラ育ちのバルタザールはそういうと呪い師がベレトのために作った夢を呼ぶ呪符を壁から剥がした。捨てるのが面倒なのか、掌中にある丸めた紙をファイアーで燃やしている。今時、クパーラ以外の土地ではなかなか見られる光景ではない。畳む
10.
───
一七一〇年
僧侶の皮、王族の皮は誠に使い勝手が良く聖人たちをうまくごまかすことができた。
目の霞んだ人々は中身が入れ替わっていることに気づかない。そのまま僧侶の皮を被って聖人たちに近づいてみると彼らの数が減っていることに気付いた。聖人たちさえ居なくなってしまえば目の霞んだ人々など敵ではない。
───
パルミラやブリギットを始めとする周辺国と比べ、フォドラで医学が発展しなかった理由はいくつもある。信仰魔法への傾倒の他に大麻や阿片などが宗教上の禁忌に触れるため栽培すら出来ず、医療に利用出来なかったことも理由のひとつだ。
部位の切断など不可逆で激しい痛みを伴う外科的処置を行う際だけは利用出来なくもなかったが、その際も禁忌に触れない強い酒を使う例が殆どだった。気休めでしかない。
一世紀ほど前、病禍の時代にフォドラの社会は激しい変化を遂げた。それまでは大量の医薬品や設備を必要とし、完治させるまで時間がかかる医師より魔道書だけですぐに人を癒す修道士の方が必要経費が掛からず優れている、とされていた。
しかし信仰魔法は使い手が同じ空間に居続けなければ発動しない。だが薬は予め渡しておけば患者が辛くなったその時に服用できる。手術も終えてしまえば後は別のものに看護させれば良い。圧倒的な人手不足に直面し、フォドラでようやく医療行為が見直され───その一環で大麻や阿片の医学利用と栽培が解禁された。
麻酔に向く芥子は産地であるブリギットの中でも標高が高い乾燥した寒冷地で栽培され、温暖なアドラステア地方やレスター地方では中々根付かない。気候の条件から言えばファーガス地方では栽培可能だ。しかし信心深い人々が多いファーガスの農家は栽培したがらない。
安定供給を目指すならブリギットやダグザから輸入するしかなかった。フォドラ統一戦争の後にブリギットの女王ペトラ一世とベレト王の間で交わされた通商条約により、少ないながらも鎮痛剤そして麻酔薬の原料となる阿片の供給は安定している。しかしいずれは自力で芥子栽培をすることが望ましいとされていた。
調査の結果、フォドラの衛生局はオグマ山脈に連なる某高原ならば栽培可能ではないかと考え、ブリギットの農業勧業局から技術官を招き試験栽培を始めている。うまく運用できれば将来的には麻酔薬を全て国産品に切り替えられるだろう。
禁止薬物の原材料を育てているので霧が試験農場の詳細を隠してくれるのはありがたい。しかし目の前に伸ばした自分の手も見えないような霧は問題だ。作物に影響が出るし、コンスタンツェがヌーヴェル家の持つ魔道の知識を注ぎ込んで作った防御結界に触れても、魔獣と遭遇しても命がなくなるだろう。
早朝の吐く息も白く濁り己も消えてなくなりそうな天候の中、ヒューベルトはブリギットから派遣された技術官であるペトラを見つめた。正確に言えば彼女が持つランプの灯りを見つめている。
「果実、大きさ、ありません」
霧の向こうから片言で話す彼女はいつも誠実で、教えを乞う側を下に見ることがない。そこが彼女の持つ確かな知識と同じくらい素晴らしい点だ、とヒューベルトは評価している。そんな彼女の声は落胆していた。
つい先日まで目の前には赤い花が咲き乱れていた。芥子は花が枯れた後で結実し、その実を傷つけると白い乳液が滲み出す。その乳液はしばらく経つと粘性を示し色は黒く変化する。この黒くなった乳液を集めて乾かしたものが麻酔の原料となる生阿片だ。ひとつまみの生阿片を精製するのに花は百本近く必要になる。ブリギットでは一面の赤い芥子の花が季節の風物詩だ。世界中の痛みに苦しむ人々が赤い花にいくらでも金を払う。
「いいえ、結実しただけでも大したものです。ここは貴殿のお国の名産地と違って湿度が高い」
「ありがとう。しかし、種子、取れます。とても小さい、とても沢山、注意、必要です」
ダグザでは小さな物を表す時に〝芥子粒のような〟という言い回しを使うのだ、とヒューベルトの上司であるコンスタンツェが言っていた。種子を採取する時には取りこぼしがないよう、細心の注意を払う必要がある。芥子も大麻も国家が完全管理して栽培する予定なので間違いは許されない。そういった細かいことならば、と言って上司であり六大貴族に連なる名家出身のコンスタンツェがヒューベルトをこの計画の責任者に推薦した。
コンスタンツェに言わせれば医学と魔術は偉大なるヌーヴェル家の者によって融合を果たす筈だが、それには他人に任せねばならないことも多いらしい。
「ご安心ください。絶対にならずものたちの財源にはさせません」
ヒューベルトの家系は代々医療に携わる、と運命づけられている。ベレト王からベストラ家再興の許可が出た日に運命は決まった。現在はともかく当時は殆ど受け継ぐ地位も領地もなく、あるのは貴族の称号と王と対立した過去だけと言う虚しい状態だった家名に何故、先祖がこだわったのかがヒューベルトには理解できない。だが王はとても喜び、自分が喜んだことを記録に記せと命じたと聞く。
都合の良い逸話かと思いきや物好きな一族のものがガルグ=マク旧市街にある公文書館で確認したところ本当に事実として記されていた。王の心は広いにも程があるのではないだろうか。
「過去を気に病む必要はないが、どうしても気になるのならその分、他の誰かの命を救えば良い」
ベレト王はもっと広い意味を込めて先祖を激励した筈だが、とにかくベストラ家においてはそう言うことになったのだ。だが血筋のせいなのか黒魔法は使えても信仰魔法の才能が全くない。当時の世の中では分が悪かったが、信仰魔法を専門とする修道士ではなく医師や薬師になるしかなかった。
ベストラ家の人々は一族郎党で医学を志していくうちに、やがて医学研究における禁忌が少ない他国へ留学するようになった。他国で出版された医学書をフォドラ語に翻訳し、人体解剖実験に参加する。ヒューベルトも薬草について学ぶためにブリギットへ行ったことがあった。ベストラ家の人々は翻訳するだけでなく一族の者が他国で参加した様々な実験、特に解剖実験について本も書いた。
これらの医学書は統一王と呼ばれたベレトが印刷と出版を自由化しなければ、セイロス教の禁忌に触れていたため発禁となっていただろう。人体解剖を忌避する感覚は未だにフォドラでは色濃く残っている。
統一王に逆らった家系、というより現在では人の体を切り刻む家系という理由でヒューベルトの一族を嫌うものたちは多い。それでも彼の一族は効率良く人を救うことをまだ目指している。
「ならずもの、意味、何ですか?」
『ならずもの、です』
ヒューベルトがブリギット語で話すとペトラがため息をついた。言葉遣いに気をつけねばならない。彼がブリギット語を多少は理解できることが計画の責任者になれた理由のひとつだった。
「ヒューベルトと私、ブリギットではブリギット話す、フォドラではフォドラ語話す、約束です」
「申し訳ない。フォドラ語で単語の説明をすべきでした」
素直に謝るとヒューベルトも芥子の果実を検分し始めた。ペトラの指摘通り実が小さい。傷をつけてヘラを使い乳液を採取する方法では必要とする量を確保するために作付面積を倍にするか、新たな抽出方法を考える必要があった。頼りたくはないのだが、遠い祖先の残した恐ろしい記録に何か手掛かりがあるかもしれない。
───
目の霞んだ人々のうち殆どのものが最初の人々が作った武器を持つことが出来ない。無理に持つと獣に成り果ててしまうからだ。
獣に成り果てたものは討ち取られた。そうしなくてはその土地を滅ぼしてしまう。
たまに人の姿を保ったまま武器を持てるものが現れるとその人々を尊い、と言って崇めた。
───
今時は魔法職で募集をかける時に勤務先が地方では中々人が集まらない。石でも投げた方がまだ効き目のありそうな理学魔法しか使えない癖に自分が選ばれし二パーセントだと分かっているので皆、成功するために都会へ行ってしまう。
ガルグ=マク新市街にある衛生局はフォドラの医療全てを統括している。信仰魔法との縦割り行政が長年の問題だったが、目標が治癒であるならば方法論の違いで管轄を分けるべきではない。
医療行為は世俗のものだ、という主張にセイロス教会がついにおれて信仰魔法も衛生局の管轄となった。衛生局側がアドラステア帝国の頃より続き、一度はお取り潰しの目にあったものの不屈の闘志で再興を果たして六大貴族にその名を連ねる名家、ヌーヴェル家のものを局長にした時点でセイロス教会が譲歩するのは決まっていたのかもしれない。医学と魔道は互いに欠けたところを補いあって更に便利になるべきだ、と言うのが衛生局の局長コンスタンツェの主張だった。
そういった高尚な議論はさておき、人口あたりの医療従事者数が足りていないと言う現状を解決するにはレストを使える修道士か鎮痛剤や麻酔を使える医師がいればいい。
全人口のうち二パーセントしかいない魔法が使えるののうち、何割が修道士になってくれるのかを考えると医師の方がまだ人数を読みやすかった。修道士は軍に入ることも多いが医師は医師になるしかない。修道士による治療と比べた時に経費の高さは問題だが、それを解決するため衛生局は鎮痛剤と麻酔薬の国産化を目指している。
勤務先がオグマ山脈の魔獣が出没する山奥、と言うこともあって試験農場の警備責任者は中々見つからなかった。コンスタンツェが張った防御結界を現地で保守点検をするものを早急に見つけねばならない。試験農場で栽培するのは依存性が極めて高い麻薬の原料でもある。関わるのは最少人数にしたいが衛生局としてもヒューベルトにそこまでさせるわけにいかなかった。試験農場の内側だけでも大変なのだから。
今日もどうせ見つからないのだろう。結界に綻びが出てヒューベルトたちを困らせる前にフェルディア総合大学まで直接探しにいかねば、と思いながらコンスタンツェは最上階の窓から実技審査の様子を眺めた。局の中庭で黒手袋をして古びたフェルディア総合大学のマントを着た男が結界を張っている。男性の場合、髪を伸ばしておいた方が多少は魔力の足しになるのだが、鬱陶しさに負けて若草色の髪を短く切っている時点で見込みはないように思えた。
しかし彼は杭も紙も使わず反閇だけで空間を閉じている。結界に向けて試験官がバケツの水をぶちまけても水が通過していくだけで何も起きなかったが、試験官が投げ込んだ木材は粉々になった。網状に結界を貼ることによって雨は通し、魔獣や人は通過させない仕組みになっているらしい。
コンスタンツェは慌てて机に戻って採用通知を書くと窓を開けて改良したウインドの呪文を唱え、採用通知を試験官の胸元に送った。
書類が風に乗って不自然な最短距離で試験官の胸元に飛び込んでくる。その様子を見たベレトは思わず口笛を吹いた。開いた窓の奥に金髪の巻き毛に囲まれた懐かしい顔を見つけ、思わず笑顔になってしまう。血筋もあるだろうが本人の努力が素晴らしい。
身なりを整えたら局長室へ向かうよう試験官から言われたベレトがチラチラと横目で局内を窺うとどうやら手狭なようで、書類が溢れ出しそうになっている。レンズ研磨も良い仕事だったが久しぶりに田舎で体を動かしたい気分なのに書類仕事は嫌だった。
ノッカーで扉を叩くと奥から入るように、と懐かしい声がベレトに話しかけてきた。久しぶりに出会うコンスタンツェは心もふたつに割れておらず安定している。一族郎党が捨て石にされ、領地も爵位も取り上げられた状態から這い上がった前のコンスタンツェが何の不安もなく育ったらこんな感じになるのだろう。第一印象だけでいえば愛されて育ったコンスタンツェの孫娘に雰囲気が似ていた。
「今時はまともに魔法が使えるものが中々いませんが貴方は違いました。安心して私の防御結界を任せられますわ!詳細は今から口頭で説明するのでこの場で覚えて帰って頂戴。何ひとつ書き残してはなりません」
オグマ山脈の某高原にある試験農場で何を栽培し誰がいるのか。どのような防御結界を張っているのか。秘匿部署とはそうしたものなので、ベレトは淀みなくコンスタンツェの説明を全て復唱した。
「ではすぐに出発します」
「路銀なしには辛い距離よ。ある程度の経費は先に下で受け取っておきなさい。それと身辺調査はもう部下がしているでしょうから事細かには聞きません」
そう言うとコンスタンツェは一度口を閉じてベレトの顔をじっと見つめた。白い肌に若草色の髪と瞳、ヌーヴェル領にある本宅に飾ってある王と六大貴族達の姿を描いた絵にどことなく雰囲気が似ているような気がする。
「貴方ガルグ=マクは初めてかしら?」
ガルグ=マクで一世紀以上を過ごし新市街を作ったのは自分だが、こう言う時は真顔でごく一部だけを伝えるに限る。
「何度か来たことはあります」
コンスタンツェは新しい部下の言葉を聞き、素直に引き下がった。彼が身につけていたフェルディア総合大学のマントは古すぎる。古着屋で買い物をしたと言われればそれ以上返す言葉はない。だが彼の姿を見るうちにコンスタンツェはヌーヴェル家に伝わる御伽噺を思い出してしまった。この御伽噺はノアの紋章を隠していた時と同じく、世間に対して隠された状態で伝えられている。
───フォドラ最後の王はまだ生きてフォドラ中を彷徨っている。正体を隠し、剣が使えることを隠して民の中に紛れ込んで様々な仕事に就いて生活を楽しんでいる。だからもし王と出くわしたとしても深く追求してはならない───
ヌーヴェル家は昔から魔道学院、つまり現在のフェルディア総合大学と縁が深く、禁退出扱いの資料も読むことが出来る。コンスタンツェの祖母が言うには3世紀ほど前に魔道学院で働いていたアンヴァル出身のベレト=アイスナーと名乗る人物と二世紀前にデアドラ港で働いていたフェルディア出身のベレト=アイスナーと名乗る人物は限りなく王である可能性が高いらしい。では先ほどまで目の前にいた人物はどうだろうか?
コンスタンツェは手を叩いて秘書を呼び、お茶の用意をするように言った。秘書が選んで淹れたベルガモットティーに口を付け、満足げに微笑むとコンスタンツェは窓の外を眺めた。
「あれっ?今日のコニーなんだかとっても嬉しそうじゃん」
「そうね、ハピ。あなたの秘書としては本当に酷い言葉遣いも全く気にならないほど機嫌が良いわ。試験農場の警備責任者も決まったし、久しぶりに大好きなお祖母様のことを思い出したからかしら」
「ふーんそうなんだ。思い出してあげるのも供養だって言うよ。じゃあこれはコニーのおばあちゃんにね」
そう言うとハピはカップをもうひとつ出して紅茶を淹れた。
11.
───
一七九〇年
武器を持っただけで獣に成り果てるならば目が霞んだ人々は獣も同然だ。
獣たちは聖人たちという牧者に飼い慣らされる羊の様だった。自分たちは違う、最初の人々はその様に考えた。
───
石炭は十七世紀初頭の病禍で魔法を産業に活かせなくなるまで、鍛冶屋の補助燃料や一般家庭の暖炉くらいにしか使い道がなかった。だが今や石炭は黒魔法の代替品となった。石炭はアドラステア地方、特にヘヴリング領の根幹をなす資源となっている。
眷族たちは自然への影響を気にかけて化石燃料ではなく、魔法を社会が消費するエネルギーの根本に据えていたが、フォドラから魔法の力が失われてしまったためこの流れはもう止まらない。
炭鉱には様々な技術が集約される。坑道から排出された地下水を汲み上げるため釣瓶や水上輪が利用され、軌道で石炭が運び出された。軌道は最初トロッコや馬車鉄道が走っていたが、のちに蒸気機関車が走るようになる。石炭を乾留したコークスを使った製鉄法が開発されると一気に安価で良質な鉄が提供されるようになった。黒いダイアモンドの力を借りたフォドラは工業化の時代を迎えている。
フレスベルグ家はアドラステア帝国の帝位継承権と免税特権を放棄することと引き換えに伯爵家として再興をベレト統一王から許された。その代わりに納税の義務を負い、苦し紛れに様々なことを模索している。そのうちのひとつがフレスベルグ製作所だ。鉱山機械の修理点検製作を生業としている。
継承権を返上し再興が許されたのはファーガス神聖王国の王位継承権を持っていたブレーダッド家も同じだ。だがブレーダッド家は民に親しまれていたので再興も民から望まれたものだろう。
しかしフレスベルグ家はそうではない。何代か前の祖先は苦労した、とエーデルガルトは幼い頃から何度も聞かされている。それはそうだろう。そもそも何故再興を目指したのか全く分からない、と彼女は思っている。
今では単に爵位を持っているだけで、やっていることは商家とほとんど変わらない。エーデルガルトは絵を描くのが好きだったのでせめて製図を引け、と言われた。その結果、流れ流れて親族が経営するフレスベルグ製作所で技術者として働いている。
接待用に絵面を綺麗にしたいから、という訳で呼び出されたエーデルガルトは豊かな茶色の髪を結い上げ、作業着ではなくドレスを身につけている。ドレスと言っても補正下着を着る必要がない簡素なものだ。羽織る上着も腰までしかない。まるで男物のような丈が短いデザインだったが動きやすいので気に入っている。
エーデルガルトはフェルディナントの作った〝火力で揚水する機械〟の実演が上手くいくかどうか、唇を真一文字にして紺色の瞳で見つめていた。執政官の案内役をしているので目線を機械だけに向けるのはよくないと分かっていたが、どうしてもそらすことが出来ない。
フェルディナントはアミッド大河で行われた櫂を外側に付けた船の実演で失敗している。彼は錨用の水平回転巻き上げ装置を使って櫂が動くように改造した。装置は理論通りに動いたのだが、巻き上げ装置のバーを押して回る人々の姿が古代の船のようだと酷評されてしまったのだ。
彼が考案した装置を帆船に導入すれば無風状態の際、船内に人手さえあれば風が受けられる地点まで到達出来る。満帆にしている帆船より速度も出た。実用性を疑われてしまったため導入する造船会社は今も存在しない。
とにかく今度は失敗するわけにいかない。〝火力で揚水する機械〟試作機の不具合を修正するため、フェルディナントは髪を切る暇も髭を剃る暇もなかった。しかしガルグ=マクからやってくる執政官とその部下たちの前で身嗜みを整えないのは問題がある。周りからそう言われた彼は慌てて髭を剃り、真新しい白い襯衣を身につけた。伸びた橙色の髪は後ろで束ねて誤魔化している。
執政官の視察先にフレスベルグ製作所が選ばれたのはフェルディナントが六大貴族エーギル家の出身だからだ。執政官から久しぶりに顔が見たい、と言われたら誰も断ることはできない。
現在の執政官は久しぶりに六大貴族から選出された。ベルグリーズ家の出身で、偉大な先祖に肖るべくカスパルと名付けられた青年は紋章も魔法適性も持たないので科学技術に嫌悪感がない。彼が身びいきする人間ではないことは知れ渡っているので、彼が褒めればフェルディナントが特許を取得する予定の〝火力で揚水する機械〟を導入する鉱山が増えるだろう。フェルディナントはフレスベルグ製作所の期待を背負っていた。
懐かしく思うもの同士、視線だけで挨拶すると補助ボイラーと主ボイラーの水量を確かめたフェルディナントはいささか緊張した面持ちで火を入れて視察団に向かって機械の説明を始めた。
「容器の中の水を蒸気で押し出し、蒸気の凝縮を利用して生まれた真空を利用してここの地下水を汲みあげます」
「フェルディナント、念のために凝縮について説明しておかないと」
先に作った資料を執政官府へ提出できるような余裕があれば良かったが、それも無理だったのでぶっつけ本番だ。技術者同士では説明する必要のない単語でも、こういう場では置いていかれるものを出さないために噛み砕いておくべきだろう。そう考えたエーデルガルトはフェルディナントに助け舟を出した。
「ありがとう、エーデルガルト。その通りだ。凝縮とはこの場合、気体が液体になることを言います」
理解したかどうかフェルディナントが目線で問うと少なくとも執政官は肯いた。興味津々と言った目つきで実演を見ている。賑やかな音を立て機械が地下水を吸い上げ始めた。
「そうか!体積が減るから真空になるんだな!」
「その通りだカスパ……いや、執政官。この機会は原理も操作も単純です。吐出し弁が音を立て、吐出し管が熱くなれば蒸気の凝縮によって真空が作り出せたと分かります。あとはレバーで切り替えるだけで地下水を汲み上げられるようになります」
良いものを見せてもらった、勉強になったと喜ぶ執政官たちを見て失敗はなかったと確信し、関係者一同の頬が緩む。
「燃料は炭鉱ならその場で採れる訳だし効率がいいな。実際に運用するとまた不具合が出てくるのかもしれないがこれはすごい。なあ、フェルディナントこれは試作品なんだろ?」
「ああそうだ。君の前での動作確認に成功したから直ちに特許は申請するが、まだまだ改良の余地はたくさんあるのだ。さらに改良を加えてフォドラ中の鉱山にこの機械を売ってみせる」
フェルディナントは拳を握りしめ高らかにカスパルの前で誓った。
「はは!その意気だぜ。法改正して安全のために設置を義務付ける日も近いな」
そんな会話も交わされたが結論から言うといざ、使おうとするとフェルディナントが発明した装置は高い圧力が必要となった。そのままでは危険すぎて鉱山で使用することは出来ない。この機会はエーデルガルトによって跡形もないほど改良され、ようやく実用化された。しかし根本となった〝火力で揚水する〟というフェルディナントの発想がなければ、世界初の商業用蒸気機関は生まれなかっただろう。
のちにエネルギー革命が起き、燃料の主役が石炭から石油に転換された。アドラステア地方の炭鉱は時の流れに逆らえず次々と閉鎖された。しかしその時すでにフォドラ有数の総合電機メーカーとして成長していたフレスベルグ製作所が閉鎖された炭鉱を離職した人々の新たな職場となり、彼らは慣れ親しんだアドラステア地方から離散することなく生活が出来た。
こうしてフレスベルグ家は産業史にも名を残した。
───
一八一〇年
微生物が宇宙空間を移動する際にどのように移動したのかについてはいくつかの説がある。
恒星からの放射圧、すなわち光圧で宇宙空間を移動した、とする光パンスペルミア説では微生物が隕石などに付着せず微生物それ自体が宇宙空間を移動したと主張している。
───
レスター地方の山岳地帯、通称フォドラの喉元に山の民と呼ばれるクパーラという少数民族が住んでいる。独自の文化とセイロス教とは異なる信仰を持ち、フォドラが統一されるまでは幻と言われるほど排他的だった。しかし信教の自由が保証された今は違う。
工業化が一気に進んだフォドラだが、彼らの居留地だけは時が止まったかのような光景を見られる。そして彼らは流れ着いた異物であるベレトが一日につき二時間くらいしか起きていられない生活を何年か続けていても全く気にしない。親切なことに毎日誰かが食べ物と飲み物と着替えを用意してくれるので、無言のまま夢遊病患者の様に食べて身綺麗にしてまた眠る。
クパーラの人々だけが魔法適性者の割合を五パーセントのまま保持しているし、フォドラの西側では珍しくなった大紋章を継ぐものもいた。野生の飛竜もクパーラの固有種だけは個体数が減少していない。
ベレトはここで眠るとごく稀にだが、ソティスの夢を見ることが出来た。数世紀分の答え合わせをゆったりと夢の中でしている。ふわふわと宙を漂う緑色の髪の少女は眉間にしわを寄せて頬を膨らませた。
「おぬし!長いことわしを思い出しもせず薄情ではないか!」
「怒られるのが怖くて」
「怒らぬ!!」
ソティスは声を思い切り荒げていたが気が付いていない。
「俺はレアを困惑させるようなことしかしなかった。今もそうだが言われないことを察するのは無理だったから」
「娘も知らないことだらけで、言えることの方が少なかったのであろう」
これはソティスのいう通りで、確かにレアは母の若き日の姿を知らなかった。久しぶりに目にするソティスの姿は髪の色を除けばフレンよりも眷族としては幼く見える。当時、ベレトにまとわりついていたソティスの姿を正確に伝えてもレアが自分の母親だと分からなかったのは当たり前かもしれない。
「そうだな。俺もレアが大司教をしていたのと同じくらい長く王をやっていたら、わからないことだらけで言えないことばかりになっただろう」
夢の中は自由な筈なのにベレトとソティスは懐かしい寮の自室にいた。自由だからどんな場所でも選べた筈なのに。
「ガルグ=マクにいた小童どもとその子孫はよくやっておる」
「きちんと俺の代わりのものも魔法の代わりになるものも見つけた」
レアは長命である己自身を社会を安定させる礎にした。しかしベレトの教え子たちは家系や血筋ではなく執政官という役職を社会を安定させる礎にした。役職に就く者が存在すれば良いだけなので、代替わりしようと先代の執政官と血縁がなかろうと揺らがないのだ。魔法を失った時も白魔法の代わりに医学を発展させ、黒魔法の代わりに科学を発展させた。
「おぬしが人間どもを全く疑わず信じて手放せたからじゃ。わしらはどこか少しは疑っておったし手放せなかった。子離れができなかった」
「俺は人間だったからなあ。ところでソティス。俺はあと何年生きていられる?」
フレンですらどんなに短く見積もっても千年以上は生きていた。レアやセテスは何千年も生きていた筈だ。だがベレトは心臓に嵌められた紋章石とそこに宿ったソティスの意識によって生かされているだけだ。
「数千年生きるのが本来の寿命だが、おぬしは千年もつかどうか分からない。わしらからすれば哀れなことに髪が若草色のまま童のうちに死ぬのじゃ」
どうやら残り時間は二世紀くらいのようだった。その間、八時間睡眠で過ごせるなら充分な時間があると言える。
「そのうち何年を眠って過ごす?」
しかし今のように二時間しか起きていられないならば、ベレトは死ぬまでこの居住区で微睡んでいるしかない。
「起きていたければ夢も含めて紋章の力を使わぬように心掛けよ。わしはおぬしと最後まで共にあろうぞ」
寂しそうなソティスの言葉には心当たりがあった。クパーラの人々が暮らす居留地には魔獣が出る。その魔獣を駆除しようとして返り討ちにあっていたバルタザールを助けるため、ベレトは久しぶりに炎の紋章の力を使った。そして起きていられなくなった。
「おい、アンタ起きたいのか?」
夢の中では目を開けていたのに現実では瞼が重く、バルタザールのたてた物音や声に反応して微かに動くだけだ。横たわったまま強張っている手を顔に乗せて指で眉間を揉む。
「起きたい」
「わっ!久しぶりに声を聞いたぞ。忘れかけてたぜ」
バルタザールはクパーラの人々が暮らす居留地にあるカジノで警備員をしている。大した産業のないクパーラではカジノが大きな収入源で、少数民族の生活や文化を守る資金もそこから捻出されている。博打うちの財布がクパーラを守っていた。そしてバルタザール本人も博打うちなので、彼のささやかな薄い財布も居留地を守ることに貢献している。
「金がかかったろうにすまなかった」
「いや、長老たちからアンタの面倒を見てやれば借金の返済日を伸ばしてやると言われたんでな。それでどんな夢を見た」
クパーラの人々は夢を重要視していた。彼らの考えでは夢だけが時と場所を超え、分からなくなってしまった真実に直接触れることができる。
現に彼らの創世神話は今も書き加えられている。夢を見るたびに分からなくなってしまった真実に触れ、分からなかったことが明らかになるからだ。神話の謎に触れるような夢は強い夢、と呼ばれる。ガルグ=マクから来た学者たちは定期的にクパーラの神話を記録に残していた。
バルタザールが起きていられなくなったベレトを今時珍しく治癒魔法が使える呪い師のところに担ぎ込んでいる。身体を信仰魔法で癒してもらった後も起きていられないベレトを見た呪い師は夢を見なければならない、と告げた。余っている部屋をベレトが夢を見るために使っても構わない、と言う。
クパーラでは昔から、人生を問うような強い夢は呪い師の管理下で見る。呪い師に夢を勧められた、ということで居留地の人々は異常な眠り方をするベレトを自然に受け入れていた。
「夢の中で会いたかった人に長生きしたければもう夢を見るなと言われた」
ため息をついたベレトの若草色の瞳から涙が一粒こぼれ落ち、頬を滑り下りていく。
ソティスの夢はおそらく炎の紋章とベレトの心臓にはまっている紋章石が揃わなければ見られない夢だ。現在、ベレトの心臓はソティスの依代でもある紋章石によって動いている。
ソティスの亡骸から作られた紋章石はまずアガルタの民から武器の動力源として利用され、次にレアが作り上げた何体もの〝お母さまの容れ物〟を生かすことにも使われた。力尽きつつある紋章石に炎の紋章の力は強すぎるのだろう。
「命を削るくらい強い夢なんだろう。たまにそういう話を聞くぜ」
「いつ頃死ぬのかも教えてもらえた」
「不思議でもなんでもないさ。夢だけが時と場所を超えられるんだから」
クパーラ育ちのバルタザールはそういうと呪い師がベレトのために作った夢を呼ぶ呪符を壁から剥がした。捨てるのが面倒なのか、掌中にある丸めた紙をファイアーで燃やしている。今時、クパーラ以外の土地ではなかなか見られる光景ではない。畳む
「flow」第1部12.「化石燃料」
#完売本 #flow #シルヴァン #アッシュ #フェリクス #ディミトリ #ヒューベルト #リンハルト
12.
───
一八五〇年
隕石や彗星などに付着して微生物が宇宙空間を移動したと主張するのが隕石パンスペルミア説だ。
光パンスペルミア説と同じく、隕石パンスペルミア説も微生物は宇宙空間の超低温と大気圏突入時の熱に耐えなくてはならないが隕石深部の温度は上がらないのではないかと予想されている。
───
ファーガス地方では昔から燃える黒水が採れた。北の隣国スレンやパルミラでは薬品や灯り油として使う事もあるらしい。だがセイロス教会はこの黒水の使用を禁止していた。そもそもファーガス地方では灯りは昔から魚の油で灯しているので使い道もない。黒水が滲み出ている場所では勝手に火事が起きることも多く、ファーガスの人々は危険を感じて近寄らないようにしていた。
アドラステア地方にはフォドラ有数の穀倉地帯と良質な炭鉱がある。レスター地方では酪農や大国であるパルミラとの交易、それとレンズや時計をはじめとする精密機械工業が盛んだ。しかしファーガス地方は工業化に乗り遅れてしまい、ガルグ=マク司教座附属大学と並んでフォドラの最高峰と言われるフェルディア総合大学の学生たちも皆、就職の際にはファーガス地方から外へと出て行ってしまう。
暖炉にかけた鍋で一日かけて茹でたくず野菜と芋で腹が満たされればそれで幸せという素朴な時代は去り、ファーガス地方は強烈に外部へ訴えかける何かを欲していた。
ゴーティエ領にある森の中で狩りに来た若者たちが円座を組んで何やら話し込んでいる。鴨が何羽かと野兎数匹は既に夕食にするための処理を終えていた。今晩の食卓は肉づくしになるだろう。互いに誤射を避けるためか、フェルディア総合大学の象徴であるファーガスブルーのローブを身につけている。彼らは皆そこの学生だった。
「シルヴァン、今回はお招きいただきありがとうございます!」
「いや、聞かれたくない話は自然の中でするのが一番だからな」
そういうとシルヴァンは辺りに生えている木の枝を手持ちの鉈で落とし、焚き火用に積み上げ始めた。乾燥した枝でなければ火がつかないのは子供でも知っている。アッシュが怪訝な顔をしているとシルヴァンは取り出した瓶から生木に向けて黒水を注ぎ、ファイアーで点火した。彼等は今時珍しく魔法適性を持っているが魔道専攻ではない。シルヴァンは地理学、フェリクスは法学、アッシュは商学が専攻だった。黒水の匂いを嗅いだフェリクスはシルヴァンを睨み付け、なんと言葉をかけるべきか考え込んでいる。
「教会に見つかったらまずいですよ!」
「そうだなアッシュ。でも冷静になって考えて欲しいんだ。今のを見ただろう?石炭が出来ることはこいつにも出来る。石炭の役割って結局は物を燃やして熱くすることだろ?それに炎の色を見てくれ。すごく明るいんだ。ランプに使える」
「だが液体は運びにくい。樽が何万個もいるな」
フェリクスは幼馴染を怒鳴りつけず冷静に反論することにした。
「でも隧道を掘ったりしなくていいんだぜ?汲み取るだけで済む」
「井戸水とは訳が違う。こんな危険なもの、汲み取るには専用の機械が必要だろう」
「それは石炭も変わらないだろ?だから一旗挙げようと思ってな」
お前らも手伝って、というとシルヴァンは右手でフェリクスを、左手でアッシュを捕まえた。アッシュは固まってしまったがフェリクスは鬱陶しそうに肩にかけられたシルヴァンの手を外した。
「シルヴァン、まさか大学が休みの時に闇雲に掘り起こすつもりか?そんな博打に俺たちを巻き込まないでくれ」
「手伝うってのはそういうことじゃなくてディミトリの説得だ」
「えっ?!ディミトリに掘ってもらうんですか?確かに彼は怪力ですけど…」
「違う!業者はもう見つけてある!ブレーダッドの名前が欲しいんだ」
シルヴァンは本気で黒い水を武器に戦うつもりだった。黒水を石炭のように使ってもらえれば子供が寒い冬、遠くまで薪を拾いに行って風邪をひく必要もない。その辺の生木で充分だ。そして石炭と違い屋内が煤で汚れることもない。生活はがらりと変わるだろう。だがファーガスの人々は保守的だ。全く新しいことを始めるにあたって、唯一無二であるブレーダッド家の名がどうしても欲しい。ブレーダッド家の威光があれば人々もシルヴァンの言うことに耳を傾けてくれる。
「なるほど。それならアッシュが適任だ」
「フェリクスが説得して下さいよ!僕には無理です!」
「いや、アッシュの言葉ならディミトリも耳を傾けるだろう。シルヴァンの癖によく考えたな。ところで俺は何故この場に呼ばれたんだ」
「だって教えなかったら後で拗ねるだろう?」
ぬけぬけと語るシルヴァンの顎に一発決めてやろうと顔を赤くしたフェリクスが無言で拳を握った瞬間、鳥が一斉に飛び立った。何かが高速で回転して耳に響く。これまで聞いたことのない不愉快な音がして、まだシルヴァンに捕まえられているままのアッシュが両耳を塞ぐ。
「ああ、始まったな。掘削を請負ってくれる業者を紹介するよ。連れてくるからここで待っててくれ。元から待ち合わせをしてたんだ」
シルヴァンが騒音がする方へ向かっていったので、フェリクスとアッシュは焚き火の前に取り残されてしまった。
「統一前は教会に禁じられていた品で商売を始めるなんて、とシルヴァンが周りから怒られないか心配ですね」
「それを言ったら統一前は活版印刷も望遠鏡も禁じられていたんだぞ」
シルヴァンの夢は叶うのだろうか。フェリクスは瓶を手に取り底に溜まった黒い水をじっと見つめた。確かに生木なのによく燃えている。薪を集める生活は変えられないとしても、いざと言う時に便利なのは悪いことではない。
現在のフォドラに王はいない。フォドラ最後の王であるベレト統一王は統一後の混乱が収まるまでのわずかな期間だけだが、セイロス教会の大司教も兼ねていた。その数年の間に大司教の名の下に行動の自由を世俗に取り戻している。大司教位はすぐに他のものに譲ってしまったが。
彼が規制を撤廃してフォドラが得たものは印刷技術、医学、科学だ。女神の恩寵を受け百五十年の長きに渡り、若々しい姿のままフォドラを治めた彼は魔法や神秘の申し子と言える。だが現代から見てみれば魔法が失われることを予測していた、としか思えない。もしそうだとしたら、何故十二世紀生まれの人物にそんな未来が予測できたのだろう。
「ただ馬鹿どもを黙らせるために小手先の工夫は必要だろうな。蒸留して色を変えるとか。それには設備も金も必要になるな」
そう言うとフェリクスは鼻を鳴らして焚き火に手をかざした。ファーガス地方のゴーティエ領は気候区分で言えば寒帯で、夏でも寒さを感じる日が多い。
「シルヴァンは融資を受けるためにディミトリが必要なんでしょうけど、上手くいくんでしょうか?」
「アッシュまで巻き込んだのにディミトリすら説得できないなら、シルヴァンに勝ち目はない」
派手に枝を踏む音とシルヴァンが誰かと話す声が聞こえた。最短距離で移動したいのか鉈で道を作りながらやってきたのは、短く切った黒髪に若草色の目をした同年代の男だった。シルヴァンから何か聞かされたのか、フェリクスとアッシュを見て笑顔を浮かべている。
「黒髪の方がフェリクス、雀斑がある方がアッシュだ」
「シルヴァンの思いつきに付き合わされて気の毒なことだ」
「いや、興味深い試みなので声をかけてもらって光栄に思っている。ガルグ=マクから来たベレトだ」
フェリクスもアッシュも黒い長手袋を取って差し出された白い手の感触をずっと昔から知っているような気がした。
───
一八五五年
「たったひとつの種」を高度に進化した知的生命体が「生命の種子」として送り込んだ、と主張するのが意図的パンスペルミア説だ。
殆どの惑星はニッケルやクロムだらけでモリブデンは希少であるにもかかわらず、生物は必須微量元素としてモリブデンを必要とする。
これはモリブデンが豊富な惑星で生命が誕生した名残であり、そこから「生命の種子」が送り出された為あらゆる生物の遺伝暗号の仕組みが驚くほど似ているのではないか、と言われている。
───
ファーガス地方の農家は昔から染み出る黒い水のせいで、収穫間際の作物が汚染されることに悩んでいた。フォドラの地図記号には黒い水に汚染され、農地に適さない土地を表すものがある。この地図記号はほぼファーガス地方でしか使われない。
他の地方に塩水の湧泉があれば塩が作れる。しかしファーガスの場合、湧泉が黒い水に汚染されていて塩は作れない。塩水と黒水の割合によっては薬用になることも多く、パルミラなどでは肌に塗る薬用油として使う。だがセイロス教会に黒い水の利用を禁じられていたため、フォドラではこうした湧泉も長らく放置されていた。
このファーガス地方にとって悩みの種でしかない黒い水を灯り油や燃料にする───初めてシルヴァンから聞かされたディミトリは混乱して、三回も同じ話をさせてしまった。その時、その場にいたアッシュもシルヴァンもこれは拙いな、という顔をしていた。
地表に染み出る黒い水の大元は地下にある。そこから安定して抽出するための井戸と黒い水を蒸留し、灯り油や燃料にするための製油所を作るには資金が無限に必要だ。シルヴァンはファーガス一の名家ブレーダッドの名さえあればあとは自分が探す、と言っていた。しかしディミトリはどうしても、誰からなんと言われようと彼の役に立ちたくて、自分の自由になる分だけではあったが資金を提供した。
五年たった今、思い返してみればあれは混乱していたわけではない。ディミトリはシルヴァンの豊かな発想に深く、とても深く感動しただけなのだ。
ゴーティエ領で採取、蒸留された灯り油と燃料は今のところ、ファーガス地方で忌避感なく使用されている。ブレーダッドオイルは創業5周年を迎えフェルディアに支社を作りそこを足場に、今後は首都ガルグ=マクやレスター、アドラステアへも売り込む予定だ。将来はもしかしたらパルミラやダグザなど海外へ販路を広げる日が来るかもしれない。
出来たばかりのフェルディア支社で、創業五周年を祝う祝賀会が行われた。関係者だけのささやかなものだったが皆、これまでにないほど満ち足りている。ディミトリ、ベレト、シルヴァン、フェリクス、アッシュの五人はなんだか離れ難く、残った酒で飲み直しをすることにしたのが数時間前の話だ。
明け方になりシルヴァン、フェリクス、アッシュの三人は酔い潰れて床に転がっている。結局フェリクスもアッシュもシルヴァンの起業に巻き込まれ、法務だ会計だと毎日忙しい日々を過ごしていた。ディミトリだけがブレーダッド家当主としてイーハをはじめとする領地を経営せねばならないため、ブレーダッドオイルを本業としていないことを少し寂しく感じている。彼らと職場が同じなら、うんざりするようなことがあってもきっと耐えられるだろう。
ディミトリも深酒が過ぎて着席したまま眠っていたのだが、物音で目が覚めてしまった。目覚めたことを後悔したくなるほど頭が痛い。
迎え酒になるものが欲しい。夜が白んでいく中で室内を見回すと立役者の一人であるベレトがブレーダッドオイルの商号を膝の上に乗せて静かに一人泣いている姿が目に入った。先ほどの物音は会場に飾った商号が落ちたか、それを彼が受け止めた音なのだろう。
「どうした、悲しいことでもあったのか?」
酔いが顔色に現れやすいディミトリは頬を赤く染めたままベレトに話しかけた。ベレトのそばにはいつもシルヴァンたちがいるので、ディミトリが彼とゆっくり二人きりで話すのはこれが初めてかもしれない。
「感動しているんだ。俺はこの商号を見るといつも感動して涙が出そうになる。酒が入ったからもう我慢できない」
ベレトは酔いがあまり顔色に出ないらしく、白い顔をしたまま若草色の瞳に涙をためて嵌めたままの黒手袋で目を擦っていた。
「何を言っているのかわからない」
横を向いた青い獅子が赤い炎を吐いているブレーダッドオイルの商号は確か、シルヴァンが金策でデアドラへ赴いた際に出会った画家に考えてもらったものだ。ファーガス地方の象徴である青獅子と灯り油に灯る炎を組み合わせている。ブレーダッドオイルがどの土地の企業で、何を扱っているのか見た瞬間にわかるよう工夫されていた。
頭の中で鐘が鳴り響くような頭痛のせいで、ディミトリはベレトの話がうまく聞き取れない。迎え酒にテーブルに残っていた誰かの飲み残しのワインを煽ったディミトリは酔っ払って泣いているベレトの言葉に再び耳を傾けた。
「ファーガスにしかないものがようやく見つかった。俺には見つけられなかったのに」
「何を言っているのかわからない。黒い水を見つけて井戸を掘ったのはお前だろう」
「シルヴァンに言われなければ掘らなかった」
「依頼がなければ掘らないのでは?」
「ではやはりシルヴァンはすごい」
ディミトリはアルコールに支配された頭で必死にベレトの言葉を理解しようとしたが上手くいかない。以前シルヴァンから聞いた、実際には目にしたことのない光景ばかりが脳裏に浮かぶ。
フェルディアにはないのだが、そしてそれがフェルディアが旧ファーガス神聖王国の首都に選ばれた理由のひとつだと今なら分かるのだが───ファーガス地方には昔から黒い水の浸み出し口がいくつもある。シルヴァンとベレトは丹念に自作の地図に浸み出し口を描き込み、周辺の土を調べて掘削する場所を決めた。
浸み出し口に現地で雇った人足たちにある程度の深さの穴を掘らせると、ベレトは先に溝が彫ってある杭を何本か差し込むのだという。手袋を外し、それらの杭に彼が指で術式を描いてウインドを発動すると螺旋状に動く風が発生する。
勝手に杭が回転し耳の奥に響くような轟音を立て、地中深くまで掘り進んでいくのだ。魔法の発動中はその場を離れられないので、効率が悪いものの蒸気機関を利用した掘削機と同じ量の作業を身ひとつでやってのけるベレトにシルヴァンは深く感謝した。
この祝賀会で彼はベレトにブレーダッドオイルの株を五株贈呈している。まだ配当金は少額だがいずれ指一本動かさずとも生活に困らない程度にはしてみせる、とシルヴァンはそう宣言していた。
ディミトリは魔道研究の本場フェルディア生まれのフェルディア育ちだ。シルヴァン、フェリクス、アッシュも魔法適性があり、フェルディア総合大学の学生である以上魔法は身近で慣れている。
だがベレトは格が違うのだ、といつだったかシルヴァンが興奮して話してくれた。フォドラの人々から魔法の力が失われる前の大魔道士のようだと言う。ベレトは身体から発する魔力の扱いに気を使っているらしい。彼の白い手を見たのは初対面の握手をした時だけで、それ以外ではいつも黒い手袋をしていた。
「いつか採掘作業を見に行ってもいいか?」
「いつでも歓迎する。試掘の手伝いができるように汚れても構わない服で来てくれ」
「鍬を壊さないように気をつけないとな。ブレーダッドの小紋章持ちなんだ」
日の出の暖かい光に照らされながら、ベレトと冗談を交わしたことをディミトリは何故かシルヴァンに話せなかった。いつもベレトを独占していたシルヴァンへの細やかな対抗心だったのかもしれない。
───
一九〇〇年
神祖は知恵をつけたという理由で最初の人々を冥界に追いやった。聖人たちは次の人々の目を霞ませて獣にした。
ヒトに知恵も永遠の命も与えるつもりがなく罰してばかりの神祖は聖人たちは聖なる存在として本当に崇めるべきなのだろうか。彼らの作った教会は伽藍堂に過ぎないのではないだろうか。
───
石炭が多く使われると燃やした時に発生するガスで空気が汚染される。ガルグ=マク、アンヴァル、フェルディア、それにデアドラ等の大都市では大気汚染が深刻だ。この件に関してセイロス教会ガルグ=マク司教座がこのまま石炭を使い続ければ、健康被害が理由で死ぬ者が更に増加するのだから便利さに耽溺せず禁欲的に生活せよ、との声明を発表した。
何にでも代替品は出てくるもので今後は燃やしても煤が出ないファーガス産の黒い水が石炭の代わりに使われるのだろう、と皆なんとなく考えている。それなら皆少し面倒に感じるだけで何とも思わないのだ。政府が法律で煤の出る燃料を規制すれば、煤が出ない燃料に需要が生まれる。そこに経済効果が生まれるのならば商人たちは全力を出す。
だがガルグ=マク旧市街の宗教家たちが出した要求には裏がある。それを感じ取った者たちは密かに強く警戒した。彼らは産業の時代から魔法の時代に立ち帰れと言っている。人々や社会から魔法の力が失われて久しい。
燃料を魔法に戻したら食い扶持が稼げず死ぬものが出てくるのにそれについては言及しない。皆聞き流し、この場では黒い水に切り替えるだけだろう。しかしこの手の手続きを考えない、考えさせない司教座の無責任さには問題がある。それともわざとなのか。
リンハルトは老眼鏡をかけ、何度読んだかわからない声明文をまた読み返した。ため息も何度吐いたかわからない。概要だけならば普通のことしか主張していない。そんな見かけが彼に更なる憂いを抱かせる
ヘヴリング領の経済は炭鉱にそこまで依存していない。だが生活は石炭に依存している。医療も信仰魔法ではなく殆ど医学によって提供されており、生活を改変しろと言われても困ることばかりだ。
ヘヴリング家の上屋敷があるハイストリートと司教座のある旧市街は大して離れていない。だがリンハルトには別の国のように感じられる。これからやってくる年若い客人も旧市街とは別の国の住人だ。リンハルトは客人のため、テフを用意するように執事に命じた。
黒衣に身を包んだ医師が召使に連れられ、リンハルトが待つ応接間に現れた。テーブルにバックギャモンのボードが開いてあるのを見た客人が微かに笑う。パルミラから輸入されたもので、近頃は老若男女を問わず流行っている。
「お招きいただきましてありがとうございます」
「僕と勝負できるのはヒューベルトくらいだからね。たまには赤でやってみない?」
ヒューベルトとリンハルトは対外的には診察のついでにバックギャモンで遊ぶ仲間、ということになっている。含みを持たせた仲であると理解しているのは同じく旧市街の干渉を嫌う極少数のものたちだけだ。
「いつも通り黒でお願いします」
互いにダイスを振って先手を決める。今日はリンハルトの方が大きい目が出たので先手となった。これはそのまま先手の出目としても使われる。執事が持ってきたテフを飲みながら遊ぶ、歳の離れた二人の姿は意外に穏やかだ。
「頼んでいたこと、調べてくれたかな」
「ある程度は。ガルグ=マク司教座で働く彼の地出身者のほとんどがキッホルとセスリーンの紋章を持っていました」
ヒューベルトの報告を受け、リンハルトはため息をついた。あの土地の領主が十傑の子孫ではないことは既に判明している。
「あの土地で血を与えたキッホルとセスリーンゆかりの聖人がいるんだろうなあ」
次にヒューベルトがダイスを振り、リンハルトの駒に邪魔される前に駒を進めた。
「確かに古代から中世にかけて、聖人たちが人の命を助けるために血を分け与えた例は枚挙にいとまがありません」
「だが集落丸ごとなんて、いくら頑丈な聖人でも血を失いすぎて死んでしまう」
「貴殿はいつ為されたとお考えですか?」
「古代や中世なら自慢して回るはずさ」
リンハルトの言葉に首肯したヒューベルトはすっかり冷めてしまったテフに口をつけた。当時の基準からしても、紋章が発現するほど沢山の血を与えられるのは特別なことだ。
「でも当時は他の土地から妬まれるような幸運だったから隠したんだ」
人間社会から魔力が失われた病禍の時期に、自らの命と引き換えにしてでも集落の命を救ってくれるような聖人と出会う幸運など滅多にあることではない。ベレト統一王の治世から三世紀ほどで制度は疲弊し、セイロス教原理主義派による異端者狩りがフォドラ全土を席巻した。病禍は互いに互いを疑う地獄のような状況で発生している。
「当時あの地域で起きたことは私も奇跡だと思います。うかつに言って回れば貴殿のおっしゃる通り、異端者狩りの対象になった可能性は高いですな」
病禍に苦しむ片田舎に偶然、血を分けてくれる聖人が現れる確率は限りなく低い。そもそも統一戦争の時点ですら、明確にナバテアの民であったと言えるのは三名だけだ。当時の大司教レアとその部下セテス、それに彼の妹でアガルタの民から血を狙われていたフレンしかいない。争いに巻き込まれることを避けて出自を隠しているものがいた可能性は否定できないが。
リンハルトの振ったダイスがゾロ目を出したのでヒューベルトの駒は弾き出され、バーに置かれることとなった。
「異端者狩りの理由も嫉妬だからね。生存戦略としては正しいし、それが強烈な成功体験になったんだろう」
だが正体を明かさず、真の目的を隠して目標を達成しようとする態度は誠実ではないとリンハルトは思う。
「聖人の血で強化された人々は当時の疲弊したフォドラにおいては珍しい、活力に溢れる有能な存在です。自然と推挙されてガルグ=マクで学んだり働いたりすることになったのでしょう」
「司教座附属の学校はキッホルとセスリーンが守護聖人だしね。彼らからしてみれば天啓だ。中々説得されない僕のことも女神から与えられた試練だと思っているね、きっと」
彼らは同じセスリーンの紋章を受け継ぎ、信仰魔法を得意とするリンハルトに親近感を持っている。だから彼らは自分たちが考える正しき道へリンハルトを誘導しようとするのだ。しかしリンハルトは彼らと正しさが共有出来ない。
「ヘヴリング家が加われば彼らにとって千人力なのは確かです。名門ですし、貴殿のような筋金入りの合理主義者が説得されたとなれば他のものにも揺さぶりをかけられる」
ダイスを振ったヒューベルトは素早く、バーの上にある自分の駒を元に戻した。互いの駒は行ったり来たりを繰り返していて、なかなかゴールしない。
「今も秘密にするのは呪術的な理由があるのかな?」
「それは私の専門外です」
ヒューベルトの駒はリンハルトの陣の中で逆転勝ちを狙い、乗るかそるかの勝負に出ていた。妻も小さな子供もいるような若者がこんなことをするのはゲームの中だけにしなくてはならない。
「君のご先祖は詳しそうだけどね。ヒューベルト、今後は僕が調べ物をするよ。君はご家族のためにも長生きしないと」
そう宣言したリンハルトは年老いて髪は白くなり、杖なしに歩けない。それでも知性の宿った瞳の色は失われていなかった。尊敬する年長者に言われて引き下がるしかなかったヒューベルトがリンハルトの葬儀に出席したのはこの翌年のことだった。彼の葬儀の場でヒューベルトだけが、リンハルトの死が不自然に早められたものであると分かっていた。畳む
#完売本 #flow #シルヴァン #アッシュ #フェリクス #ディミトリ #ヒューベルト #リンハルト
12.
───
一八五〇年
隕石や彗星などに付着して微生物が宇宙空間を移動したと主張するのが隕石パンスペルミア説だ。
光パンスペルミア説と同じく、隕石パンスペルミア説も微生物は宇宙空間の超低温と大気圏突入時の熱に耐えなくてはならないが隕石深部の温度は上がらないのではないかと予想されている。
───
ファーガス地方では昔から燃える黒水が採れた。北の隣国スレンやパルミラでは薬品や灯り油として使う事もあるらしい。だがセイロス教会はこの黒水の使用を禁止していた。そもそもファーガス地方では灯りは昔から魚の油で灯しているので使い道もない。黒水が滲み出ている場所では勝手に火事が起きることも多く、ファーガスの人々は危険を感じて近寄らないようにしていた。
アドラステア地方にはフォドラ有数の穀倉地帯と良質な炭鉱がある。レスター地方では酪農や大国であるパルミラとの交易、それとレンズや時計をはじめとする精密機械工業が盛んだ。しかしファーガス地方は工業化に乗り遅れてしまい、ガルグ=マク司教座附属大学と並んでフォドラの最高峰と言われるフェルディア総合大学の学生たちも皆、就職の際にはファーガス地方から外へと出て行ってしまう。
暖炉にかけた鍋で一日かけて茹でたくず野菜と芋で腹が満たされればそれで幸せという素朴な時代は去り、ファーガス地方は強烈に外部へ訴えかける何かを欲していた。
ゴーティエ領にある森の中で狩りに来た若者たちが円座を組んで何やら話し込んでいる。鴨が何羽かと野兎数匹は既に夕食にするための処理を終えていた。今晩の食卓は肉づくしになるだろう。互いに誤射を避けるためか、フェルディア総合大学の象徴であるファーガスブルーのローブを身につけている。彼らは皆そこの学生だった。
「シルヴァン、今回はお招きいただきありがとうございます!」
「いや、聞かれたくない話は自然の中でするのが一番だからな」
そういうとシルヴァンは辺りに生えている木の枝を手持ちの鉈で落とし、焚き火用に積み上げ始めた。乾燥した枝でなければ火がつかないのは子供でも知っている。アッシュが怪訝な顔をしているとシルヴァンは取り出した瓶から生木に向けて黒水を注ぎ、ファイアーで点火した。彼等は今時珍しく魔法適性を持っているが魔道専攻ではない。シルヴァンは地理学、フェリクスは法学、アッシュは商学が専攻だった。黒水の匂いを嗅いだフェリクスはシルヴァンを睨み付け、なんと言葉をかけるべきか考え込んでいる。
「教会に見つかったらまずいですよ!」
「そうだなアッシュ。でも冷静になって考えて欲しいんだ。今のを見ただろう?石炭が出来ることはこいつにも出来る。石炭の役割って結局は物を燃やして熱くすることだろ?それに炎の色を見てくれ。すごく明るいんだ。ランプに使える」
「だが液体は運びにくい。樽が何万個もいるな」
フェリクスは幼馴染を怒鳴りつけず冷静に反論することにした。
「でも隧道を掘ったりしなくていいんだぜ?汲み取るだけで済む」
「井戸水とは訳が違う。こんな危険なもの、汲み取るには専用の機械が必要だろう」
「それは石炭も変わらないだろ?だから一旗挙げようと思ってな」
お前らも手伝って、というとシルヴァンは右手でフェリクスを、左手でアッシュを捕まえた。アッシュは固まってしまったがフェリクスは鬱陶しそうに肩にかけられたシルヴァンの手を外した。
「シルヴァン、まさか大学が休みの時に闇雲に掘り起こすつもりか?そんな博打に俺たちを巻き込まないでくれ」
「手伝うってのはそういうことじゃなくてディミトリの説得だ」
「えっ?!ディミトリに掘ってもらうんですか?確かに彼は怪力ですけど…」
「違う!業者はもう見つけてある!ブレーダッドの名前が欲しいんだ」
シルヴァンは本気で黒い水を武器に戦うつもりだった。黒水を石炭のように使ってもらえれば子供が寒い冬、遠くまで薪を拾いに行って風邪をひく必要もない。その辺の生木で充分だ。そして石炭と違い屋内が煤で汚れることもない。生活はがらりと変わるだろう。だがファーガスの人々は保守的だ。全く新しいことを始めるにあたって、唯一無二であるブレーダッド家の名がどうしても欲しい。ブレーダッド家の威光があれば人々もシルヴァンの言うことに耳を傾けてくれる。
「なるほど。それならアッシュが適任だ」
「フェリクスが説得して下さいよ!僕には無理です!」
「いや、アッシュの言葉ならディミトリも耳を傾けるだろう。シルヴァンの癖によく考えたな。ところで俺は何故この場に呼ばれたんだ」
「だって教えなかったら後で拗ねるだろう?」
ぬけぬけと語るシルヴァンの顎に一発決めてやろうと顔を赤くしたフェリクスが無言で拳を握った瞬間、鳥が一斉に飛び立った。何かが高速で回転して耳に響く。これまで聞いたことのない不愉快な音がして、まだシルヴァンに捕まえられているままのアッシュが両耳を塞ぐ。
「ああ、始まったな。掘削を請負ってくれる業者を紹介するよ。連れてくるからここで待っててくれ。元から待ち合わせをしてたんだ」
シルヴァンが騒音がする方へ向かっていったので、フェリクスとアッシュは焚き火の前に取り残されてしまった。
「統一前は教会に禁じられていた品で商売を始めるなんて、とシルヴァンが周りから怒られないか心配ですね」
「それを言ったら統一前は活版印刷も望遠鏡も禁じられていたんだぞ」
シルヴァンの夢は叶うのだろうか。フェリクスは瓶を手に取り底に溜まった黒い水をじっと見つめた。確かに生木なのによく燃えている。薪を集める生活は変えられないとしても、いざと言う時に便利なのは悪いことではない。
現在のフォドラに王はいない。フォドラ最後の王であるベレト統一王は統一後の混乱が収まるまでのわずかな期間だけだが、セイロス教会の大司教も兼ねていた。その数年の間に大司教の名の下に行動の自由を世俗に取り戻している。大司教位はすぐに他のものに譲ってしまったが。
彼が規制を撤廃してフォドラが得たものは印刷技術、医学、科学だ。女神の恩寵を受け百五十年の長きに渡り、若々しい姿のままフォドラを治めた彼は魔法や神秘の申し子と言える。だが現代から見てみれば魔法が失われることを予測していた、としか思えない。もしそうだとしたら、何故十二世紀生まれの人物にそんな未来が予測できたのだろう。
「ただ馬鹿どもを黙らせるために小手先の工夫は必要だろうな。蒸留して色を変えるとか。それには設備も金も必要になるな」
そう言うとフェリクスは鼻を鳴らして焚き火に手をかざした。ファーガス地方のゴーティエ領は気候区分で言えば寒帯で、夏でも寒さを感じる日が多い。
「シルヴァンは融資を受けるためにディミトリが必要なんでしょうけど、上手くいくんでしょうか?」
「アッシュまで巻き込んだのにディミトリすら説得できないなら、シルヴァンに勝ち目はない」
派手に枝を踏む音とシルヴァンが誰かと話す声が聞こえた。最短距離で移動したいのか鉈で道を作りながらやってきたのは、短く切った黒髪に若草色の目をした同年代の男だった。シルヴァンから何か聞かされたのか、フェリクスとアッシュを見て笑顔を浮かべている。
「黒髪の方がフェリクス、雀斑がある方がアッシュだ」
「シルヴァンの思いつきに付き合わされて気の毒なことだ」
「いや、興味深い試みなので声をかけてもらって光栄に思っている。ガルグ=マクから来たベレトだ」
フェリクスもアッシュも黒い長手袋を取って差し出された白い手の感触をずっと昔から知っているような気がした。
───
一八五五年
「たったひとつの種」を高度に進化した知的生命体が「生命の種子」として送り込んだ、と主張するのが意図的パンスペルミア説だ。
殆どの惑星はニッケルやクロムだらけでモリブデンは希少であるにもかかわらず、生物は必須微量元素としてモリブデンを必要とする。
これはモリブデンが豊富な惑星で生命が誕生した名残であり、そこから「生命の種子」が送り出された為あらゆる生物の遺伝暗号の仕組みが驚くほど似ているのではないか、と言われている。
───
ファーガス地方の農家は昔から染み出る黒い水のせいで、収穫間際の作物が汚染されることに悩んでいた。フォドラの地図記号には黒い水に汚染され、農地に適さない土地を表すものがある。この地図記号はほぼファーガス地方でしか使われない。
他の地方に塩水の湧泉があれば塩が作れる。しかしファーガスの場合、湧泉が黒い水に汚染されていて塩は作れない。塩水と黒水の割合によっては薬用になることも多く、パルミラなどでは肌に塗る薬用油として使う。だがセイロス教会に黒い水の利用を禁じられていたため、フォドラではこうした湧泉も長らく放置されていた。
このファーガス地方にとって悩みの種でしかない黒い水を灯り油や燃料にする───初めてシルヴァンから聞かされたディミトリは混乱して、三回も同じ話をさせてしまった。その時、その場にいたアッシュもシルヴァンもこれは拙いな、という顔をしていた。
地表に染み出る黒い水の大元は地下にある。そこから安定して抽出するための井戸と黒い水を蒸留し、灯り油や燃料にするための製油所を作るには資金が無限に必要だ。シルヴァンはファーガス一の名家ブレーダッドの名さえあればあとは自分が探す、と言っていた。しかしディミトリはどうしても、誰からなんと言われようと彼の役に立ちたくて、自分の自由になる分だけではあったが資金を提供した。
五年たった今、思い返してみればあれは混乱していたわけではない。ディミトリはシルヴァンの豊かな発想に深く、とても深く感動しただけなのだ。
ゴーティエ領で採取、蒸留された灯り油と燃料は今のところ、ファーガス地方で忌避感なく使用されている。ブレーダッドオイルは創業5周年を迎えフェルディアに支社を作りそこを足場に、今後は首都ガルグ=マクやレスター、アドラステアへも売り込む予定だ。将来はもしかしたらパルミラやダグザなど海外へ販路を広げる日が来るかもしれない。
出来たばかりのフェルディア支社で、創業五周年を祝う祝賀会が行われた。関係者だけのささやかなものだったが皆、これまでにないほど満ち足りている。ディミトリ、ベレト、シルヴァン、フェリクス、アッシュの五人はなんだか離れ難く、残った酒で飲み直しをすることにしたのが数時間前の話だ。
明け方になりシルヴァン、フェリクス、アッシュの三人は酔い潰れて床に転がっている。結局フェリクスもアッシュもシルヴァンの起業に巻き込まれ、法務だ会計だと毎日忙しい日々を過ごしていた。ディミトリだけがブレーダッド家当主としてイーハをはじめとする領地を経営せねばならないため、ブレーダッドオイルを本業としていないことを少し寂しく感じている。彼らと職場が同じなら、うんざりするようなことがあってもきっと耐えられるだろう。
ディミトリも深酒が過ぎて着席したまま眠っていたのだが、物音で目が覚めてしまった。目覚めたことを後悔したくなるほど頭が痛い。
迎え酒になるものが欲しい。夜が白んでいく中で室内を見回すと立役者の一人であるベレトがブレーダッドオイルの商号を膝の上に乗せて静かに一人泣いている姿が目に入った。先ほどの物音は会場に飾った商号が落ちたか、それを彼が受け止めた音なのだろう。
「どうした、悲しいことでもあったのか?」
酔いが顔色に現れやすいディミトリは頬を赤く染めたままベレトに話しかけた。ベレトのそばにはいつもシルヴァンたちがいるので、ディミトリが彼とゆっくり二人きりで話すのはこれが初めてかもしれない。
「感動しているんだ。俺はこの商号を見るといつも感動して涙が出そうになる。酒が入ったからもう我慢できない」
ベレトは酔いがあまり顔色に出ないらしく、白い顔をしたまま若草色の瞳に涙をためて嵌めたままの黒手袋で目を擦っていた。
「何を言っているのかわからない」
横を向いた青い獅子が赤い炎を吐いているブレーダッドオイルの商号は確か、シルヴァンが金策でデアドラへ赴いた際に出会った画家に考えてもらったものだ。ファーガス地方の象徴である青獅子と灯り油に灯る炎を組み合わせている。ブレーダッドオイルがどの土地の企業で、何を扱っているのか見た瞬間にわかるよう工夫されていた。
頭の中で鐘が鳴り響くような頭痛のせいで、ディミトリはベレトの話がうまく聞き取れない。迎え酒にテーブルに残っていた誰かの飲み残しのワインを煽ったディミトリは酔っ払って泣いているベレトの言葉に再び耳を傾けた。
「ファーガスにしかないものがようやく見つかった。俺には見つけられなかったのに」
「何を言っているのかわからない。黒い水を見つけて井戸を掘ったのはお前だろう」
「シルヴァンに言われなければ掘らなかった」
「依頼がなければ掘らないのでは?」
「ではやはりシルヴァンはすごい」
ディミトリはアルコールに支配された頭で必死にベレトの言葉を理解しようとしたが上手くいかない。以前シルヴァンから聞いた、実際には目にしたことのない光景ばかりが脳裏に浮かぶ。
フェルディアにはないのだが、そしてそれがフェルディアが旧ファーガス神聖王国の首都に選ばれた理由のひとつだと今なら分かるのだが───ファーガス地方には昔から黒い水の浸み出し口がいくつもある。シルヴァンとベレトは丹念に自作の地図に浸み出し口を描き込み、周辺の土を調べて掘削する場所を決めた。
浸み出し口に現地で雇った人足たちにある程度の深さの穴を掘らせると、ベレトは先に溝が彫ってある杭を何本か差し込むのだという。手袋を外し、それらの杭に彼が指で術式を描いてウインドを発動すると螺旋状に動く風が発生する。
勝手に杭が回転し耳の奥に響くような轟音を立て、地中深くまで掘り進んでいくのだ。魔法の発動中はその場を離れられないので、効率が悪いものの蒸気機関を利用した掘削機と同じ量の作業を身ひとつでやってのけるベレトにシルヴァンは深く感謝した。
この祝賀会で彼はベレトにブレーダッドオイルの株を五株贈呈している。まだ配当金は少額だがいずれ指一本動かさずとも生活に困らない程度にはしてみせる、とシルヴァンはそう宣言していた。
ディミトリは魔道研究の本場フェルディア生まれのフェルディア育ちだ。シルヴァン、フェリクス、アッシュも魔法適性があり、フェルディア総合大学の学生である以上魔法は身近で慣れている。
だがベレトは格が違うのだ、といつだったかシルヴァンが興奮して話してくれた。フォドラの人々から魔法の力が失われる前の大魔道士のようだと言う。ベレトは身体から発する魔力の扱いに気を使っているらしい。彼の白い手を見たのは初対面の握手をした時だけで、それ以外ではいつも黒い手袋をしていた。
「いつか採掘作業を見に行ってもいいか?」
「いつでも歓迎する。試掘の手伝いができるように汚れても構わない服で来てくれ」
「鍬を壊さないように気をつけないとな。ブレーダッドの小紋章持ちなんだ」
日の出の暖かい光に照らされながら、ベレトと冗談を交わしたことをディミトリは何故かシルヴァンに話せなかった。いつもベレトを独占していたシルヴァンへの細やかな対抗心だったのかもしれない。
───
一九〇〇年
神祖は知恵をつけたという理由で最初の人々を冥界に追いやった。聖人たちは次の人々の目を霞ませて獣にした。
ヒトに知恵も永遠の命も与えるつもりがなく罰してばかりの神祖は聖人たちは聖なる存在として本当に崇めるべきなのだろうか。彼らの作った教会は伽藍堂に過ぎないのではないだろうか。
───
石炭が多く使われると燃やした時に発生するガスで空気が汚染される。ガルグ=マク、アンヴァル、フェルディア、それにデアドラ等の大都市では大気汚染が深刻だ。この件に関してセイロス教会ガルグ=マク司教座がこのまま石炭を使い続ければ、健康被害が理由で死ぬ者が更に増加するのだから便利さに耽溺せず禁欲的に生活せよ、との声明を発表した。
何にでも代替品は出てくるもので今後は燃やしても煤が出ないファーガス産の黒い水が石炭の代わりに使われるのだろう、と皆なんとなく考えている。それなら皆少し面倒に感じるだけで何とも思わないのだ。政府が法律で煤の出る燃料を規制すれば、煤が出ない燃料に需要が生まれる。そこに経済効果が生まれるのならば商人たちは全力を出す。
だがガルグ=マク旧市街の宗教家たちが出した要求には裏がある。それを感じ取った者たちは密かに強く警戒した。彼らは産業の時代から魔法の時代に立ち帰れと言っている。人々や社会から魔法の力が失われて久しい。
燃料を魔法に戻したら食い扶持が稼げず死ぬものが出てくるのにそれについては言及しない。皆聞き流し、この場では黒い水に切り替えるだけだろう。しかしこの手の手続きを考えない、考えさせない司教座の無責任さには問題がある。それともわざとなのか。
リンハルトは老眼鏡をかけ、何度読んだかわからない声明文をまた読み返した。ため息も何度吐いたかわからない。概要だけならば普通のことしか主張していない。そんな見かけが彼に更なる憂いを抱かせる
ヘヴリング領の経済は炭鉱にそこまで依存していない。だが生活は石炭に依存している。医療も信仰魔法ではなく殆ど医学によって提供されており、生活を改変しろと言われても困ることばかりだ。
ヘヴリング家の上屋敷があるハイストリートと司教座のある旧市街は大して離れていない。だがリンハルトには別の国のように感じられる。これからやってくる年若い客人も旧市街とは別の国の住人だ。リンハルトは客人のため、テフを用意するように執事に命じた。
黒衣に身を包んだ医師が召使に連れられ、リンハルトが待つ応接間に現れた。テーブルにバックギャモンのボードが開いてあるのを見た客人が微かに笑う。パルミラから輸入されたもので、近頃は老若男女を問わず流行っている。
「お招きいただきましてありがとうございます」
「僕と勝負できるのはヒューベルトくらいだからね。たまには赤でやってみない?」
ヒューベルトとリンハルトは対外的には診察のついでにバックギャモンで遊ぶ仲間、ということになっている。含みを持たせた仲であると理解しているのは同じく旧市街の干渉を嫌う極少数のものたちだけだ。
「いつも通り黒でお願いします」
互いにダイスを振って先手を決める。今日はリンハルトの方が大きい目が出たので先手となった。これはそのまま先手の出目としても使われる。執事が持ってきたテフを飲みながら遊ぶ、歳の離れた二人の姿は意外に穏やかだ。
「頼んでいたこと、調べてくれたかな」
「ある程度は。ガルグ=マク司教座で働く彼の地出身者のほとんどがキッホルとセスリーンの紋章を持っていました」
ヒューベルトの報告を受け、リンハルトはため息をついた。あの土地の領主が十傑の子孫ではないことは既に判明している。
「あの土地で血を与えたキッホルとセスリーンゆかりの聖人がいるんだろうなあ」
次にヒューベルトがダイスを振り、リンハルトの駒に邪魔される前に駒を進めた。
「確かに古代から中世にかけて、聖人たちが人の命を助けるために血を分け与えた例は枚挙にいとまがありません」
「だが集落丸ごとなんて、いくら頑丈な聖人でも血を失いすぎて死んでしまう」
「貴殿はいつ為されたとお考えですか?」
「古代や中世なら自慢して回るはずさ」
リンハルトの言葉に首肯したヒューベルトはすっかり冷めてしまったテフに口をつけた。当時の基準からしても、紋章が発現するほど沢山の血を与えられるのは特別なことだ。
「でも当時は他の土地から妬まれるような幸運だったから隠したんだ」
人間社会から魔力が失われた病禍の時期に、自らの命と引き換えにしてでも集落の命を救ってくれるような聖人と出会う幸運など滅多にあることではない。ベレト統一王の治世から三世紀ほどで制度は疲弊し、セイロス教原理主義派による異端者狩りがフォドラ全土を席巻した。病禍は互いに互いを疑う地獄のような状況で発生している。
「当時あの地域で起きたことは私も奇跡だと思います。うかつに言って回れば貴殿のおっしゃる通り、異端者狩りの対象になった可能性は高いですな」
病禍に苦しむ片田舎に偶然、血を分けてくれる聖人が現れる確率は限りなく低い。そもそも統一戦争の時点ですら、明確にナバテアの民であったと言えるのは三名だけだ。当時の大司教レアとその部下セテス、それに彼の妹でアガルタの民から血を狙われていたフレンしかいない。争いに巻き込まれることを避けて出自を隠しているものがいた可能性は否定できないが。
リンハルトの振ったダイスがゾロ目を出したのでヒューベルトの駒は弾き出され、バーに置かれることとなった。
「異端者狩りの理由も嫉妬だからね。生存戦略としては正しいし、それが強烈な成功体験になったんだろう」
だが正体を明かさず、真の目的を隠して目標を達成しようとする態度は誠実ではないとリンハルトは思う。
「聖人の血で強化された人々は当時の疲弊したフォドラにおいては珍しい、活力に溢れる有能な存在です。自然と推挙されてガルグ=マクで学んだり働いたりすることになったのでしょう」
「司教座附属の学校はキッホルとセスリーンが守護聖人だしね。彼らからしてみれば天啓だ。中々説得されない僕のことも女神から与えられた試練だと思っているね、きっと」
彼らは同じセスリーンの紋章を受け継ぎ、信仰魔法を得意とするリンハルトに親近感を持っている。だから彼らは自分たちが考える正しき道へリンハルトを誘導しようとするのだ。しかしリンハルトは彼らと正しさが共有出来ない。
「ヘヴリング家が加われば彼らにとって千人力なのは確かです。名門ですし、貴殿のような筋金入りの合理主義者が説得されたとなれば他のものにも揺さぶりをかけられる」
ダイスを振ったヒューベルトは素早く、バーの上にある自分の駒を元に戻した。互いの駒は行ったり来たりを繰り返していて、なかなかゴールしない。
「今も秘密にするのは呪術的な理由があるのかな?」
「それは私の専門外です」
ヒューベルトの駒はリンハルトの陣の中で逆転勝ちを狙い、乗るかそるかの勝負に出ていた。妻も小さな子供もいるような若者がこんなことをするのはゲームの中だけにしなくてはならない。
「君のご先祖は詳しそうだけどね。ヒューベルト、今後は僕が調べ物をするよ。君はご家族のためにも長生きしないと」
そう宣言したリンハルトは年老いて髪は白くなり、杖なしに歩けない。それでも知性の宿った瞳の色は失われていなかった。尊敬する年長者に言われて引き下がるしかなかったヒューベルトがリンハルトの葬儀に出席したのはこの翌年のことだった。彼の葬儀の場でヒューベルトだけが、リンハルトの死が不自然に早められたものであると分かっていた。畳む
「flow」第1部13.「ラジオ・デアドラ」
#完売本 #ヒルマリ #flow #レオニー #ラファエル
13.
───
一九二五年
そのように考えた最初の人々は神祖と聖人たちの至らなさを理由として欲のままに地上で生き、冥界へと追放された。
彼らは欲のままに真善美のすべてに反したので満たされぬ欲に苦しむ生と冥界以外の世界を持たない。
───
フォドラにおける無線通信の歴史はデアドラ港から始まっている。パルミラの電気技術者による無線音声送受信実験成功を受けてデアドラ港と船舶が連絡を取るための船舶無線が導入された。安全情報などの業務用でこの時点ではまだ電波を利用した航行用レーダーは開発されていない。音質が悪かったので通話には使えず船舶無線用の信号、次に電報のコードが決められ電報局が開局しフォドラの人々は新たな双方向通信手段を手に入れた。
数年後、首都であるガルグ=マク新市街に放送塔が建てられ試験放送が開始されると各地で開局申請が出された。しかしガルグ=マクの逓信省が許可を出したのは首都のガルグ=マク、アンヴァル、フェルディア、デアドラの四局だけだった。
ラジオデアドラは他局と違い日曜夜以外は二十四時間放送をし続けている。深夜帯のラジオパーソナリティとして雇用されたレオニーは元々は百貨店のエレベーターガールとして働いていたのだが買い物に訪れたラジオ局の構成作家が彼女の声の美しさと客の話し声に埋没しないその通りの良さに目を、いや耳を付けてスカウトしたのだった。
深夜帯一時から五時のうち三時から五時が彼女の担当で番組を終える時はおはようございます、という。早寝早起き派だったレオニーの生活は一変してしまった。
百貨店のエレベーターガールは街の小さな女の子なら誰もが憧れる花形職業だ。それだけで済んだらまだレオニーは動きやすく華やかな黄色と黒のチェック柄のジャケットに黒のスカートに身を包みエレベーターガールを続けていただろう。そんな素敵な制服に身を包みにこやかに客と接する姿が誘蛾灯の様におかしな男性を惹きつけることがある。
それは休日にレオニーが客として職場に買い物に来たときのことだった。あの時あのエレベーターにマリアンヌが乗っていなかったらレオニーは今でも百貨店で働いていたかもしれない。縁や運は本当に不思議なものだ。
その日、レオニーとマリアンヌが乗り合わせたエレベーターの中でレオニーは同僚が男性客から触られている事に気づいた。前からたちの悪い客がいるという話がエレベーターガール達の間で共有されていた。
モスグリーンのスカートが捲れ上がりストッキング用のガーターベルト着けた太ももが露わになる事もストッキングが傷む事もいとわずレオニーは不埒な振る舞いに及んだ男性客の腰に膝蹴りをくらわせ怯んだところで腕を捻じ上げて確保した。体が咄嗟に動いたのだという。レオニーは自分が男を確保している隙に早く非常ボタンを押す様に言ったのだが恐怖で竦んでいる同僚は手が震えて何も出来ずその場にいたマリアンヌが隙間から腕を伸ばして非常ボタンを押した。通信回線が開き何事か問う声に対して痴漢が出た、エレベーター内で既に確保したから警備員を呼んで欲しい、とレオニーが報告した。
「今日はもう仕事って気分じゃないだろうから許可が出たら私が代わってやるよ」
警察での手続きの都合上結局代わりに入る事は出来なかったようですが被害にあわれた方にそう提案したレオニーさんには後光がさして見えました、とマリアンヌは警察で証言している。
緊急停止したエレベーターの前には買い物客に犯人を見せない為か被害者が誰なのかを隠す為か警備員によって従業員用の出入り口まで衝立が並べられていた。人目につかぬよう搬入口に警察車両も到着していたがそれが地味な紺色だったのはどうやら百貨店側が配慮を、と警察に頼んだかららしい。
警察の事情聴取まで受けたマリアンヌは警察署前にある二十四時間営業のダイナーでレオニーに温かいココアを奢ってもらっていた。そこそこ消耗していたのでありがたくいただく。マリアンヌにとって久しぶりのココアだった。朝の情報番組担当のリシテアが死にたくなった時には大体脳に甘味が足りていないからまずココアを飲め、としつこく言っていたせいで一時期店頭からココアは姿を消していたが再び街中で見かけるようになった。リシテアは迂闊に自分の好きなものを番組内で挙げるせいで好物をなかなか食べられなくなる飲めなくなると言う事を繰り返している。
「マリアンヌだっけ?さっきはありがとな!」
ハキハキと喋るレオニーはエレベーターガールという機械的なイメージのある職についているせいか私服も女性の曲線美を目立たせる保守的ものではなく直線的なシルエットをつくるツーピースの体が動かしやすそうな服を身に付けていた。
「警察は第三者の証言があると動きやすいそうです」
「慣れてるんで驚いた!私なんか時間がかかりすぎてびっくりしたのに。予定とか合ったんじゃないか?大丈夫?」
レオニーは改めて物好きにも警察で証言してくれたマリアンヌを見つめた。流行りの釣鐘型をした帽子に収まっている水色の髪は短くしているようにも見えたがどうやら編み上げているらしい。書き物をする仕事なのか所作に問題があるのかその両方なのか短めにまくった上着から見えたブラウスの袖にインクの染みがついていた。
「私はラジオデアドラの構成作家で取材の手伝いもします。警察の方からお話を伺ったこともあります。だから慣れていると言ってもいい、のかもしれません」
遅れましたがと言ってマリアンヌが差し出した名刺には確かにラジオデアドラの物で表面に名前と部署とラジオ局の住所、裏には彼女が担当する番組名と放送時間が書いてある。レオニーが聞いたことのない深夜から早朝にかけて放送される番組ばかりだった。
「うちには受信機がないから職場の社員食堂で聞いてる。昼のドラマにみんな夢中だよ!作家って事はあれの脚本書いたりしてるのか?」
マリアンヌは構成作家なので台本は書くが脚本は書かない。口で説明するのは面倒なのでこの誤解についてはいつも言葉を濁してしまう。書き言葉ならばどんな面倒なことでもすらすらと説明が出来るのに話すとなると途端に口が動かなくなる。
「部署が違うので…」
「そっか。警察沙汰をきっかけにして営業をかけるのも変な話だけどさ、良かったらまた買い物に来てくれよな!私はエレベーターに乗りっぱなしだから値引きはできないけどさ」
「買い物もですがラジオデアドラの社員として百貨店に取材に伺う事もあるかもしれません。その時にもよろしくお願いします」
「分かった。上司にもそれとなく話しておくさ。とりあえず疲れたから今日は素直に帰るよ」
そう言うとレオニーは残りのココアを飲み干し伝票を手に取った。彼女がきびきびと動くので幅広の帽子についた大ぶりな羽飾りが楽しげに揺れる。躍動感と自信に満ち溢れる都会の働く女性そのものだった。
レオニーが去った後マリアンヌはココアのおかわりを頼み鞄から手帳を取り出した。忘れないうちに警察で逆に何を聞き出せたのか必死で書き留める。レオニーの溌剌さはこれで伝わるだろう。そう思ってメモを満足気に読み返していたマリアンヌだったがこの時、彼女はレオニーの個人的な連絡先を聞き忘れていた。その為思ったより早くラジオデアドラの社員として百貨店へ訪れることになる。
───
神祖に、聖人に、教会に至らぬ所があったとしても教会は聖なるものを、真善美を求めて生きる人々の為にそれらを示し続け理想と人々を繋ぐ架け橋でなくてはならない。
示された聖なるものを見た人々が自らの悪しき行いを恥じ良き行いをする様に心がけるからだ。
───
レオニーがガラス越しに出されたディレクターであるヒルダの合図に合わせてマイクロホンのスイッチを切った。目の前には構成作家のマリアンヌが座っていて清々しい日の出の光が放送を終えたばかりのレオニーたちを照らす。
「今日もなんてひどい台本なんだ!」
「ええ〜そうかなあ〜?マリアンヌちゃんの台本すっごく良かったと思うけど!」
「なんなんだよ!この焦げた私物プレゼントって!」
「レオニーさんなら絶対に面白く出来ると思いまして」
先週新市街にあるマリアンヌの住むアパートが火事で半焼した。半分残っている、とだけ聞くと暮らせそうな気もするが実際の現場は酷いものでとても生活など出来ない。幸いな事にその時、彼女は不在で焼けずに残った物もあった。余談だがその話を聞いたラジオデアドラの関係者たちは皆、一瞬はマリアンヌの不注意を疑ったという。
彼女は顔見知りからいきなり静謐の美を称えられるほど美しい女性なのだが構成作家として書く台本はレオニーに言わせればネジが飛んだ物ばかりだ。レオニーとマリアンヌの間にある机には番組で使った焦げた帽子それに焦げた辞書や焦げた詩集が数冊積み上げられている。
「使い物にならない上に番組パーソナリティの私物ですらないと言う事実とレオニーさんの真っ当さが正面からぶつかった時に笑いが生まれる、と思いまして」
「私マリアンヌちゃんの嫌なことがあってもタダで起きないところ大好き〜!」
「ありがとうございます。私も親切なヒルダさんがとても……好きです」
今はディレクターのヒルダが焼け出されたマリアンヌを「うちは部屋が余ってるから」という理由で自宅に住まわせてやっている。今日マリアンヌが着ている洋服も彼女の借り物だ。きっと一人暮らしをしていた数日前よりまともな生活を送っている筈だ。ヒルダはマリアンヌと違って化粧品を腐らせない。
「レオニーちゃんも一緒に朝ご飯食べよ!」
レオニーはこの二人に言い返してやろう、と番組放送中はいつも思っているのだが終わる頃には疲れと空腹で言い返す気力が残っていない。三人がやって来たラジオ局の目の前にあるダイナーは関係者御用達で二十四時間営業をしている。当然、この店の店内放送はラジオデアドラだ。早朝のニュース番組でアナウンサーが読み上げるニュースを聞きながら番組スタッフ達と朝食をとっているとまた火事が起きたようだった。火事のニュースを耳にしたマリアンヌが焼けたアパートのことを思い出して伏し目がちになる。
「なんか最近火事が多くない?取材に行ったら怒られるかなあ?」
目玉焼きの黄身を潰しながら何か思い付いたらしいヒルダがメモをし始めた。レオニーが担当している2時間はこんな時間はどうせ誰も聞いていない、と言う理由でやりたい放題の枠だ。こんな時間帯でも聞いているのは荷揚げや荷下ろしの為に待機しているデアドラ港の沖仲仕達が多く彼らに向けてボートレースや競馬中継の予告が入る。しかし朝5時を過ぎて嘘のように内容が真面目になった。今は解説員が最近の天候不順について語っている。
「焼け出された直後は忙しいので…」
マリアンヌがスクランブルエッグをケチャップとかき混ぜながら応じた。この口ぶりだと先方の都合がつきそうな頃に取材に行っても不思議ではない。相手を怒らせても泣かせても放送ではレオニーならなんとかしてくれるだろうと思っているので2人ともやりたい放題だ。
「そっかあ、それもそうだよね!あ、レオニーちゃんにまた手紙が来てるよ。食べ終わったら読んであげて」
ヒルダから渡される手紙の束はいつも開封済みだ。あんな時間に聞いていてわざわざレオニー宛の手紙を出すような聴取者は基本、好意があって好かれようとして手紙を出すが中にはきっと見るに耐えないようなものもあるだろう。しかし ヒルダはそういった類の手紙がレオニーの目に触れないようにしてくれている。
「あんた達がパーソナリティに見せられなかった手紙特集を出来ないんだからきっとすごいのをみてるんだろうな」
レオニーは塩で味付けしてある豆の煮物をトーストに乗せふたつ折りにして頬張った。朝食についての葉書やお便りを募集した際に書いてあった食べ方で試してみたら美味しかったのでよく真似している。豆が溢れないように器用に食べるとレオニーは手についたパン屑を払って手紙の束を手に取った。
「さあ、路面電車も動き始めたしレオニーちゃんは帰って一眠りして!」
「ヒルダ達は水上バスの始発待ちか。歴史地区は素敵だけど住むには少し不便だな」
ヒルダの自宅がある一帯は十五年前に歴史地区に指定されてから手押しの台車と乳母車と車椅子以外の車輪は使用が禁止されている。移動には足と船しか使えない。デアドラの新市街にあるマリーナに自家用船を係留するには莫大な費用がかかり空きがなかなか出ない為どうしても水上バスと水上タクシーを利用する様になる。
ヒルダはレスター地方屈指の名家であるゴネリル家の娘だ。ゴネリル家のルーツはパルミラの首飾り建設時までは確実に遡ることが可能で、それ以前になるとお伽話や神話の領域になる。ヒルダ言うところの由緒正しいご先祖サマ、がまだデアドラがレスター諸侯同盟の首都だった頃に建てた上屋敷は現在の新市街にあったのでまだその上屋敷を所有していればヒルダもレオニーの様に路面電車で帰宅できただろう。しかし彼女の曽祖父がその上屋敷をデアドラ市に売却し改めて網の様に水路が張り巡らされている旧市街へ家を建て直した。船着場がある立派な屋敷で ヒルダの曽祖父は毎朝、自宅からボートで釣りに出てその日に食べる魚を釣っていたらしい。ヒルダは釣りに興味がないが同居している父や兄は釣りが好きなので活用している。
「それじゃ遠慮なくお先に失礼するよ、二人ともおやすみ!」
レオニーが去るとヒルダはハンドバッグから彼女に渡さなかった開封済みの封筒を取り出した。マリアンヌに中身を確認させる。
「分かりにくいですがファイアーの術式です。レオニーさんに魔法適性があった場合、読み上げさせたらスタジオが火事になります」
マリアンヌは意外性の宝庫だ。口下手なのに文章を書かせれば誰よりも奇抜なものを書くし、引っ込み思案で人付き合いが苦手なのに全寮制の士官学校で理学魔法の訓練を受けていたのでメイジとプリースト双方の資格を持っている。寮でのあだ名はその無口さからサイレスだったらしい。
「あーあ、女だけで番組を作ってるからかしら?また警察に行かないと。その前に上に相談か」
「そうですね、誰かに読み上げられる前に加筆して術式を無効にしますから証言してください」
マリアンヌが万年筆で悪意の塊の様な便箋に記号や文字列を書き込むとそれらは一瞬だけ青く光り、すぐに輝きを失っていった。もしかしたら彼女のアパートの住人にもこんな手紙が来て知らずに読み上げた結果、火事になったのかもしれない。ヒルダもマリアンヌと同じことを考えたのか無言で頷いた。
───
隕石の衝突エネルギーで高温となった地表はどろどろに溶けて鉄などの重いものが沈み高い圧力の下で固まっていく。固形の内核と液状の外核が生まれ自転により液状の外核は回転し電気が発生した。その電気により生じた地磁気は惑星全体を覆い宇宙線や太陽風を遮る防御壁となる。
磁気微生物の中にあるマグネトソームは地磁気によって守られた惑星に引き寄せられていった。
───
ヒルダとマリアンヌから報告を受けた上司が悪意のある攻撃をされたと判断し局の法務部にこの案件は委ねられた。ラジオデアドラは警備体制の強化が必要と判断し警備員を新たに二名雇い入れた。大柄な金髪で、玄関に立っているだけで抑止力になるであろうラファエルと魔法を使った嫌がらせに対処出来るベレトだ。
ラファエルは休憩中、筋肉をいじめると称して背中に誰かを座らせながら腕立て伏せをしている姿が評判を呼び、たまにギャラなしで番組に出演させられている。もう1人のベレトは誰かの過去を思い起こさせる静かさなので番組でパーソナリティがたまに話題に出すものの出演した事はない。ただ、マリアンヌとは通じ合うものがあったのかすぐに打ち解けた為その姿を見た局内の男性陣は衝撃を受けた。今日もまた2人で立ち話をしている。
「ヒルダさん、一瞬だけ便箋に環が見えたんだそうです」
「魔法適性検査は」
「本家筋の方々は十傑の遺産絡みで受けていると聞いたことはありますが、ヒルダさん本人はどうなのか分かりません」
「今時はそんなものか……。自分のことだと捉えないと皆、ますます魔法とは縁遠くなるな」
ファイアーの術式が仕込んである新たな手紙をマリアンヌに見せられた際ベレトは線をたった一本書き足すだけで無効にした。マリアンヌはガルグ=マクの士官学校で正式な訓練を受けた身なので、目の前のベレトの腕が本物であることがそれだけで分かる。彼なら警察や軍の魔法部門で上級職にだってつける筈だが、地方で警備員をやっていると言うことはきっと訳ありなのだろう。
「でも私がプリーストの資格を持っていると知ると皆さんレストやライブをかけてもらいたがるんです。訳のわからない医薬品より自然で良い、と」
ふふ、と静かに笑うマリアンヌが内心で何を考えているのかベレトには手に取るようにわかる。レストやライブの術式だって訳がわからない癖に、と思っているのだ。今のマリアンヌはそこで笑えるから構成作家が出来る。ベレトが最初に出会ったマリアンヌなら無理だった筈だ。改めて良い時代になったと思う。豊かさで紋章も魔法も存在意義を薄められ、最初のマリアンヌが背負っていた重荷は今やないに等しい。
「人間は身勝手なものだ。だがそれも今や飯の種だね?今後は番組宛の手紙の開封は警備部がするべきだ。それと局員全ての魔法適性検査が必要だ」
「このおかしな嫌がらせがデアドラで横行しているなら皆自分の状態を知るべきですね、確かに」
ベレトはマリアンヌの言葉を首肯しながら大欠伸をした。もう交代要員も来たので帰る前に男性用仮眠室で寝るのだという。ラジオデアドラの男性用仮眠室はいつシーツを交換したのか誰も知らない。殆どの局員はここで寝るなら廊下の床に、という代物だ。一体どんな生き方をしてきたのだろう。マリアンヌだって紆余曲折あったがベレトのそれはなんだか途方もないような気がした。
一方その頃、ヒルダは損害保険代理店で一連の火事に火災保険の詐欺の可能性があるかどうか意見を聞き終え、市立図書館で新聞の縮刷版を読んでいた。不審な火事が起きたのはどこの誰の家なのかを調べている。まるで科学から魔法に立ち返れ、と言わんばかりに先端技術に関わる人の家ばかりが火事を起こしていた。放送局が狙われてもおかしくない。それに確かマリアンヌの隣人はレスター光学の研究所勤務だった。
続けてヒルダは警察白書にも手を伸ばした。犯罪被害者の分析が載っている筈だ。だが警察白書には年齢・性別・年収・居住地別の被害者分析は載っていても職業での分析はなかった。では加害者はどうだろうか。単独犯なのか組織なのか。脅迫の為に放火するのは犯罪組織の手口だと書いてあるが技術者を脅迫する犯罪組織とは一体どんな組織なのだろう。ヒルダには見当がつかなかった。一人で考え込んでいてもこれ以上いい考えは浮かびそうにない。今日のところはこれで時間切れのようだった。
ラジオ局に戻るとちょうど休憩室で放送終了後のリシテアが1人でココアを飲んでいた。ヒルダも自動販売機でソーダを買って向かいに座る。
「マリアンヌなら打ち合わせで会議室に行きましたよ」
「あーいいのいいの。リシテアちゃんにも考えてもらいたいんだけど、これ見てくれる?」
ヒルダのメモを見たリシテアが口に手を当ててうーん、と唸りながら考え込んでいる。年上のヒルダに頼られたからには気の利いた事を言いたいと思っていた。
「えっ、これはマリアンヌのアパートも関係あるんですか……?」
「それにレオニーちゃん宛にも変な手紙が来たの。おかしいって気がついてマリアンヌちゃんが無効にしてくれた」
「レオニーにもですか……。私にも来るかもしれませんね。その変な手紙」
リシテアはカップの底に残っていたココアを飲み干すと彼女なりの答えを出した。
「宗教関係とか?」
「えーっ!うちの局、司祭様の人生相談番組もあるのに?」
デアドラのセイロス教会聖職者は番組を持っているだけでなく、大規模な記念礼拝を行う際にラジオデアドラに広告も出すしラジオで説法もする。ラジオという新しい場と積極的に関わっていた。
「いや、デアドラのセイロス教会がどうのって話ではないです。今って二十世紀ですよ?ラジオもガス灯もある今、そんな主張をするならよっぽど強い後ろ盾がある、と確信していないと無理です。言えません。だから女神様が自分達の味方だと信じ込んでいる人達、それで宗教関係と言いました」
リシテアの説明はヒルダの腑に落ちたので大げさに礼を言った。彼女は手短に宗教関係、とは言ったが町中の小さな聖堂を守り、託児所を開いている修道女や神父の様な地に足がついた人々ではなく暗黒時代の異端審問官のような集団を指している。己の身に宿る魔力を蔑ろにしていた技術者たちを彼ら自身が持つ魔力で罰する、という残酷な発想はなかなか出てくるものではない。
リシテアが気がついたようなことを警察や保険会社の保険調査員が見逃すとも思えないが、警備部には伝えておくべきだろう。ヒルダが自分の机でベレト宛にメモを書きおえた時に近所の教会の鐘が鳴った。ヒルダにとっては放送準備の時間を知らせる鐘の音なのでスタジオにいかねばならない。放送終了後にベレトにすぐ渡せるようわかりやすい場所にメモを置いた。
放送中、誰もいなくなった部屋に緑の髪をした社員がそっと入り込みヒルダがベレトに渡す筈だったメモはその社員の手の中で燃やされた。最新の火災報知器も感知できないくらい小さな魔法の炎だった。
翌日、デイリーレスターの一面を宗教警察設立が検討されているという記事が飾った。写真は白黒なので読者は全く気がつかなかったがガルグ=マクでその準備にあたる人々は皆全て緑の髪に緑の目をしていた。
※細かい顛末が気になる場合はこちらもお読みください
https://horreum.sub.jp/teg/?tag=%e3%83%a...
畳む
#完売本 #ヒルマリ #flow #レオニー #ラファエル
13.
───
一九二五年
そのように考えた最初の人々は神祖と聖人たちの至らなさを理由として欲のままに地上で生き、冥界へと追放された。
彼らは欲のままに真善美のすべてに反したので満たされぬ欲に苦しむ生と冥界以外の世界を持たない。
───
フォドラにおける無線通信の歴史はデアドラ港から始まっている。パルミラの電気技術者による無線音声送受信実験成功を受けてデアドラ港と船舶が連絡を取るための船舶無線が導入された。安全情報などの業務用でこの時点ではまだ電波を利用した航行用レーダーは開発されていない。音質が悪かったので通話には使えず船舶無線用の信号、次に電報のコードが決められ電報局が開局しフォドラの人々は新たな双方向通信手段を手に入れた。
数年後、首都であるガルグ=マク新市街に放送塔が建てられ試験放送が開始されると各地で開局申請が出された。しかしガルグ=マクの逓信省が許可を出したのは首都のガルグ=マク、アンヴァル、フェルディア、デアドラの四局だけだった。
ラジオデアドラは他局と違い日曜夜以外は二十四時間放送をし続けている。深夜帯のラジオパーソナリティとして雇用されたレオニーは元々は百貨店のエレベーターガールとして働いていたのだが買い物に訪れたラジオ局の構成作家が彼女の声の美しさと客の話し声に埋没しないその通りの良さに目を、いや耳を付けてスカウトしたのだった。
深夜帯一時から五時のうち三時から五時が彼女の担当で番組を終える時はおはようございます、という。早寝早起き派だったレオニーの生活は一変してしまった。
百貨店のエレベーターガールは街の小さな女の子なら誰もが憧れる花形職業だ。それだけで済んだらまだレオニーは動きやすく華やかな黄色と黒のチェック柄のジャケットに黒のスカートに身を包みエレベーターガールを続けていただろう。そんな素敵な制服に身を包みにこやかに客と接する姿が誘蛾灯の様におかしな男性を惹きつけることがある。
それは休日にレオニーが客として職場に買い物に来たときのことだった。あの時あのエレベーターにマリアンヌが乗っていなかったらレオニーは今でも百貨店で働いていたかもしれない。縁や運は本当に不思議なものだ。
その日、レオニーとマリアンヌが乗り合わせたエレベーターの中でレオニーは同僚が男性客から触られている事に気づいた。前からたちの悪い客がいるという話がエレベーターガール達の間で共有されていた。
モスグリーンのスカートが捲れ上がりストッキング用のガーターベルト着けた太ももが露わになる事もストッキングが傷む事もいとわずレオニーは不埒な振る舞いに及んだ男性客の腰に膝蹴りをくらわせ怯んだところで腕を捻じ上げて確保した。体が咄嗟に動いたのだという。レオニーは自分が男を確保している隙に早く非常ボタンを押す様に言ったのだが恐怖で竦んでいる同僚は手が震えて何も出来ずその場にいたマリアンヌが隙間から腕を伸ばして非常ボタンを押した。通信回線が開き何事か問う声に対して痴漢が出た、エレベーター内で既に確保したから警備員を呼んで欲しい、とレオニーが報告した。
「今日はもう仕事って気分じゃないだろうから許可が出たら私が代わってやるよ」
警察での手続きの都合上結局代わりに入る事は出来なかったようですが被害にあわれた方にそう提案したレオニーさんには後光がさして見えました、とマリアンヌは警察で証言している。
緊急停止したエレベーターの前には買い物客に犯人を見せない為か被害者が誰なのかを隠す為か警備員によって従業員用の出入り口まで衝立が並べられていた。人目につかぬよう搬入口に警察車両も到着していたがそれが地味な紺色だったのはどうやら百貨店側が配慮を、と警察に頼んだかららしい。
警察の事情聴取まで受けたマリアンヌは警察署前にある二十四時間営業のダイナーでレオニーに温かいココアを奢ってもらっていた。そこそこ消耗していたのでありがたくいただく。マリアンヌにとって久しぶりのココアだった。朝の情報番組担当のリシテアが死にたくなった時には大体脳に甘味が足りていないからまずココアを飲め、としつこく言っていたせいで一時期店頭からココアは姿を消していたが再び街中で見かけるようになった。リシテアは迂闊に自分の好きなものを番組内で挙げるせいで好物をなかなか食べられなくなる飲めなくなると言う事を繰り返している。
「マリアンヌだっけ?さっきはありがとな!」
ハキハキと喋るレオニーはエレベーターガールという機械的なイメージのある職についているせいか私服も女性の曲線美を目立たせる保守的ものではなく直線的なシルエットをつくるツーピースの体が動かしやすそうな服を身に付けていた。
「警察は第三者の証言があると動きやすいそうです」
「慣れてるんで驚いた!私なんか時間がかかりすぎてびっくりしたのに。予定とか合ったんじゃないか?大丈夫?」
レオニーは改めて物好きにも警察で証言してくれたマリアンヌを見つめた。流行りの釣鐘型をした帽子に収まっている水色の髪は短くしているようにも見えたがどうやら編み上げているらしい。書き物をする仕事なのか所作に問題があるのかその両方なのか短めにまくった上着から見えたブラウスの袖にインクの染みがついていた。
「私はラジオデアドラの構成作家で取材の手伝いもします。警察の方からお話を伺ったこともあります。だから慣れていると言ってもいい、のかもしれません」
遅れましたがと言ってマリアンヌが差し出した名刺には確かにラジオデアドラの物で表面に名前と部署とラジオ局の住所、裏には彼女が担当する番組名と放送時間が書いてある。レオニーが聞いたことのない深夜から早朝にかけて放送される番組ばかりだった。
「うちには受信機がないから職場の社員食堂で聞いてる。昼のドラマにみんな夢中だよ!作家って事はあれの脚本書いたりしてるのか?」
マリアンヌは構成作家なので台本は書くが脚本は書かない。口で説明するのは面倒なのでこの誤解についてはいつも言葉を濁してしまう。書き言葉ならばどんな面倒なことでもすらすらと説明が出来るのに話すとなると途端に口が動かなくなる。
「部署が違うので…」
「そっか。警察沙汰をきっかけにして営業をかけるのも変な話だけどさ、良かったらまた買い物に来てくれよな!私はエレベーターに乗りっぱなしだから値引きはできないけどさ」
「買い物もですがラジオデアドラの社員として百貨店に取材に伺う事もあるかもしれません。その時にもよろしくお願いします」
「分かった。上司にもそれとなく話しておくさ。とりあえず疲れたから今日は素直に帰るよ」
そう言うとレオニーは残りのココアを飲み干し伝票を手に取った。彼女がきびきびと動くので幅広の帽子についた大ぶりな羽飾りが楽しげに揺れる。躍動感と自信に満ち溢れる都会の働く女性そのものだった。
レオニーが去った後マリアンヌはココアのおかわりを頼み鞄から手帳を取り出した。忘れないうちに警察で逆に何を聞き出せたのか必死で書き留める。レオニーの溌剌さはこれで伝わるだろう。そう思ってメモを満足気に読み返していたマリアンヌだったがこの時、彼女はレオニーの個人的な連絡先を聞き忘れていた。その為思ったより早くラジオデアドラの社員として百貨店へ訪れることになる。
───
神祖に、聖人に、教会に至らぬ所があったとしても教会は聖なるものを、真善美を求めて生きる人々の為にそれらを示し続け理想と人々を繋ぐ架け橋でなくてはならない。
示された聖なるものを見た人々が自らの悪しき行いを恥じ良き行いをする様に心がけるからだ。
───
レオニーがガラス越しに出されたディレクターであるヒルダの合図に合わせてマイクロホンのスイッチを切った。目の前には構成作家のマリアンヌが座っていて清々しい日の出の光が放送を終えたばかりのレオニーたちを照らす。
「今日もなんてひどい台本なんだ!」
「ええ〜そうかなあ〜?マリアンヌちゃんの台本すっごく良かったと思うけど!」
「なんなんだよ!この焦げた私物プレゼントって!」
「レオニーさんなら絶対に面白く出来ると思いまして」
先週新市街にあるマリアンヌの住むアパートが火事で半焼した。半分残っている、とだけ聞くと暮らせそうな気もするが実際の現場は酷いものでとても生活など出来ない。幸いな事にその時、彼女は不在で焼けずに残った物もあった。余談だがその話を聞いたラジオデアドラの関係者たちは皆、一瞬はマリアンヌの不注意を疑ったという。
彼女は顔見知りからいきなり静謐の美を称えられるほど美しい女性なのだが構成作家として書く台本はレオニーに言わせればネジが飛んだ物ばかりだ。レオニーとマリアンヌの間にある机には番組で使った焦げた帽子それに焦げた辞書や焦げた詩集が数冊積み上げられている。
「使い物にならない上に番組パーソナリティの私物ですらないと言う事実とレオニーさんの真っ当さが正面からぶつかった時に笑いが生まれる、と思いまして」
「私マリアンヌちゃんの嫌なことがあってもタダで起きないところ大好き〜!」
「ありがとうございます。私も親切なヒルダさんがとても……好きです」
今はディレクターのヒルダが焼け出されたマリアンヌを「うちは部屋が余ってるから」という理由で自宅に住まわせてやっている。今日マリアンヌが着ている洋服も彼女の借り物だ。きっと一人暮らしをしていた数日前よりまともな生活を送っている筈だ。ヒルダはマリアンヌと違って化粧品を腐らせない。
「レオニーちゃんも一緒に朝ご飯食べよ!」
レオニーはこの二人に言い返してやろう、と番組放送中はいつも思っているのだが終わる頃には疲れと空腹で言い返す気力が残っていない。三人がやって来たラジオ局の目の前にあるダイナーは関係者御用達で二十四時間営業をしている。当然、この店の店内放送はラジオデアドラだ。早朝のニュース番組でアナウンサーが読み上げるニュースを聞きながら番組スタッフ達と朝食をとっているとまた火事が起きたようだった。火事のニュースを耳にしたマリアンヌが焼けたアパートのことを思い出して伏し目がちになる。
「なんか最近火事が多くない?取材に行ったら怒られるかなあ?」
目玉焼きの黄身を潰しながら何か思い付いたらしいヒルダがメモをし始めた。レオニーが担当している2時間はこんな時間はどうせ誰も聞いていない、と言う理由でやりたい放題の枠だ。こんな時間帯でも聞いているのは荷揚げや荷下ろしの為に待機しているデアドラ港の沖仲仕達が多く彼らに向けてボートレースや競馬中継の予告が入る。しかし朝5時を過ぎて嘘のように内容が真面目になった。今は解説員が最近の天候不順について語っている。
「焼け出された直後は忙しいので…」
マリアンヌがスクランブルエッグをケチャップとかき混ぜながら応じた。この口ぶりだと先方の都合がつきそうな頃に取材に行っても不思議ではない。相手を怒らせても泣かせても放送ではレオニーならなんとかしてくれるだろうと思っているので2人ともやりたい放題だ。
「そっかあ、それもそうだよね!あ、レオニーちゃんにまた手紙が来てるよ。食べ終わったら読んであげて」
ヒルダから渡される手紙の束はいつも開封済みだ。あんな時間に聞いていてわざわざレオニー宛の手紙を出すような聴取者は基本、好意があって好かれようとして手紙を出すが中にはきっと見るに耐えないようなものもあるだろう。しかし ヒルダはそういった類の手紙がレオニーの目に触れないようにしてくれている。
「あんた達がパーソナリティに見せられなかった手紙特集を出来ないんだからきっとすごいのをみてるんだろうな」
レオニーは塩で味付けしてある豆の煮物をトーストに乗せふたつ折りにして頬張った。朝食についての葉書やお便りを募集した際に書いてあった食べ方で試してみたら美味しかったのでよく真似している。豆が溢れないように器用に食べるとレオニーは手についたパン屑を払って手紙の束を手に取った。
「さあ、路面電車も動き始めたしレオニーちゃんは帰って一眠りして!」
「ヒルダ達は水上バスの始発待ちか。歴史地区は素敵だけど住むには少し不便だな」
ヒルダの自宅がある一帯は十五年前に歴史地区に指定されてから手押しの台車と乳母車と車椅子以外の車輪は使用が禁止されている。移動には足と船しか使えない。デアドラの新市街にあるマリーナに自家用船を係留するには莫大な費用がかかり空きがなかなか出ない為どうしても水上バスと水上タクシーを利用する様になる。
ヒルダはレスター地方屈指の名家であるゴネリル家の娘だ。ゴネリル家のルーツはパルミラの首飾り建設時までは確実に遡ることが可能で、それ以前になるとお伽話や神話の領域になる。ヒルダ言うところの由緒正しいご先祖サマ、がまだデアドラがレスター諸侯同盟の首都だった頃に建てた上屋敷は現在の新市街にあったのでまだその上屋敷を所有していればヒルダもレオニーの様に路面電車で帰宅できただろう。しかし彼女の曽祖父がその上屋敷をデアドラ市に売却し改めて網の様に水路が張り巡らされている旧市街へ家を建て直した。船着場がある立派な屋敷で ヒルダの曽祖父は毎朝、自宅からボートで釣りに出てその日に食べる魚を釣っていたらしい。ヒルダは釣りに興味がないが同居している父や兄は釣りが好きなので活用している。
「それじゃ遠慮なくお先に失礼するよ、二人ともおやすみ!」
レオニーが去るとヒルダはハンドバッグから彼女に渡さなかった開封済みの封筒を取り出した。マリアンヌに中身を確認させる。
「分かりにくいですがファイアーの術式です。レオニーさんに魔法適性があった場合、読み上げさせたらスタジオが火事になります」
マリアンヌは意外性の宝庫だ。口下手なのに文章を書かせれば誰よりも奇抜なものを書くし、引っ込み思案で人付き合いが苦手なのに全寮制の士官学校で理学魔法の訓練を受けていたのでメイジとプリースト双方の資格を持っている。寮でのあだ名はその無口さからサイレスだったらしい。
「あーあ、女だけで番組を作ってるからかしら?また警察に行かないと。その前に上に相談か」
「そうですね、誰かに読み上げられる前に加筆して術式を無効にしますから証言してください」
マリアンヌが万年筆で悪意の塊の様な便箋に記号や文字列を書き込むとそれらは一瞬だけ青く光り、すぐに輝きを失っていった。もしかしたら彼女のアパートの住人にもこんな手紙が来て知らずに読み上げた結果、火事になったのかもしれない。ヒルダもマリアンヌと同じことを考えたのか無言で頷いた。
───
隕石の衝突エネルギーで高温となった地表はどろどろに溶けて鉄などの重いものが沈み高い圧力の下で固まっていく。固形の内核と液状の外核が生まれ自転により液状の外核は回転し電気が発生した。その電気により生じた地磁気は惑星全体を覆い宇宙線や太陽風を遮る防御壁となる。
磁気微生物の中にあるマグネトソームは地磁気によって守られた惑星に引き寄せられていった。
───
ヒルダとマリアンヌから報告を受けた上司が悪意のある攻撃をされたと判断し局の法務部にこの案件は委ねられた。ラジオデアドラは警備体制の強化が必要と判断し警備員を新たに二名雇い入れた。大柄な金髪で、玄関に立っているだけで抑止力になるであろうラファエルと魔法を使った嫌がらせに対処出来るベレトだ。
ラファエルは休憩中、筋肉をいじめると称して背中に誰かを座らせながら腕立て伏せをしている姿が評判を呼び、たまにギャラなしで番組に出演させられている。もう1人のベレトは誰かの過去を思い起こさせる静かさなので番組でパーソナリティがたまに話題に出すものの出演した事はない。ただ、マリアンヌとは通じ合うものがあったのかすぐに打ち解けた為その姿を見た局内の男性陣は衝撃を受けた。今日もまた2人で立ち話をしている。
「ヒルダさん、一瞬だけ便箋に環が見えたんだそうです」
「魔法適性検査は」
「本家筋の方々は十傑の遺産絡みで受けていると聞いたことはありますが、ヒルダさん本人はどうなのか分かりません」
「今時はそんなものか……。自分のことだと捉えないと皆、ますます魔法とは縁遠くなるな」
ファイアーの術式が仕込んである新たな手紙をマリアンヌに見せられた際ベレトは線をたった一本書き足すだけで無効にした。マリアンヌはガルグ=マクの士官学校で正式な訓練を受けた身なので、目の前のベレトの腕が本物であることがそれだけで分かる。彼なら警察や軍の魔法部門で上級職にだってつける筈だが、地方で警備員をやっていると言うことはきっと訳ありなのだろう。
「でも私がプリーストの資格を持っていると知ると皆さんレストやライブをかけてもらいたがるんです。訳のわからない医薬品より自然で良い、と」
ふふ、と静かに笑うマリアンヌが内心で何を考えているのかベレトには手に取るようにわかる。レストやライブの術式だって訳がわからない癖に、と思っているのだ。今のマリアンヌはそこで笑えるから構成作家が出来る。ベレトが最初に出会ったマリアンヌなら無理だった筈だ。改めて良い時代になったと思う。豊かさで紋章も魔法も存在意義を薄められ、最初のマリアンヌが背負っていた重荷は今やないに等しい。
「人間は身勝手なものだ。だがそれも今や飯の種だね?今後は番組宛の手紙の開封は警備部がするべきだ。それと局員全ての魔法適性検査が必要だ」
「このおかしな嫌がらせがデアドラで横行しているなら皆自分の状態を知るべきですね、確かに」
ベレトはマリアンヌの言葉を首肯しながら大欠伸をした。もう交代要員も来たので帰る前に男性用仮眠室で寝るのだという。ラジオデアドラの男性用仮眠室はいつシーツを交換したのか誰も知らない。殆どの局員はここで寝るなら廊下の床に、という代物だ。一体どんな生き方をしてきたのだろう。マリアンヌだって紆余曲折あったがベレトのそれはなんだか途方もないような気がした。
一方その頃、ヒルダは損害保険代理店で一連の火事に火災保険の詐欺の可能性があるかどうか意見を聞き終え、市立図書館で新聞の縮刷版を読んでいた。不審な火事が起きたのはどこの誰の家なのかを調べている。まるで科学から魔法に立ち返れ、と言わんばかりに先端技術に関わる人の家ばかりが火事を起こしていた。放送局が狙われてもおかしくない。それに確かマリアンヌの隣人はレスター光学の研究所勤務だった。
続けてヒルダは警察白書にも手を伸ばした。犯罪被害者の分析が載っている筈だ。だが警察白書には年齢・性別・年収・居住地別の被害者分析は載っていても職業での分析はなかった。では加害者はどうだろうか。単独犯なのか組織なのか。脅迫の為に放火するのは犯罪組織の手口だと書いてあるが技術者を脅迫する犯罪組織とは一体どんな組織なのだろう。ヒルダには見当がつかなかった。一人で考え込んでいてもこれ以上いい考えは浮かびそうにない。今日のところはこれで時間切れのようだった。
ラジオ局に戻るとちょうど休憩室で放送終了後のリシテアが1人でココアを飲んでいた。ヒルダも自動販売機でソーダを買って向かいに座る。
「マリアンヌなら打ち合わせで会議室に行きましたよ」
「あーいいのいいの。リシテアちゃんにも考えてもらいたいんだけど、これ見てくれる?」
ヒルダのメモを見たリシテアが口に手を当ててうーん、と唸りながら考え込んでいる。年上のヒルダに頼られたからには気の利いた事を言いたいと思っていた。
「えっ、これはマリアンヌのアパートも関係あるんですか……?」
「それにレオニーちゃん宛にも変な手紙が来たの。おかしいって気がついてマリアンヌちゃんが無効にしてくれた」
「レオニーにもですか……。私にも来るかもしれませんね。その変な手紙」
リシテアはカップの底に残っていたココアを飲み干すと彼女なりの答えを出した。
「宗教関係とか?」
「えーっ!うちの局、司祭様の人生相談番組もあるのに?」
デアドラのセイロス教会聖職者は番組を持っているだけでなく、大規模な記念礼拝を行う際にラジオデアドラに広告も出すしラジオで説法もする。ラジオという新しい場と積極的に関わっていた。
「いや、デアドラのセイロス教会がどうのって話ではないです。今って二十世紀ですよ?ラジオもガス灯もある今、そんな主張をするならよっぽど強い後ろ盾がある、と確信していないと無理です。言えません。だから女神様が自分達の味方だと信じ込んでいる人達、それで宗教関係と言いました」
リシテアの説明はヒルダの腑に落ちたので大げさに礼を言った。彼女は手短に宗教関係、とは言ったが町中の小さな聖堂を守り、託児所を開いている修道女や神父の様な地に足がついた人々ではなく暗黒時代の異端審問官のような集団を指している。己の身に宿る魔力を蔑ろにしていた技術者たちを彼ら自身が持つ魔力で罰する、という残酷な発想はなかなか出てくるものではない。
リシテアが気がついたようなことを警察や保険会社の保険調査員が見逃すとも思えないが、警備部には伝えておくべきだろう。ヒルダが自分の机でベレト宛にメモを書きおえた時に近所の教会の鐘が鳴った。ヒルダにとっては放送準備の時間を知らせる鐘の音なのでスタジオにいかねばならない。放送終了後にベレトにすぐ渡せるようわかりやすい場所にメモを置いた。
放送中、誰もいなくなった部屋に緑の髪をした社員がそっと入り込みヒルダがベレトに渡す筈だったメモはその社員の手の中で燃やされた。最新の火災報知器も感知できないくらい小さな魔法の炎だった。
翌日、デイリーレスターの一面を宗教警察設立が検討されているという記事が飾った。写真は白黒なので読者は全く気がつかなかったがガルグ=マクでその準備にあたる人々は皆全て緑の髪に緑の目をしていた。
※細かい顛末が気になる場合はこちらもお読みください
https://horreum.sub.jp/teg/?tag=%e3%83%a...
畳む
「flow」第1部 最終話「クロード」
#flow #完売本 #現パロ
───
教会は伽藍堂である。真善美はその壁に刻まれているだけに過ぎない。
だがそれ故に聖なるものを、真善美を求める人々の全てを受け入れ、人々の悪しき部分を赦し、人々に良き行いを促すことができる。
教会は伽藍堂である。だが教会は伽藍堂でなければならない。
───
ベレトはこのままヒトが発展するところを眺めつつ、穏やかに長い生を閉じられると思っていた。科学の恩恵を受け、これだけ豊かに自由に暮らせるようになったのに何故ヒトは他人の行動を縛ろうとする動きを支持できるのだろうか。宗教警察は異端審問官という古い葡萄酒を入れた新しい皮袋にすぎない。
十七世紀にイングリットやユーリスに手伝ってもらったようなことも監視カメラがあると難しく、どうすべきか分からなかった。ソティスに叱られるのもまた良し、という気持ちでヒルダたちの安全が確保されたのを見届けたベレトはデアドラを去り、再びクパーラで眠ることにした。
以前と変わらず野生の飛竜もまだ健在で群をなして飛ぶ姿が見られるし、羽音を聞きながら眠ることができる。もしかしたら夢の中では自分も白きものになって空を飛んだり炎を吐きたり出来るかもしれない、と思って眠りについたがそれは叶わなかった。
今回、クパーラでベレトが見た夢にソティスや白きものは登場せず、ヒトとして過ごした最後の一年間、士官学校で教師をしていたあの一年間の夢しか見なかった。
フォドラ統一戦争の夢すら見なかった。
教師に戻るのが自分の運命なのかもしれない。そう考えたベレトは勝手知ったるフェルディア総合大学で高校教師の資格を取った。ガルグ=マクも庭のようなものだったが、石油化学産業で食べている土地なだけあって宗教警察から学生を守ってくれる、シルヴァン=ジョゼ=ゴーティエ記念奨学金で学費の支払いが出来る、という点でフェルディアに軍配があがった。二十世紀になってもまだ入学時にフェルディアブルーのローブを渡す伝統は続いている。
石油産業で豊かになったファーガスは十二世紀末の貧しい姿が嘘のようだった。レアはセイロス教の禁忌に石油の利用を入れていたが、古代にしても十二世紀末にしても当時は精製する技術がなかった。わざわざ禁忌にせずとも魔法を推奨するだけで充分だったろう。
フレスベルグ製作所の蒸気機関なくしてファーガスの発展は見込めなかった。結局、全ては絡み合っている。こんな風に技術が進歩していくことを直接知っているせいか、ベレトの授業は臨場感があって分かりやすいと評判が良かった。
社会科全ての資格があり、剣術と魔道も指導できる教師としてベレトはフォドラ中の高校で教えて回った。ガルグ=マクにこだわるつもりはなかったので場所は何処でも構わなかったが、オグマ山脈が見える土地にいる時にはベレト先生は気がつくと山を見ている、と生徒や同僚皆から言われた。
当時はまだ全てが紙の書類で管理されていたし、コンタクトレンズで瞳の色が変えられるようになったので各地で沢山名義を作り、別人を装って教師をするのは簡単だった。アンヴァルの教え子はフレスベルグ製作所に就職が決まったと言って喜び、ヌーヴェルの教え子は地元の大学へ進学した後ブリギットでフォドラ語を教える教師になった。ガラテアやゴーティエの高校はブレーダッドオイルから全生徒へ教科書の提供があり、フェルディアの教え子たちはやはり地元フェルディア総合大学へ進学したがった。エドマンドの教え子は地元の農学校で酪農を学び、デアドラの教え子は外航船の船員になった。
サウィン村にある分校の教師をしていた時の校長がガルグ=マクへ移動し、彼女から国立ガルグ=マク大学附属高校で教師をやらないか、と打診されたベレトは二つ返事で引き受けた。少し怖かったが例え士官学校ではないとしても何者かに呼ばれたのだろう。
国立ガルグ=マク大学附属高校は全寮制のためフォドラ中から優秀な学生が集まり、交換留学生も多数受け入れている。交換留学生はパルミラとブリギット出身の学生が多い。ベレトはレンズ研磨の修行をした際にパルミラ語を覚えたことを今の職場では明かしていなかった。
しかしうっかり同僚の前で生徒のパルミラ土産の説明文をすらすらと読んだことが災いし、新年度から地理と倫理と剣術クラブの顧問の他に留学生の受け入れ担当もするはめになってしまった。基本的にはフォドラ語でやりとりをするとはいえ、いざという時のためにパルミラ語のおさらいもしなくてはならない。
剣術クラブの指導後、誰も残っていない職員室でようやくベレトは来年度受け入れる予定の留学生たちに関する資料を開いた。とあるページで資料を捲る手が止まる。彼と再会するのは五世紀ぶりだった。二年早かったら金鹿の学級の名物コンビが再結成されていただろう。だが、ローレンツは二年前に卒業していた。彼はこのご時世には珍しい紋章持ちで、大学の紋章研究科から身体を調べられたりしてそれなりに面倒な高校生活を送っていたが、数世紀前に再会できた時のように守ってやれたと思う。
───親族同士で揉めている様子を多感な年頃の息子に見せたくない、という両親の意向でクロードは母親の故郷であるフォドラへ一年間留学することになった。特に興味もないのだが、母に言わせるとパルミラ訛りだという自分のフォドラ語が矯正できればそれで充分だと思っている。国立ガルグ=マク大学附属高校への留学生受け入れ試験に合格し、地元でお別れパーティをやったと思ったらもうフォドラの学校に到着していた、そんな状態だった。
どうやらクロードの到着は早過ぎたらしく構内は人影がまばらだ。事前に送られていた名札を胸元につけ大きなトランクを引っ張りながら歩いていく。乾燥したパルミラとは全く違う、春先の山の湿った空気を吸い込むと何故か肺の中まで冷えるような気がする。
クロードから見て広場の向こうに〝留学生はこちら〟という表示が見えた。その真下には黒髪に黒い瞳をしたスーツ姿の男性教師が立っている。学生の顔と名前でも確認しているのか書類を懸命に見ていたが、クロードに気がつくと近寄って手を差し出してきた。
『初めまして、クロード。留学生受け入れ担当のベレト=アイスナーです。君の学年に教える科目は倫理。フォドラでの一年間を有意義に楽しく過ごして下さい』
クロードは一瞬だけ何故名乗る前に名前を知られているのかと不思議に思ったが、胸元の名札に思い当たった。何度か瞬きをして、ベレトから差し出された手を握り返す。
『驚いた、ガルグ=マクにパルミラ語が話せる教師がいるなんて知らなかった!』
『少し話せるのがバレたせいで君ら留学生担当になった。ちなみに明日からはジャージしか着ないしフォドラ語しか話さないよ』
軽口を叩いてにこやかに笑うベレトを見ているとパルミラ出国前には母親から、フォドラ入国後にはガルグ=マクのパルミラ大使館から、きつく注意された宗教警察がらみのことが疑わしくなってくる。クロードはガルグ=マクでは誰がセイロス教宗教警察の協力者か分からないから言動に注意せよ、セイロス教の禁忌に触れるな、と言う助言を受けていた。
『じゃあベレト先生、俺も明日からフォドラ語しか話さないことにします。訛ってるけど』
ベレトは無言でクロードに向かって親指を立てた。ベレトの最初の教え子はベレトの最後の教え子でもあった。畳む
#flow #完売本 #現パロ
───
教会は伽藍堂である。真善美はその壁に刻まれているだけに過ぎない。
だがそれ故に聖なるものを、真善美を求める人々の全てを受け入れ、人々の悪しき部分を赦し、人々に良き行いを促すことができる。
教会は伽藍堂である。だが教会は伽藍堂でなければならない。
───
ベレトはこのままヒトが発展するところを眺めつつ、穏やかに長い生を閉じられると思っていた。科学の恩恵を受け、これだけ豊かに自由に暮らせるようになったのに何故ヒトは他人の行動を縛ろうとする動きを支持できるのだろうか。宗教警察は異端審問官という古い葡萄酒を入れた新しい皮袋にすぎない。
十七世紀にイングリットやユーリスに手伝ってもらったようなことも監視カメラがあると難しく、どうすべきか分からなかった。ソティスに叱られるのもまた良し、という気持ちでヒルダたちの安全が確保されたのを見届けたベレトはデアドラを去り、再びクパーラで眠ることにした。
以前と変わらず野生の飛竜もまだ健在で群をなして飛ぶ姿が見られるし、羽音を聞きながら眠ることができる。もしかしたら夢の中では自分も白きものになって空を飛んだり炎を吐きたり出来るかもしれない、と思って眠りについたがそれは叶わなかった。
今回、クパーラでベレトが見た夢にソティスや白きものは登場せず、ヒトとして過ごした最後の一年間、士官学校で教師をしていたあの一年間の夢しか見なかった。
フォドラ統一戦争の夢すら見なかった。
教師に戻るのが自分の運命なのかもしれない。そう考えたベレトは勝手知ったるフェルディア総合大学で高校教師の資格を取った。ガルグ=マクも庭のようなものだったが、石油化学産業で食べている土地なだけあって宗教警察から学生を守ってくれる、シルヴァン=ジョゼ=ゴーティエ記念奨学金で学費の支払いが出来る、という点でフェルディアに軍配があがった。二十世紀になってもまだ入学時にフェルディアブルーのローブを渡す伝統は続いている。
石油産業で豊かになったファーガスは十二世紀末の貧しい姿が嘘のようだった。レアはセイロス教の禁忌に石油の利用を入れていたが、古代にしても十二世紀末にしても当時は精製する技術がなかった。わざわざ禁忌にせずとも魔法を推奨するだけで充分だったろう。
フレスベルグ製作所の蒸気機関なくしてファーガスの発展は見込めなかった。結局、全ては絡み合っている。こんな風に技術が進歩していくことを直接知っているせいか、ベレトの授業は臨場感があって分かりやすいと評判が良かった。
社会科全ての資格があり、剣術と魔道も指導できる教師としてベレトはフォドラ中の高校で教えて回った。ガルグ=マクにこだわるつもりはなかったので場所は何処でも構わなかったが、オグマ山脈が見える土地にいる時にはベレト先生は気がつくと山を見ている、と生徒や同僚皆から言われた。
当時はまだ全てが紙の書類で管理されていたし、コンタクトレンズで瞳の色が変えられるようになったので各地で沢山名義を作り、別人を装って教師をするのは簡単だった。アンヴァルの教え子はフレスベルグ製作所に就職が決まったと言って喜び、ヌーヴェルの教え子は地元の大学へ進学した後ブリギットでフォドラ語を教える教師になった。ガラテアやゴーティエの高校はブレーダッドオイルから全生徒へ教科書の提供があり、フェルディアの教え子たちはやはり地元フェルディア総合大学へ進学したがった。エドマンドの教え子は地元の農学校で酪農を学び、デアドラの教え子は外航船の船員になった。
サウィン村にある分校の教師をしていた時の校長がガルグ=マクへ移動し、彼女から国立ガルグ=マク大学附属高校で教師をやらないか、と打診されたベレトは二つ返事で引き受けた。少し怖かったが例え士官学校ではないとしても何者かに呼ばれたのだろう。
国立ガルグ=マク大学附属高校は全寮制のためフォドラ中から優秀な学生が集まり、交換留学生も多数受け入れている。交換留学生はパルミラとブリギット出身の学生が多い。ベレトはレンズ研磨の修行をした際にパルミラ語を覚えたことを今の職場では明かしていなかった。
しかしうっかり同僚の前で生徒のパルミラ土産の説明文をすらすらと読んだことが災いし、新年度から地理と倫理と剣術クラブの顧問の他に留学生の受け入れ担当もするはめになってしまった。基本的にはフォドラ語でやりとりをするとはいえ、いざという時のためにパルミラ語のおさらいもしなくてはならない。
剣術クラブの指導後、誰も残っていない職員室でようやくベレトは来年度受け入れる予定の留学生たちに関する資料を開いた。とあるページで資料を捲る手が止まる。彼と再会するのは五世紀ぶりだった。二年早かったら金鹿の学級の名物コンビが再結成されていただろう。だが、ローレンツは二年前に卒業していた。彼はこのご時世には珍しい紋章持ちで、大学の紋章研究科から身体を調べられたりしてそれなりに面倒な高校生活を送っていたが、数世紀前に再会できた時のように守ってやれたと思う。
───親族同士で揉めている様子を多感な年頃の息子に見せたくない、という両親の意向でクロードは母親の故郷であるフォドラへ一年間留学することになった。特に興味もないのだが、母に言わせるとパルミラ訛りだという自分のフォドラ語が矯正できればそれで充分だと思っている。国立ガルグ=マク大学附属高校への留学生受け入れ試験に合格し、地元でお別れパーティをやったと思ったらもうフォドラの学校に到着していた、そんな状態だった。
どうやらクロードの到着は早過ぎたらしく構内は人影がまばらだ。事前に送られていた名札を胸元につけ大きなトランクを引っ張りながら歩いていく。乾燥したパルミラとは全く違う、春先の山の湿った空気を吸い込むと何故か肺の中まで冷えるような気がする。
クロードから見て広場の向こうに〝留学生はこちら〟という表示が見えた。その真下には黒髪に黒い瞳をしたスーツ姿の男性教師が立っている。学生の顔と名前でも確認しているのか書類を懸命に見ていたが、クロードに気がつくと近寄って手を差し出してきた。
『初めまして、クロード。留学生受け入れ担当のベレト=アイスナーです。君の学年に教える科目は倫理。フォドラでの一年間を有意義に楽しく過ごして下さい』
クロードは一瞬だけ何故名乗る前に名前を知られているのかと不思議に思ったが、胸元の名札に思い当たった。何度か瞬きをして、ベレトから差し出された手を握り返す。
『驚いた、ガルグ=マクにパルミラ語が話せる教師がいるなんて知らなかった!』
『少し話せるのがバレたせいで君ら留学生担当になった。ちなみに明日からはジャージしか着ないしフォドラ語しか話さないよ』
軽口を叩いてにこやかに笑うベレトを見ているとパルミラ出国前には母親から、フォドラ入国後にはガルグ=マクのパルミラ大使館から、きつく注意された宗教警察がらみのことが疑わしくなってくる。クロードはガルグ=マクでは誰がセイロス教宗教警察の協力者か分からないから言動に注意せよ、セイロス教の禁忌に触れるな、と言う助言を受けていた。
『じゃあベレト先生、俺も明日からフォドラ語しか話さないことにします。訛ってるけど』
ベレトは無言でクロードに向かって親指を立てた。ベレトの最初の教え子はベレトの最後の教え子でもあった。畳む
「flow」番外編"Bargain.2"
#完売本 #クロロレ #年齢操作 #flow #イグナーツ #リシテア
※イグナーツとリシテアが結婚しています
リシテアとイグナーツがデアドラからコーデリア領に戻る途中、グロスタールの屋敷で一泊するのは留守居をしているストームに会うためだった。だが傷心旅行を早めに切り上げたのか父親であるローレンツも戻っているという。ストームは嵐の日に生まれたローレンツの一人息子のあだ名で、彼の本名はエドガー=ローレンツ=グロスタールだ。
ストームの母は家同士の付き合いでグロスタール家に嫁いでいる。だがリシテアの婿としてコーデリア家に入った騎士上がりのイグナーツにも丁寧に接してくれる人だった。五歳年下のローレンツとはどこへ行くのも一緒な仲睦まじい夫婦でその頃の思い出話はたえることがない。彼女の死は皆に衝撃を与え、ローレンツは一年間祝事には一切参加しなかったし、その後もどこへ行くにも喪服しか着なかった。
それまでは伊達男と名高く、しょっちゅう服を仕立てていたというのに。長い間本当に酷い有りさまだったので気分を変えさせるため、彼の両親はローレンツに無理やり平服を着せた。
これまで縁のなかったパルミラへ一人で旅行へ行かせた、とローレンツの父エルヴィンから聞いた時にリシテアもイグナーツも良い機会だと思った。それなのに三ヶ月の予定を一ヶ月で切り上げて帰ってきている。執事からそう告げられたリシテアもイグナーツも不安しか感じなかった。旅行も続けられなかったのだろうか。
不安は募ったが、再会したローレンツは喪服ではなく旅先で気に入って買い求めた青い光沢のある生地で仕立てさせた上着を着ていた。しかも家中の人々を心配させた、本人に全く自覚がないのに涙を流す現象もどうやら治ったらしい。
見事な腕前で淹れてくれた紅茶はパルミラ風でいつもより少し味が濃かったが、向こうで買ってきたと言う変わった食感の茶菓子によく合っている。
「二人にも随分と心配をかけたね」
「いえ、気にしないでください。少なくとも私はこの珍しいお菓子で許してさしあげます」
「気に入ったので現物も料理本もたくさん買い込んでしまってね」
リシテアとの会話から察するにローレンツは物欲が戻ったらしい。日々の暮らしを楽しんでいた彼が生きている己を罰するかのように、内側にに篭る姿は見る者全ての涙を誘ったし、イグナーツも胸が締め付けられるように辛かった。人生は本当にままならない。
だが、もうすぐ一歳半になるよちよち歩きのストームを連れて、薔薇園を散歩する彼の姿は隣に亡くなった奥方がいないのが不思議なくらい元のローレンツそのものだった。
皆、ひとまずは安心した。そうなると次は詮索が身をもたげてくる。一体旅先のパルミラで何があったのか。久しぶりになんの憂いもなく、グロスタールの屋敷で過ごしたリシテアは幼い頃から何度も泊まっている馴染みの客室で夫のイグナーツに推理を披露していた。
「イグナーツ。私が思うにローレンツ兄様には新しく好い人が出来たのかもしれません」
「朗らかになってましたよね、確かに。ストームのためにも本当に良かった」
豊かな黒髪をブラシで梳かしていたリシテアが目元を押さえた。
「あら……いやだ、今度は私が泣いてしまうなんて。でも胸元に薔薇も付けていたし元のローレンツ兄様に戻ってくれたみたいで嬉しくて」
「紹介してもらえたら、僕たちからもその方にお礼を言いましょう」
イグナーツから濡れた手巾を渡されたリシテアは、それが絞って冷やしたものであることに気付いた。気を利かせてブリザーで冷やしてくれたのだろう。目が腫れないよう、目元にあててしまったのでイグナーツの顔は見えない。寝室で夜眠る前に話を聞いてくれる相手が失われてしまったら、と考えるだけで恐ろしい。楽しそうに相槌を打ってくれるイグナーツを失ってしまったら、リシテアだってどうなってしまうのかわからないのだ。
一方でカリードはフォドラに関する本を読み漁るため、図書館へ通い詰める日々を送っていた。カリードの住む港町はフォドラと近いこともあり、パルミラ語で書かれた本だけでなくフォドラ語の本もおいてある。どちらも読んだ。
カリードはフォドラの言葉は話せるが読み書きは得意ではない。口に出して音を聞かねば上手く意味が理解出来ず、フォドラ語の本を読むのにはかなり手間取った。その上、手当たり次第に読んだせいで調べ物としての効率も悪かった。しかしそのおかげでカリードのフォドラの文化への理解は深まっている。
彼は数週間かけついに知るべきだったこと、に自力で辿り着いた。カリードは彼をグロスタールのローレンツ=ヘルマンだと思っていたが違うらしい。ようやく何が書いてあるのか理解できるようになった貴族名鑑によると、彼はグロスタール伯爵家の一員だった。グロスタール家は十傑の遺産テュルソスの杖を受け継ぐ名門で、グロスタール領という土地の名前が彼の家名に因んで付けられている。彼は貴族の中の貴族だった。
カリードはフォドラの貴族というのはもっと冷酷で情がないものだと思っていた。だが実際に出会った彼は妻を亡くしたことが悲しくて悲しくて仕方ない人だったし、カリードが汚した服を洗ってくれて母譲りの緑色の瞳をきれいだと褒めてくれて───それ以上のこともあったし、別れ際の涙はもう不随意ではなかった、と思う。あんなに情の深い人をカリードは他に知らない。もう一度ローレンツに会いたい。ただ、彼から再会するにあたって条件を出されていた。それは別れ際の態度から察するに、ローレンツ自身の誓いでもあったのだ。
十六世紀のパルミラはダグザと海の覇権を争っており、海軍の主力はほぼダグザ方面へ割いていた。海軍の名においてフォドラの通商航路の妨害をする余裕はない。そこでパルミラ国王は民間船に対し、私掠免許を発行した。私掠免許を持つ船は敵国及び中立国の船を攻撃し、船や積荷を奪う許可を得たことになる。略奪や拿捕で得た利益は一割が国王個人、一割が船長、二割が出資者、残りの六割が乗組員達に分配された。乗組員達は受け取った六割を更に人数で割って分かち合う。その際に操舵手と船医は少しだけ取り分を多くしてもらえるのが常だった。
大型船は拿捕や略奪に備えて武装している。海賊行為は命がけだが一攫千金を狙うものたちからも投資家たちからも人気があった。私掠船は利益率の良い投資先で、それに絡んだ詐欺行為や私掠免許の強奪や偽造も横行している。
特に私掠免許の強奪や偽造は発覚すれば許可のない海賊行為を行った罪で海事裁判所に訴えられ、死刑になる。だがそれでもなお利益目当てに手を染める者が跡を絶たない。
命がけと言えば私掠船に入り込み、パルミラ国王が発行した私掠免許の真贋や正確な名義を確かめる密偵たちもそうだ。密偵は私掠船の数を正確に把握し統制したいパルミラの王府が雇うこともあれば、敵対国や中立国の政府や民間人が雇うこともある。旧レスター諸侯同盟の名家たちも海事に限らずパルミラに多数の密偵を放っていた。
少しでもフォドラと縁があり、大金を稼げる仕事がしたかったカリードは旧レスター諸侯同盟の名家ゴネリル家の密偵となった。彼を現地採用した密偵がグロスタール領出身だったこともかなり大きい。実際、上司の故郷の話を聞くだけで心が躍った。特に若様がまだ再婚なさらない、という話を聞けた晩は興奮して寝付けなかったほどだ。
カリードは様々な船に乗り込み、パルミラ人の外見と流暢なフォドラ語を利用しありとあらゆるものを煙に巻いて船長たちの秘密を暴いた。秘密を暴かれた私掠船の船長たちはそのまま海事裁判所に訴えられ、裁かれるものと脅迫されフォドラに協力させられるものに分かれる。
その判断を下すのが密偵頭の〝クロード〟だった。レスターからパルミラへ送り込まれた密偵たちはそれぞれ協力するように言われている。彼らの頭の名はそれがどこの誰であろうといつも〝クロード〟だ。〝クロード〟になれたら出自がなんであろうと、名家の人々からは一目置かれるようになる。船上で野蛮な行為のあった晩、カリードはいつもローレンツのことを思い出して正気を保った。
「本当に明日フォドラに帰っちゃうのか?」
「帰るよ。君のおかげで落ち込んでいる自分のことも許せたし、幼い息子には父親が必要だから」
フォドラへ連れて行って欲しいとせがむか格好をつけて自分もすぐに行くから待っていて欲しい、と言うべきか。迷ったカリードは眉尻を下げ、黙ってローレンツの顔を見つめた。頼まれごとが嬉しくて頑張ってしまったが、乗れる船なんか見つけてやらなければよかった気がする。でもローレンツから無能だと見做されるのはもっと嫌だった。
「僕のように心を病んだ男が何を言っても説得力はないかもしれないが、君は善良で頭が良いのだから優れた何か、になるべきだ」
カリードが黙って身体を強張らせているとローレンツが手を握ってきた。長くて白い指と褐色の指が組み合わさり白い顔が上から近づいてくる。
「それに君の未来が僕の性欲で定まるのはいやだな」
ローレンツは冗談めかしていたが、カリードは自分の耳元で囁かれたその言葉に雷に打たれたような衝撃を受けた。その時は分かっていなかったがグロスタール家の力があれば、あの時点の野良犬のようなカリードをフォドラへ連れて帰ってしまうのは簡単だった。だがローレンツは本当に誠実な人物で、それが搾取であると考えた。カリードには自力で優れた人間になる可能性があり、自力で自分と対等な人間になれると信じてくれた。
愛する人に信頼されたからには全力で応えるしかない。こうして優れた何か、になろうとしてもがき苦しむカリードの姿が女神の御心を動かしたのかもしれない。もしくさたった半月しか共に過ごさなかったのにカリードの可能性を信じて、突き放したローレンツの真面目さが女神の御心を動かしたのかもしれない。
正確なところは分からないがとにかく事態は動いた。近々デアドラ港の港長が代替わりする、という噂はカリードの耳にも入っている。それにまつわる人事異動の噂で持ちきりだ。港長が代替わりするなら今の〝クロード〟も引退する可能性がある。聞くところによると二人とも隠居してもおかしくない老人だ。次の〝クロード〟になったカリードがデアドラで暮らすようになれば、ローレンツは再び連絡を取ってくれるかもしれない。グロスタール領からローレンツが会いに来てくれるかもしれない。
そのためには今までと同じく、今回の航海でもしくじることは出来かった。甲板では船員たちが食糧不足を解消するために釣った鮫が大暴れしている。その様子をマストの上から眺めながらカリードは不敵に笑った。畳む
#完売本 #クロロレ #年齢操作 #flow #イグナーツ #リシテア
※イグナーツとリシテアが結婚しています
リシテアとイグナーツがデアドラからコーデリア領に戻る途中、グロスタールの屋敷で一泊するのは留守居をしているストームに会うためだった。だが傷心旅行を早めに切り上げたのか父親であるローレンツも戻っているという。ストームは嵐の日に生まれたローレンツの一人息子のあだ名で、彼の本名はエドガー=ローレンツ=グロスタールだ。
ストームの母は家同士の付き合いでグロスタール家に嫁いでいる。だがリシテアの婿としてコーデリア家に入った騎士上がりのイグナーツにも丁寧に接してくれる人だった。五歳年下のローレンツとはどこへ行くのも一緒な仲睦まじい夫婦でその頃の思い出話はたえることがない。彼女の死は皆に衝撃を与え、ローレンツは一年間祝事には一切参加しなかったし、その後もどこへ行くにも喪服しか着なかった。
それまでは伊達男と名高く、しょっちゅう服を仕立てていたというのに。長い間本当に酷い有りさまだったので気分を変えさせるため、彼の両親はローレンツに無理やり平服を着せた。
これまで縁のなかったパルミラへ一人で旅行へ行かせた、とローレンツの父エルヴィンから聞いた時にリシテアもイグナーツも良い機会だと思った。それなのに三ヶ月の予定を一ヶ月で切り上げて帰ってきている。執事からそう告げられたリシテアもイグナーツも不安しか感じなかった。旅行も続けられなかったのだろうか。
不安は募ったが、再会したローレンツは喪服ではなく旅先で気に入って買い求めた青い光沢のある生地で仕立てさせた上着を着ていた。しかも家中の人々を心配させた、本人に全く自覚がないのに涙を流す現象もどうやら治ったらしい。
見事な腕前で淹れてくれた紅茶はパルミラ風でいつもより少し味が濃かったが、向こうで買ってきたと言う変わった食感の茶菓子によく合っている。
「二人にも随分と心配をかけたね」
「いえ、気にしないでください。少なくとも私はこの珍しいお菓子で許してさしあげます」
「気に入ったので現物も料理本もたくさん買い込んでしまってね」
リシテアとの会話から察するにローレンツは物欲が戻ったらしい。日々の暮らしを楽しんでいた彼が生きている己を罰するかのように、内側にに篭る姿は見る者全ての涙を誘ったし、イグナーツも胸が締め付けられるように辛かった。人生は本当にままならない。
だが、もうすぐ一歳半になるよちよち歩きのストームを連れて、薔薇園を散歩する彼の姿は隣に亡くなった奥方がいないのが不思議なくらい元のローレンツそのものだった。
皆、ひとまずは安心した。そうなると次は詮索が身をもたげてくる。一体旅先のパルミラで何があったのか。久しぶりになんの憂いもなく、グロスタールの屋敷で過ごしたリシテアは幼い頃から何度も泊まっている馴染みの客室で夫のイグナーツに推理を披露していた。
「イグナーツ。私が思うにローレンツ兄様には新しく好い人が出来たのかもしれません」
「朗らかになってましたよね、確かに。ストームのためにも本当に良かった」
豊かな黒髪をブラシで梳かしていたリシテアが目元を押さえた。
「あら……いやだ、今度は私が泣いてしまうなんて。でも胸元に薔薇も付けていたし元のローレンツ兄様に戻ってくれたみたいで嬉しくて」
「紹介してもらえたら、僕たちからもその方にお礼を言いましょう」
イグナーツから濡れた手巾を渡されたリシテアは、それが絞って冷やしたものであることに気付いた。気を利かせてブリザーで冷やしてくれたのだろう。目が腫れないよう、目元にあててしまったのでイグナーツの顔は見えない。寝室で夜眠る前に話を聞いてくれる相手が失われてしまったら、と考えるだけで恐ろしい。楽しそうに相槌を打ってくれるイグナーツを失ってしまったら、リシテアだってどうなってしまうのかわからないのだ。
一方でカリードはフォドラに関する本を読み漁るため、図書館へ通い詰める日々を送っていた。カリードの住む港町はフォドラと近いこともあり、パルミラ語で書かれた本だけでなくフォドラ語の本もおいてある。どちらも読んだ。
カリードはフォドラの言葉は話せるが読み書きは得意ではない。口に出して音を聞かねば上手く意味が理解出来ず、フォドラ語の本を読むのにはかなり手間取った。その上、手当たり次第に読んだせいで調べ物としての効率も悪かった。しかしそのおかげでカリードのフォドラの文化への理解は深まっている。
彼は数週間かけついに知るべきだったこと、に自力で辿り着いた。カリードは彼をグロスタールのローレンツ=ヘルマンだと思っていたが違うらしい。ようやく何が書いてあるのか理解できるようになった貴族名鑑によると、彼はグロスタール伯爵家の一員だった。グロスタール家は十傑の遺産テュルソスの杖を受け継ぐ名門で、グロスタール領という土地の名前が彼の家名に因んで付けられている。彼は貴族の中の貴族だった。
カリードはフォドラの貴族というのはもっと冷酷で情がないものだと思っていた。だが実際に出会った彼は妻を亡くしたことが悲しくて悲しくて仕方ない人だったし、カリードが汚した服を洗ってくれて母譲りの緑色の瞳をきれいだと褒めてくれて───それ以上のこともあったし、別れ際の涙はもう不随意ではなかった、と思う。あんなに情の深い人をカリードは他に知らない。もう一度ローレンツに会いたい。ただ、彼から再会するにあたって条件を出されていた。それは別れ際の態度から察するに、ローレンツ自身の誓いでもあったのだ。
十六世紀のパルミラはダグザと海の覇権を争っており、海軍の主力はほぼダグザ方面へ割いていた。海軍の名においてフォドラの通商航路の妨害をする余裕はない。そこでパルミラ国王は民間船に対し、私掠免許を発行した。私掠免許を持つ船は敵国及び中立国の船を攻撃し、船や積荷を奪う許可を得たことになる。略奪や拿捕で得た利益は一割が国王個人、一割が船長、二割が出資者、残りの六割が乗組員達に分配された。乗組員達は受け取った六割を更に人数で割って分かち合う。その際に操舵手と船医は少しだけ取り分を多くしてもらえるのが常だった。
大型船は拿捕や略奪に備えて武装している。海賊行為は命がけだが一攫千金を狙うものたちからも投資家たちからも人気があった。私掠船は利益率の良い投資先で、それに絡んだ詐欺行為や私掠免許の強奪や偽造も横行している。
特に私掠免許の強奪や偽造は発覚すれば許可のない海賊行為を行った罪で海事裁判所に訴えられ、死刑になる。だがそれでもなお利益目当てに手を染める者が跡を絶たない。
命がけと言えば私掠船に入り込み、パルミラ国王が発行した私掠免許の真贋や正確な名義を確かめる密偵たちもそうだ。密偵は私掠船の数を正確に把握し統制したいパルミラの王府が雇うこともあれば、敵対国や中立国の政府や民間人が雇うこともある。旧レスター諸侯同盟の名家たちも海事に限らずパルミラに多数の密偵を放っていた。
少しでもフォドラと縁があり、大金を稼げる仕事がしたかったカリードは旧レスター諸侯同盟の名家ゴネリル家の密偵となった。彼を現地採用した密偵がグロスタール領出身だったこともかなり大きい。実際、上司の故郷の話を聞くだけで心が躍った。特に若様がまだ再婚なさらない、という話を聞けた晩は興奮して寝付けなかったほどだ。
カリードは様々な船に乗り込み、パルミラ人の外見と流暢なフォドラ語を利用しありとあらゆるものを煙に巻いて船長たちの秘密を暴いた。秘密を暴かれた私掠船の船長たちはそのまま海事裁判所に訴えられ、裁かれるものと脅迫されフォドラに協力させられるものに分かれる。
その判断を下すのが密偵頭の〝クロード〟だった。レスターからパルミラへ送り込まれた密偵たちはそれぞれ協力するように言われている。彼らの頭の名はそれがどこの誰であろうといつも〝クロード〟だ。〝クロード〟になれたら出自がなんであろうと、名家の人々からは一目置かれるようになる。船上で野蛮な行為のあった晩、カリードはいつもローレンツのことを思い出して正気を保った。
「本当に明日フォドラに帰っちゃうのか?」
「帰るよ。君のおかげで落ち込んでいる自分のことも許せたし、幼い息子には父親が必要だから」
フォドラへ連れて行って欲しいとせがむか格好をつけて自分もすぐに行くから待っていて欲しい、と言うべきか。迷ったカリードは眉尻を下げ、黙ってローレンツの顔を見つめた。頼まれごとが嬉しくて頑張ってしまったが、乗れる船なんか見つけてやらなければよかった気がする。でもローレンツから無能だと見做されるのはもっと嫌だった。
「僕のように心を病んだ男が何を言っても説得力はないかもしれないが、君は善良で頭が良いのだから優れた何か、になるべきだ」
カリードが黙って身体を強張らせているとローレンツが手を握ってきた。長くて白い指と褐色の指が組み合わさり白い顔が上から近づいてくる。
「それに君の未来が僕の性欲で定まるのはいやだな」
ローレンツは冗談めかしていたが、カリードは自分の耳元で囁かれたその言葉に雷に打たれたような衝撃を受けた。その時は分かっていなかったがグロスタール家の力があれば、あの時点の野良犬のようなカリードをフォドラへ連れて帰ってしまうのは簡単だった。だがローレンツは本当に誠実な人物で、それが搾取であると考えた。カリードには自力で優れた人間になる可能性があり、自力で自分と対等な人間になれると信じてくれた。
愛する人に信頼されたからには全力で応えるしかない。こうして優れた何か、になろうとしてもがき苦しむカリードの姿が女神の御心を動かしたのかもしれない。もしくさたった半月しか共に過ごさなかったのにカリードの可能性を信じて、突き放したローレンツの真面目さが女神の御心を動かしたのかもしれない。
正確なところは分からないがとにかく事態は動いた。近々デアドラ港の港長が代替わりする、という噂はカリードの耳にも入っている。それにまつわる人事異動の噂で持ちきりだ。港長が代替わりするなら今の〝クロード〟も引退する可能性がある。聞くところによると二人とも隠居してもおかしくない老人だ。次の〝クロード〟になったカリードがデアドラで暮らすようになれば、ローレンツは再び連絡を取ってくれるかもしれない。グロスタール領からローレンツが会いに来てくれるかもしれない。
そのためには今までと同じく、今回の航海でもしくじることは出来かった。甲板では船員たちが食糧不足を解消するために釣った鮫が大暴れしている。その様子をマストの上から眺めながらカリードは不敵に笑った。畳む
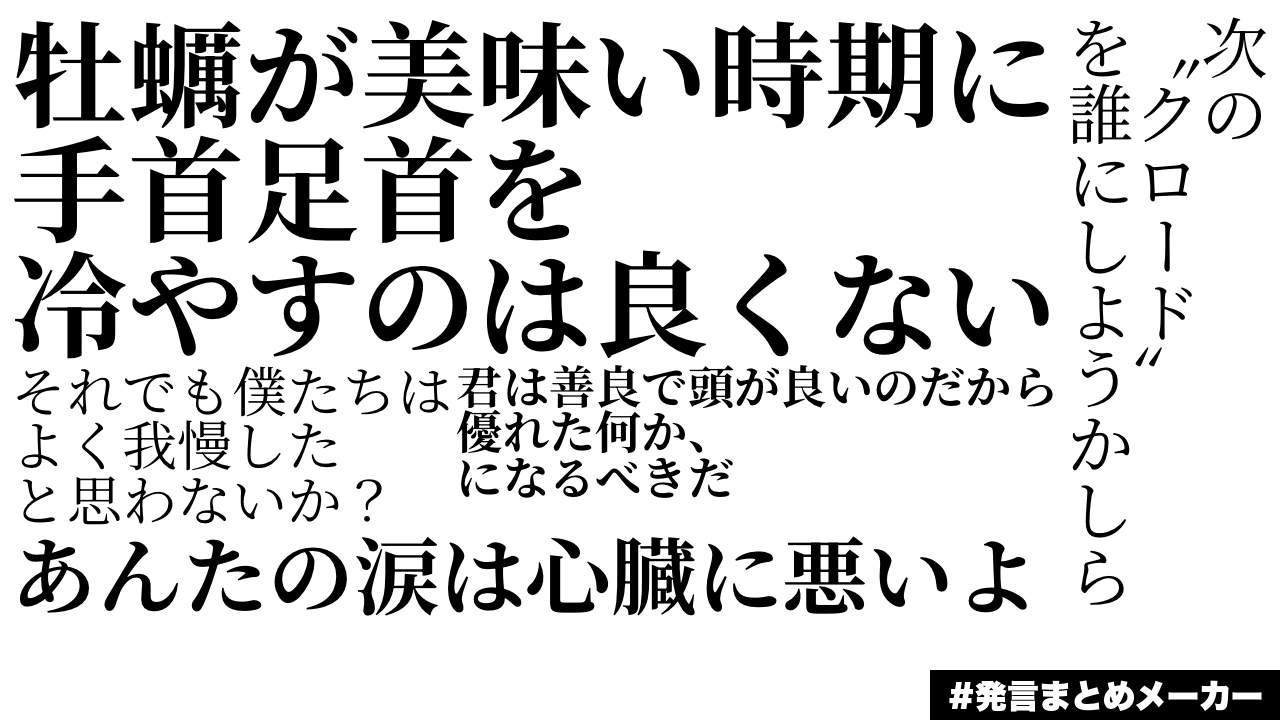
8.
───
一六一二年
聖人たちだけは地の底から地上へ戻らんと伸ばされる最初の人々の手足に気付いた。彼らの目は霞んでいないからである。
聖人たちは神祖に安らぎを与えた次の人々を守るために地の底から伸ばされる手足を切り捨てることにした。
───
ローヴェ領の人目につくところには必ず、ある落書きがされていた。やがてこの落書きは異端者狩りが行われていた地域全てに広がっていくのだが、この段階ではローヴェ領の中だけにとどまっている。落書きはなんであれ治安が乱れる兆しだ。意味のわからない記号のような落書きは大体、盗人たちの符丁で後日、強盗に入られたり火事にあったりすることが多い。巡警たちは記号を見つけるとどういう意味なのか、解読しようとする。だからこそ最近やたらみかける落書きの意図が読めずに困っていた。
〝NO〟と書いてあるだけだった。風刺や嫌がらせならば領主や名の知れた役人の名前や行状について.あることないことが書いてあるだろう。それにその中身から書き手を辿ることが出来る。しかし肝心の落書きは〝NO〟の一言だけなのだ。落書きだけではない。畑の麦がその形に踏みしめられていたこともある。今日は少し毛色が違っていて、役場の壁に貼ってあった官報やチラシ、ご老人言うところの引き札が〝NO〟の形に貼ってある。
この現象に困惑しているのはささやかな行政や司法だけではない。ささやかな規模ではあるがこの街には無法者たちも存在している。巡警たちがやたらとこちらを疑うが、彼らにとっても無意味な符丁だ。ただひたすら不愉快で我慢ならない。
例の形に貼り直されているチラシや官報を目にしたユーリスはまた自分たちが疑われてしまうと思い、苛立ちのあまり舌打ちをした。凝視しているうちに違和感を覚えた彼は魔が射したのか、白い指でチラシをそっと触った。この壁に貼られる紙は糊で貼られるのが常だが魔法で接着されている。やっていることは下らないが使われている魔法は恐ろしく高度だ。ローヴェ領出身でこんなことが出来るものはローヴェ領などに留まらず、成功するためにフェルディアかガルグ=マクへ行ってしまう。一連の落書きの下手人は余所者だ。
ただユーリスはこれをひたすら真面目な、馴染みの巡警に教えてやるかどうかを即決できなかった。彼女はユーリスを週に何度か市で屋台を出す串焼き屋としか思っていない。本人は口が硬いのだがいくらでも身上など調べられるものでガラテア出身であること、口減らしで巡警になったものの頑なさと正義感が邪魔をして任地から弾き出され、流れ流れてローヴェ領まで来たことをユーリスは知っている。
考えごとに没頭し過ぎていたせいだろうか。ユーリスは視線に気がつかなかった。自分に視線が向けられていると思った瞬間、振り向くと少し離れた建物の屋根が光った。遠眼鏡こと望遠鏡はセイロス教の禁忌に触れるとのことで他領はともかく、ローヴェ領内では使用出来なくなって久しい。食い荒らすほどの実りのないこの土地に余所者がなんの用事で来たのだろうか。利益も得られないのにこんなところに来るような余所者に顔を見られるのは嫌だったが、睨んでいることだけは判らせてやりたい。ユーリスはガラスが反射した光の方を睨みつけてやった。
一方、睨みつけられたベレトは離れた建物の平らな屋根の上で苦笑していた。セテスたち親子と別れた後で髪を切って黒く染めたので、士官学校で教師をしていた頃のような見た目になっている。ベレトは顔を上げて様子を見たがるイングリットの頭を軽く抑えた。
「ユーリスが気づいたな。まだ頭は下げたままで……三数えたら頭を上げていい」
ベレトは三数えると術式を解除した。壁に張り付いていた紙がバラバラと剥がれ落ち、何が表現されていたのかはその瞬間に壁を見ていたごく少数のものにしか伝わらない。
「本当にこんなことで捕らえられたメルセデスを助けられるのですか?」
「今すぐ助け出せというならオーラとライナロックをぶっ放すだけで済むが、それではメルセデスしか助けられない。今後このローヴェ領で火炙りにされるものが出ないようにするには少し時間はかかるが、これが一番だ」
ファーガスブルーの制服に身を包んだイングリッドは渋々引き下がったが、それは禁制品である望遠鏡を持った男の体捌きから彼が凄腕の戦士であることを察しているからだ。
「ユーリスは単なる串焼き屋の若者です。巻き込んでしまって良いものでしょうか?」
「いや、巻き込もう。審問会までに一人でも多く味方が欲しい」
異端審問は審問者による数日間の取り調べの後、住民たちが審問会を開催するかどうかを決める。住民たちが被疑者を守ろうとすれば開かれない。だが審問会が開かれた場合の有罪率は九割以上だ。審問会の有無は地域によってかなりの開きがある。残念ながらローヴェ領は尋問官から取り調べを受けた時点で有罪と感じる住民が多いため、審問会は開かれる確率が高い。
「デアドラのような都会の人からすれば不思議でしょうね」
イングリットが自嘲気味に呟いた。長い睫毛で陰が目元に落ちる。ガラテアもあまり雰囲気が変わらないらしい。領主たちは領民たちを導いているつもりでいるが、実際は領民たちに合わせた行動をする。王を失った混乱と恐怖でダスカーの民を犯人と決めつけ、一方的に殺戮に及んだし、若く美しいエーデルガルトが気に食わない領主を失脚させてくれるなら、と言って大陸中を侵攻した。
───貴族が必死で平民たちを導こうとしても最終的に政治は納税する彼らの意志に従わざるを得ない。それならば大衆の意志がより良いものになるような機会を与え、環境を整えるべきだ───
フェルディナント一世は義務教育について戦乱の最中からずっと考えていたという。彼の父親は為政者としては選択を失敗し続けたが、子育てには成功した。現実や大衆がフェルディナント一世の高い理想にまだ追いつかないとしても、理想を掲げ続けるのはエーギル家の使命だった。しかし六大貴族は実権を失いつつあり、それがこのような形で社会に影響を与えている。
「過ちを改めるのに遅すぎるということはない。時期の遅さは過ちを改めない理由にならない。メルセデスのところに行こうか」
デアドラから来た男は全く見覚えがないはずなのにどこか懐かしい。彼はメルセデスが異端審問官に連行された場に居合わせた際、息を呑んでから彼女の名前を小さく叫んだ。彼女が連行される様な人物ではないと証言してくれるかもしれない。審問官の側について護衛をしていたイングリットは聞き取れた、その声に驚いて男の顔を見た。メルセデスを拘束するふりをして励ましながらも、男から目を離さなかった結果がユーリスを覗き見している。尋問が芳しくなければメルセデスへの取り調べは激化していくだろう。
メルセデスが拘束されたのは彼女がよそ者であったこと、修道士であるにも関わらず信仰魔法ではなく薬草で医療行為を行ったことが理由だ。患者の中には稀に信仰魔法に拒絶反応を起こすものがいる。怪我を治しても、その代わりに視力聴力の一時的な低下や激しい頭痛に苛まれてしまう。メルセデスが判断した通り体質によって治療法を変更する方が合理的なのだが、彼女を訝しんだものがいたのだ。
禁制品の双眼鏡を胸元にしまうとベレトは屋根から地上の路地裏へ直接、繋がっている外階段を一段跳びで駆け下りた。イングリットも後に続いたが階段がぐらついていて冷や冷やする。それでも巡警である彼女が同行しなくてはベレトは留置所に入ることが出来ないので慌てて彼を追いかけた。
───
国際宇宙ステーションの実験モジュールにおいてエアロゲルを用いた宇宙塵の収集と微生物の曝露実験が開始された。
収集された宇宙塵は実験モジュールに回収され着陸・帰還カプセルに搭載され地上に向け射出される。
───
メルセデスはガルグ=マク旧市街にあるガルグ=マク司教座付属医学校で、医療を専門とする修道士になるため教育を受けた。メルセデスの母校は聖セスリーンを守護聖人とし、信仰魔法だけでなく薬学や医学を学ぶことができる。同じ頃、イングリットも聖キッホルを守護聖人とするガルグ=マク司教座付属法学校にいた。検事それに裁判官や弁護士を目指すものは資格取得を目指して四年間、巡警や裁判所の書記を目指すものは二年間ここで学ぶ。
ふたつの学校は共にフォドラ統一戦争の際に統一王ベレトに協力し、共に戦った司教セテスとその妹フレンが対になるかのように設立した。寮も共同だったため、イングリットとメルセデスはそこで出会っている。
留置所に入れられたメルセデスはイングリットが目を離した隙に手錠を後ろ手に変えられていた。あれでは飲み物や食べ物を口にする際、犬猫のように皿に顔を近づけねばならない。異端審問官の意図を理解したイングリットは震えるような怒りを覚えた。
後ろ手で印を結んで魔法を発動させるかもしれないのに何を考えているのか、と自分と入れ替わりに留置所へ詰めていた異端審問官の衛兵を叱り付ける。その勢いを借りて今日の尋問は異端審問官ではなく自分がやる、と言って彼らを追い出した。
手錠の位置を肩が少しでも楽になるように再び前へと変える。本来ならば魔法の使い手を拘束する時は定期的にサイレスで呪文が唱えられないようにせねばならない。
それも知らなかったのかそれとも出来なかったのか。とにかく異端審問官の質の悪さが分かる。メルセデスは憔悴していたが、イングリットの一連の茶番の意図を正確に読み深く安堵のため息をついた。肩を小さく回して凝りをほぐしている。
「流石に参ってしまったわ〜。私は治療をしただけなのに」
「メルセデス、デアドラに知人はいますか?」
淡い色の短く整えられた頭を横に振って、メルセデスは友人の質問に答えた。瞳には戸惑いが浮かんでいる。では近頃、落書きをして回っている謎の男ベレトはどこでメルセデスのことを知ったのだろうか。
改めて怪しんでいるとどこからかリブローが発動し、メルセデスの体が癒されていくのがイングリットにもわかった。彼女はベレトを参考人として留置所に連れて入る予定だったが、ベレトから拒否されている。怪しまれないため建物には入らず手助けをする、と言っていたがこういうことかと合点がいった。
「質問を変えます。こういう芸当をやってのける知人はいますか?」
メルセデスはしばし考え込んだ後に直接はいない、と返答した。心当たりはあるのだが、荒唐無稽過ぎて真面目な友人には言えない。今後どうしたものか───迷えるイングリットが口を開けたまま無言でいるとメルセデスが手首に鎖をつけたまま腕を伸ばし、両手でイングリットの頭を撫でた。
「私はまだ耐えられるから大丈夫よ」
囚われの身である友人から気を使われたイングリットが情けなさにため息をついた。気持ちばかりが空回りしている。
無為なやり取りを終え、部屋を去るイングリットの後ろ姿がメルセデスには何だか小さく見えた。きっと自信を失っているからだろう。
歴史の長いガルグ=マクには数多くの怪談が伝わっていて、その中のひとつに「不死の借り出し人」がある。本名を名乗れないものがあからさまな偽名としてわざと統一王の名を使っただけであろう、という種明かしも込みでメルセデスはその怪談が好きだった。「不死の借り出し人」にはメルセデスの実家に伝わる書き残してはいけない口伝と内容が一致する部分がある。不死者はかつてメルセデスの先祖に言った。
───探さなければ何も見つからない。だから気が済むまで彷徨うつもりだ───
留置所を出たイングリットが待ち合わせ場所であるユーリスの串焼き屋につくと、ベレトが既に串焼きに齧り付いていた。目の前の皿には既に大量の串が積み重ねられている。リブローをかけたあとでさっさと撤退していたらしい。
「変わった知り合いだな、イングリット」
ユーリスの言葉を適当に誤魔化し、雑踏に消えていってくれるような小声でイングリットはベレトに質問した。
「どこでメルセデスと知り合ったのですか?」
「彼女の親戚と古い知り合いで元から名前だけは知っていた」
「たったそれだけの繋がりで何故、こんなややこしいやり方で助けようとするんだ?」
「でもユーリス、あれの影響かは分かりませんが、離婚する勇気のなかった方がきちんと離婚しました。あのままではいつか夫から殺されてしまうと心配だったので良かったです」
そういうとイングリットはベレトから差し出された串焼きにかぶりついた。ユーリスの串焼きはあいかわらず絶妙な味付けで、毎日食べたくなる。
「参事会の連中が同意したらどうするんだ?」
「ライナロックでなんとかするが、そうならずに済むようにこの屋台をユーリスが店を出さない日に貸してくれ。椅子もあるしちょうど良さそうだ。明日なんてどうだろうか」
「俺様になんの得があるんだ!どんな裏がある?」
「裏はないが得はある。イングリットが好きになってくれるかもしれないぞ」
虚を突かれ顔を真っ赤にするユーリスたちを見て、黒鷲の教え子たちが教え子同士で付き合っていたならばこんな感じだったのだろうかとベレトは思った。
翌日からユーリスの厚意で貸してもらった屋台でベレトは身分や立場で分け隔てることなく無料で悩みごとを聞き、治癒魔法を連日かけ続けた。夜はユーリスと二人で領内に〝NO〟と刻む。
落書きの犯人であることはばれなかった。しかし教会の許可を取らず、世俗の極みである市場で数日間に渡って治癒魔法を無料でかけ続けたため、ベレトは計算通り異端審問官に取り調べされることになった。
イングリットに叱られたことを覚えていたのか、異端審問官の衛兵は手が前になるようにベレトに手錠をかけた。イングリットから聞いた通り、留置所は男女で檻が別れている。だが真向かいなのでメルセデスと直接話すためベレトはわざと逮捕された。
ベレトを尋問した異端審問官は職業というより商売で異端審問官をやっている類の人間らしく、罪を贖うために浄財を出してくれそうな本家はあるのかとしきりに聞いてくる。メルセデスもベレトも外れだったのであからさまにやる気をなくしたようで、なんの儲けも出せないローヴェ領での裁判をさっさと終えたがっている。腹いせに異端者を火炙りにして、もっと豊かな土地へ移動しようと考えているのが丸分かりだった。
「メルセデス、聞いていたか?俺の名前を聞いた瞬間にやる気をなくしていたな。アイスナーなんてファーガスでは典型的な平民の名字だからな」
見張り番も眠る夜更けに、ベレトは狭い廊下越しに苦笑しながらメルセデスにそう話しかけた。窓から入る白い月明かりが彼女を照らし神々しい雰囲気になっている。
「私の実家に伝わる不死者の話をしても良いかしら?こちらは名乗った覚えはないのに不死者は何故か私たちの名を知っているのよ」
「それは不思議な話だな」
一方でベレトのいる部屋は窓の位置の都合か月明かりはあまり入らず顔に濃い影が下りている。ベレトの探し物は未だに見つかっていないが、それを伝えてメルセデスの一族の口伝が変化してしまうのも何となくもったいない。
───
地上の微生物が宇宙空間でどれくらい生存できるのか、どの様に変化していくのかについて調査する為に極限環境微生物と酵母を入れた容器を実験モジュール外に設置。
生物及び有機化合物の惑星間移動が可能かどうかを検証する。
───
巡回中の異端審問官が見つけた異端者を審問会にかけるには領主と領民から作る参事会双方の合意が必要だ。審問の結果、命を奪うことが殆どであるため異端審問官は必ず地元の事情も汲んだ、という形式を守らねばならない。実入りの悪い地域では異端者を弾劾する動きが地元の領主批判の熱狂に繋がる前に異端者を速やかに火炙りにして終わるものだが、街に溢れる妙な落書きのせいか今回のローヴェ領では珍しく領主と参事会の意見が割れた。
何に対しての〝NO〟なのか全く明示されていないため教会が落書きの内容を取り締まることはできない。それに落書きという行為を取り締まるのは世俗の権力の仕事だ。領内の巡警たちが田舎故の人手不足の中で本当に困惑しながら、下手人を探し続けていたことが記録にきちんと残っている。イングリットが真面目に書類を作成していたので異端審問官は地元の巡警が怠惰だと難癖をつけることもできなかった。
残されていた記録によるとやり方も段々と巧妙になり、巡警たちも取り締まれないようになっていった。〝NO〟と読めるように物が並べ替えてあったり地面が濡れている。前者はともかく後者は上からバケツで水をかけてしまえばもう読めない。物を並べ替えるもよは厳罰に処す、道に水を撒くものは厳罰に処す、などと世俗に属する彼らが言えるわけはなかった。どちらも日常の行為で、許可制になどしてしまったら業務を圧迫してしまう。
領主である現在のローヴェ伯は個人的な意見はともかくガルグ=マクで教育を受け、神学について多少は知識がある。異端審問官が何をもって修道士たちを異端と判断したのか、彼にも多少は把握できた。
だから異端審問官に逆らえなかった。しかし参事会の人々はそうではない。彼らは皆信心深く毎週末必ず礼拝に出席する。しかしセイロス教聖典の読み方を理解していない。綴りは判れど教義の読み解き方を知らずに祈りを捧げている。
領民たちにとって余所者はこちらが田舎ものであることを蔑む、非常に腹が立つ存在だ。今回槍玉に挙げられた余所者二人は何やらよく分からない教会の難しい作法を守らなかったらしい。それでもローヴェ領の病人とけが人に尽くしてくれた。
たった一言〝NO〟と言えば二人を助けられる。そんな訳で参事会の出した結論は〝NO〟だった。
領主さまや尊い教会から派遣された偉い人の意見に異議を唱えるなど恐ろしくて出来ない。ずっとそう感じていたが実際は呆気なかった。それは違う、と主張しても世界は滅びなかった。それに領主が恐れていたようなことも起きていない。領民が領主や教会に少しでも異議を唱えるのは叛乱や暴動の始まりで、そんなことは絶対にあってはならないと考えていた。だが街は平穏を保っている。
しばらく入浴をしていないから、と焦って頬を染めるメルセデスをイングリットが喜びのあまり抱き上げていた。雲の隙間から陽が射す煉瓦造りの留置所の前で、地域に尽くすことを示すファーガスブルーに染められた巡警の制服と純潔と民への奉仕を表す白の修道服が重なり合っている。二色が風ではためく姿はただひたすら美しい。
彼女たちの顔立ちが美しいことはこの場合、重要ではなかった。修道士の本分通り病人と怪我人に尽くしたメルセデスを、巡警として真面目に職務を遂行していたイングリットが害することなく済んで幸せそうにはしゃいでいる姿が美しい。
美は人の心を動かし心の在り方を変える。心の在り方が変われば言動が変化する。イングリット自身はあまり意識していないが、真面目で巡警として地域の人に寄り添う彼女は人気者だ。参事会の面々は息子の嫁に来てくれないだろうかと皆思っている。彼女たちの作り上げた美しさによって、彼らは言語化できずとも己の選択の正しさを知った。領主であるローヴェ伯も内心では暴動が起きず、自領内で火炙りにされる異端者を出さずに済んだことを良しとしている。
ベレトは湧き立つ人々から背を向けて、祝祭のような空間から急いで距離を取ろうとする異端審問官の馬車を眺めていた。自分もセテスもいないガルグ=マクで誰がどのように絶望し、異端審問などと言う恐ろしい行為が流行ったのだろうか。
肩を軽く叩かれ振り向くとユーリスがベレトの背後をとっているをすり抜けられた。こんなことはかれこれ何年ぶりだろうか。
「あの馬車に向けてライナロックを一発かまそうなんて思ってないよな?」
ベレトが無言で首を横に振ったのを見てユーリスが人の悪そうな笑みを浮かべる。
「残念だ。手伝ってやりたかったよ」
「イングリットのところに行かなくていいのか?」
「俺は野暮じゃないからああ言う場に割り込まないんだ。楽しそうだし好きなだけくるくるまわらせておこうぜ」
ユーリスもベレトと同じく、審問官たちが乗り込んだ馬車がどこへ向かっているのか確認しに来たらしい。
「あれはガルグ=マクだな。あいつら司教座に泣きつきたくても、どう報告すれば良いか分からねえだろうな。上手いやり方だよ」
「流行るといいんだが」
これからガルグ=マクに乗り込むか地方の様子を見て回るか決めねば───そう思った瞬間、ベレトは強烈な眠気に襲われて意識を失った。ユーリスがいなければ頭を石畳で強打していただろう。彼が血相を変えて身体を支えてくれたことも分からず、これがフレンが嫌っていた〝眠り〟かと思う隙もなかった。
〝眠り〟からベレトが目覚めた時、傍にいたのはベレトの知らないメルセデスだった。確か彼女は肩より長く髪を伸ばしていたはずなのに。それに課題協力を依頼した覚えもない。何故自分を看病しているのがマヌエラやリンハルトではないのだろうか、と思った瞬間にベレトの中で時が四世紀ほど進んだ。こんな風に時間の感覚を失うのは久しぶりで、身体にも負荷がかかっていたのか咳き込んでしまう。自分はヒトとしては規格外の長命だが、眷族の中ではきっと驚くほどの短命なのだろうとベレトは悟った。
「倒れてから十日経過したわ。イングリットとユーリスは仕事。ユーリスは宿代を立て替えてくれたのよ。後で返してあげてね」
日付を聞いて深く安堵のため息をついたベレトは左胸に右手を置き再び目を閉じた。まだひたすら怠くて目を開けていられない。意識がある時はウインドを応用して鼓動があるように見せかけられるのだが、完全に意識を失ってしまったし今も怠いのでやりたくない。メルセデスは十日前、ベレトの心音や呼吸を確認した時に何を感じただろうか。
「言いふらすことでもないから言わないわ」
メルセデスはそう言ってベレトの右手の上にそっと手を重ねた。ひんやりとした心地がいい手だった。
「ありがとう。俺が探しているものはまだ見つからないんだが、たまに君たちに会えると本当に嬉しいよ」
ベレトは遥か昔に失った半身ソティスのこと、孤独感に蝕まれてしまったレアのことを考えた。ベレトが地位を手放した結果、フォドラは閉塞感に満ち満ちている。眷族はどうあるべきだったのだろうか。その答えが未だにベレトには見つけられない。
9.
───
一六五〇年
生命を構成する要素がどの様にして組み合わさったのか、細胞の中にそれらが閉じ込められた理由、これらのプロセスを進めるためのエネルギーは何であったのかを説明できなければどのように生命が始まったかを説明できたとは言えない。
パンスペルミア説は根本的な疑問に答えていないという意見もある。
───
三十年ほど前に辺境の風土病がフォドラ全土を襲った。感染率と致死率が共に高く小さな村の住民が全滅したこともあったという。当時の記録によると街には節々が黒ずんだ亡骸があふれていたらしい。
医師たちは感染を予防するため革製の長衣に全身を包み仮面をつけ、無力感に苛まれながら歩き回って死者の数を数えた。医師たちと似たような格好をした聖職者たちは動けなくなった病人たちへ最後の祈りを捧げて回る。そんな日々はフォドラ全土の人口が三分の二に減少するまで続いた。
病禍を経た社会は大きな変化を遂げていく。フォドラは長らく王を持たず、貴族たちの中から執政官が選ばれていたが人材が枯渇した。この時期に初めて騎士階級出身の執政官が選ばれている。
人口減以外の、何よりも大きな変化は魔法が使えるヒトの割合が激しく減少してしまったことだ。それまでも全人口の五パーセントほどしか存在しなかったが、病禍の後は二パーセントに減少してしまった。社会は魔法に代わる何か、を早急に見つけなくてはならない。
そんな状況下で、フェルディアとフェルディアを参考に下水道が整備された各地の新市街だけは難を逃れることが出来た。皮肉なことにアガルタの民、つまり闇に蠢くものたちの技術や知識が人々を救っている。後に病は悪臭が原因とされ、生き残った人々が各地で持ち主のいなくなった土地を使い下水道や公衆浴場を整備した。
飛竜や天馬に乗って首都であるガルグ=マクからファーガス方面に向かうと大きな黒い森が見える。ガルグ=マクから北上した人々はここがもうファーガスであることを木の葉の形で知るし、ファーガスから南下した人々はこの先にもう見慣れた木々はないことを知る。その森の端には歴史は長いが規模の小さな女子修道院があった。
修道院で眠り続ける娘の介護をするため、長逗留しているセテスは行きがけに目にした光景にずっと心を痛めていた。その村では病を持ち込む余所者との接触を避けるため沈黙交易をしていたらしい。村境に木箱に入れた金銭を置いておくと商人が木箱の金銭を受け取り、必要な物を木箱の中に置いて去る。村人は商人が完全にいなくなったのを確認してから購入した物を村の中に運ぶ。セテスが上空から目にした木箱は中身が回収されないまま数日が経過していた。村人が全て死に絶えたか身動き出来る者がもういなくなってしまったのだろう。
眷族がヒトを管理するようになってから何度か病が流行ることはあったが、今回のものは規模が違う。フェルディアの下水道にしても予防手段に過ぎず治療法は見つからないままだ。セテスがつい、アガルタの民が健在であれば全く違う方法で流行病に対抗できたかもしれない、と考えてしまうほどの惨状だった。このままではフォドラの首飾りから西は無人の荒野になってしまう。ある程度の人口がなければ文明を維持することも出来ない。レアが慈しんでいたフォドラの人々、娘のフレンを愛してくれた人々の子孫が死に絶えてしまうかもしれない。
フレンの体を拭いた修道女たちはいつもなら娘の眠る病室のすぐ近くに控えているセテスが見当たらないので、不思議に思い手分けして敷地内を探した。夕闇の中、熱心に聖堂で祈るセテスの横顔は苦悩と迷いに満ちている。少しでも気を紛らわすことができればと思った修道女たちはセテスを談話室でのお茶に誘った。
質素な作りの談話室には大きな年代物の給茶器と茶碗などをしまっている硝子戸の棚があった。給茶器は三段重ねのものでファーガス特有のデザインをしている。下段に熱した炭を入れ、小さな蛇口がついた中段に入れておいた水を沸かす。上段には茶葉と湯を入れっぱなしのティーポットを置いておく。当然煮詰まっていくのだが飲む時には中段のお湯で薄める。
老いた修道女は慣れた手つきで給茶器上段からティーポットを取り外し中身を確かめた。この修道院に黒魔法の使い手はいないので炭はその代わりだろう。煮詰まって濃くなってしまったお茶をお湯で薄める。
「寒い田舎では紅茶の楽しみ方も異なるものです。来客用ではなく自分たちが楽しむためですので多少の無作法はお許しください」
そういうとセテスを招いた修道女は若い修道女に人数分の茶碗と小皿と小匙を用意させた。手早く準備するためだろうか。何を求められているのか完全に分かっている若い修道女は更に戸棚から何かの瓶とジャムの瓶を取り出した。ジャムは色からすると木苺か何かのようだった。お茶請けだろうか。蓋を開けると素朴な甘い香りが部屋中に広がった。手慣れた様子で赤いジャムを小皿に盛り付けていく。
皆の茶碗にお茶を入れて回っていた修道女が再びティーポットに中段のお湯を入れ、給茶器上段に戻すと謎の瓶の蓋を開けた。ふわっと香った匂いから察するにそれはかなりきつそうな蒸留酒だった。セイロス教では飲酒を禁止していないが推奨もしていない。修行の一環で絶つことが望ましいとされているが、この寒さでは体を温めるために必要なのだろう。
老いた修道女が上機嫌でそれぞれのジャムの上に蒸留酒を振りかけていく。呆気にとられてその様子をセテスが見ていると、ある者は幸せそうに蒸留酒で伸ばしたジャムを舐めながら紅茶を口に含み、別の者はジャムの蒸留酒がけを紅茶に混ぜて飲み始めた。セテスも見よう見まねでジャムを舐めながら紅茶を飲んでみる。紅茶も淹れ方からして異なった。濃く煮詰めたものをお湯で薄めて飲むため全く味が違う。
「これはなかなか強烈な……だが癖になるというかなんというか……」
「私どもは辛いことがある時はこうして飲み干してしまうことにしております」
老いた修道女の言葉を聞いたセテスの脳裏にある考えが閃いた。自分の血がどんな影響を及ぼすのか正確に確かめる時間も設備もない。だが眷族の血が病を予防すること、病の症状を軽くすることだけは経験から知っている。検証なしにすぐに血を与えるとしたら騒ぎにならぬよう、偽りの希望にならぬよう、分からないように与える必要があった。
だがこのお茶に混ぜてしまえばジャムの香りと甘味、蒸留酒の香りと味で血の味や匂いをごまかせるだろう。セテスも血を与えることによって、かなり自分の寿命が縮まると分かっている。だがこの惨状を目にして出来ることがあるのに何もせずにはいられなかった。
流行病は森の近くにある小さな女子修道院や周りの集落も襲ったが、不思議とその地域では発症率が低かった。白魔法を使える人材の減少を受け、フェルディア総合大学に新設された医学部の医師たちが調査にやってきた。その地域は地下水が湧き、森には薪が豊富で毎日入浴する習慣と寒くて風邪が流行る時期には沸かしたお茶しか飲まない習慣があったことを致死率の低さと結びつけている。
医師たちは気がつかなかったが、この地域で生き延びた人々には他にも共通点があった。皆、髪と瞳の色が緑色で黒魔法も白魔法も使うことができた。
そしてそれは生まれつきではなかった筈なのに、彼らの子供たちにその形質が受け継がれた。
───
一六七五年
地上に伸ばした手足が全て切られてしまったので最初の人々は目が霞んだ者たちの皮をかぶって地上の様子をうかがった。
目が霞んだ者たちは宝が宝だと分からず、地中に打ち捨てていた。宝さえあればまた地上に戻れるかもしれないと考えた最初の人々はまず目が霞んだ者たちの皮を集めることにした。
───
山を切り開いて作られた首都ガルグ=マクの新市街には、統一王に仕えた六大貴族の上屋敷が固まっている地区がある。半世紀ほど前、病が流行った時代に貴族階級はかつてのような力を失った。だが人々はそれでも執政官を輩出し続けた六大貴族を名家として扱い、敬意を払う。誰が呼びはじめたか定かではないがこの地区はハイストリートと呼ばれていた。
ここの住民はその殆どが.本宅がある自領と首都であるガルグ=マクを行き来しながら暮らしている。その一画、アールノルト家の上屋敷に士官学校へ放り込まれて不満たっぷりな子供たちが集まっていた。先祖の立派な名を与えられたリンハルト、ドロテア、ベルナデッタの三名は休日になると窮屈な寮を出て、数時間だけでも誰かの上屋敷に集まるのを何よりも大きな楽しみにしている。
ベレト統一王の御代からの習慣で、セイロス教会に叙勲されて新たに貴族となったものたちはアドラステア帝国由来の称号である〝フォン〟を冠することがなくなっていた。これは叙勲された初代アールノルト家の当主ドロテアがフォンという称号を拒否したことによる。某貴族の私生児であったという彼女が生物学上の父親への反発を持ち続けていたからだ、とも言われるが真相は明らかになっていない。
四世紀もの長い間、離れずに過ごした六大貴族たちは互いに婚姻関係を結び、名乗る姓は違えど今や気の知れた親戚のような存在になっている。三人はまずドロテアがアンヴァルから取り寄せておいた銘菓を食べ尽くした。数世紀前から歌劇団の劇場前にある名店は数多くの著名人に愛されたという。
ベルナデッタは勝手知ったるドロテアの部屋の床に大きなクッションを抱いて座り込んでいる。リンハルトに至ってはドロテアのベッドに勝手に上がって横たわり、夢うつつ状態になっていた。
「野外演習やだあ!寮に帰りたくなぁい!一週間くらいお部屋でゴロゴロしてお絵描きしたい!」
この部屋の主であるドロテアだけが室内で立っていた。机の上の箱を持って寝転んでいる幼馴染みたちに声をかける。
「二人共見てよ!」
のろのろと起き上がった二人がドロテアの持つ箱を覗き込むと見事な細工の美しい硝子ペンが天鵞絨張りの箱の中に入っていた。ベルナデッタは基本やる気がない。だがひと目見て気に入ったのか素敵だ、何か描きたい、と騒ぎ出す。
「これは綺麗だね。どこで買ったの?」
「近くの店よ。前にリンハルトが欲しがってたものも置いてあったわ」
リンハルトが欲しがっているのは片眼鏡と拡大鏡だ。
「連れて行ってよ」
二人の会話を聞いたベルナデッタがベルも絵を描くのに硝子ペンが欲しいです!と珍しく乗り気なので三人は出かけることにした。庭の様なハイストリートから外れてどんどん路地裏に入っていく。ベルナデッタの記憶では靴屋だった店の前でドロテアが立ち止まった。看板も何もかもそのままだったが、中に入ると所狭しと硝子製品が靴と靴の間に飾られている。肩まで伸ばした黒髪を黄色いリボンでひとまとめにした店主が椅子に座って商品を布で拭いていた。傍には店内に入りこんだ野良犬が丸まって眠り込んでいる。初見の客に気付いた瞳は若葉色だった。
「靴屋が夜逃げした後でこの店の権利を中身ごと買ったんだ。欲しい靴があったら履いてみるといい。売るぞ」
「あなた変わり者ですね!ベルにはわかります!」
そんなことをわざわざ本人に向かって告げるベルナデッタこそどうなんだ、と思ったが面倒くさかったのでリンハルトは黙って店内を物色している。ドロテアが言っていた通り、硝子工芸品に混ざって様々なレンズが靴と靴の間に置いてある。壁には様々な枠がかけてあって、その場で好きな枠にはめてその場で拡大鏡にしてくれるらしい。
「レンズは全部あなたが研磨したの?」
「半々かな。パルミラで修行したんだ。自分が研磨したものは眼鏡屋に卸したりご覧の通り加工してして売ってる。工芸品もパルミラのものが多いかな?あれもそう」
店主が指差した先にはトンボの羽をモチーフにしたランプシェードが飾ってあった。何故か長靴の上に。この美しくもどこか人を食ったようなふざけた感覚は確かにドロテア好みだろう、とリンハルトは思った。
ベルナデッタは球体硝子から見た風景を描きたい、とのことで球体硝子と硝子ペンを買った。いつの世も芸術家はそのモチーフが好きらしい。夢中になって球体ガラス越しに店内を眺めている。
ドロテアは売れ残っていたサンダルを買い、リンハルトは片眼鏡をひとつと片眼鏡と寸法が同じ拡大鏡をひとつ買った。リンハルトが無意識に片眼鏡をつけたまま顔の前に拡大鏡をかざす。
「リンハルト!だめですよぉ!」
「ちょっと!そういうことはヘヴリング領でやってちょうだい!」
旧市街はセイロス教の総本山だ。顔を真っ青にして焦るベルナデッタとドロテアの声を聞き、店主は眉間にしわを寄せた。親指は首をかき切っている。
「へぇ信心深いね」
セイロス教ではレンズを縦に重ねることを禁止されている。見えないものを見ようとしてはならないのだ。天上におわす女神の姿を人間が見ようと試みるなど不敬そのものである、と読み取れなくもない文章が聖典にあるから仕方がない。宗教とはそういうものだ。
「客に死なれると夢見が悪いものだ。その代わりにこれをどうぞ。そのうち試そうと思っていたものだが忙しくてまだ試していない」
店主は小さなカードの真ん中に錐で穴を開けたもの、に何かを書き付けるとリンハルトに渡した。リンハルトは中身を改めてなるほどなるほど、と言いながら片目を瞑っている。意図が完全に伝わったのか受け取ったカードを窓にかざしている。好奇心が沸きあがって興奮したせいか、白い頰は朱に染まり瞳が輝いていた。
「硝子ビーズもいただこうかな。ねえ、あなた名前は何ていうの?これからしばらく相談に乗ってもらうから知らないと不便だよ」
「ベレト=アイスナーだ」
店主の名を聞いたドロテアとベルナデッタがため息をついた。皆、偉大な歴史上の人物と名前が全く同じなのでベレトへの視線が同意や共感に満ちている。
「おや、随分と高貴な名前だね。僕はリンハルト=フォン=ヘヴリングだ」
自分の名前を棚に上げ、リンハルトがベレトを揶揄った。統一戦争の際に活躍した先祖たちもこんな風に語り合っていたのだろうか。
「ファーガスでは典型的な平民の名字だよ。石を投げればアイスナー家の者に当たる」
ベレトの言葉を聞いたリンハルトがまあ名前なんてそんなもんだよね、と言うので皆で笑ったその時、狙いすましたかのように休日の終わりを告げる教会の鐘が鳴り響いた。
数週間後の休日にリンハルト一人でベレトの店に現れた。その手にはふたつ折りにした厚紙に穴を開け、硝子ビーズを嵌めて作った単レンズ式の簡素な顕微鏡の雛型がある。
「研磨できる?あと厚紙より真鍮か何かで作った方が良さそうだよ」
レンズを前後に重ねず、ガラスビーズをひと粒使用するだけで倍率は百五十倍になる。球体レンズとして職人が研磨したレンズを使えば倍率は更に上がるだろう。
ヘヴリング卿が作った単レンズ式顕微鏡はフォドラの生物学を大きく進歩させた。構造は単純なので現在では子供たちの自由研究の定番でもある。畳む